認知症ケアの本質は「目の前のその人」にある
「この方は、アルツハイマー型認知症だろうか」
「レビー小体型のような症状があるから、幻視が出ているのかな」
「前頭側頭型なら、感情の起伏に注意して接した方がいいかもしれない」
こうした“分類”や“特徴”を把握しながら認知症の方に関わろうとするのは、介護職にとって自然な姿勢です。
知識を持っておくことは、相手を理解するための第一歩になるからです。
しかし、私は現場で様々な認知症の方と関わる中で、こうも感じています。
どれだけ知識があっても、行き着くところは「今、目の前にいるその人」を見つめることこそがもっとも重要、ということです。
知識や分類は「地図」になる
認知症にはさまざまな類型があります。アルツハイマー型、脳血管性、レビー小体型、前頭側頭型……それぞれに特徴や経過、対応の工夫があります。たとえば
- アルツハイマー型:記憶障害が中心。出来事そのものを忘れてしまうことが多く、繰り返しの質問が増える。
- 脳血管性:できることとできないことの差が大きい。状態の変動が激しく、周囲の理解が求められる。
- レビー小体型:幻視が特徴的。見えないものが見えているため、否定せず安心させる関わりが大切。
- 前頭側頭型:感情や社会性のコントロールが難しくなる。行動の変化を「性格」と誤解されやすい。
こうした、各認知症に対する基本的な知識を知っているかどうかで、対応がスムーズになることも多く、トラブルの予防にもつながります。
つまり、知識は“地図”のようなもので、方向を見失わないための助けになります。
でも、地図だけだと目的地に辿り着けない
ただ、忘れてはならないのは「人は分類できない」ということです。
どの認知症にも“その人なり”の現れ方があります。
たとえば「同じアルツハイマー型」でも、感情の動き、言葉の残り方、家族との関係性によって症状の意味や現れ方は大きく違ってきます。
分類や知識に頼りすぎてしまうと、つい目の前の人を「枠」に当てはめてしまいます。
「この方は○○型認知症だから、きっとこういう反応をするはずだ」
——その“思い込み”が、かえってその人の本当の困りごとを見えなくしてしまうことも少なくありません。
知識は、対応のヒントをくれる道具でもあります。
けれど、使いこなすためには、「今、この人に何が起きているのか」を、毎回ゼロから観察し、感じる必要があります。
見るべきは「この人が、今、何に困っているのか」
認知症ケアでいちばん大切なのは、「この人にとって、今、何が困りごとなのか」「何が不安なのか」を知ろうとする姿勢です。
たとえば、「家に帰る」と言う人がいたとします。
その言葉をただの“帰宅願望の前兆”として、その方の言動を止めるのではなく、
- 今ここにいる場所がわからず、不安を感じているのかもしれない
- 慣れ親しんだ場所での安心感を求めているのかもしれない
- 実際に帰りたいわけではなく「今の状況に馴染めていない」ことを訴えているのかもしれない
——と、その言葉の“奥”にある感情やニーズに気づけるかどうかが、ケアの質を左右します。
認知症の方の言動の多くは、自分の気持ちを伝えられず、必死に絞り出した「SOS」なのです。
それを「問題行動」として処理せず「困りごとのサイン」として見ていくことが必要です。
ケアの“正解”は、日々変わる
もう一つ、認知症ケアの難しさは「昨日まで通じていたことが、今日はうまくいかない」ということが頻繁にあるという点ではないでしょうか。
- 昨日は落ち着いて食事できたのに、今日は怒りっぽい
- 昨日は一緒に散歩できたのに、今日はベッドから出てきてくれない
こうした“変化”に対して「どうして昨日と違うんだろう」と戸惑うこともあります。
けれどそれは、認知症の自然な姿です。
むしろ『昨日と違うこと』は、私たち支援者の生活に当てはめてみても、当たり前なのではないでしょうか。
認知症の方にとっては「毎日が初対面のような世界」でもあります。
だからこそ、私たちも毎日「新しい目でその人を見る」ことが必要です。
同じ関わりが通じないなら、その日その時の“今の状態”に合わせて関わりを変えていく。
そうやって固定された正解ではなく「その人にとっての今の正解」を探していくのが、認知症ケアなのだと、私は思います。
「その人の人生」に立ち返ること
知識やテクニックは確かに必要です。
でも、それ以上に大切なのは、
「この人は、どんな人生を生きてきたのか」
「どんな価値観を持ち、どんな言葉を大切にしてきたのか」を、本気で知ろうとする姿勢です。
なぜなら、その人の過去や思い出こそが「今の不安」や「今の言葉」の背景にあるからです。
たとえば、いつも「子どもを迎えに行かなきゃ」と言う女性がいました。
ご本人の娘さんはもう大人ですが、話をよく聞くと、かつて教師をしており、毎日保護者に子どもを引き渡すのが日課だったそうです。
つまり、その方の言葉は「自分の責任を果たしたい」という気持ちから来ていたものであり、それに寄り添って「お仕事はもう終わりましたよ」「お母さん頑張りましたね」と伝えることで、表情が和らぎました。
このように“行動”だけを見ているとわからないことも、その人の“人生”に寄り添うことで見えてくることがあります。
終わりに
認知症ケアは、知識と技術だけで成り立つものではありません。
知識は「地図」、技術は「道具」。
でも、その“地図”も“道具”も、目の前のその人を見て、適切に使わなければ、意味を持ちません。
症状を見る前に「人」を見ること。
分類に当てはめる前に「声」を聴くこと。
その積み重ねこそが、認知症ケアの本質であり、支援者の有るべき姿ではないかと思います。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
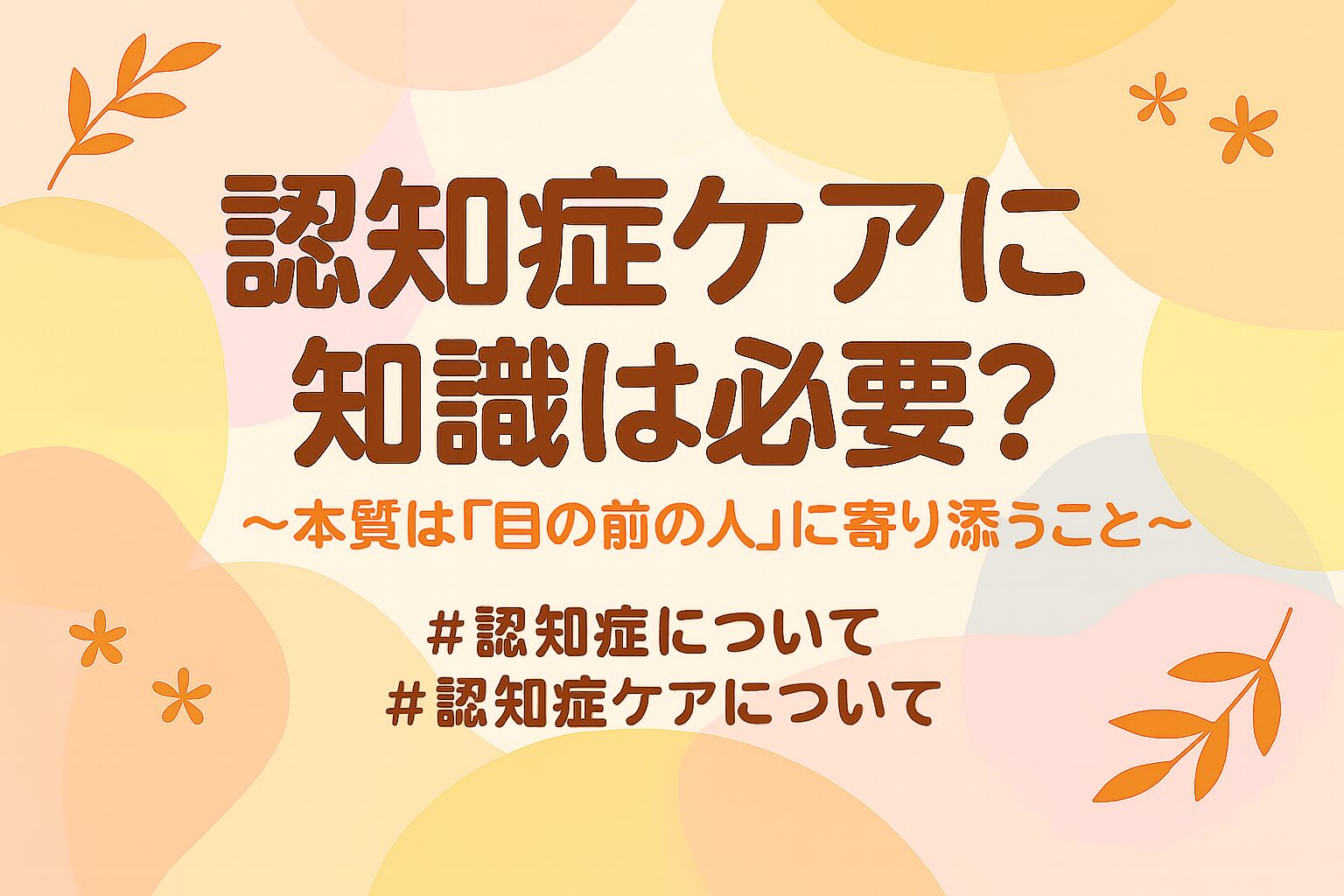
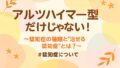
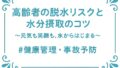
コメント