認知症の定義
実は、認知症ケアを提供する人が知らなければいけないこと
認知症ケアに関わるすべての人が知っておくべき『原点』とは何でしょうか?
親の認知症介護に奮闘するご家族、認知症専門棟やグループホームなどで働く職員――日々たくさんの方が、認知症の方の笑顔のために支援にあたっています。
しかし、我々が認知症ケアを提供するに当たり理解しておかなければならない、出発点ともいえる非常に大切なことがあります。
それは『そもそも認知症とは何か』という基本を理解することです。
この記事では
- 認知症とは何なのか
- 代表的な4つの認知症
について、お伝えいたします。
認知症の定義
認知症の一般的な定義とは
認知症とは、いったん正常に発達した脳の機能がさまざまな原因で低下し、記憶、判断、言葉、行動などの能力に障害が起こり、日常生活に支障が出ている状態をいいます。
つまり認知症とは、病名ではなく『症候群(状態の総称)』である、ということです。
ですので認知症ケアとは『病気を治す』ことを目的として行われるのではなく『状態の改善』を目指して提供されなければいけません。
これは『中核症状』と『行動・心理症状』の違いを理解して認知症の方へケアを提供していくうえでも非常に重要な考え方なのですが、それについては別の記事でお伝えいたします。
認知症と診断されるまでの流れ
では日常生活に支障が出ている状態とは、誰がどのように判断するのでしょうか。
①記憶や思考などの認知症状に障害があること
例えば
- 物忘れ(体験そのものを忘れる、新しいことを覚えられないなど)
- 時間や場所が分からなくなる
- 会話がうまく続けられない
- 判断や理解に時間がかかる
などの症状があらわれることです。
実は、近しい人がこのような状態に気づけるかどうかは、非常に重要です。
大抵の場合、このような状態となった親に対して家族は違和感を覚えるものの『まさかうちの親が』とその可能性を無理やり排除してしまい、何もしない間に認知症が進行してしまう、なんてことがとても多いのです。
②日常生活に支障が出ていること
- 買い物や食事の支度、金銭管理や火の取り扱いなどに困難がある
- 一人で外出すると迷うようになった
などです。重要なのは『加齢による物忘れ』とは違う、ということです。
ここまでくると、さすがに家族も目の前の『現実』を受け入れざるを得ません。
地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請をし、ケアマネージャーが付いて介護サービスを受け始めるのは、多くの場合はこの段階でしょう。
③脳の病気や変化が原因であると確認される
- MRIやCTなどで、脳の器質的変化が認められる
- 認知機能検査(長谷川式スケール、MMSEなど)
- 認知症のような症状が出る他の病気が除外されている(うつ病、甲状腺疾患、せん妄など)
④医師による診断がある
要介護状態となり専門医に受診すると③のような検査を行うこととなります。
そして①~③の情報をもとに、専門医(主に脳外科医、精神科医、神経内科医、老年内科医など)が認知症の診断をします。
認知症の診断が出るまでには、このようなプロセスを踏む必要があります。
しかしここで大事なのは『①~④の流れをくまないと認知症であるという診断は付きませんが、認知症は①の段階から始まっている』ということです。
つまり、本人の違和感に気付いた支援者が、いかに早く動けるか、ということがとても大事なのです。
代表的な4つの認知症
次に、代表的な4つの認知症について説明いたします。
認知症と聞いて多くの方が思い浮かべるのは『アルツハイマー型認知症』であるかと思います。
アルツハイマー型認知症に『脳血管性認知症』『レビー小体型認知症』『前頭側頭型認知症』という3つを加えた4つが代表的な認知症であり、この4つの認知症が全体の95%を占めています。
それぞれのタイプについての詳しい説明や、支援するうえで何に気を付ければいいのか、ということについては別の記事でお伝えいたします。
アルツハイマー型認知症
脳が徐々に小さくなる(委縮する)ことで発症します。
- 物忘れ。日にち、場所、時間の認識があいまいになる
- 財布などを盗られたと思い込む。急に怒る、泣く、笑うなどの変化が起きる
- 言葉が出ない、意思が伝えられない。表情が乏しくなる。家族の顔が分からなくなる
といった段階を踏みながら、ゆっくりと進行していきます。
およそ全体の約60%であり、女性に多いとされています。
脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血が起こり脳の一部の機能が失われることで発症します。
一部の機能が失われるのみなので症状にムラがあることが特徴です。また通常の脳梗塞の後遺症と同様に、麻痺や感情の波が現れることもあります。
およそ全体の15~20%であり、男性に多いとされています。
レビー小体型認知症
主な症状は、幻視(人や虫、火など見えないものがリアル見える)、手足のこわばりです。また、調子が良い時と悪い時の波が大きいことも特徴です。
薬が効きにくかったり、逆に副作用が強く出るといったこともあります。
およそ全体の10~15%を占めています。
前頭側頭型認知症
脳の前頭葉や側頭葉が委縮することで起こる認知症です。
前頭葉は、感情や衝動を抑え、社会的にふさわしい行動をとるようにコントロールする部分です。
側頭葉は、言語の理解について重要な場所であり、理解したり、意味を認識する部分です。
常識に反するような行動(万引きなど)を取ってしまうことで発覚することが多く、記憶に障害をうけるというより、人格や行動に変化が見られるようになります。
およそ全体の5%であり、若い頃より発症しやすいことが特徴です。また、他の認知症よりも進行が速い場合もあります。
おそらく、前頭側頭型認知症を患ってしまった方を自宅で介護することは、他の認知症介護よりも困難であることが多く、支援者の理解と忍耐が必要となります。
また現在は、複数のタイプの認知症の症状が現れる、複合型の認知症も多いです。一昔前は何となく一種類の認知症に当てはめていましたが、今では複数の認知症が発症していると扱うことが普通になりました。
今回は主に『認知症とは』ということについて基本的な部分をお伝えさせて頂きました。
認知症ケアを提供するうえで、病名や診断の知識が最重要というわけではありません。
しかし、基本的な知識があるかどうかで『ケアを受ける側の安心感』にも『ケアを行う側の負担感』も大きく変わってきます。
また、今後投稿を予定している記事の中で
- 中核症状と、行動・心理症状
- 代表的ではない認知症のタイプと特徴
- 代表的な4つのタイプの詳細と、支援する際の注意点
- 支援するに当たり、認知症ごとの特徴の把握は必要なのか
ということもお伝えしていく予定です。
今後も、具体的な症状やケアのヒントをご紹介していきます。どうぞこれからも「ここにん」をご覧いただき、皆様の認知症ケアに少しでもお役立ていただければ幸いです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
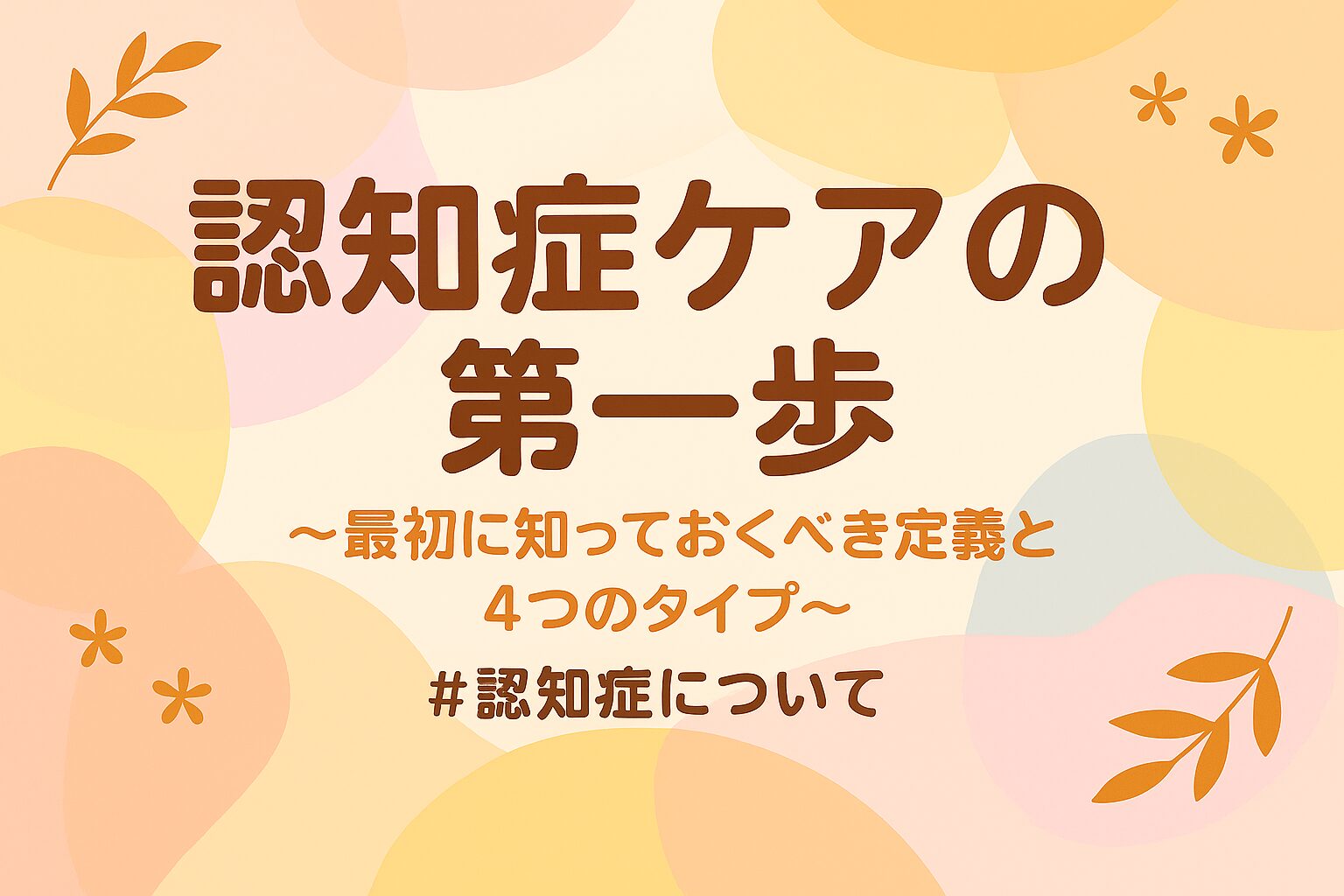
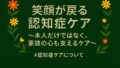
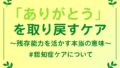
コメント