「認知症 = アルツハイマー型」と思っていませんか?
たしかに、認知症のなかで最も多いのが「アルツハイマー型認知症」で、全体の約6割を占めているといわれています。
他にも『脳血管性認知症』『レビー小体型認知症』『前頭側頭型認知症』を合わせて「4大認知症」と呼ばれていることが多いです。
しかし実は、これ以外にも認知症を引き起こす原因はたくさんあります。
しかもその中には、治療によって改善が期待できる――“治る認知症”もあるのです。
今回は、「4大認知症以外の原因」と「5番目・6番目に多い認知症」、そして「可逆性(治る可能性のある)認知症」について、分かりやすくお伝えいたします。
4大認知症とは?
まずおさらいとして、代表的な4つの認知症を簡単に紹介します。
- アルツハイマー型認知症:記憶障害が中心。ゆっくり進行するのが特徴です。
- 脳血管性認知症:脳梗塞や脳出血などのあとに起こることが多く、記憶より「感情の浮き沈み」や「意欲の低下」が目立ちます。
- レビー小体型認知症:幻視や体のふらつき、認知の波があるタイプです。
- 前頭側頭型認知症:感情や行動のコントロールが難しくなるのが特徴。感情の抑制がきかなくなり、強い言葉や自己中心的な行動が見られることもあります。
実はこれら以外にも、認知症になる原因はたくさんあるのです。
意外と多い! 4大認知症以外の原因たち
認知症は「記憶の病気」ではなく「脳の病気」です。
つまり、脳に影響を与える病気や状態なら、すべて認知症の原因になり得るということです。
例をあげると……
- パーキンソン病
- 長年の飲酒(アルコール性認知症)
- 頭のケガ(慢性硬膜下血腫)
- ビタミンB1やB12の欠乏
- 甲状腺の病気(橋本病など)
- 正常圧水頭症(NPH)
- HIVや梅毒といった感染症
- 自己免疫性脳炎(抗NMDA受容体脳炎など)
- うつ病(仮性認知症)
- 抗不安薬や睡眠薬など薬の副作用
【注目】4大認知症に続く2つの認知症
【5番目】パーキンソン病認知症(PDD)
パーキンソン病が進行することで起こる認知症です。
発症してから10年ほどたち、運動症状(手のふるえや筋肉のこわばり)に加えて、注意力や判断力の低下、幻視が見られるようになります。
言葉が出づらく、思考もゆっくりになるため、会話についていけず無口になる方もいます。
また、テーブルの上の影を「虫」と誤認して払ったり、部屋の隅に「人がいる」と話すなど、幻視もよく見られます。
接し方のヒント:
- 一度にたくさん話さず、ゆっくり・短く伝える
- 幻視があっても否定せず、安心感を持ってもらう
- 抗精神病薬が逆効果になることがあるので、薬の扱いや医師との連携は慎重に
【6番目】アルコール性認知症
長年の多量飲酒が原因で、脳が萎縮したり、ビタミンB1の欠乏によるダメージが蓄積して発症します。
新しいことが覚えられず、昔の話ばかりを繰り返すのが特徴です。
しかもその話は「お酒を飲んでいたころ」の話ばかり──
これは記憶障害だけでなく、「自分はこんなに立派だった」と自尊心を保ちたい心理も影響しているといわれます。
金銭管理の失敗や、突然怒り出すなどの前頭葉の障害も見られ、トラブルになりやすいタイプでもあります。
接し方のヒント:
- 否定せず、昔話は「そのとき楽しかったんですね」と受け止める
- 日課を決めて、忘れても自然に行動できる仕組みをつくる
- ビタミン補給や禁酒が重要なので、医師と連携を
実は“治る”こともある!?可逆性認知症とは
認知症といっても、原因によっては“治る”場合もあることをご存知でしょうか?
これは「可逆性認知症」と呼ばれ、原因を取り除けば改善が期待できる認知症なのです。
代表的な例は次の通りです。
| 原因 | 対応 |
|---|---|
| 正常圧水頭症 | 脳脊髄液の流れが悪くなり、脳が圧迫される。シャント手術で脳の圧迫を改善すれば、回復することがある。 |
| 慢性硬膜下血腫 | 頭を打ったあと、ゆっくり血がたまり脳を圧迫。手術でたまった血液を取り除けば回復可能。 |
| ビタミンB1・B12の欠乏 | サプリメントや食事療法で改善することが多い。 |
| 甲状腺機能低下症 | 橋本病などで起こるが、ホルモン治療で改善。 |
| 薬剤性認知症 | 睡眠薬や抗不安薬の副作用として表れます。減薬で回復することも。 |
| うつ病による仮性認知症 | 認知症と似たような症状が現れますが、実際には認知症ではありません。うつ病治療で改善可能。 |
認知症は“種類を知る”ことが大切
『認知症 = アルツハイマー型』というイメージが強いですが、実は原因はさまざま。
「お酒の影響」「脳の病気」「ビタミン不足」「薬の副作用」など、対応次第で改善できるものも少なくありません。
「認知症だから治らない」と決めてしまう前に、正確な診断を受けることがとても大切です。
身近な人に「いつもと違う」サインが見られたら、ぜひ専門医やかかりつけ医に相談してみてください。
その気付きや行動が、その方を救うことになるかも知れません。
身近な人を支えるために、まず「知ること」から
「認知症=アルツハイマー型」と思いがちですが、実際にはさまざまな原因があり、中には生活習慣やビタミン不足、薬の影響など、対処によって改善が期待できるものもあります。
「認知症だから治らない」と決めつけず、まずは正確な診断を受けること。そして「もしかして?」と思ったときに、早めに専門家へ相談することがとても大切です。
家族として介護に関わると、どうしても「何が正解かわからない」「この人は本当に認知症なの?」と悩むことがあります。
そんなときは“知識”が不安を減らし、関わり方を見直すヒントになります。
完璧な対応を目指す必要はありません。
大切なのは、「今、その人にとって何が必要か」を少しずつ考えながら、一緒に歩んでいくことです。
戸惑いながらも寄り添おうとする気持ちは、必ず相手に伝わります。
焦らず、ひとつずつ向き合っていただきたいと思います。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
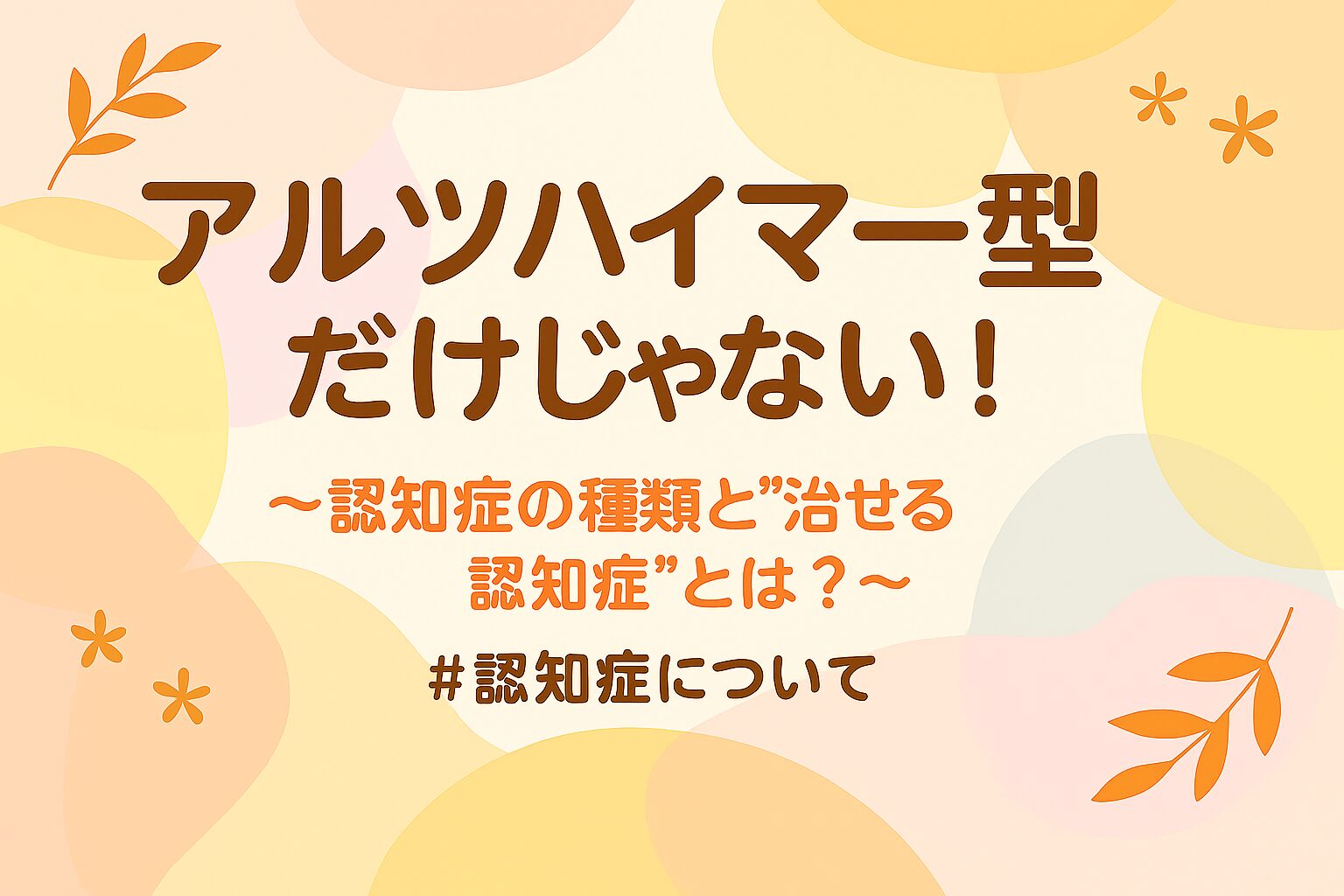
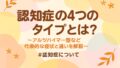
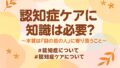
コメント