認知症のタイプを知ると、介護が少しラクになる理由
「もしかしてうちの家族、認知症かも…?」
そんな不安を感じている方にとって、認知症という言葉はとても重たく感じるのではないでしょうか。
よく『認知症 = 物忘れが進む病気』だと思われますが、実は認知症にはいくつかのタイプがあり、それぞれに現れ方や特徴が違います。
そして、関わり方や接し方のコツも変わってきます。
「タイプなんて難しそう……」と思うかもしれませんが、それらを何となくでも知っておくことで、日々の介護の中で「なんでこんな行動をするの?」「私の言い方が悪いの?」と、悩む回数が減っていくことでしょう。
そして、ご本人の気持ちにも、介護する側の心にも、少しだけゆとりが生まれるのです。
この記事では、特に多く見られる「4つの認知症のタイプ」について、介護がはじめての方でも分かりやすいようにまとめました。
ご家族を支えるヒントになれば嬉しいです。
認知症にはどんなタイプがあるの?
認知症と一言で言っても、実はいろいろな種類があります。
その中でも、よく知られていて、多くの人に当てはまる4つのタイプがあります。
| タイプ | どんな特徴がある? |
|---|---|
| アルツハイマー型 | 物忘れがだんだんひどくなるタイプ。 |
| 脳血管性認知症 | 脳梗塞などが原因で、できることとできないことにムラがあるタイプ。 |
| レビー小体型認知症 | 実際にはいない人が見えたり、体がこわばったりするタイプ。 |
| 前頭側頭型認知症 | 性格が変わったように見える。急に怒ったり、非常識な行動をとることがあるタイプ。 |
このあと、それぞれの特徴と、どう関わればいいかを詳しく説明します。
アルツハイマー型認知症
主な原因
アミロイドβというタンパク質が脳に溜まることと、神経細胞の中でタウタンパクというものが異常化し、神経伝達が阻害されることで発症します。
どんな様子?
一番多いタイプの認知症です。
ゆっくり少しずつ、できないことが増えていくのが特徴です。
よくある行動の例
- 同じ話を何度も繰り返す
- 財布や鍵を置いた場所を忘れて探し回る
- 曜日や時間がわからなくなる
接し方のヒント
- 「またその話?」「さっきも言ったでしょ!」と本人の言動を責めず、安心できるように優しく声をかけましょう。
- 写真やカレンダー、メモなどで思い出しやすくする工夫も役に立ちます。
- 本人の不安を受け止め「一緒に探そうね」「何かお手伝いできますか?」と声をかけるだけでも、安心感につながります。
脳血管性認知症
主な原因
脳梗塞や脳出血などで脳の一部が損傷することで、損傷した部分の機能を失ってしまいます。
どんな様子?
脳梗塞や脳出血がきっかけになることが多い認知症です。
できること・できないことが日によって違うこともあります。
よくある行動の例
- 昨日は普通にできたことが、今日はできない
- ちょっとしたことでイライラしたり、怒ったりする
- 後遺症で歩きにくくなる、手足が動かしづらいことがある
接し方のヒント
- 「この前はできたでしょ?」ではなく、「今日は少し体が大変ですか?」「ゆっくりで大丈夫ですよ」と様子に合わせて関わりましょう。
- 生活リズムを整えることも大切です。
- 「ムラがあるのはこのタイプの特徴」と理解しているだけでも、こちらの心がラクになります。
レビー小体型認知症
主な原因
神経細胞にα-シヌクレインというタンパク質が集まってできる『レビー小体』が広がり、発症します。
どんな様子?
実際にはいない人や動物が見える「幻視(げんし)」が出ることがある認知症です。
また、体が固くなる、歩きにくくなるといった身体の変化も特徴です。
よくある行動の例
- 「部屋に知らない人がいる」「虫が見える」などリアルに話す
- 朝はしっかりしているのに、夜になるとぼんやりしてしまう
- 転びやすくなる、動きがぎこちなくなる
接し方のヒント
- 「そんな人いないよ」と否定せず、「怖かったね」「大丈夫だよ」と気持ちに寄り添いましょう。
- 転倒しやすくなるので、部屋の環境を整えることも大切です。
- 日によって調子が違うこともあるので、介護者側も柔軟に対応できるとよいでしょう。
前頭側頭型認知症(ピック病)
主な原因
前頭葉・側頭葉の神経にタウタンパクなどが蓄積することで発症します。また、遺伝的要因が関わることもあります。
どんな様子?
比較的若い人(50〜60代)にも見られる認知症です。
「性格が変わったように見える」のが大きな特徴です。
よくある行動の例
- これまで礼儀正しかった人が、急に怒ったり、失礼なことを言うようになる
- 万引きや食べすぎなど、これまでしなかった行動をする
- 自分のことばかりで、相手の気持ちを考えられなくなる
接し方のヒント
- 「わざとやっている」「反抗している」と思ってしまいがちですが、病気による行動です。
- 頭ごなしに叱るのではなく、周囲の理解と環境を整えることがとても大切です。
- 決まりやルールに縛るより、「症状が起こりやすい場面を減らす」ことで対応できます。
まとめ|タイプを知ると、見え方が変わる
認知症の症状や行動には、それぞれに理由があります。
「なぜこんなことをするのか」「どう関わればいいのか」と悩んだとき、タイプを知っておくと少しだけ安心できます。
どのタイプであっても、ご本人は「安心したい」「わかってほしい」と思っているのは同じです。
大切なのは、その人に合った関わり方を見つけること。
そして、介護する側も一人で抱え込まず、周りのサポートや情報を頼ってください。
「知らないこと」を知るだけで、気持ちがラクになることもあります。
正解のない介護だからこそ、自分なりの関わり方を少しずつ見つけていただきたいと思います。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
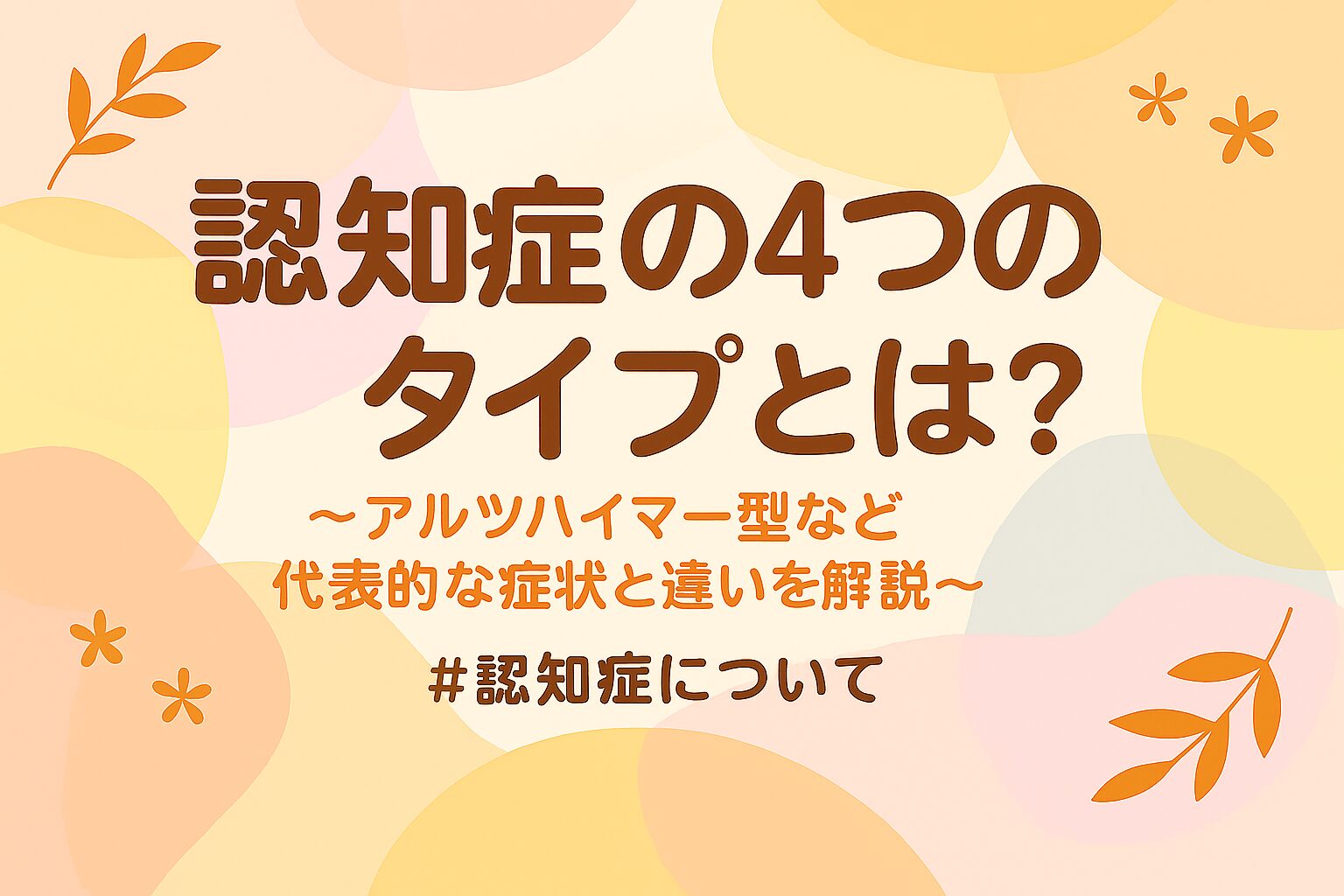

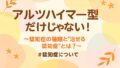
コメント