記憶や判断が難しくなる『中核症状』とは
なぜ怒鳴るのか? なぜ歩き回るのか?
「なぜ急に怒鳴るのか」「なぜ夜中に歩き回るのか」――認知症の方を支援している時、思いがけない『行動』に戸惑った経験はありませんか?
実はその背景には中核症状という『脳の機能低下によって起きる症状』があります。
中核症状とは?
中核症状には、以下のようなものがあります。
- 記憶障害(最近のことを忘れる。新しいことを覚えられない)
- 見当識障害(時間や場所、季節が分からなくなる)
- 理解力や判断力の低下(状況や会話がうまくつかめない)
- 言語障害(言葉が出にくい。言いたいことがうまく伝えられない)
- 失行・失認(手順が分からなくなる。道具の使い方が分からない)
- 実行機能障害(計画を立てて物事を進めるのが難しくなる)
これらは、認知症であれば誰にでもある程度共通して現れるものです。そして、脳の機能が低下しているため『元に戻る』ことは難しいとされていますが、支援の仕方によっては『暮らしやすさ・生活のしやすさ』は大きく変えることが出来ます。
そしてこの中核症状が、いわゆるBPSD(行動・心理症状)の土台になっているのです。
”困った行動”の背景には理由がある
BPSDは、本人の『反応』であり『サイン』である
BPSDは多くの場合、認知症の方本人の『声にならない訴え』『サイン』です。
例えば
- 不安や混乱
- 環境の変化によるストレス
- 人間関係のトラブル
こうした、外からの要因によって発生した『困りごと』に対して、認知症の方が何とかして自分なりに解決・対応しようとして表れる行動がBPSDであり、支援者にとっての”困った行動”になってしまうのです。
行動の裏にある心の声(事例紹介)
徘徊:不安や使命感
Aさんは、夕方になると施設の廊下を歩き回ります。
職員が「どこへ行くんですか?」と尋ねると、Aさんは『子どもを迎えに行かないと』」と答えます。
実際には子どもは成人して独立しているのですが、Aさんの中では『母親としての役割』が強く残っていて、不安や使命感に突き動かされていたのです。
暴言・暴力:もどかしさや痛み
『痛い』『嫌だ』『やめて欲しい』――
そんな思いがあっても、それを言葉で上手く伝えることができないために、暴言や暴力という形で現れることがあります。
介護拒否:恐怖や過去の記憶
『何をされるのか分からない』『過去の嫌な体験がよみがえる』など、恐怖心が『拒否』という反応になって現れることも少なくありません。
※海馬や偏桃体の機能も関係しているのですが、それについては別の記事で詳しくお伝えいたします。
『治す』のではなく『和らげる』ケアを目指して
BPSDへの支援で大切なことは
『どうすれば行動を止められるか』と考えて解決方法を探るのではなく
『どうすれば安心して過ごしてもらえるか?』と考える視点を持つことです。
- 行動の背景を読み取る
- 環境や関わり方を見直す
- 本人の目線で世界を見る
これは『パーソンセンタードケア(本人中心のケア)』という支援の考え方に繋がります。
本当に”困っている”のは誰なのか
支援者にとっては対応が難しいBPSDですが、一番”困っている”のは、認知症を患ってしまった本人です。
- 分かってもらえない
- 安心できない
- 自分の気持ちを伝えられない
その苦しさの中で、必死にサインを出しているのです。
“困った行動”を、責めずに受け止める
重要なことは、認知症の方の行動を『介護者にとって困る行動』ではなく『本人が困り果てた末に取った手段』として捉え直すことです。
そうすると、支援の質も大きく変わると思います。
- なぜこのような行動をするのか?
- 何を伝えようとしているのか?
その理由に寄り添おうとする姿勢が、最大の支援になるのです。
『寄り添う』『分かろうとする』ことが、最大の支援
介護者にとっては支援方法が難しいBPSDですが、本人にとっては『当たり前の反応』であり、一番“困っている”のは、本人自身に他なりません。
私たちにできるのは、その心の声に耳を傾けることです。
BPSDに対する認知症ケアは、そこから始まるのです。
そしてこの考え方や姿勢こそが『本人の笑顔や安心へと繋がる支援』なのです。
支援の現場では「正しい対応」を探すあまり、行動の抑制やマニュアル的な対応に偏ってしまうこともあるでしょう。
しかし認知症ケアにおいて本当に大切なのは、目の前の方が歩んできた人生や、その背景に思いをはせる姿勢ではないでしょうか。
今この瞬間、目の前で起きていることには、その人なりの理由と意味がある。
それに気づくことができれば、関わり方はきっと変わります。
介護の中で「寄り添う」とは、相手の不安や戸惑いに共感しようとする気持ちに他なりません。
それは専門職だけでなく、誰にでも出来る温かいケアの始まりです。
そしてその小さな積み重ねが、本人の安心や尊厳を守ることに繋がっていくのです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
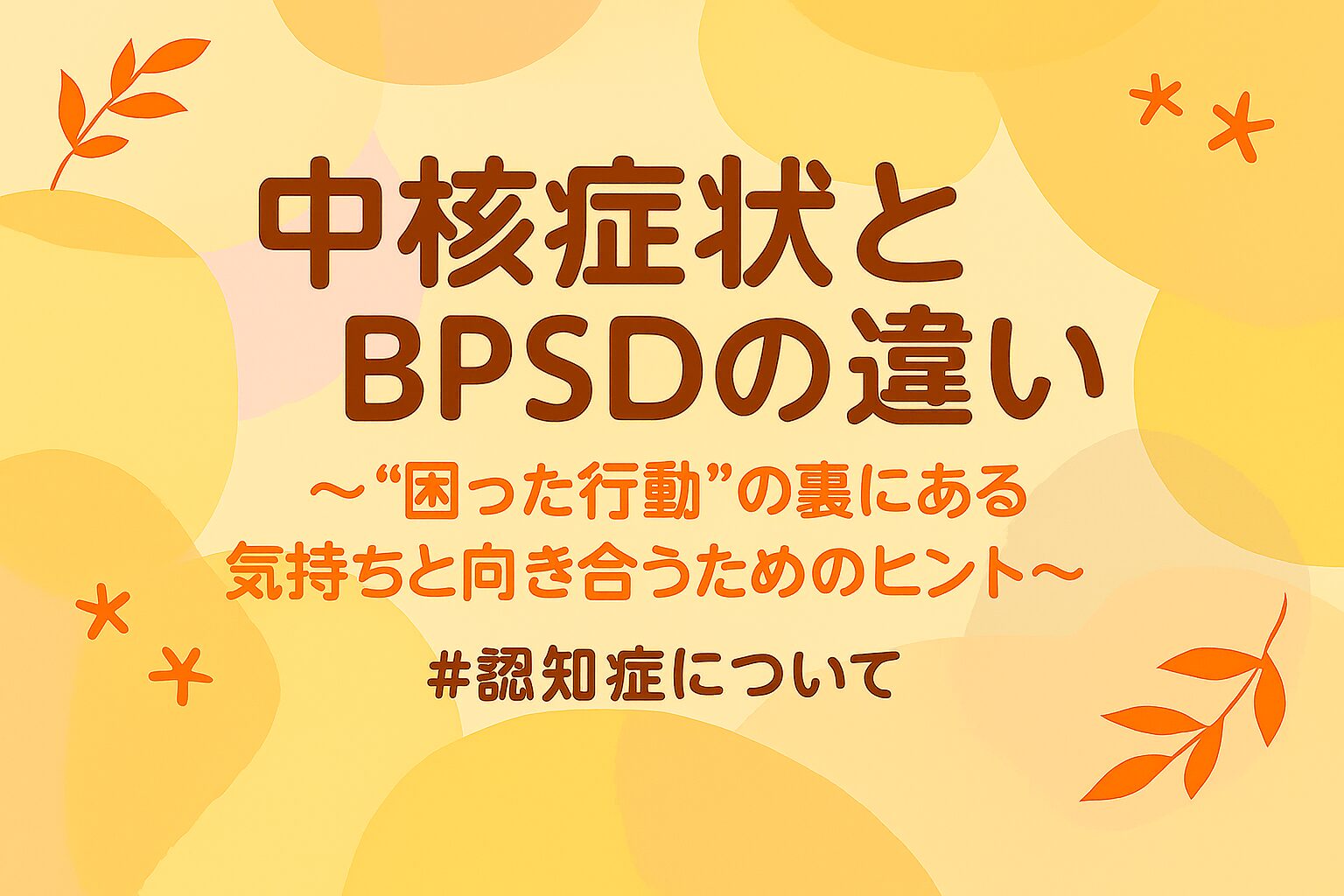
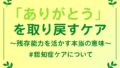
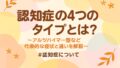
コメント