
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では「まだ食べてない」「トイレに行きたい」など、認知症によって起こる「感覚の誤認」と脳の仕組みについて分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに:よくある介護の戸惑いから
介護現場や家庭で、高齢者がこんな訴えをすることはありませんか?
- 食事を終えたばかりなのに「まだ食べてない」と言い張る
- トイレに行った直後なのに「トイレに行かないと」と焦る
- 皮膚に異常がないのに「かゆい」「痛い」と頻繁に訴える
- 排泄を済ませた直後に「まだ出ていない気がする」と繰り返す
これらは決して珍しいことではなく、多くの介護職員や家族が経験する“困った行動”のひとつです。
しかし、それが「わがまま」「構ってほしいだけ」「気にしすぎ」といった誤解で受け止められると、本人の苦しさは置き去りにされ、関係がぎくしゃくすることもあります。
実はこうした行動の背景には、脳の萎縮による「感覚の誤認」という現象が関係している可能性があるのです。
感覚とは「体が発する信号」と「脳の処理」の二重構造
私たちは、五感や内臓から送られてくるさまざまな電気信号を、脳が受け取り、解釈することで「空腹だ」「トイレに行きたい」といった感覚を得ています。
たとえば、以下のような流れが起きています。
- 血糖値が下がる → 脳が「空腹」と認識
- 胃が満たされる → 「満腹」と判断
- 膀胱に尿が溜まる → 視床や前頭葉が「尿意」として認識
- 腸内に便がたまる → 便意として認識
- 刺激が皮膚に伝わる → 脳が「痛み」「かゆみ」として処理
つまり、感覚とは「身体」だけではなく「脳」というフィルターを通して感じているものなのです。
そして脳が萎縮や変性を起こすと、本来なら正しく処理できるはずの信号を“誤って認識”してしまう現象=感覚の誤認が起こります。
脳の萎縮と感覚の誤認:具体的な仕組み
感覚の“入り口”は壊れていない
多くの方が誤解するのは「感覚がおかしいということは、身体の感覚器や神経に異常があるのだろう」という推測です。
しかし、感覚器(胃、膀胱、腸、皮膚など)や末梢神経が正常でも、脳がその情報を正しく受け取れない・処理できないことで【誤認】が起きるのです。
それには、以下のような脳部位が関係しています。
| 脳の部位 | 主な役割 | 関連する誤認例 |
|---|---|---|
| 視床下部 | 満腹中枢・摂食中枢の調整 | 食べ過ぎ、過食、拒食 |
| 前頭前野 | 意識的判断・抑制機能 | 頻尿、失禁、我慢できない |
| 視床 | 感覚信号の中継地点 | 尿意、便意、痛み、かゆみ |
| 海馬・扁桃体 | 記憶と感情の結びつき | 食事した記憶がない、不安からの訴え |
感覚の誤認が起きる具体例
1. 空腹・満腹の感覚異常
- 食後でも「何も食べていない」と感じて繰り返し食事を求める
- 満腹中枢がうまく働かず、過食や異食に至ることも
- 逆に、空腹感を認識できず、拒食や低栄養のリスクも
➡ 主に視床下部(満腹・摂食中枢)や海馬(記憶の定着)などの変性が関与。
身体からの信号と脳の認識がずれることで「食べた記憶がない」「まだ空腹だと感じる」などの誤認が生じます。
ときに“食べさせてもらえない”という不安や被害感情に結びつくこともあり、否定や制止は本人の混乱を強めます。
穏やかにお茶を出したり、少量の間食で安心感を与える対応が有効です。
2. 尿意・排尿感のズレ
- 尿が溜まっていないのに「トイレに行きたい」と訴える
- トイレに行ったばかりなのにまた訴える
- 尿意がわからず失禁してしまう
- トイレ後に「まだ出てない」と不安になる
➡ 視床~前頭前野の排尿制御回路の異常や、失禁体験による不安が背景に。
膀胱からの信号を正確に判断できなくなります。
さらに「失禁してしまった経験」が不安記憶として残ると、実際の尿意とは無関係に“再発を恐れる”訴えが続きます。
こうした場合、否定よりも「行っておこうか」「心配だね」と受け止める姿勢が安心につながります。
排尿記録を取り、実際のリズムと訴えを照らし合わせると支援の方向性が見えやすくなります。
3. 便意・便失禁の感覚喪失
便意についても、感じる・我慢する・タイミングを選ぶという高度な制御が脳によって行われています。
- 便が溜まっているのに「出そう」という感覚がない
- 排便のタイミングを自分で判断できない
- 突然便失禁が起こる
- 便意を訴え続けるが実際には出ない
- トイレに座ってすぐ「もう出た」と感じるが出ていない
➡ これらは、視床や前頭前野、補足運動野などの萎縮や機能低下によって起こる“排便の誤認”です。
さらに、便失禁は「社会的な羞恥」「自尊心の崩れ」に直結しやすく、介護者・本人の双方に精神的ストレスが強くかかる領域でもあります。
そのため、「感覚の喪失や誤認」という脳の変化を正しく理解しないまま対応すると、誤解や怒り、不信感が生まれやすくなります。
4. 痛み・かゆみの誤認
- 実際に皮膚トラブルがなくても「痛い」「かゆい」と訴える
- 同じ場所を繰り返し掻いて傷つけてしまう
- 介護者が異常を見つけられず困惑する
➡ 視床や感覚皮質の過敏化、あるいは偏桃体との連携異常によって、感情の過去記憶との混線が関与。
過去の痛みや不快感の記憶が誤って再生される場合もあり「また痛くなるのでは」という不安が症状を強める要因になります。
「痛いのね」「ここが気になるんだね」と受け止めつつ、皮膚保護や清潔保持、安心できるタッチケアが有効です。
5. 呼吸困難や体調不良の訴え
- 酸素飽和度が正常でも「息苦しい」「倒れそう」と感じる
- 医学的に説明のつかない体調不良を訴える
➡ 間脳(視床下部)や自律神経系の調節異常により、体の内側感覚(内臓感覚)のずれが影響。
実際には正常でも「息苦しい」「体が重い」と感じてしまいます。
また、記憶障害や不安症状を伴うと「このまま死んでしまうのでは」という強い恐怖感に発展することもあります。
身体的な異常を否定するより「少し休みましょう」「深呼吸してみようか」と安心を優先する対応が望まれます。
感覚の誤認にどう対応するか?
1. 「現実」よりも「感じ方」を尊重する
介護者にとっては「さっき食べた」「さっきトイレに行った」という事実が重要に見えますが、本人にとっては“今そう感じている”ということが現実なのです。
繰り返される本人の訴えを「嘘をついている」「わがまま」と捉えるのではなく、脳がそう感じてしまっているのだと理解することが出発点です。
2. 記録や客観的データで判断する
- 排尿パターンや食事摂取量を記録することで、対応の指針が見える
- 本人の訴えと客観的状況のギャップを「否定」ではなく「補う」視点で見る
3. 感情・不安・記憶障害を読み解く
- 記憶障害が背景にある場合「忘れたことが分からない」ということが多く、さっき食べたこと自体が脳に残っていない
- トイレに行けなかった経験が“強い不安”として蓄積され、繰り返し訴える
こうした場合、身体的な原因よりも「心理的背景」の方が強い動機になっていることが多くあります。
4. 否定しない・受け止める
- 「さっき食べたでしょ?」ではなく――「お腹すいてるんだね」「ちょっとお茶を飲もうか」
- 「トイレ行ったばかり」ではなく――「行っておこうか」「心配だよね」
➡ 本人の感じ方に寄り添いつつ、実際の身体状態に合わせた支援を行う。
5. 同じ訴えが続くときは環境や刺激も調整
- 退屈さや孤独が背景にある場合、違う関わりで注意をそらす
- 食事後の時間にリラックスできる習慣をつくる
- 不安が強い方には「トイレマップ」や「食事カレンダー」で可視化する工夫も
おわりに:感覚の誤認は“嘘”ではなく“脳の現実”
理解が「我慢」を「共感」に変える
介護する側にとって、本人の繰り返す訴えに疲れや苛立ちを感じるのは、決して悪いことではありません。
むしろ、誰しもが経験する自然な反応です。
しかし、その背後に「脳がうまく信号を受け取れていない」という理由があることを理解するだけで、関わり方は大きく変わっていきます。
それを知っているだけで「なぜ分かってもらえないのか」という苛立ちは「どうすれば安心してもらえるか」という考えに変わります。
知識は、介護者に“余裕”を取り戻す力にもなるのです。
「また同じことを言っている」ではなく、
「今、脳がそう感じているのだな」と捉える。
この小さな視点の転換が、ケアを“我慢”から“共感”へと変える第一歩です。
感覚の誤認は、本人にとってはまぎれもない現実です。
その現実を否定するのではなく「どうすれば安心できるか」「どうすれば落ち着けるか」という発想に切り替えることで、介護はもっと穏やかな時間になります。
ときに、それは医療的な正しさよりも“一緒にいる時間の心地よさ”を優先する選択かもしれません。
“感じ方”を大切にするケアへ
たとえば——
「お腹がすいた」と言う人に小さな和菓子を差し出す。
「トイレに行きたい」と言う人に一緒に歩いて行く。
「かゆい」と訴える人の手をやさしく握る。
これらは単なる対応ではなく「あなたの感じ方を大切にしています」というメッセージです。
そのメッセージこそが、本人の安心と尊厳を支える最も確かなケアになります。
介護とは、相手の“現実”を理解し、そこに寄り添う営みです。
脳が変われば感じ方も変わる――それを知ることで、見えなかった苦しさが見えるようになり「なぜこんなことを言うのか」が「そう感じていたんだね」に変わります。
脳の現実を知ることが、介護者をもやさしくする
そしてそれは、介護者自身をもやさしくします。
「分からない人」ではなく「感じ方が変わってしまった人」として見つめ直すとき、
怒りや戸惑いは少しずつ理解と温かさに変わっていきます。
感覚の誤認を知ることは“正しい知識”を得ることだけではなく、
「共感の幅を広げること」でもあるのです。
今日から、目の前の訴えを「脳の現実」として受け止めてみてください。
そこから生まれる一つのやさしい対応が、本人にとっての安心と、介護者自身の穏やかさにつながっていくはずです。
本人の行動を「困ったこと」としてだけ捉えるのではなく、
「脳の変化が引き起こす、本人にとっての“事実”」として捉えることが、
私たちのケアをより優しく、深いものへと導いてくれるのです。
【補足】本記事の参考文献・出典
- Fowler CJ, et al. (2008). The neural control of micturition. Nature Reviews Neuroscience.
― 排尿制御に関わる脳領域の構造とその変化の影響について解説。 - Khan NA, et al. (2014). Altered hypothalamic function in Alzheimer’s disease. Current Alzheimer Research.
― アルツハイマー病における視床下部の変性と食欲・代謝の関係を明示。 - Katsumata Y, et al. (2015). Discrepancy between subjective and objective assessments of urinary incontinence in elderly patients with dementia. Dement Geriatr Cogn Disord.
― 認知症患者の尿意自己申告と実測データの乖離に関する研究。 - Murphy C. (2019). Olfactory and other sensory impairments in Alzheimer disease. Nature Reviews Neurology.
― アルツハイマー型認知症における感覚処理の障害とその影響。 - Winge K, et al. (2003). Constipation and incontinence in Parkinson’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.
― 神経疾患における排便制御の異常と脳機能の関連を論じた先行研究。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
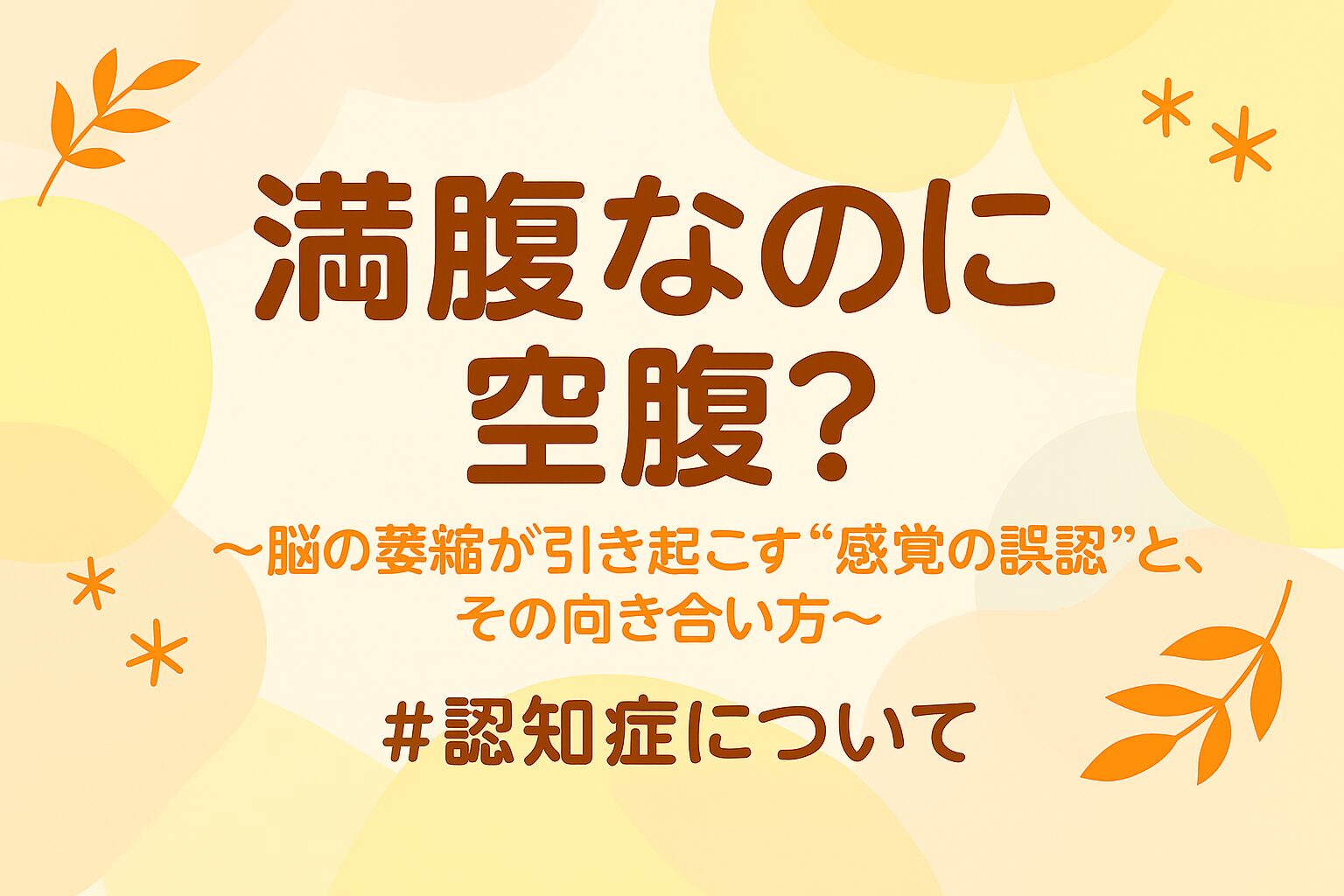
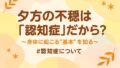
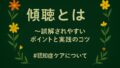
コメント