なぜグループホームでは『残存能力を活かす』のか
「その人の有する能力に応じて役割を持ち、能力の保持に努める」
グループホームでのケアにおいて、この文言は多くの場面で目にしますし、現場でもよく使われています。ですが、改めてこの言葉と向き合うと、一つの疑問が生まれてきます。
なぜ私たちは、入居者様の「残存能力を活かす」必要があるのでしょうか?
単に機能訓練の一環としてでしょうか? それとも、その方の自立を促すためでしょうか?
もちろん、そうした目的もあります。ですが、それだけではないと、私は思うのです。
今回は「残存能力を活かす」という私たち介護者や支援者にとって当たり前の姿勢が、どれほど深く人を支えているのか、そして、私たちが理解しておくべきその意図を、少し丁寧に紐解いてみたいと思います。
歳を重ねるとは、喪失を重ねること
人は年齢を重ねていく中で、さまざまなものを失っていきます。
仕事を辞め、社会とのつながりを手放す。
大切な人――配偶者、友人、時には子ども――との別れを経験する。
体力が落ち、思うように動けなくなる。食べこぼしが増えたり、服のボタンがうまく留められなかったり――その変化は目に見えるものばかりではありませんが『出来ていたことが出来なくなる』というもどかしさが、悔しさと寂しさを強く感じさせるでしょう。
そして、もし認知症を患えば、自分自身が「自分である」という感覚までもがおぼろげになっていきます。
自分の名前や家族の顔があいまいになり、記憶の中で時間が過去と現在がごちゃごちゃになり『今を生きている』という実感が持てなくなってきます。
そして「私は誰?」と、確固たる“自分”すら見失いかけてしまう。
こうした“喪失”は、ひとつひとつが小さくても、積み重なるととても大きな影を落とします。
それは、自分の存在が誰かに必要とされているという実感をも、徐々に奪っていくのです。
感謝される機会の減少
人生の中で、人から「ありがとう」と言われる場面は、役割と共にあります。
仕事をしていた時は、何かを提供したり、成果を出したりすることで「ありがとう」が返ってきた。
家族と生活する中では、料理を作ったり、子どもを育てたり、生活を支える中で自然と感謝の言葉を受け取っていた。
ですが、加齢や病気によって人の役に立つ機会が少なくなっていくと「ありがとう」と言われる機会も、同時に少なくなっていきます。
感謝の言葉が少なくなるというのは、自分の“存在の価値”が見えにくくなるということでもあります。
「自分なんて、もう誰の役にも立たない」
そんな思いが、じわじわと心を蝕んでいくのです。
残存能力を活かすとは、役割を取り戻すこと
「○○さん、よかったらこの洗濯物を畳んでもらえますか?」
「お花に水をあげてもらえると助かります」
「お味噌汁をよそってくれたらうれしいです」
グループホームでは、こんな会話が当たり前のように交わされています。
そんなふうに、その人に応じた“できること”を探し、小さなお願いをしてみる。
もちろん無理強いではありません。あくまでも、その方の残された力に合わせて、自然な形で「役割」を提案するのです。
すると、その人はきっと一生懸命に手を動かしてくれるでしょう。
ゆっくりであっても、慎重であっても、自分なりに取り組んでくれる。
その姿に、私たちは心から「ありがとう」と伝えることができます。
「助かりました」「○○さんがやってくれてうれしいです」
それは、単なる感謝の言葉ではありません。
感謝の言葉であると同時に“あなたがいてくれて良かった”という存在の承認でもあるのです。
「人に感謝できるようになる」という視点
よく、介護職を目指す人がこんなことを言います。
「人から『ありがとう』と言ってもらえるとうれしいから、介護の仕事を選びました」
その気持ちはよく分かります。誰しも『ありがとう』と言われるとうれしいものです。
ですが、実は介護の現場に長く携わるほどに、逆の実感が湧いてくることがあります。
それは――
「人に感謝できるようになる」ことの、ありがたさ。です
何かをやってもらうことが当たり前になってしまうと「ありがとう」は形だけの言葉になりがちです。
以前『感謝の反対は当たり前』という言葉を聞いたことがありますが、全くその通りです。
でも、自分ではできないことをしてもらう。
相手が真摯に自分のことを思って関わってくれる。
そんな時、自然と心から「ありがとう」が言えるようになる。
それは、介護という営みの中で、人としての優しさや思いやりを深めることが出来る――まるで自分自身の人間性が磨かれていくような瞬間なのではないかと、私は感じています。
つまり、残存能力を活かす場面というのは、支援する側が“心からの感謝”を伝えられる場面でもあるのだと、私はそう思います。
だからこそ、それは一方的な支援ではなく、双方向の「関係性」になるのです。
認知症ケアとは、関係性の再構築である
私たちが行っている「認知症ケア」は、決して一方的な奉仕ではありません。
食事介助や排泄介助、入浴介助――どれもただの「お世話」ではなく、相手の尊厳を守る関わりであり、信頼を築き上げていくための過程なのです。
その中でも「残された能力を見つけて、それを活かせる場面をつくる」ということは、その人がもう一度“誰かの役に立てる自分”を取り戻すための、かけがえのない支援です。
そしてそれは、支援者が“ありがとう”を伝えられる喜びでもあります。
喪失を重ねた先に、ただ手を差し伸べるのではなく「あなたにお願いしたい」「あなたが必要なんです」と伝えるケア。
それは“人と人との関係性”をもう一度つくり直していく行為だと、私は思っています。
おわりに
「残存能力を活かす」という言葉には、ただの介護技術を超えた、深い意味があります。
人は歳を重ね、いろいろなものを失っていきます。
けれど「ありがとう」と言われる体験と権利を失ってはいけません。
残された力を見つけて、それを使って誰かに感謝される。
その瞬間にこそ「私はまだ大丈夫」「私にもできることがある」と思っていただけるのです。
そしてその瞬間こそ、支援者である私たちにとっても“人にありがとうを伝えられる”ことの尊さを、もう一度思い出させてくれるのです。
様々な経験を積み重ねてきた目の前のその方が、再び『ありがとう』と言われる機会を持てるように、私たち介護者・支援者が、その最初の一歩を作っていけたら――
こんなに幸せな関わり、こんなに幸せな仕事は、他に無いのではないかと、私は心の底から思うのです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
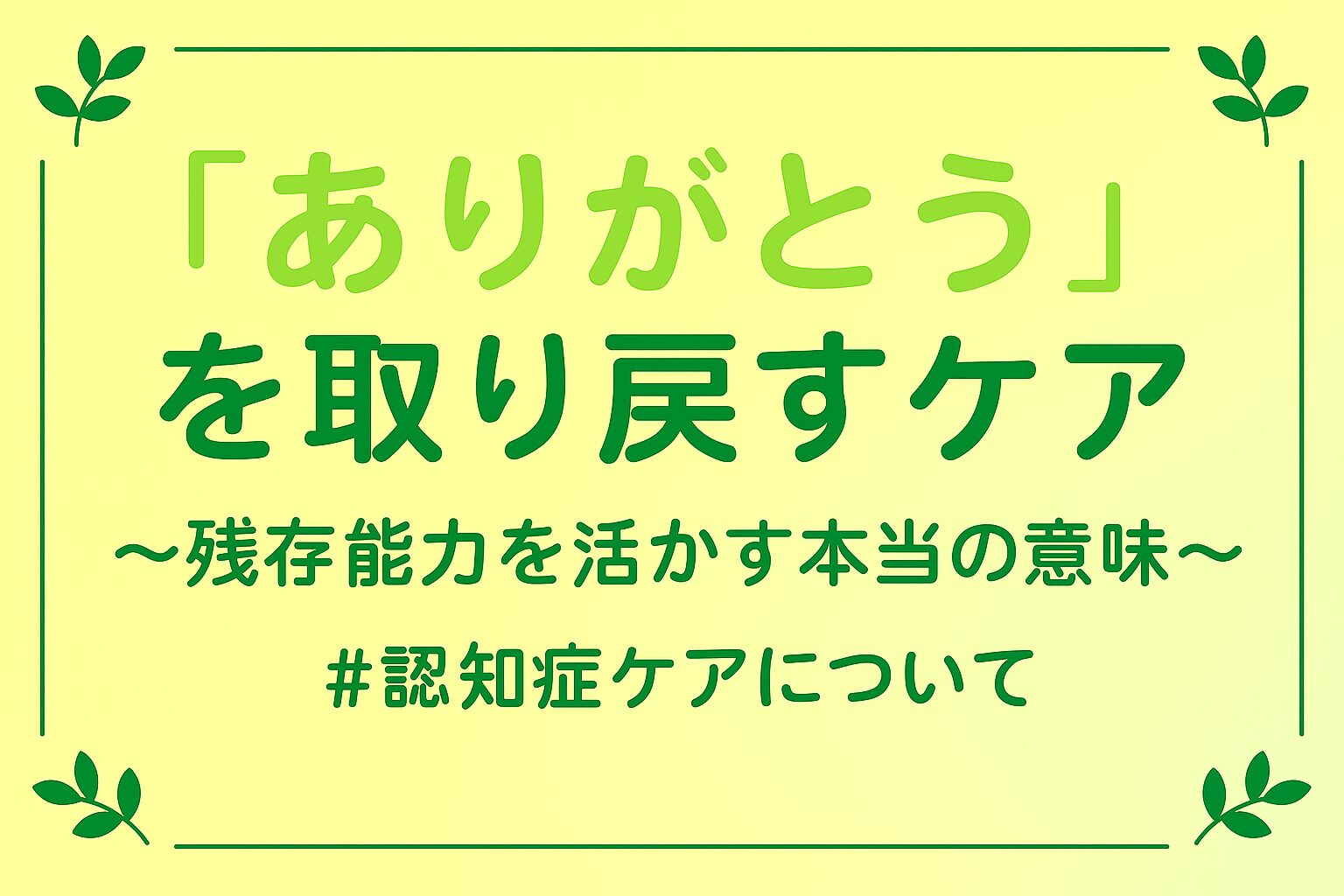
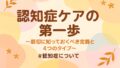

コメント