
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、認知症の方に残る“感情の記憶”とケアへの活かし方、穏やかな日々を支える関わり方の工夫が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
出来事は忘れても、感情は残る――
認知症ケアでは、この“感情の余韻”こそが、次の行動や表情を左右します。
「昨日あんなに怒っていたのに、今日はケロッとしている」
「さっきは理由もなく不機嫌だったのに、急に落ち着いた」
「何が嫌だったのかは覚えていないのに、嫌な気持ちだけ残っているみたい」
認知症の方と関わっていると、こうした場面に出会うことは珍しくありません。
家族介護でも施設介護でも、この“感情だけが残っている”ような様子は印象的で、時に介護者を戸惑わせます。
この記事では、なぜこのような現象が起こるのか、脳のしくみと認知症の進行という視点からやさしく解説します。
そして最後に、日々のケアや接し方にどう活かせるのかを具体的にお伝えします。
出来事の記憶と感情の記憶は別物
人間の記憶にはいくつかの種類がありますが、大きく分けると以下の二つがポイントです。
- エピソード記憶(出来事の記憶)
- 「昨日、友人と喫茶店に行った」というような、いつ・どこで・何があったかを含む記憶
- 主に海馬という脳の部位が深く関わります。
- 感情記憶(気持ちの記憶)
- その出来事を通じて感じたうれしさ、悲しさ、恐怖、安心感といった感情
- 主に扁桃体が関与します。
健康な状態では、海馬と扁桃体が連携し「出来事+感情」をセットで保存します。
しかし、認知症ではこの連携が崩れやすくなります。
認知症で起こる「出来事は消えるのに感情は残る」現象
アルツハイマー型認知症など多くの認知症では、海馬が早期からダメージを受けやすいことがわかっています。
海馬の機能が低下すると「何があったか」という出来事の記憶が短時間で消えやすくなります。
一方で、扁桃体は初期の段階では比較的機能が保たれ、刺激に対する感情反応を残しやすい状態です。
そのため「何があったか」は忘れても「そのとき感じた気持ち」だけが長く残るのです。
よくある場面
- 職員が慌ただしい声で誘導した
→ 数分後には誘導理由を忘れているが、落ち着かない表情や不機嫌さが続く - 家族が少し強い口調で注意した
→ 注意されたことは忘れるが、漠然とした嫌な気分や不安感が残る
科学的な裏づけ
アメリカ・アイオワ大学の研究では、アルツハイマー型認知症の人がポジティブまたはネガティブな映像を見た後、その内容は数分以内に忘れても、感情の変化は30分以上持続することが示されました。*1
つまり「事実は消えても、気持ちは残る」ことが科学的に確認されています。
さらに、軽度認知障害(MCI)や初期アルツハイマー型認知症では、海馬が萎縮しているほど、他人の表情や出来事に対して扁桃体への反応が強まりやすいという報告もあります。*2
これは「扁桃体が物理的に強化される」というより、脳のネットワークのバランスが崩れ、感情ネットワークが相対的に優位になると考えられています。
このように、科学的にも「感情は記憶より長く残る」ことが裏づけられています。
そのため、介護の場面では『何を言ったか』『何をしたか』よりも“どんな気持ちを届けられたか”――そのとき相手が、どんな気持ちになったかを意識することが、とても大切なのです。
*1:Guzmán-Vélez E, Feinstein JS, Tranel D. Feelings without memory in Alzheimer disease. Cogn Behav Neurol. 2014;27(3):117-129.
*2:Kumfor F, et al. Hippocampal atrophy correlates with emotion contagion in mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2013;8(8):880–889.
感情の余韻がもたらすケアの変化
現場で働く中で、私は何度も「感情だけが残る」という現象を目の当たりにしてきました。
ある日、入浴を拒否していたAさん。
最初の職員は時間に追われるあまり、やや急かす口調で誘導しましたがうまくいかず、その後もAさんは落ち着かない表情のまま。理由を尋ねても「わからない」と言いながら、不機嫌さだけが続きました。
そこで交代した職員は、浴室から少し離れた場所で世間話をしながら、ゆっくり手を取り「お湯加減見に行きません?」と提案しました。数分後、Aさんは笑顔で入浴され、その後も穏やかに過ごされました。
これは「声のかけ方」や「雰囲気づくり」が感情の余韻に直結している好例です。
感情の余韻は「ケアの連鎖反応」を生む
感情は次の行動や判断に影響します。
ネガティブな感情が残ると、食事・入浴・排泄など他の場面にも波及し、拒否や不安が増えることがあります。
一方、ポジティブな感情が残れば「ここなら安心」「この人なら大丈夫」という土台ができ、日々のケアが格段にやりやすくなります。
これは家族介護でも同じです。
短い時間でも「笑顔で迎える」「ありがとうを伝える」「寄り添う姿勢」を積み重ねることで、本人にとっての“安心のベース”が厚くなります。
実践的な関わり方の工夫
1. 声のトーン・表情を整える
- 穏やかで安心感のある声
- 柔らかい表情
- 相手のペースに合わせた間
2. 雰囲気を優先する
- 急かさない、遮らない
- 周囲の環境(音・光・人の動き)を落ち着かせる
- 「安全」「安心」の空気を先につくる
3. 説明よりも“感じてもらう”
- 言葉での説明よりジェスチャーや一緒に動く
- 安心感を体感させる
4. ポジティブな感情を積み重ねる
- 褒める、感謝する、小さな成功体験を共有
- 「安心の貯金」を毎日少しずつ増やす
家族介護で意識したいこと
家族介護では、介護者の感情がそのまま本人に伝わります。
苛立ちや強い口調は、出来事が消えても嫌な気持ちだけを残してしまいます。
逆に、短時間でも笑顔や優しいタッチがあれば、良い感情が長く残ります。
「どうせすぐ忘れるんだから」と思ってしまう瞬間もあるかもしれません。
でも、忘れるのは出来事であって、感情は残る――この視点を持つことで関わりの質は大きく変わります。
これからの提案
認知症の方は、出来事は早く忘れても、その時に感じた感情は長く残ります。
海馬(出来事の記憶)と扁桃体(感情の記憶)のバランスが崩れることが、その背景にあります。
これは、嫌な感情も良い感情も同じように残るという意味です。
だからこそ、私たち介護者や家族は「どんな出来事を残すか」よりも「どんな気持ちを残すか」に意識を向ける必要があります。
そしてそれは、特別なことではなく、小さな関わりの積み重ねで十分に実現できます。
今日からできる、小さな工夫
- 朝は笑顔で声をかける
一日のはじまりに安心感を与えると、その後の時間が穏やかに流れやすくなります。 - 不快なやり取りの直後には“安心の上書き”
怖さや不安の感情が残らないよう、短い言葉やタッチで切り替える。 - できたことを一緒に喜ぶ
成功体験は「うれしい感情」を強く残します。 - 話すより感じてもらう
長い説明より、表情や雰囲気で安心を届ける。
まとめ
介護の現場でも、家庭でも、毎日は慌ただしく過ぎていきます。
時には、思わずきつい言葉をかけてしまったり、余裕がなくなることもあるでしょう。
そんなときは「ああ、またやってしまった…」と自分を責めるよりも、これからの時間で安心を積み直せばいいと考えてみてください。
認知症の方は、出来事は忘れても、あなたと過ごしたときの「心地よさ」や「大切にされている感覚」は、ちゃんと心の中に残ります。
だから、たとえ一瞬うまくいかなかったとしても、その後にやさしい言葉や笑顔を添えることで、関係を何度でも修復できます。
介護は「正しい対応」を重ねるだけでなく「良い余韻」を残すことができる仕事です。
そして、その余韻は本人だけでなく、介護する私たちの心も温めてくれます。
今日のあなたの笑顔が、明日の安心をつくります。
その笑顔は、何よりも強いケアの力なのです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
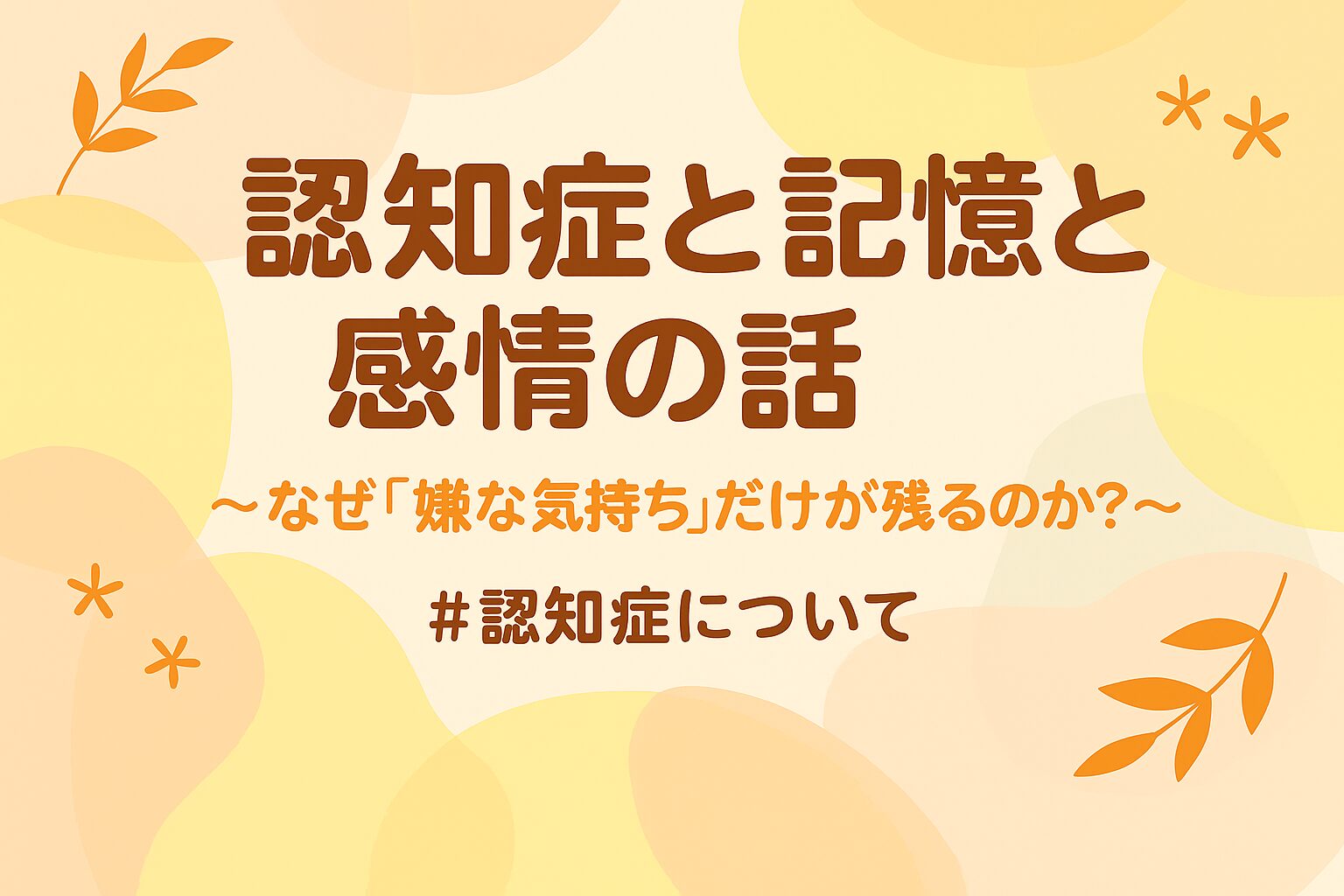

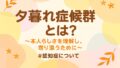
コメント