
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では「傾聴」は“黙って聞く”ことではなく“積極的に関わる”ことだということが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
「傾聴」という言葉の重み
認知症介護の現場では、日々の会話や関わりの中で「どう応答すればいいのか」「本人の言葉にどう寄り添えばいいのか」と悩む場面が少なくありません。その中でしばしば強調されるのが「傾聴」という姿勢です。
傾聴は、介護において非常に重要なテクニックの一つですが、実際には誤解されていることも多いのが現状です。
「とにかく否定も肯定もせず、本人の意見を受け止めること」
「ただ静かに耳を傾けること」
——こうした理解をしている人もいるかもしれません。しかし、それだけでは本来の傾聴の意味を十分に捉えているとはいえません。
傾聴の本質は「積極的に聞くこと」
実際には、傾聴とは「何も返さなくてよい」「本人の気持ちに同意しなくてよい」という消極的なものではなく、相手の言葉や感情に寄り添いながら“積極的に聞く”姿勢が求められます。英語では「アクティブリスニング(Active Listening)」と呼ばれることが、その意味を端的に表しています。
それでは、この「積極的に聞く」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。
本記事では、傾聴の誤解を整理しつつ、介護現場で活用できるテクニックとその根拠、そして実践する際の注意点をわかりやすく解説していきます。
傾聴の誤解:ただ黙って聞くだけではない
まず整理したいのは「傾聴=受け身で黙って聞くこと」という誤解です。
確かに、相手の言葉を遮らずに聞くことは大切ですが、それだけでは「ただそこにいる人」にすぎません。本人からすれば「本当に聞いてくれているのだろうか?」「理解されていないのではないか?」と不安を感じることもあります。
傾聴の本質は「言葉の背後にある感情や思いを理解しようと努めること」です。聞いている姿勢を相手に伝え、相手自身が自分の気持ちを整理したり安心できるように関わることが重要なのです。
言葉の裏にある“気持ち”を聴くということ
傾聴が難しいのは、言葉を「聞くこと」自体よりも、その裏にある“気持ち”を汲み取る力が求められるからです。
たとえば「帰りたい」と言う方がいたとき、多くの職員は「今は帰れません」と正直に伝えよようとするでしょう。間違ってはいませんが、それでは相手の“本当の思い”に届きません。
この言葉の裏には「家族が恋しい」「安心したい」「ここが自分の居場所だと思えない」といった、不安や孤独、喪失の感情が隠れていることが多いのです。
傾聴とは、その表面的な言葉を「訂正」することではなく「気持ちの声」に耳を傾けること。
「家族のことが気になりますよね」「急に寂しくなってしまいましたか」と言葉で寄り添うことで、本人の心が少しずつほどけていきます。
つまり傾聴とは“正しい返答”を探す技術ではなく、相手の存在、今の気持ちを認める姿勢の積み重ねです。
この姿勢があると、たとえ会話が途切れても、沈黙の時間が「安心の時間」に変わっていきます。
「積極的に聞く」とはどういうことか?
積極的に聞くとは、単なる受け身ではなく、相手の話に対して理解と関心を示すことです。ポイントは次の3つに集約できます。
- 相手の言葉を正確に受け止めていることを伝える
- 感情や思いに共感しようとする姿勢を示す
- 本人が自分の気持ちに気づき、安心できるように関わる
これらを具体的に実践するために、いくつかのテクニックがあります。以下で代表的な方法を解説します。
傾聴の具体的なテクニックと根拠
時間ではなく“意識”で変わる関わり
介護の現場で傾聴を実践する上で、多くの職員がぶつかる壁があります。
それは「忙しい中で一人ひとりの話を丁寧に聞く余裕がない」という現実です。
食事介助、排泄介助、記録、送迎——分刻みのスケジュールの中で、ゆっくりと向き合う時間を確保するのは簡単ではありません。
それでも傾聴が大切なのは、それがケアの“質”を左右する土台だからです。
たとえば、落ち着かない利用者への声かけが「早く座ってください」から「何か気になることがありますか?」に変わるだけで、関係性が変わります。
ほんの数秒でも「気持ちを受け止めよう」という意識があると、相手の反応や表情がやわらぐのです。
傾聴は、時間をかけることではなく「意識の向け方」を変えること。
「この方はいま何を感じているのか」「どうしてその言葉を選んだのか」と想像するだけでも、関わり方が違ってきます。
そしてこの意識は、チーム全体の空気を穏やかにする力を持っています。
一人の職員が傾聴的な姿勢を保つことで、他の職員も自然とそれを見習い、施設全体が落ち着いた空気に変わっていく——そうした変化を、現場では何度も目にします。
① おうむ返し(リフレクティング)
相手の言葉を繰り返したり、少し言い換えて返す方法です。
例:「今日は疲れた」と言われたら「疲れたんですね」と返す。
- 効果:相手に「ちゃんと聞いてもらえている」と感じてもらえる。認知症の方は不安を抱えやすいため、こうした確認が安心感をもたらす。
- 根拠:心理療法でも用いられる基本技術で、信頼関係構築に有効とされている。
② 感情のラベリング(感情の明確化)
言葉にされていない感情をこちらが言語化して伝える方法です。
例:「帰らなきゃ」と落ち着かない方に「ご家族のことが心配なんですね」と返す。
- 効果:本人が自分の感情を客観的に把握でき、不安や混乱が整理されやすい。
- 根拠:心理学では「感情をラベル化するだけでストレスが軽減される」と報告されている。
③ 要約(サマライジング)
相手の話をまとめて返す方法です。
例:「今日は買い物に行って、友達と話して、楽しかったのね」。
- 効果:長く散漫な会話を整理して提示することで、本人が理解しやすくなる。
- 根拠:カウンセリング技法の一つで、相手の自己理解を助ける。
④ 沈黙の活用
あえてすぐに返答せず、沈黙を保つことも傾聴の一部です。
- 効果:相手が自分のペースで考えたり話を続けたりできる。
- 根拠:急かされない安心感を生む。特に認知症の方は言葉を探すのに時間がかかるため有効。
⑤ 非言語的サイン
うなずき、視線、表情、姿勢なども「聞いていますよ」というメッセージになります。
- 効果:言葉が出にくい方にも安心感を与える。
- 根拠:コミュニケーションの大部分は非言語で行われるとされ、特に認知症介護においては重要性が増す。
傾聴がもたらす効果
傾聴は単に「よく話を聞いてあげる」ことにとどまらず、さまざまな効果をもたらします。
- 心理的安心:「理解してもらえた」という安心感が、不安や混乱をやわらげる。
- 信頼関係の構築:職員や家族を「自分をわかってくれる存在」と認識し、協力的な関係が築きやすくなる。
- BPSD(行動・心理症状)の緩和:不安や孤独感の軽減は、徘徊や興奮といった症状の緩和にもつながる。
- 自己表現の支援:言葉にしづらい思いを引き出すことで、本人の尊厳を守る。
傾聴でやってはいけないこと
傾聴のつもりでも、次のような対応は逆効果になることがあります。
- すぐにアドバイスする
→ 話を「解決してあげること」が目的になり、本人の気持ちを置き去りにしてしまう。 - 話を遮る・急かす
→ 認知症の方は言葉を探すのに時間がかかることが多く、遮られると自信を失う。 - 否定や訂正ばかりする
→ 「違うよ、それはこうだよ」と事実を正すことが本人にとっては安心ではなく混乱を生む場合がある。 - 上の空の相槌
→ 形式的な「はいはい」では逆に不信感を与えてしまう。
傾聴は、自分自身へのケアでもある
傾聴を難しくしているもう一つの要素は「自分の感情」との付き合い方です。
相手の話を聞きながら「それは違う」「自分も大変なのに」と心の中で反応してしまうのは、人として当然のことです。
しかし、傾聴の目的は“相手を変えること”ではなく“相手の世界を理解すること”にあります。
感情を押し殺すのではなく、介護者自身も「私はいま、こう感じた」と気づくだけで十分です。
その“気づき”が、介護者自身の冷静さと優しさを保つ支えになります。
傾聴とは、相手だけでなく自分自身の心にも耳を傾ける行為なのです。
介護の現場では、他者の気持ちを理解する力と、自分の気持ちを整える力は、表裏一体です。
どちらかが欠けると、共感は「共倒れ」に変わってしまうこともあります。
だからこそ、傾聴は“技術”であると同時に“ケアする人の生き方”にも通じる大切な姿勢だといえます。
介護現場での応用例
- 「帰らなきゃ」と言う方 → 「ご家族が気になるんですね」と感情をラベル化しつつ「今はここで一緒にお茶を飲みましょう」と安心につなげる。
- 「寂しい」と漏らす方 → 「寂しい気持ちなんですね」と受け止めた後「私も一緒にいますよ」と具体的な安心を伝える。
こうした小さな積み重ねが、介護の質を大きく左右します。
おわりに
傾聴は「ただ聞く」ことではなく「積極的に聞く」ことです。本人の言葉や感情に寄り添い、理解しようとする姿勢そのものが、安心や信頼を生み出します。
認知症介護において傾聴は、時に薬以上の効果をもたらすともいわれます。
新人職員にとっては難しく感じられるかもしれませんが、「話をさえぎらない」「気持ちを言葉にして返す」「理解していることを伝える」——この3つを意識するだけでも大きな一歩になります。
誤解を解き、本来の意味での傾聴を実践することは、介護者にとっても本人にとっても「安心できる関係」を築く礎となるでしょう。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
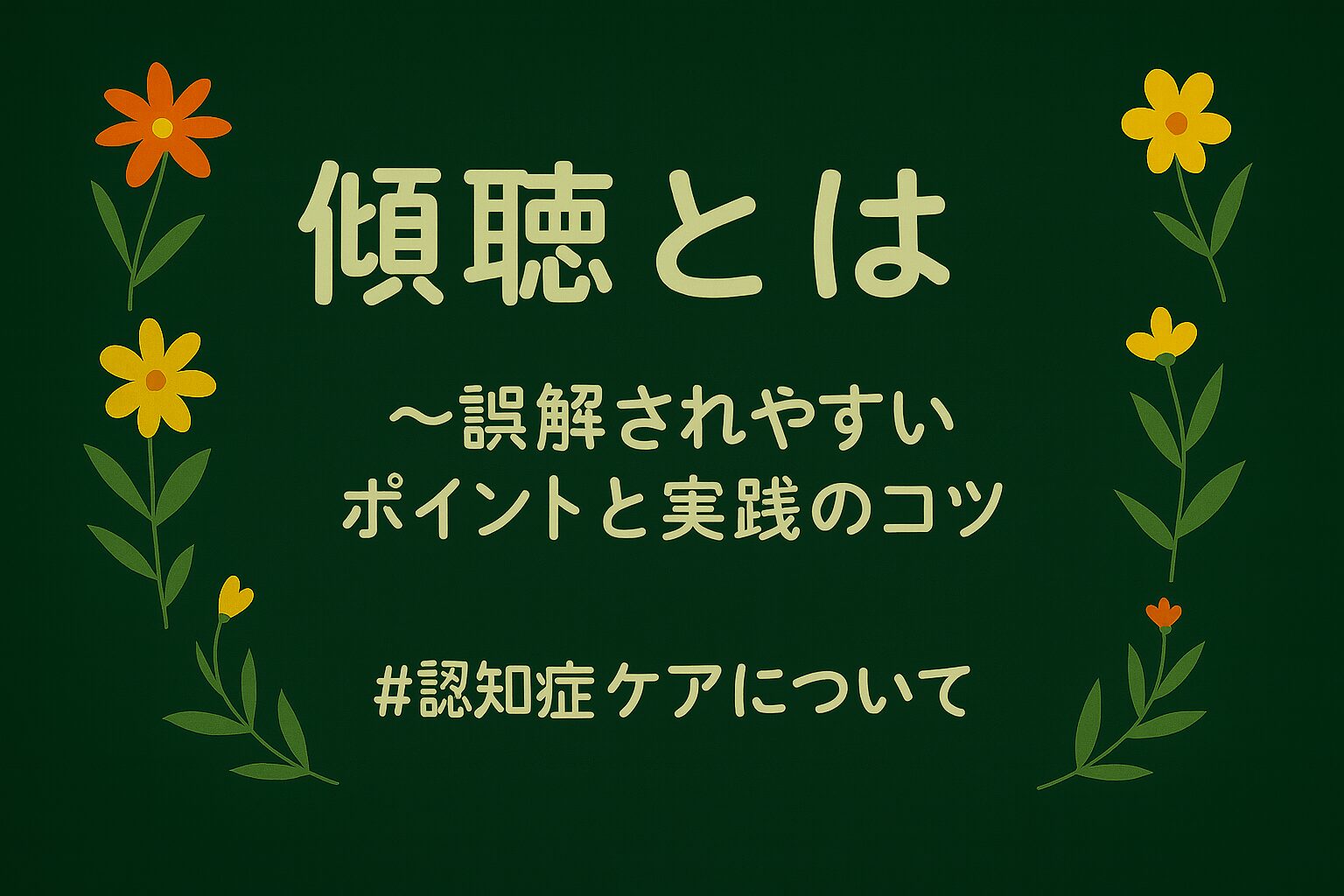
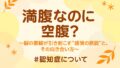

コメント