
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、夕方に不穏になるのは認知症の症状だけではなく、高齢者の体に起こる自然な変化やエネルギー不足も関係していることが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
「夕方になると落ち着かない」「急に帰りたがる」「ソワソワして歩き回る」「誰かを探しているように見える」
認知症の方のケアに携わる中で、こうした“夕方に突然落ち着かなくなる”という状況に戸惑った経験がある方は、多いのではないでしょうか。
これは一般に「夕暮れ症候群(サンダウン症候群)」と呼ばれる現象で、認知症の方に多く見られる行動・心理症状(BPSD)の一つとされています。
しかし私は最近「これは本当に認知症“だけ”が原因なのだろうか?」と感じるようになりました。
実際、認知症でない高齢者にも、夕方になると混乱や疲労、不安が強まる方は少なくありません。
本記事では、夕方の不穏は“認知症の症状”に限定されるものではなく“高齢者の身体的リズムとエネルギー”に根差した現象でもあるという視点で、ケアを見つめ直してみたいと思います。
夕暮れ症候群とは
「夕暮れ症候群」とは、夕方から夜間にかけての時間帯に、認知症の方に見られる混乱・興奮・不安・帰宅願望などの行動が顕著になる現象を指します。
代表的な言動としては
- 「子どもが帰ってくるから迎えに行かないと」
- 「家に帰らないと」
- 「何か忘れてる気がする」
- 「ここにいたくない」
- 歩き回る、落ち着かない、怒りっぽくなる など
これらの行動は「問題行動」や「症状」としてラベルが貼られやすい状態ですが、背景には高齢者の体の変化や、暮らしのリズムのズレがある可能性も高いのです。
帰宅の訴えに込められた“気持ち”に目を向ける
夕方になると「家に帰らなきゃ」「お母さんが待ってる」といった言葉を繰り返す方は少なくありません。これは単なる“徘徊”や“症状”ではなく、不安や疲労による混乱の中で、安心できる場所や人を求めているとも受け取れます。
帰宅願望の背景には「自分の居場所を確認したい」「誰かに会いたい」「昔の生活リズムが体に残っている」といった複雑な感情が絡んでいることもあるのです。
こうした言葉が出た時「ここがあなたの家ですよ」と正面から否定するよりも、気持ちに寄り添った対応が、安心感や信頼関係を築く第一歩となるでしょう。
実は「夕方に不穏になりやすい」理由が、高齢者の体にはある
ここでは、認知症の方に限らず高齢者に共通する“体の仕組み”に注目して、夕方の不穏がなぜ起きやすいのかを考えてみます。
① 脳のエネルギー源が不足する
私たちの脳は、主にブドウ糖(グルコース)をエネルギー源として動いています。特に高齢者では、食事量の低下や代謝機能の変化により、午後~夕方にかけて血糖値が下がりやすい傾向にあります。
高齢者の方は食事量の個人差が大きく、特に咀嚼する力や食欲、飲み込みの状態などによって食べられる量が少なくなりがちです。
このような要因で昼食の摂取量が減った場合、午後の活動に必要なエネルギーが十分に補給されず、夕方にかけて低血糖状態に近づくケースもあります。
「15時のおやつ」は、このエネルギーの空白を埋め、脳と体の活動を支える“補助食”の役割も果たしているのです。
- 低血糖が起きると、集中力の低下、混乱、怒りっぽさ、不安定な感情が出やすくなることは医学的に広く知られています。【1】
- 認知症高齢者では、低血糖による「警告症状」を自覚しづらく、行動の変化として現れやすいとされています。【2】
- 大規模研究では、重度の低血糖エピソードを経験した高齢者は、認知症の発症リスクが最大2倍以上に上がるというデータもあります。【3】
つまり「夕方に不穏になる=認知症だから」ではなく「脳のエネルギー不足が原因で、感情や行動が不安定になる」という見方もできるのです。
② 生活リズムと体内時計のズレ
人間の体には、日内リズム(サーカディアンリズム)と呼ばれる、24時間周期の生体リズムがあります。
高齢になるとこのリズムが乱れやすくなり、午後~夕方にかけて眠気や疲労感が強く出る人が増えます。
また、夕暮れ時は暗くなり、視覚刺激が減ることで不安感が強まることもあります。
- 高齢者では、メラトニン(睡眠に関わるホルモン)分泌のリズムが前倒しになる傾向があり、夕方に眠気が出やすくなると報告されています。【4】
- 認知症のある高齢者では、このリズムの乱れがさらに顕著で、日没とともに不安定さが増すケースが多くみられます。【5】
だからこそ「15時のおやつ」が大事
ある医師が「夕方に不穏になる方には、15時頃に糖分を含む間食を摂ってもらうと落ち着くことがある」と話していたのを聞いたことがあります。
実際に、私が働く施設でも
- 15時のおやつを軽視せず、エネルギー補給と楽しみの時間として大切にしている
- 果物、バナナ、甘酒の他、それぞれの好物などを工夫して取り入れている
- 飲み物も使って、水分+糖分の両方を補う
このような工夫を行うことで、夕方の不穏が和らいだ事例もあります。
エピソードから見る夕方の不穏
ある女性の入居者の方は、15時を過ぎると必ずそわそわと歩き回り「お母さんが迎えに来るから外で待ってる」と言って玄関に立っていました。
最初は「不穏行動」として見られていましたが、ある日、本人の好物だった甘酒とカステラをティータイムの形で提供したところ、座ってゆっくり過ごせる時間が生まれたのです。
その後も、おやつの時間を“楽しみの場”として丁寧に演出し「今日は◯◯さんの好きなものですよ」と声かけを工夫したことで、不安そうな表情が少しずつ減っていきました。
このように「何を食べるか」と同時に「どんな気持ちでその時間を過ごしてもらうか」を大切にすることが、夕方の不穏を和らげる支えになると感じます。
15時おやつの工夫例
| おやつ | 特徴 |
|---|---|
| 果物(バナナ、みかん) | 自然な糖分+食物繊維 |
| プリン・ゼリー | 嚥下が不安な方にも取り入れやすい |
| 甘酒(ノンアルコール) | 栄養価が高く、腸内環境にも良い |
| 小さなおにぎり | エネルギー補給+安心感 |
| カステラやビスケット | 少量でも満足感あり |
ケアの視点:夕方の不穏を“症状”ではなく“サイン”として捉える
夕方の不穏を予防するには、もちろん「おやつを出せば良い」という単純な話ではありません。
糖分補給はあくまで“手段のひとつ”であり、その人のリズム・疲れ・心の動きに気づくまなざしこそが大切です。
例えば「おやつの時間なのに手をつけない」「急に席を立ってソワソワする」といった何気ない変化に対して「どうしたのかな?」と丁寧に向き合う姿勢が、その後の不穏を防ぐきっかけになることもあります。
また、おやつの場面を“楽しみの時間”として丁寧に演出することは、安心感や一体感を生み、夕方の不安感を和らげる空気づくりにもつながります。
“何を食べるか”ではなく“どんな気持ちで過ごしてもらうか”を考える視点が、より穏やかな夕暮れのケアに近づく鍵になるのではないでしょうか。
夕方に起こる不穏な行動を「認知症だから仕方ない」と片づけてしまうのではなく、
- 「疲れているサインかもしれない」
- 「お腹が空いて混乱しているのかも」
- 「不安を言葉にできず、行動に出ているのかも」
と考えるだけで、ケアの質は大きく変わります。
高齢者の体の基本を理解することは、本人の“つらさ”に気づくための第一歩です。
「不穏」が広がらないために大切なこと
不穏な行動が起こると、つい職員や家族も「なんとかしなければ」と焦り、対応が慌ただしくなってしまうことがあります。
しかし、そうした周囲の緊張感や焦燥感は、本人の不安や混乱をさらに強める要因にもなりえます。
たとえ行動としては落ち着きがなく見えても「なぜそうなるのか」を冷静に捉え、あえて一呼吸おいて関わることが、状況を穏やかにすることもあります。
ケアとは、相手の感情だけでなく、自分たちの感情との付き合い方も問われる営みなのかもしれません。
最後に:夕暮れ時は、見守る側の感性が問われる時間
夕方という時間帯は、光も音も減り、気温も変わり、空気が変化する独特の時間です。
そんな中で、本人の体調や不安が“症状”のように見えるかもしれません。
しかし、私たちが「これは認知症だから」と決めつける前にできることは、まだたくさんあるのではないでしょうか。
夕暮れに寄り添うケアとは、
“症状を見る目”ではなく“背景を見るまなざし”を持つこと。
それこそが、高齢者ケアの本質なのかもしれません。
すべてを完璧に理解することはできなくても「なぜ今この行動が起きているのか?」と一度立ち止まって考えてみることが、より良いケアへの第一歩に繋がります。
小さな気づきが、穏やかな夕暮れを支える大きな力になるかもしれません。
参考文献・出典
【1】Briscoe VJ, Davis SN. Hypoglycemia in type 1 and type 2 diabetes: physiology, pathophysiology, and management. Clin Diabetes. 2006
【2】田中昌彦 他. 認知症高齢者における低血糖時の行動変化の特徴. 日本老年医学会雑誌 2015
【3】Whitmer RA et al. Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA. 2009;301(15):1565–72.
【4】Duffy JF, Czeisler CA. Age-related change in the relationship between circadian period, circadian phase, and diurnal preference in humans. Neurosci Lett. 2002.
【5】国立長寿医療研究センター. サンセット症候群と高齢者の生活リズム.
【6】Caregiving in dementia: Sundowning. Alzheimer’s Association.
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
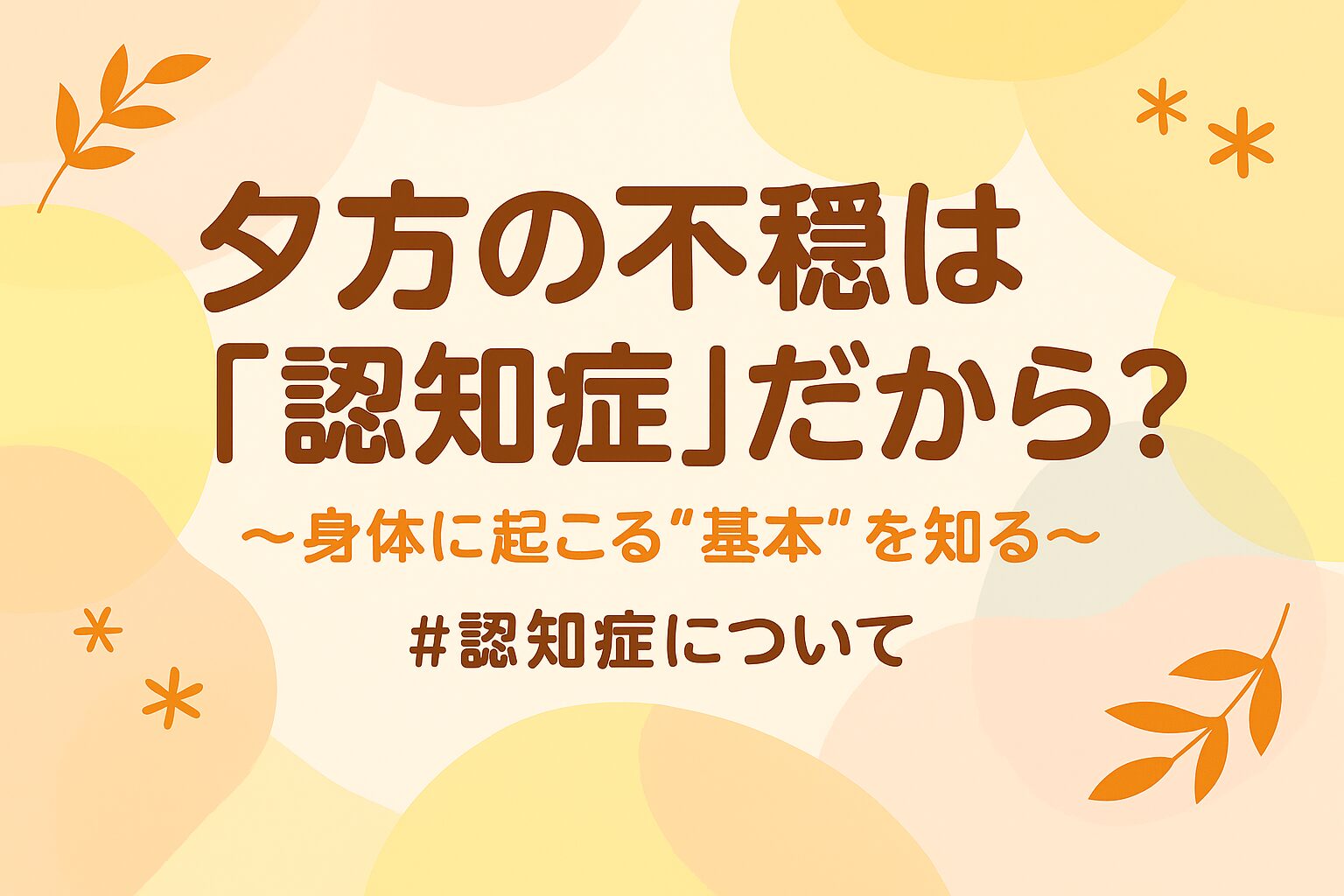
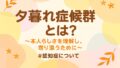
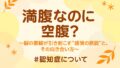
コメント