
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、夕暮れ症候群の原因と背景を整理し、家族や職員がどのように理解し寄り添えばよいかが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
認知症の方と関わる中で、夕方になると落ち着かなくなったり「家に帰る」「子どもが心配だから迎えに行かないと」と言い出したりする場面に出会ったことはないでしょうか。
これは「夕暮れ症候群(サンダウン症候群)」と呼ばれる現象で、多くの介護者を悩ませる行動・心理症状(BPSD)の一つです。
一般的には「問題行動」として受け止められることもありますが、果たして本当に、そして誰にとって「問題」なのでしょうか。
本記事では、夕暮れ症候群の原因や背景を整理しつつ「本人にとっての意味」に光を当てたいと思います。
在宅で介護をされているご家族、新しく現場に立った介護職員の方々にとって、対応のヒントになれば幸いです。
夕暮れ症候群とは何か
夕暮れ症候群とは、夕方から夜にかけて認知症の方に見られる混乱や不安、帰宅願望、多動などの行動を指します。
特徴的なのは「日中は比較的落ち着いているのに、夕方になると急に落ち着かなくなる」ことです。
例えば
- 家に帰ろうとして玄関に向かう
- 「子どもが帰ってきていない」と心配する
- 「迎えが来ているはず」と外に出ようとする
- イライラしたり、不安が強くなったりする
といった様子が見られます。
そして重要なことは、これらは単なる「困った行動」ではなく、その方がこれまで歩んできた人生や役割と深く結びついているということなのです。
夕暮れ症候群が起きる原因
夕暮れ症候群の要因は一つではなく、環境的・身体的・心理的な要因が複雑に絡み合っています。
(1) 環境の変化
- 夕方になると光が弱まり、部屋が暗くなることで不安感が増す。
- 職員交代や家族の生活リズムの変化により、落ち着かない雰囲気が伝わる。
- 外から聞こえる車の音や人の足音が「帰宅時間」を連想させ、気持ちをかき立てる。
- テレビのニュースや、夕食準備の音・匂いが刺激となり「自分も動かなければ」と焦りが生じる。
(2) 体内リズムの乱れ
- 認知症の影響で体内時計(概日リズム)が乱れ、夕方以降に混乱が強まりやすい。
- 睡眠障害や昼間の活動不足も、リズムの乱れに影響している。
- 日中に十分な日光を浴びられず、昼夜の区別がつきにくくなる。
- 昼寝の時間や食事時間が日によってバラつくことで、体のリズムがさらに不安定になる。
(3) 心理的要因
- 一日の疲れが出やすい時間帯。
- 「帰宅時間」「家族の時間」という記憶が強く呼び起こされる。
- 周囲が慌ただしくなることで「自分だけが取り残されている」と感じてしまう。
- 慣れない施設の環境では「ここはどこだろう」「家に帰らなきゃ」という不安が高まりやすい。
(4) 生活史に基づく役割意識
- 女性なら「子どもにご飯を食べさせなければ」
- 男性なら「仕事を終えて家に帰らなければ」
- 元々の仕事によっては『明日の準備を』と机に向かおうとしたり『日が暮れる前に片付けを』と外に出ようとする。
このように、夕暮れ症候群の背景には環境刺激・身体リズム・心理的記憶・生活史がそれぞれ影響し合っています。
どの要因にも“その人らしさ”が表れていることを理解することが、寄り添いの第一歩です。
一般的な捉えられ方 ――「問題行動」として見られがちな夕暮れ症候群
介護現場では、夕暮れ症候群はしばしば「多動」「帰宅願望」「妄想」といったBPSD(行動・心理症状)の一つとされます。
事実、在宅介護の家族にとっても、職員にとっても、夕方の混乱は心身の負担になり、時には事故や介護拒否につながるため「困った行動」として扱われがちです。
しかし、その一方で大切なのは、その人にとっての意味ある行動を「問題行動」というラベルを貼って終わらせないことです。
夕暮れ症候群の本質 ―本人らしい生活の延長
夕暮れ症候群で見られる行動は、本人にとっては「自然な行動」です。
- 子どもが帰ってきていないことを心配する母親
- 仕事が終わったから帰宅しようとする父親
- 「自分の家に帰りたい」と願う高齢者
これらは「過去の世界に生きている」のではなく、その人の生活史と役割が今も心の中で続いている証拠です。
つまり夕暮れ症候群とは「その人が自分らしく生き続けている姿」といえるのです。
「理解=我慢」ではない——支える側を守るケア
とはいえ、そうした「本人らしさ」を理解しようと頭では分かっていても、実際に目の前で何度も「帰る」「帰る」と繰り返されると、介護する側は疲れや無力感を覚えるものです。
特に夕方は、介護者自身も一日の疲れが出てくる時間帯であり、他の利用者への対応や家事、夜勤の引き継ぎなどが重なることもあります。
そんな中で、何度も同じ説明をしなければならない状況は、誰にとっても大きなストレスです。
ここで大切なのは「理解する=我慢する」ではないということです。
介護者自身の感情を押し殺す必要はなく「今日は少し距離を取ろう」「職員同士で協力して交代しよう」という選択も、立派なケアの一部です。
本人の安心を支えるためには、支える側が心の余裕を持つことが欠かせません。
夕暮れ症候群への対応は、本人だけでなく、介護者自身をどう守るかという視点も大切にしていきたいところです。
在宅介護の家族に向けて ――対応のヒント
在宅で夕暮れ症候群に直面すると、家族はどうして「なぜ分かってくれないの」と思ってしまいます。ここで重要なのは、本人にとっての現実を否定しないことです。
具体的な工夫
- 部屋を明るくして、不安を和らげる。
- 「ご飯の支度はできているから大丈夫だよ」と安心させる声かけ。
- 「少し一緒にお茶を飲んでから行こう」と気持ちを切り替える。
- 「今日はお休みだから帰らなくても大丈夫ですよ」と役割を尊重しつつ安心を与える。
家族自身も、完全に「止めよう」とするよりも「本人の思いを理解して受け止める」という思いで関わることで、心が楽になります。
新人職員に向けて ―学んでほしい視点
新人職員は、夕暮れ症候群を「困った行動」とだけ捉えてしまいがちです。
ですが、ここにこそ認知症ケアの本質があります。
学んでほしいポイント
- 行動には必ず「その人なりの理由」がある。
- 「帰りたい」という言葉の裏には「安心したい」「役割を果たしたい」という気持ちが隠れている。
- 認知症ケアは「制止すること」ではなく「理解し支えること」である。
夕暮れ症候群を通して、新人職員は「本人理解」の第一歩を踏み出すことができるでしょう。
まとめ ――「問題」ではなく「本人らしさ」
夕暮れ症候群は、介護する側にとって大きな負担になることもあります。しかし、それを単なる「問題行動」と見るのか「その人らしい生活の延長」と捉えるのかで、ケアの姿勢は大きく変わります。
夕暮れ症候群は、その人が今もなお家族を思い、役割を大切にして生きている証拠です。
その気持ちを理解し、支援することこそが、認知症ケアの本質の一つではないでしょうか。
大袈裟な言葉に聞こえるかもしれませんが「尊厳を守る」「尊重する」という言葉の受け止めと理解なしに、私たちの介護の仕事は成立しづらいのです。
おわりに
在宅介護を続けるご家族、新人として現場に立つ職員の方にとって、夕暮れ症候群は避けて通れないテーマです。
ただし、その背景にある「本人らしさ」を理解できれば、介護者の視点も変わり、ケアの質も高まります。
「夕方になると不安定になる」――その一つひとつの行動を、生活史の延長線上にある大切なサインとして受け止め、支援へと繋げていきましょう。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
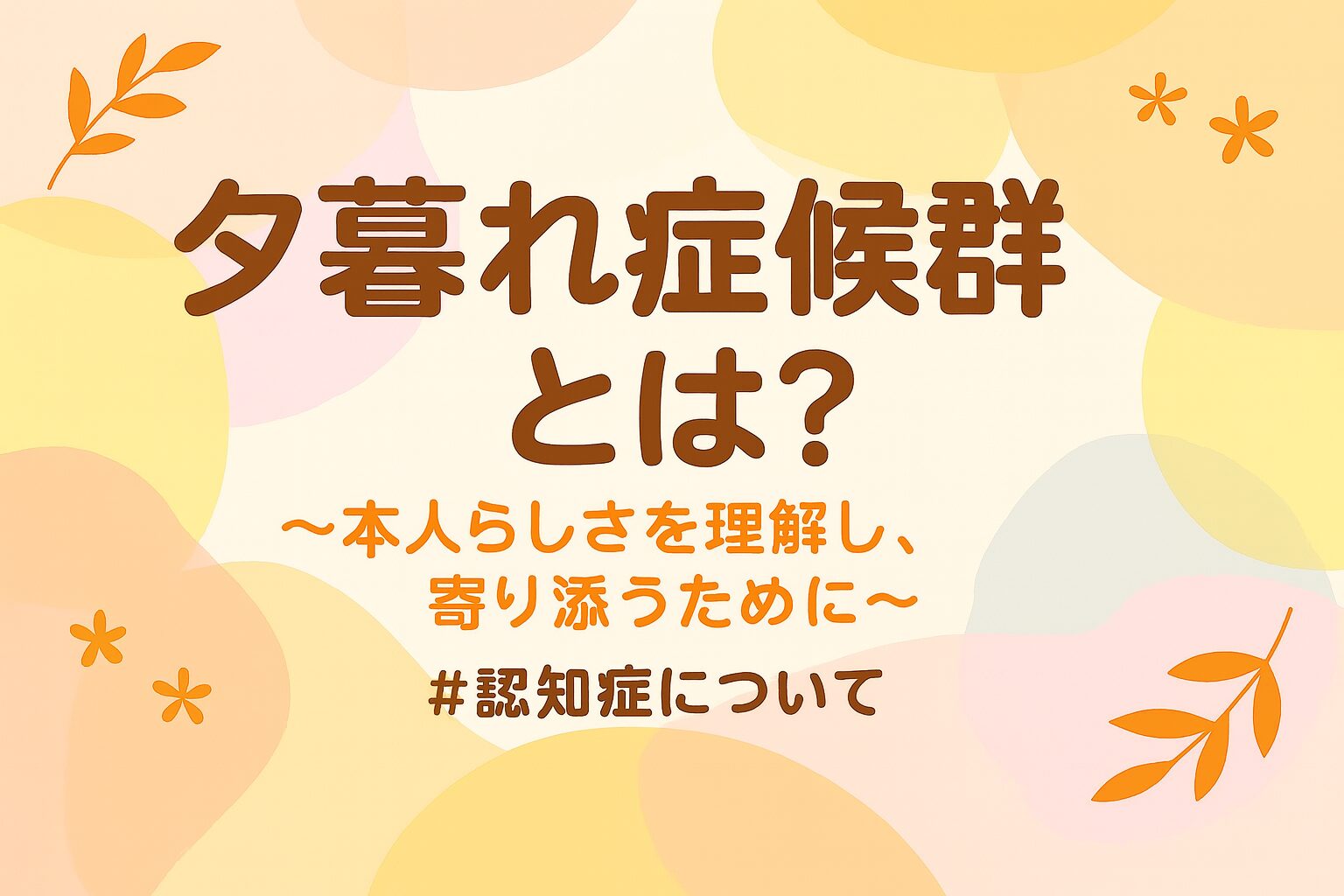

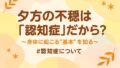
コメント