介護職員向けの記事に使用
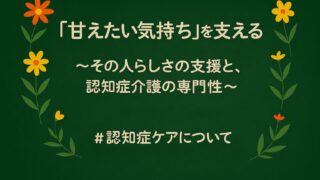 認知症ケアについて
認知症ケアについて 『甘えたい気持ち』を支える ~その人らしさの支援と、認知症介護の専門性〜
認知症介護で大切な「自立支援」と「甘えたい気持ち」の両立とは。手を出しすぎない専門性と、安心を支える匙加減を、現場と家族の視点から具体的に解説します。
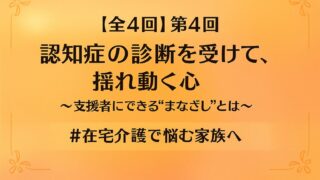 在宅介護で悩む家族へ
在宅介護で悩む家族へ 【全4回】第4回:認知症の診断を受けて、揺れ動く心 ~支援者に出来る“まなざし”とは~
認知症と向き合う家族は、迷い、揺れ、言葉にならない苦しさを抱えています。支援者に求められるのは正解ではなく「まなざし」。本人と家族の両方を支える心理的支援の視点を丁寧に解説します。
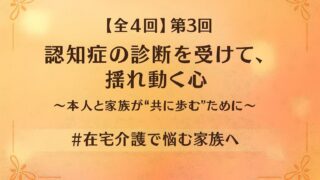 在宅介護で悩む家族へ
在宅介護で悩む家族へ 【全4回】第3回:認知症の診断を受けて、揺れ動く心 ~本人と家族が『共に歩む』ために~
認知症と向き合うのは本人だけではありません。家族との気持ちのすれ違いを埋め、否定しない伝え方や「一緒にやる」関わりで、心の距離を近づけるヒントを解説します。
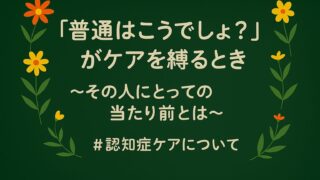 認知症ケアについて
認知症ケアについて 「普通はこうでしょ?」がケアを縛るとき 〜その人にとっての当たり前とは〜
「施設の当たり前」と「その人の普通」。介護現場で見落としがちな“常識”とは何かを考えながら、認知症ケアのあり方を見直します。“その人らしさ”を守るケアとは何かを考える記事です。
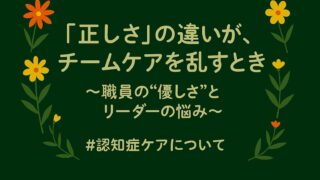 認知症ケアについて
認知症ケアについて 「正しさ」の違いが、チームケアを乱すとき 〜職員の“優しさ”とリーダーの悩み〜
介護現場で起こる“優しさ”や“寄り添い”のズレ。その背景と、リーダーが軌道修正するための伝え方を解説します。
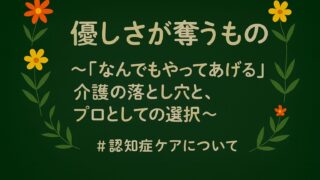 認知症ケアについて
認知症ケアについて 優しさが奪うもの 〜「なんでもやってあげる」介護の落とし穴と、プロとしての選択〜
「本人のため」が実は逆効果に。やさしさと専門性が交差する現場で、認知症ケアに潜む“やりすぎ”の落とし穴と、介護職のあるべき姿を問い直す記事です。
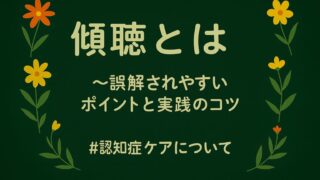 認知症ケアについて
認知症ケアについて 傾聴とは ~誤解されやすいポイントと実践のコツ~
「傾聴=静かに聞く」ではない。認知症ケアで大切なのは、気持ちを汲み取り“理解している”と伝える姿勢。現場で使える具体例も紹介。
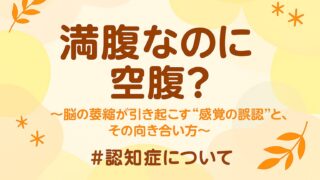 認知症について
認知症について 満腹なのに空腹? 〜脳の萎縮が引き起こす“感覚の誤認”と、その向き合い方〜
「まだ食べてない」「トイレに行きたい」は“感覚の誤認”かも。脳の仕組み(視床下部・前頭前野など)と原因、家族・介護職が今すぐ使える「否定しない受け止め」と見立て方をまとめます。
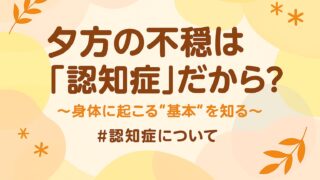 認知症について
認知症について 夕方の不穏は「認知症」だから? ~身体に起こる“基本”を知る~
夕方の不穏は認知症だけが原因ではない可能性も。体内時計の乱れやエネルギー不足も関与。15時おやつの工夫や声かけで穏やかさを支える方法を解説。
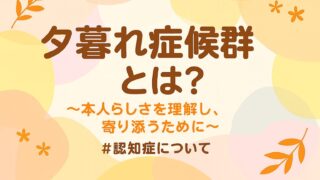 認知症について
認知症について 夕暮れ症候群とは? ~本人らしさを理解し、寄り添うために~
夕方になると落ち着かない――その背景にある「本人らしさ」とは。認知症の方の不安の意味と、夕暮れ症候群の原因と理解のポイント、家族や職員の対応法を解説。