事故を防ぐ第一歩は、「ヒヤリ」に気づくことから
「この前ヒヤッとしたことがあって……」
介護の現場では日々、そんな言葉が聞かれているのではないでしょうか。
歩いていたが椅子につまづく、立とうとしたら力が抜ける、口に入れようとした薬が落ちる、水分を飲んだら激しくむせる――介護現場での事故には「ヒヤリ」とした瞬間が付きものです。
ですがその「ヒヤリ」にこそ、重大な事故を防ぐヒントが詰まっているのです。
特に、転倒による骨折事故がもたらす影響は非常に大きく「本人の生活の質の低下」や「家族の精神的ダメージ」「職員のメンタルへの影響」「施設への信頼低下」など、少なくとも11の深刻な影響が連鎖的に発生します。
関連記事:骨折を伴う転倒が深刻な理由とは? ~介護現場における11のリスクと予防のヒント~
このような事故を防ぐには、事故が起こる前の兆し――つまり、日常的に発生しているヒヤリハットにどれだけ気づけるかがカギになります。
今回は、ヒヤリハットとハインリッヒの法則の関係、そしてヒヤリハットをチームでどう活かすかについて考えてみたいと思います。
ハインリッヒの法則とは?
まずは有名な「ハインリッヒの法則」について簡単に説明しましょう。
アメリカの損害保険会社の技術者であるハインリッヒ氏が1930年代に発表した研究によると、1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故、そして300件のヒヤリハットが存在するとされています。
この「1:29:300」の法則は、労働災害の分野では非常に有名ですが、介護現場にもそのまま当てはまります。
たとえば、ある方が転倒して骨折するという重大事故が起きたとします。
その背景には、転びそうになったが何とか踏みとどまった場面、よろけたが職員が支えた場面、立ち上がり動作でふらついていた場面など、たくさんの「ヒヤリ」があったはずです。
つまりこのハインリッヒの法則とは、重大事故は突発的に起きるのではなく、日常的な小さなミスや異常(ヒヤリハット)が蓄積された結果であることを示しています。
「ヒヤリ」に気づけるかどうかが、分かれ道
私たちが事故を防ごうとするとき、つい「重大な事故だけを防ごう」と考えてしまいがちです。
でも、事故が起きるまでの“予兆”を見逃していたら、対策は後手に回ってしまいます。
ここで大事なのが、ハインリッヒの法則を逆から見る視点です。
「重大事故の裏には300のヒヤリがある」ではなく、
「300のヒヤリに気づき、それを積み重ねて改善していけば、1つの重大事故を防げる」という考え方――ピラミッドを下から登るように、小さなヒヤリを積み重ねていくことが、未来の事故を予防する最善策なのです。
ヒヤリを「見つけた数=守った未来の数」と考える意義
ヒヤリハットは、単なる「小さな失敗」ではありません。
ヒヤリハットに気づいた瞬間は”未来の重大事故を防いだ瞬間”と捉える視点が大切です。
つまり、ヒヤリを一つ見つけるごとに、一人の利用者、一人の職員、施設全体の未来を守ったのかもしれないのです。
「何も起きなかった」から価値がないのではなく「気づけたこと」自体に価値があります。
報告数は、注意力の高さと感性の証明です。
ヒヤリを見つけた数だけ、未来の安全が守られているのだと捉えることで、報告文化やチームの意識が変わっていきます。
ヒヤリハットを見つける「目」を育てるには?
では、どうしたら私たちはヒヤリハットに気づけるようになるのでしょうか?
①「ヒヤリ」に敏感になる習慣をつける
「転びそうだったけど何とかなったから報告はいいや」
「ちょっと怖かったけど事故じゃないし……」
そんな“スルー”をしていませんか?
ヒヤリハットは「ちょっと危なかったけど何も起きなかったから良かった」ではなく「事故に繋がっていてもおかしくなかった」という視点が必要です。
何か違和感を覚えたとき「なぜそう感じたのか?」を少し立ち止まって考えてみるだけでも“ご利用者を守るための目”は鍛えられていきます。
② チームで共有し、感度を高め合う
ヒヤリハットは、共有して初めて価値を持つ情報です。
「○○さん、最近立ち上がりのときにふらつきがある気がします」
「□□さん、歩行器が少し手前に引かれていて危なかったです」
こうした些細な気づきも、カンファレンスで共有することを習慣づけると、メンバー全体の感度が上がっていきます。
ヒヤリハット報告を「個人の失敗報告」と捉えるのではなく「未来の事故を防ぐ気づきの共有」と捉える文化を育てていきたいですね。
③「人」だけでなく「環境」や「流れ」にも目を向ける
ヒヤリハットを見つけるには、本人の行動だけでなく、それを取り巻く「環境」や「導線」への視点も重要です。
- 夕方になると部屋が暗くなり、足元が見えにくい
- 濡れた床に滑りやすいスリッパを履いていた
- 脱衣所の床にマットがなく、濡れて危ない
- 就寝中に掛け布団がずれて落ちてしまうことがある
- ベッドからドアの途中に、とっさに手をつく場所がない
こうした小さな“気づき”を拾う力を、チームで育てていきましょう。
ヒヤリハットが多い施設は、実は安全意識が高い施設
「ヒヤリハット報告が多いと、施設の印象が悪くなるのでは?」と心配する声も聞かれますが、実際はその逆です。
ヒヤリハットが報告されていない施設の方が、むしろリスクが高いともいえるでしょう。
なぜなら「何も起きていない」のではなく「起きていることに気づけていない」可能性があるからです。
ヒヤリハットは、事故を未然に防ぐセンサー。
それをどれだけ受信できるかが、チームの安全意識の高さに直結するのです。
おわりに:事故を防ぐのは“奇跡”ではなく“習慣”
介護現場において「事故ゼロ」は決して簡単な目標ではありません。
人の動き、体調、感情、環境――それらすべてが日々変わっていく中で、日々すべてのリスクを完全に消し去ることはできません。
だからこそ大切なのは「リスクをゼロにすること」よりも「リスクに気づき、減らし続ける努力を、チーム全体で継続すること」です。
事故が起きたときに「どう防げたか」を検証するのはもちろん、
事故が起きる前にどれだけ“気配”に目を向けられたかが、
その施設の安全文化の成熟度を表しているともいえるでしょう。
ヒヤリハットを「問題」ではなく「未来を守るための気づき」と捉える文化が根づけば、
それは間違いなく利用者にとっても、職員にとっても安心できる場所に変わっていきます。
そして何より「事故が起きなかった」という“普通の日常”を守るために、
現場の一人ひとりがヒヤリハットを見つけ、共有し、対策につなげていく――。
その積み重ねが、介護現場を静かに、確かに変えていく力になるのです。
そして変化した先にはきっと、ご利用者にとっての『笑顔』と『穏やかな生活』が待っていることでしょう。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
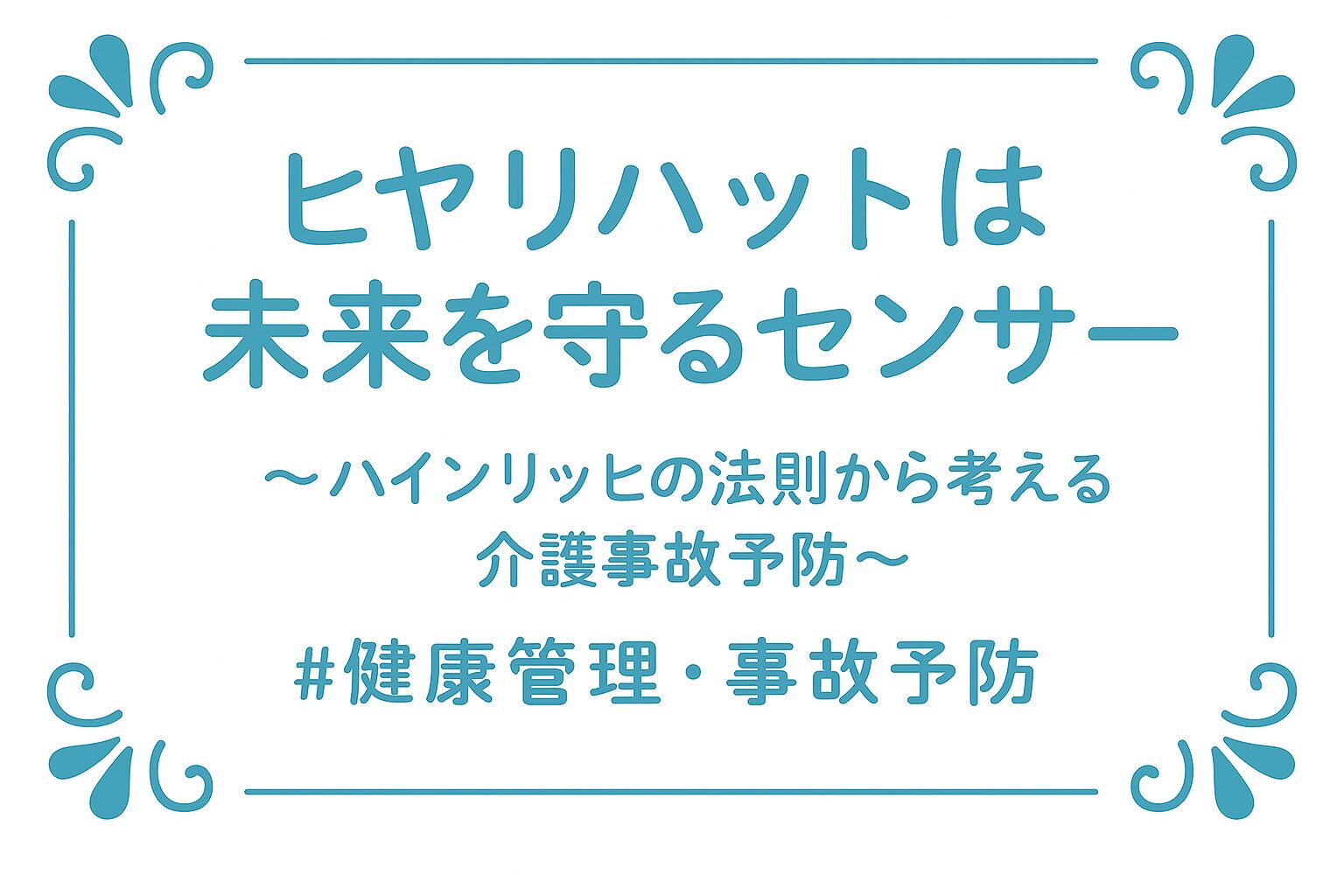


コメント