“当たり前のケア”は当たり前じゃない
私たち介護職が日々当たり前のように提供しているケア――服薬介助、排泄介助、入浴介助。
毎日繰り返される業務のひとつとして、スケジュールの中に淡々と組み込まれ、滞りなく進めていくことが求められます。
でも、ふと立ち止まって考えてみてほしいのです。
それは本当に“当たり前”にさせてもらえることなのか?
その行為を、あなたが「受ける側」になったとき、どんな感情が湧くでしょうか?
見ず知らずの人から薬を差し出されたら?
想像してみてください。
あなたがある日、知らない場所に連れて行かれ、そこにいた「誰だか分からない人」が笑顔で薬を差し出してきたら――
「はい、お薬ですよ。飲んでくださいね」
どんなに素敵な笑顔で、安心できる優しい声かけであっても、相手が“知らない人”なら、あなたはすぐにその薬を口に運べますか?
「この人は医療の知識を持っている」「自分の健康のためなんだ」と頭では分かっていても、すんなり薬を飲むことは出来ないのではないでしょうか。
ましてや、相手の言葉がうまく理解できない状態であれば、警戒するのは当然の反応です。
それと同じことが、認知症の方の毎日の生活で起こっているのです。
認知症の人にとって「職員は知らない人」
認知症の症状が進むと、記憶の保持や判断力が低下します。
特に短期記憶が保ちにくくなるため「昨日何をしたか」「さっき誰が来たか」はすぐに忘れてしまいます。
つまり、施設職員が毎日顔を合わせていても“初対面”のように感じられることは珍しくありません。
私たちがどんなに丁寧に接しても「この人は誰だろう?」という警戒心がある状態で、服薬を促し、排泄を介助し、体を洗わせてもらう――
それは、本人にとっては相当な負担と不安をともなう行為なのです。
本来なら「一線を越える行為」
服薬介助、排泄介助、入浴介助。
どれも非常にプライベートな行為です。
自分の体に関すること、自分の意思や尊厳に深く関わることばかりです。
たとえば排泄介助。
たとえ家族であっても、成人した子どもが相手では、なかなか素直に介助を受け入れることは難しいのではないでしょうか?
入浴介助も同じです。
裸を見せるというのは、信頼や関係性がなければ成立しない極めてデリケートな領域です。
それを“見知らぬ誰か”に任せなければならないとしたら?
たとえそれが「プロの介護士」だと説明されても、心のどこかで抵抗感や恥ずかしさ、不信感が芽生えるのは当然です。
しかし、認知症の方々はその感情を「うまく表現できない」ことも多いのです。
不安や恐怖を“拒否”や“暴言”といった形でしか表せないこともある――それが「問題行動」と誤解されてしまうことも少なくありません。
ケアは「させてもらっている」もの
ここで大切なのは、私たちの行っているケアは“してあげている”ものではないということです。
介助が成立するのは、相手がその行為を“受け入れてくれている”からです。
薬を飲んでくれるのも、排泄を任せてくれるのも、入浴で体を洗わせてくれるのも、本人が“預けてくれている”からできること。
つまり、ケアとは「させていただいていること」なのです。
この視点が抜けると、ケアはいつの間にか“効率化”や“手順”ばかりが優先される“作業”になってしまいます。
拒否があれば「やりにくい人」、手がかかれば「困った人」――そんなレッテルすら貼ってしまいかねません。
でも本当は、その“拒否”や“困難”の裏側に、その人の当たり前の感情があるのです。
信頼関係は一日にしてならず
「でも、仕事として介助は毎日あるし、信頼関係を築いている余裕がない」
そんな声もあるかもしれません。
たしかに、時間的制約、人員不足、タスクの多さ――介護現場には現実的なハードルがたくさんあります。
それでも私たちは、「信頼がないと成り立たないことを、日々やらせてもらっている」という前提を、忘れずにいたいのです。
たった一言の声かけでも、視線の合わせ方でも、スピードを緩める工夫でも、
「あなたを大切に思っていますよ」というメッセージは、必ず伝わります。
そして、それは本人だけでなく、周囲のご家族やチームの中にも届いていきます。
“ありがたい”という気持ちを持ち続ける
介護職として長く働いていると、いつの間にか「当たり前」に感じてしまうことが増えていきます。
でも、本当に大切なのは、その当たり前の中にある“ありがたさ”に気付き、感謝の心を持ち続けることではないでしょうか。
今日も薬を受け取ってくれた。
今日も排泄を任せてくれた。
今日もお風呂で体を洗わせてくれた。
それは、決して当たり前のことではありません。
それができるのは、少しずつでも、私たちを「信じてくれているから」に他なりません。
まとめ:ケアの本質を、忘れない
「ケアする」とは、ただ手を貸すこと、助けることではありません。
そこには、相手の意思や感情、尊厳を大切にする気持ちと、信頼を築こうとする姿勢が欠かせません。
介護の現場は、常に時間に追われています。
業務をこなすことで精一杯な日もあるかと思います。
それでも、私たち職員一人ひとりが心のどこかに
「このケアは、目の前の方が“受け入れてくださっている”もの」
「私を信じてくれているからこそ、成り立っている」
――その思いを持ち続けることが、ケアの原点だと思うのです。
たとえ認知症によって、名前や関係性がわからなくなったとしても、
人は「安心」や「大切にされている」という感覚は受け取ることができます。
だからこそ
・声かけのトーンにやわらかさを込めること
・目線を合わせること
・急がず、待つ姿勢をもつこと
・嫌がったときに無理強いせず、一歩引いてみること
――そういった小さな“心の表現”が、相手に伝わり、信頼が積み重なっていきます。
これはご家族の方にも、ぜひ知っておいていただきたい視点です。
認知症の方の世界では、ずっと過ごした家であっても、どれだけ長く一緒にいた家族であっても「自分がどこにいるのか」「目の前の人は誰か」が分からなくなることが、突然起きてしまうのです。
そんなとき「どうして分かってくれないの?」「こんなに尽くしているのに」と思ってしまうことがあるかもしれません。
でも、どうかご自身を責めないでください。
認知症の方は“分かっていない”のではなく“分からない状況に戸惑っている”だけなのです。
そんな戸惑いの中で「お薬飲もうね」「お風呂に入ろうね」と言われるのは、本人にとっては、知らない人から突然プライベートな領域に踏み込まれるようなことかもしれません。
それでも、怒らず、逃げず、委ねてくれるとしたら――
それは、私たちを信じてくれている証であり、心の奥にある「つながろうとする力」が、まだしっかりと、本人と私たちの間に残っているということなのです。
焦らず、怒らず、「大丈夫だよ」「そばにいるよ」と、安心を届けるような接し方を心がけるだけで、相手の心には、言葉を超えた“つながり”が必ず届いています。
ケアは、完璧である必要は全くありません。
「あなたを大切に思っている」という気持ちを、何度でも重ねていくこと――
それが、信頼の橋をつくり、つながりを取り戻す力になるのです。
だからこそ私たちは
「今日も薬を受け取ってくれてありがとう」
「今日も私を信じて任せてくれてありがとう」
という感謝の気持ちを忘れずに、目の前の方と笑顔で向き合うべきなのではないでしょうか。
その積み重ねが、本人にとっても、家族にとっても、職員にとっても、
お互いが“人と人”として関われる安心の土台になるのではないでしょうか。
介護とは、信頼を築く営みであり、
誰かに寄り添わせてもらえるという“特別な関係”です。
だからこそ――
その一つひとつを「ありがたい」と感じられる心を、私たちは大切にしていきたいのです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
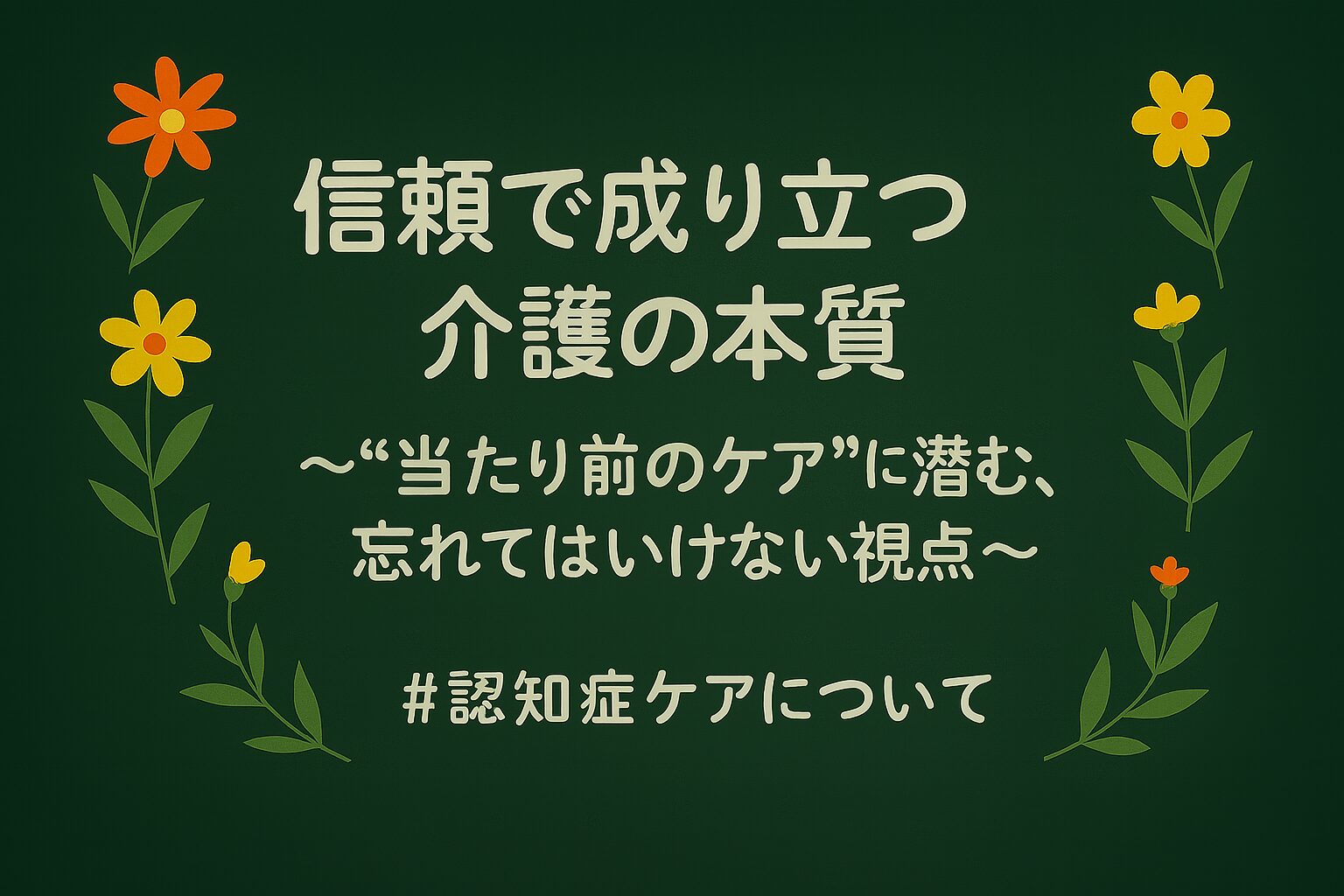


コメント