
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
【この記事で伝えたいこと】
在宅介護は「一人で背負うもの」ではなく、介護者自身の心と生活を守りながら、支援と繋がって続けていくものです。
頑張り続けることが美徳なのではなく『無理に気付き』『次の選択肢を考える』ことも、本人と家族、双方を守るケアなのです。
【要点】
- 在宅介護は、終わりの見えない負担を家族に与える
在宅介護には時間の区切りがなく、夜間対応や日中の不安が積み重なり、身体よりも心の消耗が大きくなっていきます。 - 家族の「優しさ」や「責任感」が、限界に気付きにくくさせる
親を思う気持ちから始まった介護は「まだ見られる」という思いによって無理を重ね、介護者自身を縛り、孤独や疲弊を深めてしまうことがあります。 - 一人で抱え込まないことが、より良い介護に繋がる
在宅介護を否定する必要はありませんが、違和感を覚えたときは、他の支援に繋げても良いタイミングです。介護者が自分を守ることが、本人の安心にも繋がります。
【この記事で分かること】
・在宅で認知症介護を続ける家族が、なぜ心身ともに消耗していくのか
・「優しさ」や「責任感」が、限界を見えにくくしてしまう心理的な構造
・同居と別居は優劣ではなく「状況に応じた選択」であるという考え方
・在宅介護を続けるために必要な「一人で抱え込まない」という視点
・介護者自身の心と体を守ることが、より良い認知症ケアに繋がる理由
家族介護の方が「一人で抱え込まない」ための考え方と、支援につながるヒントをまとめました。
※詳しい説明・根拠・事例は、このあと本文でやさしく解説します。
ともに家で生活するということ
長くなりますが、自宅で介護をしている多くの方に読んでいただければと思います。
私は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の管理者として、多くのご家族様と関わり、悩みを聞き、認知症になってしまった親への思いに触れてきました。
ご家族様と話している時に強く感じたのは、いまだに『親の面倒を見るのは子供の役目』『家で見られるうちは家で頑張る』『介護施設に親を入れるのは最終手段』という考え方が、まだまだ根強いということです。
そしてこの考えは、介護をする側だけではなく、介護を受ける側にとっても『当然だ』ととらえている様子があります。
その結果、要介護状態となった親を家で介護することが当たり前、という流れがいまだに残っているのだと思います。
在宅介護に「終わりの時間」はありません
在宅での介護は、仕事のように「勤務が終わる」という区切りがありません。
朝も夜も、食事の時間も、自分が休みたいと思っている瞬間でさえ、常に何かが起こり得る状態で過ごしています。
そのため、身体の疲れよりも、
“気持ちがずっと張りつめていること” が大きな負担になります。
介護をしていると、ほんの10分の休憩さえ贅沢に感じることがあります。
「ちょっと横になりたい」「コーヒーを飲みたい」
その小さな願いさえ、なかなか叶わない日が続くと、心がじわじわと削られていきます。
こうした“自分の時間の消失”は、在宅介護をしているご家族に共通する、静かで、しかし確実に大きな苦労です。
頑張り始めは、考え始めのきっかけ
もちろん背景には『地域性』『金銭的』『親族との関係』といった課題もあるでしょう。
ですが『家族介護を頑張り始めたタイミングは、次の段階を考え始めるタイミングでもある』といえます。
頑張り始めるということは、徐々に無理が出てき始めている、誰かが我慢し始めているということでもあると、今までの経験から感じています。
「限界」は、誰にでも訪れる
厚生労働省の調査でも、在宅介護を続けている家族の多くが「自分の体調悪化」や「精神的負担の増加」を限界の理由に挙げています(※厚生労働省「令和4年度 介護サービス施設・事業所調査」)。
つまり「頑張りすぎたから施設に入れる」のではなく「頑張り始めたら次のステップを考える」という視点が、むしろ健全なのです。
認知症の家族と家で生活し、その方の認知症が進行していくにつれて、日々の介護に悩みや不安を感じることが次第に増えていくと思います。
本記事では、介護者が抱える課題とその対処法について、私の経験を踏まえてご紹介します。
介護の負担が増す家族の心理とその影響
自分たちを今まで育ててくれた大切な親だから自分たちが見てあげたい、と思う気持ちは偽善でも美徳でもなく、当然な思いです。
この気持ちのスタートは、間違いなく『優しさ』や『思いやり』、『感謝』です。
ですが、その思いが強くなり過ぎるあまり、頑張り過ぎてしまう家族が多いように感じます。
優しさが、少しずつ負担に変わっていくとき
つまり『自分たちの生活に影響が出始めても『まだ見れる』と、無理をし始めてしまう』ということです。この思いの強さはやがて、介護者である自分たちを縛り始め、生活に何かしらの影響を与え始め、いつしか『優しさ』を見えなくしてしまいます。
特に、認知症の方を自宅で支える介護者(配偶者や子供、子供の配偶者)の責任感と忍耐力は凄まじいものがあります。
それ故に、縄が深く食い込んでいくことに中々気づけません。そして気づかぬうちに、介護を始めた頃に心を満たしていた『優しさ』という感情に蓋をしてしまいます。
夜間の排泄時
排泄に向かうため、認知症の方が起き出します。
我が家なのに、トイレの場所が分かりません。
トイレにたどり着いても排泄の仕方が分かりません。ズボンや床が濡れてしまいます。
排泄を済ませてもどう始末していいのか分かりません。触ったら手が汚れたので、ひとまず壁にこすり付けて手を拭きます。
入る時にはカギを掛けたのに、カギの開け方が分かりません。
『開けて!』と大きな声で叫んでみます。
トイレを出たら、部屋に戻れません。目の前は暗く、歩き出すのが憚られます。
だから、トイレに起きるたびに、介護者も起きなければなりません。
日中、一人になるタイミングで
夫婦は共働きで、子供は学校です。
デイサービスに送り出すために着替えたのに、排泄を失敗して濡らしてしまいました。
やっと着替え終わったのに、なぜか自分でパジャマに着替えてしまいました。
また着替えさせなければいけません。出勤前の忙しい時間がさらににバタバタします。
自宅での介護が始まってから、勤務時間と収入が限られてしまいました。
デイサービスを毎日利用できなければ、その間は認知症の方が一人になります。
デイサービスを利用していても、仕事から帰ってくるまでは認知症の方は一人で過ごさなければなりません。
火の不始末があり、隣の方が気づいてくれました。急な出費ですが、全てIHに交換しました。
買い物に行ったのに、お金を持っていきませんでした。いつものスーパーから連絡が来ます。
一人で出歩いてしまい、警察から連絡が来たこともあります。
そのような過去の出来事が、仕事中であっても、常に頭の片隅でうごめいています。
夕方~夕食時の混乱
やっと家族が揃います。
夕食後、認知症の方が「ご飯はまだ?」と言い始めます。もう食べたことを伝えても「私はまだ食べていないよ」と全く話が進みません。
しまいには「ここはご飯も食べさせてくれないのか!」と怒り始めます。
やっと収まったと思ったら次は「そろそろ帰ります」と席を立ちました。
『ここが家ですよ』と伝えても「ここは私の家じゃない」「何で帰してくれないんだ」「私をここに閉じ込めてどうしようというのか」「あんたは誰なんだ!」とまたしても怒りだしてしまいました。
建て直したとはいえ、間違いなく家はここだけです。なのに「ここは家じゃない」と繰り返し、興奮し、やがて疲れたのか座り込み、ウトウトし始めました。
また声を荒げたらどうしようと思いながら声を掛けると「もう夜ですね。じゃあ寝ますよ」とさっぱりした表情で言ったので、寝室に案内するとさっさと寝てしまいました。
余りにコロコロ変わる感情や表情に、どっと疲れが押し寄せます。
そしてまた、夜が始まります。
こういった不安や気持ちを抱えている介護者の方は、決して少なくないと思います。
これらの生活に終わりが見えず『いつまでこれが続くのか』という思いが、重くのしかかります。
先が見えない不安は、気持ちを暗くします。
認知症介護で、家族が最も傷つきやすいこと
そして、認知症介護で最も辛いことは『認知症の方の攻撃性は、一番良く見てくれている人に向きやすい』ということではないでしょうか。
一番身近な介護者が、一番攻撃されてしまい、最も疲れてしまいます。
● なぜ、一番身近な人に向かってしまうのか
実際、認知症ケア学会誌やBPSD(行動・心理症状)の研究でも「認知症の方の不安や混乱は、最も身近な介護者に表出しやすい」と指摘されています。これは「信頼しているからこそ感情をぶつけやすい」側面もあるとされています(※日本認知症ケア学会誌 2019年特集より)。
つまり、攻撃されるということは、実は攻撃対象となっている方が『認知症の人にとって一番信頼できる相手』で『一番近くで見ていてくれている人』という何よりの証明です。
● 分かっていても、受け止めきれない気持ち
ですが攻撃を受けている最中に、それを前向きにとらえることが出来る人が、果たしてどれだけいるでしょうか。
攻撃された辛さ、疑われた悲しさが、優しかった介護者を心理的にも孤独にしていきます。
こうなってしまうと、優しさからスタートして笑顔を目指すどころか、日々ストレスとどう向き合うのか、どう解消していくのかということを考える時間が多くなっていくと思います。
大切な親や配偶者を支えながらともに生活し、笑い合いたいと思って一緒に暮らすことを選んだのに、その思いと現在の状況の乖離が着実に大きくなっていきます。
在宅介護を続けるために、大切な視点
在宅介護で大切なのは『全部自分で抱え込まない』ことです。
できないことがあって当然で、介護はチームで支えていいものです。
手を抜くことは悪いことではなく、
あなたの心身を守るために必要な工夫です。
同居と別居:最適な介護スタイルを考える
『認知症の方とともに暮らす』ということと『同じ家で生活をする』『家族で介護する』ということは、必ずしもイコールでは無いと思います。
・同じ家で生活することにこだわるあまり、介護者も介護される側もストレスを感じる暮らし
・住む場所こそ離れていても、適度な距離感を持って笑顔で関わり合える暮らし
この書き方には、少なからず私の思惑が含まれていると思います。ですが、大きく間違っているとも思いません。
そして、認知症の方本人にとっても、その方を大事に思う家族にとっても、どちらの選択がより良いのかということは、一目瞭然かと思います。
どちらの選択にも、意味があります
誤解しないでいただきたいのは、この記事は、すべての自宅介護を否定するものではありません。
家でともに生活をしていて、ストレスがない、笑顔があふれているのであれば、それはとても素晴らしいケアが提供できている証拠です。もちろんそのような状況であれば、施設に入るという選択肢を取る必要は全くありません。
ですが、今までと同じ生活をしているのに、違和感を覚えることやイライラすることが増えてきたのであれば、次のステップを考え始める時期なのかもしれません。
極端な例えや表現をしてしまったと思いますが、しかしこれらは、決して他人事ではありません。
いつ『介護者』という当事者になるかわかりませんし、いつ『介護される側』という当事者になるかもわかりません。
介護に関する事柄こそ、そして認知症が絡んだ介護であるならなおさら、早めに動くべきだと、私は身にしみて感じています。
一人で抱え込まなくていい理由
ぐるっと周囲を見渡してみれば
- 包括支援センター(地域の高齢者の介護や福祉に関する総合相談窓口)
- 市区町村の介護保険関係の窓口(介護保険制度に関する申請や手続きを行う場所)
- 居宅介護支援事業所(ケアマネージャーが在籍し、在宅介護を支える拠点)
- 近隣の介護施設(特別養護老人ホームやグループホームなど)の管理者や相談員
- 認知症の人と家族の会(認知症の本人とその家族を支援する全国組織)
など、不安や悩みを吐き出す先は、意外と多くあります。
そして上記の専門職は、家族が爆発し潰れてしまう前に、その思いを吐き出してくれることを待っています。
漠然とした不安や悩み、自分はこれだけ頑張っているのに、という思いを吐露するだけでも違うと思います。
認知症ケアが目指すもの
認知症ケアは『笑顔を目指すケア』です。
WHO(世界保健機関)の高齢者QOLに関する報告でも「本人と介護者のウェルビーイングは相互に関連している」とされており、日本でも「介護者の笑顔や安心感が、認知症の方の情緒安定につながる」という研究が報告されています(※日本老年社会科学会誌 2020年)。
誰かを笑顔にしようと思った時、大事なことは『自分が笑顔でいること』です。
自分が笑顔でない状態で、誰かを笑顔にすることは、非常に難しいと思います。
自分にとって大切な人の不安を取り除き、笑顔にしたいと思った時は、先ず何よりも、自分を大切にしてください。
そして、自分にとって大切な人と笑いあうために、ともに暮らしていくために、使える制度は遠慮なく、惜しみなく利用していただきたいと思います。
最後に伝えたいこと
認知症の家族の介護に悩んだ時、もっとも大事なことは、一人で抱え込まないことです。地域の支援機関や専門家に相談することは、自分のためにも家族のためにも、とても大切なことなのです。
自分自身の心と体の健康を守ることが、間違いなく、より良い介護に繋がっていくことでしょう。
最後に、もう一度、相談できる場所をまとめます。
- 地域包括支援センター(地域の高齢者の介護や福祉に関する総合相談窓口)
- 市区町村の介護保険窓口(介護保険制度の申請や手続き)
- 居宅介護支援事業所(ケアマネージャーが在宅介護をサポート)
- 近隣の介護施設(特養・グループホームなど、管理者や相談員)
- 認知症の人と家族の会(本人と家族を支援する全国組織)
こうした機関は「もう限界」となる前に、相談してほしいと待っています。
どうか一人で抱え込まず、遠慮なく頼ってください。
【補足】本記事の参考文献・出典
- 厚生労働省「令和4年度 介護サービス施設・事業所調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/25-23.html - 日本認知症ケア学会誌(2019年特集号:BPSDへの理解と対応)
https://www.ja-dc.jp/ - 日本老年社会科学会誌(2020年:介護者の心理的健康とケアの質に関する研究)
https://jaros.jp/ - WHO(世界保健機関)「World report on ageing and health」(2015)
https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
参考記事
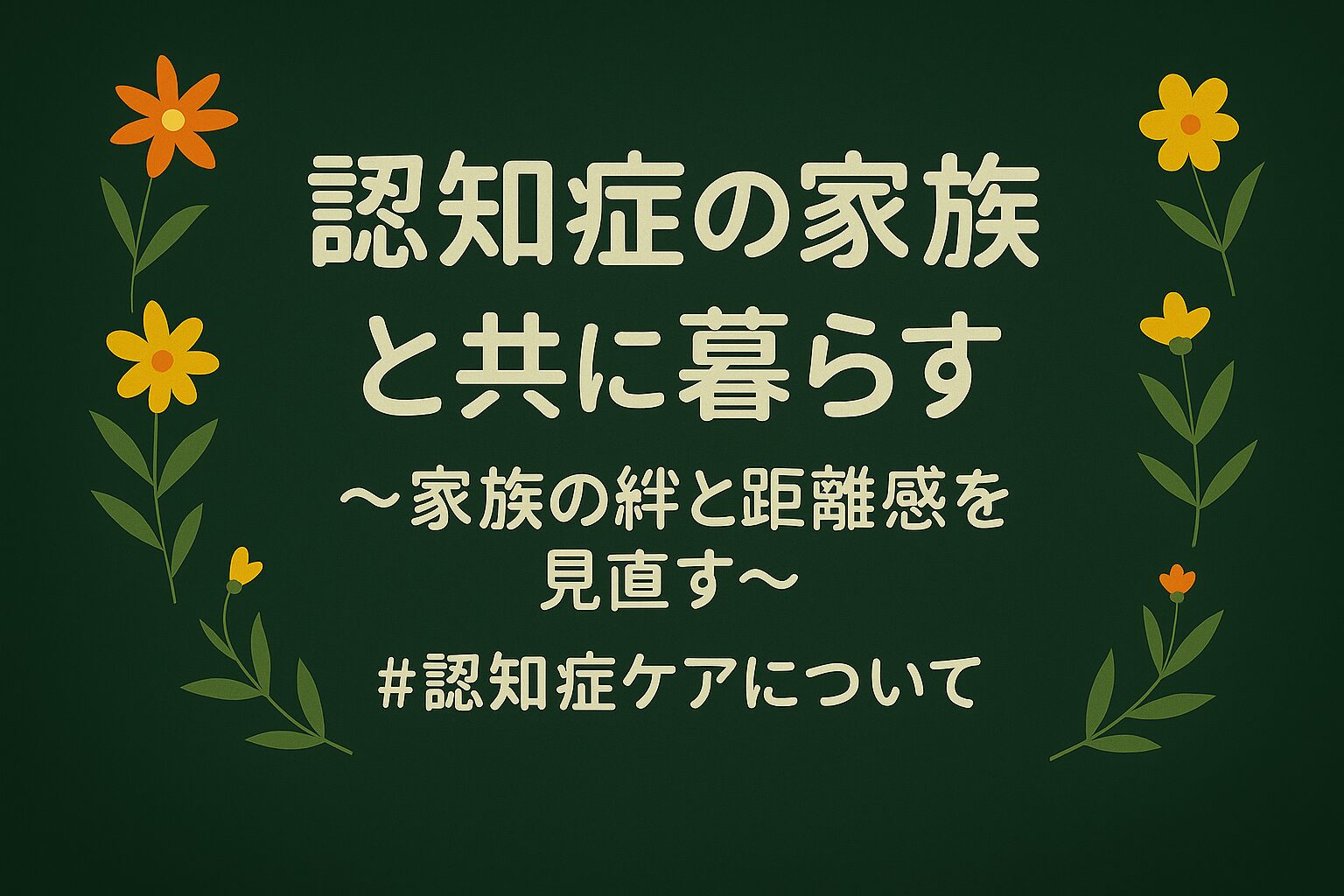
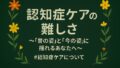
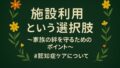
コメント