
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、転倒が起きてしまった時の職員、介護リーダー、管理者が事故とどう向き合い、どう活かしていくかについて、分かりやすくお伝えします。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに:「ゼロリスク」は幻想か?
「転倒事故をゼロにしてください」
介護現場で働いていれば、一度は言われたことのある言葉かもしれません。家族から、施設経営者から、時には自分自身からも湧き上がる願いです。
しかし、私たちは痛感しています。
高齢者の転倒事故を“完全になくす”ことは現実的には不可能だということを。
特に認知症を持つ方は、注意力の低下、判断力の低下、行動の予測困難性といった要因が重なり、私たちの見守りの網をすり抜けて、ふと立ち上がり、ふと歩き出し、そして転倒してしまうことが少なくありません。
では、私たちは諦めるべきでしょうか?
事故を運命として受け入れるべきでしょうか?
もちろん、答えはNOです。
大切なことは「ゼロにできないからこそ、どう向き合い、どう減らし、どう支え合っていくか」を考えていくことです。
現場の介護職員が向き合うこと
自分を責めすぎず、それでも問い続ける
転倒事故が起きた時に一番心を痛めているのは、間違いなく、その場にいた職員です。
- 「さっき声をかけておけば…」
- 「あと5分早く巡回していれば…」
- 「あの場所にマットを敷いておくべきだった…」
こうした“たられば”が頭の中をぐるぐると巡り、涙する職員もいます。
「私のせいで転んでしまった」「私が気を付ければ、痛い思いをさせずに済んだのに」と自責の念にとらわれ、しばらく立ち直れないこともあるでしょう。
ですがその悔しさは、事故を“ただのミス”にせず、「次に生かす知恵」に変えていける力でもあります。
職員に必要なのは、自分を責め続けることではなく「この事故から何を学ぶか」「同じ事故を防ぐにはどうするか」という前向きな問いを持ち続ける姿勢です。
事故を防ぐための見守りの工夫、声かけのタイミング、環境チェックの積み重ねーー
一見遠回りのようで、実はそれこそが安全への最短距離です。
介護リーダーが向き合うこと
責めない空気と、再発防止の仕組みづくり
現場のリーダーは、感情に流されすぎず、冷静に全体を見渡す視点が求められます。
事故が起きた時、まず必要なのは「誰が悪いか」探しではありません。
事実を整理し、原因を分けて、再発防止に生かすことです。
- どんな状況だったか
- 何が見落とされていたか
- なぜ起きたか
これらを“犯人探し”ではなく“再発防止”のために確認するのが、リーダーの役割です。
たとえば、事故後に職員全員で行う振り返りミーティングにおいて、
「ここがまずかったですね」「この人の見守りが足りなかったかもですね」
という発言が飛び交ってしまうと、萎縮したり黙ってしまう職員が増えます。
そうではなく、
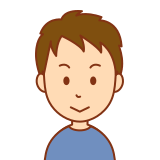
「この場面、私たち全体でどう対策できたか考えましょう!」
といった言い方で、個人ではなくチーム全体で振り返る雰囲気をつくることが大切です。
また、職員がヒヤリハットや小さな事故を「報告しやすい空気」を保つこと。
隠さず、恐れず、オープンに共有できることが、重大事故を防ぐ第一歩です。
また、事故後に行うミーティングは、KPT形式が有効です。
KPT例
- Keep(良かった点):声かけ自体はできていた
- Problem(課題):巡回間隔が長かった
- Try(次回試すこと):15時と16時に巡回を追加(担当者を明記する)
この形式であれば、誰かを責める空気を避け、改善に直結する話し合いができます。
ホーム長・管理者が向き合い、伝えること
職員の盾であり、家族への誠実な窓口であること
ホーム長や施設管理者には、現場と家族の“間”に立つ役割があります。
事故の報告や説明で家族の元へ出向くとき、求められるのは“形だけの謝罪”ではありません。
「何があったのか」「どう対応したのか」「今後どうするのか」
そして、その方がどういう生活を送っていて、なぜ今回の行動が起きたのか――
こうした背景をしっかり伝え、理解を得る努力が必要です。
たとえば、こんなふうに伝えることができます。
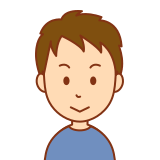
〇〇さんは、いつもご自身で歩くことを大切にされています。その“自分でやりたい”というお気持ちを私たちは尊重してきました。しかし、今回はその中で転倒が起きてしまいました。今後は環境を再確認し、移動の際は必ず声をかけて見守りを強化していきます。
こうした言葉には「本人らしさ」と「安全のバランス」を真剣に考えている姿勢が込められています。
また、事故に対して憤慨しているご家族に対しては
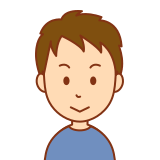
お怒りはもっともです。まず時系列で事実をご説明します――
当ホームは“自分らしさと安全の両立”を方針としていますが、今回の反省として
①通路マットの見直し
②移動前声かけのルール化
③15時巡回のダブルチェックを実施します。
進捗は◯月◯日にご報告します。不安な点は遠慮なくお聞かせください。
このように「事実」→「方針」→「具体策」→「再確認日」の順で伝えると、安心感と信頼感が高まるでしょう。
家族説明用の「時系列メモ用紙」テンプレを作り事故時に使用すれば、情報が整理しやすかったり、事故の原因に気付きやすかったり、ということもあるでしょう。
一方で、職員には「ちゃんと守られている」と思ってもらえるように、家族への対応をただ任せるのではなく、管理者自らが前に立ち、矢面に立つことも必要です。
職員が「責められて終わった」と感じるような説明の仕方をすれば、次の事故への取り組み意欲は削がれてしまうでしょう。
家族との信頼関係は「事故前」に築くもの
事故が起きてから「信頼してください」と言っても、それは難しい話です。
だからこそ、事故が起きる“前”のコミュニケーションが何より重要です。
普段から意識しておきたい関わり方のポイント
- 毎日の様子をこまめに(良い事も悪い事も)伝える
- 小さな体調の変化も「なぜそう見えるのか」という理由まで丁寧に共有する
- 家族から話を引き出す(「普段はどんな方でしたか?」「最近気になることありますか?」)
- 意思決定に参加してもらう(例:ケアプランの説明に際して一言意見を求める)
家族が「任せっぱなしで不安」ではなく「ちゃんと見てくれている」「一緒に支えてくれている」と思える関係づくりが、いざという時に、心からの「信頼」や「理解」に変わります。
ヒヤリハットとハインリッヒの法則を活かす
ヒヤリハット:重大事故には至らなかったが“ヒヤッ”とした事例
ハインリッヒの法則:1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故と300件のヒヤリがあるという経験則
報告件数より大事なのは「再発防止につながる学びの数」です。
仕組み化例
- 「3行報告カード」(いつ/どこで/何があった)を配布
- 週1回のミニ共有会(5分)でTryを1つ決定
- 月末にTryの実施率と学び数を確認
(関連記事:ヒヤリハットは未来を守るセンサー 〜ハインリッヒの法則から考える介護事故予防〜)
おわりに:ゼロにはできない。でも、ゼロに近づこうとする姿勢は見られている
私たちは、転倒事故を完全に防ぐことはできません。
しかし、それを前提にして甘えてはいけません。
- 「防げたかもしれない」を問い続けること
- 「どうすれば繰り返さないか」をチームで考え抜くこと
- 「その人らしい暮らし」を諦めず、安全とのバランスを取り続けること
こうした姿勢を持ち続けることこそが、介護のプロとしての責任であり、誇りです。
そしてこの姿勢は、家族にもきっと届くと信じています。
「事故は起きたけれど、ここに預けてよかった」
「大切にしてくれていることが伝わってくる」
「一緒に考えてくれる、支えてくれる存在がいる」
そんなふうに思ってもらえることが、
介護に携わる私たちの“もう一つの報酬”ではないでしょうか。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
- 骨折を伴う転倒が深刻な理由とは? ~介護現場における11のリスクと予防のヒント~
- ヒヤリハットは未来を守るセンサー 〜ハインリッヒの法則から考える介護事故予防〜
- 【全7回】第1回:認知症高齢者が転倒しやすい6つの理由 〜原因と予防のために知っておきたいこと〜
- 【全7回】第2回:転倒の身体的要因とは? ~筋力・バランス・疾患との関係~
- 【全7回】第3回:「認知機能の障害」と転倒の関係 ~見えないリスクを理解して予防に繋げる~
- 【全7回】第4回:「また歩き出した…」その行動には理由がある ~BPSDの背景にある感情を知り、転倒を未然に防ぐ~
- 【全7回】第5回:認知症高齢者の転倒を防ぐために ~見逃せない「環境要因」とは~
- 【全7回】第6回:薬が多いと転びやすくなる? 〜認知症高齢者と「ポリファーマシー」の落とし穴〜
- 【全7回】第7回:「生活リズムの乱れ」が招く転倒 ~認知症ケアで本当に守るべき“いつも通り”とは?~
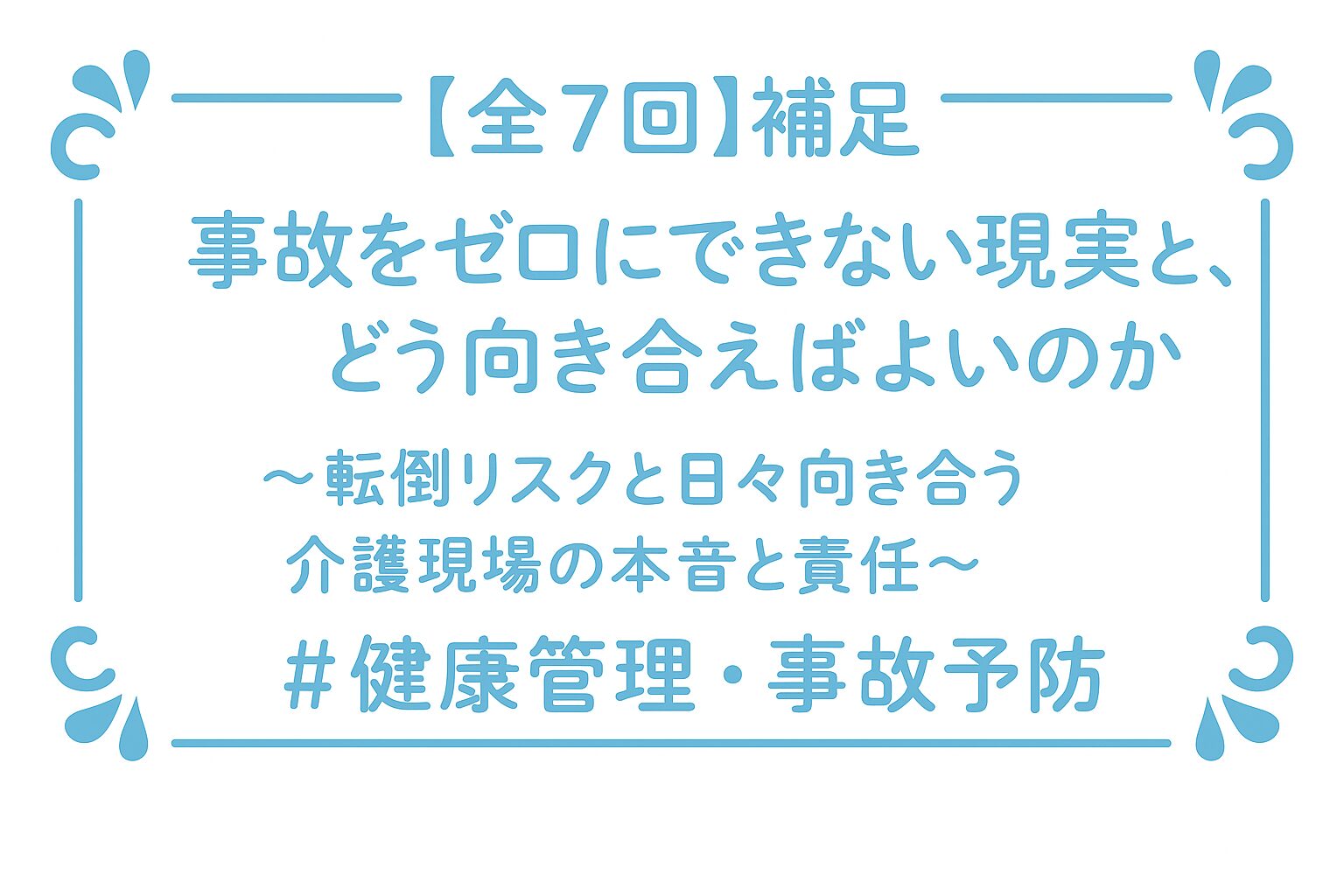

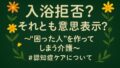
コメント