
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、認知症のある方の転倒リスクが「生活リズム」や「日常習慣の変化」によって高まる理由と、それによる転倒を防ぐ方法について、分かりやすくお伝えします。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
筋力の低下や環境が原因で転倒するイメージはありますが、実は『生活リズムの乱れ』や『日常習慣の変化』が転倒を引き起こす大きな要因になることをご存じでしょうか?
特に認知症のある方にとって、生活リズムの乱れや習慣の変化は、認知機能や身体機能に大きな影響を与え、転倒のリスクを高める要因となります。
この記事では、生活リズムや習慣が崩れることでなぜ転倒に繋がるのか、その背景や具体例、そしてご家族と介護職員それぞれが果たすべき役割について掘り下げてお伝えします。
なぜ「生活リズム」が転倒につながるのか?
睡眠リズムの乱れによる昼夜逆転
認知症では、体内時計をつかさどる脳の視交叉上核がダメージを受け、睡眠覚醒リズムが乱れやすくなります。
夜間に活動し、昼間にウトウトする「昼夜逆転」が生じると、日中の活動量が低下し、転倒しやすい身体状態になります。
また、夜間の動き出しやトイレのための起き上がりで転倒する危険性も高まります。
(出典:Satlin A, Volicer L, Ross V, Herz L, Campbell S. Sleep abnormalities in Alzheimer’s disease: A comparison to normal aging. Psychiatry Res. 1995;57(2):171-179)
食事や排泄などの習慣の乱れ
・以前は決まった時間に食事やトイレを済ませていた方が、認知症の進行に伴い「今が何時か」「お腹が空いたか」がわかりにくくなり、不適切な時間帯の行動が増える
・排泄の失敗を避けようとして、頻回にトイレに行きたがり、そのたびに転倒リスクにさらされる
こうした「時間感覚のズレ」が、行動のタイミングを狂わせ、転倒に繋がってしまいます。
(出典:Hale L, Gordon S, Kaplan KA. Sleep and circadian rhythm disruption in Alzheimer’s disease and related dementias. Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2019;7:100056)
「いつも通り」が崩れた時に起こる混乱と転倒
「いつもの動線」が変わることによる戸惑い
認知症のある方にとって「トイレの場所が変わる」「寝る場所が変わる」といった些細な変化は、大きな混乱を引き起こします。
記憶や空間認知機能が低下しているため、かつての「身体が覚えている習慣」に頼って動こうとし、結果的に見当違いの方向へ進んだり、物の配置を見誤っていつも通りの動きを取ってしまい転倒することもあります。
(出典:日本老年医学会. 高齢者の転倒予防ガイドライン. 2019年)
「やるべきことがない」生活がもたらす活動性の低下
習慣的に庭掃除や新聞取りなどをしていた方が、施設入居などで急に“役割”を失うと、生活に張りがなくなり、活動量が低下します。
活動量の低下は筋力低下・バランス低下を招き、転倒しやすい身体状態をつくってしまいます。
(出典:岡田靖, 中西正子. 高齢者の活動性低下が転倒に及ぼす影響. 理学療法科学. 2010;25(2):255-260)
【事例】“昔の時間感覚”で起きた転倒
80代女性・要介護2・認知症中等度
昔から朝5時に起きて農作業していた生活習慣があり、施設でも早朝に起きて活動しようとする。
しかし、スタッフ2人での見守り体制は7時から。
1人で居室から出ようとしたが、足元のカーペットに微妙な段差があり、それに躓いて転倒。手首を骨折。
→家族には「母は昔から早起きでした」と情報があったが、施設職員には共有されていなかった。生活リズムに配慮した個別対応ができれば、防げた可能性が高い。
家族と介護職で分かれやすい「生活リズム」の視点
家族の視点:「その人の昔の生活リズム」を知っている
- 「父は、夕食後すぐにお風呂に入る人だった」
- 「祖母は、朝食後すぐにトイレに行くのが習慣だった」
こうした情報は、本人の行動の“予測”につながります。
しかし、施設や通所などのケア現場では、残念ながら、それら有益な情報を『入居した後の動きを確認すれば良い』と、共有されていないこともしばしばあります。
介護職の視点:「現在の状態」からリズムを再構築しようとする
介護現場では「安全性」や「他の利用者との調和」も重視されるため“その人らしさ”よりも“標準的なリズム”への誘導が優先されがちです。
→このギャップが、本人の違和感や混乱を引き起こし、行動異常や転倒につながるリスクになります。
(出典:大川一郎. 認知症ケアにおける生活支援の個別化と集団性のバランス. 老年精神医学雑誌. 2016;27(9):1005-1012)
転倒を防ぐためにできること
1. 生活歴と習慣の「聞き取り・記録・共有」
- 家族から、過去の生活パターンを丁寧に聞き取る
- 「起床・排泄・入浴・食事・活動・就寝」などのリズムを可視化する
- ケアスタッフ間で共有し、個別支援計画に反映する
(出典:厚生労働省. 認知症介護実践研修テキスト. 2021年改訂版)
2. 習慣を活かした転倒予防
- 早起きが習慣の人には、早朝にも安全に動ける環境を整える(ナイトライト、見守り体制など)
- 排泄の習慣に合わせたタイミングでトイレ誘導を行う
- 昔の生活リズムを活かした“役割”や“活動”を生活に組み込む(新聞配り、ごみ捨て同行など)
3. 日課・リズムの再構築支援(ただし押しつけない)
- 生活が無秩序であっても、まずは「起床・食事・排泄・活動・休憩・就寝」の流れをつくる
- 本人の好みや体調に合わせたリズムを整える(例:午前は活動的だが午後はウトウトする人には、午前に散歩・午後は静養など)
おわりに:その人の「時間のリズム」を尊重するという視点
認知症ケアにおいて「生活リズムを整えること」は、単に“規則正しい生活”を押しつけることではありません。
本人が長年培ってきた「時間の感覚」や「生活習慣」を尊重し、それを土台に安全な環境やケア体制をつくることこそが、転倒予防にも繋がるのです。
家族が持っている“生活の記憶”と、介護職が持つ“現在の支援スキル”とが協働してこそ、
その人にとって安心で安全な生活が成り立ちます。
生活リズムを知ることは、その方の”転ばない暮らし”を守るための第一歩です。
認知症のある方が「いつも通り」でいられるように。
その積み重ねが、転倒を防ぎ「その人らしい暮らし」を支えていくのです。
家族と介護職が一緒に考える「その人らしい暮らし」の守り方――この記事が、それを考えるきっかけとなれれば幸いです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
- 骨折を伴う転倒が深刻な理由とは? ~介護現場における11のリスクと予防のヒント~
- ヒヤリハットは未来を守るセンサー 〜ハインリッヒの法則から考える介護事故予防〜
- 【全7回】第1回:認知症高齢者が転倒しやすい6つの理由 〜原因と予防のために知っておきたいこと〜
- 【全7回】第2回:転倒の身体的要因とは? ~筋力・バランス・疾患との関係~
- 【全7回】第3回:「認知機能の障害」と転倒の関係 ~見えないリスクを理解して予防に繋げる~
- 【全7回】第4回:「また歩き出した…」その行動には理由がある ~BPSDの背景にある感情を知り、転倒を未然に防ぐ~
- 【全7回】第5回:認知症高齢者の転倒を防ぐために ~見逃せない「環境要因」とは~
- 【全7回】第6回:薬が多いと転びやすくなる? 〜認知症高齢者と「ポリファーマシー」の落とし穴〜
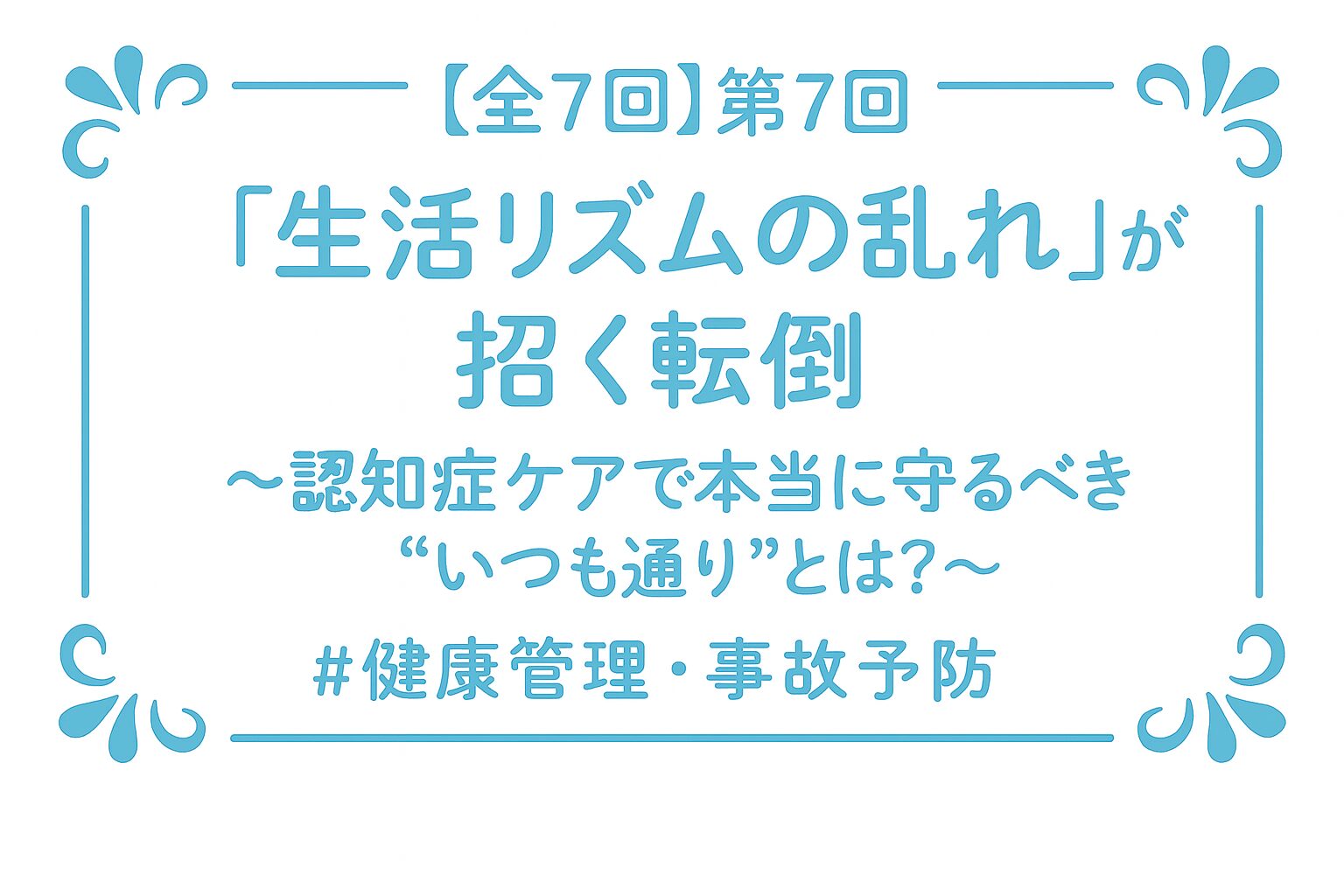

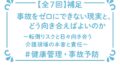
コメント