
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、環境要因が原因で起こる転倒の背景と予防策、本人の視点に立った環境整備の考え方が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
高齢者の転倒は、骨折や寝たきり、さらには命に関わることもある重大なリスクです。とくに認知症の方は、記憶や判断力、注意力の低下が重なることで、転倒リスクがさらに高まります。
「もしも」が現実になる、その前に――できる備えがあります。
転倒の原因には、身体機能の衰えや服薬の影響、生活リズムなどさまざまな要因がありますが、本記事では「環境要因」に注目します。私たちには“当たり前”に感じられる部屋や廊下の景色も、認知症の方にとっては“危険の連続”であることも少なくありません。
そして環境は、本人にとって使いやすいように整えることで転倒のリスクを大きく軽減できる、数少ない“変えられる要因”です。認知症ケアにおいて、環境整備の重要性を理解し、具体的にどこをどう見直せば良いかを、実例とともに解説します。
認知症の方にとって「環境」が危険になりやすい理由
私たちは、普段過ごす部屋や廊下の段差、照明、物の配置に注意を向けることは少ないかもしれません。しかし、認知症の方にとって、日常の環境は想像以上に「危険の入り口」になり得ます。
これは、認知症によって以下のような認知機能の低下が起きるためです。
- 注意の持続や分配が難しい(例:床の変化に気づけない)
- 見えていても意味が理解できない(例:黒いマットが“穴”に見える)
- 記憶の障害(例:物の配置を忘れ、つまずく)
- 見当識障害(例:場所や方向が分からず慌てて動く)
つまり、私たちにとっては何気ない空間でも、認知症の方にとっては“予測のつかない危険”が潜んでしまうのです。
さらに、環境要因のリスクは『転倒して初めて気づく』ことが多いため、ヒヤリハットが出るまで発見されにくかったり、生活に直結する不自由が感じにくいため対処が後回しになりがちです。しかし、見逃されやすいからこそ、日常的に注意と改善を積み重ねる価値があるのです。
環境要因の具体例と、転倒に至る仕組み
以下に、代表的な環境要因について具体例と転倒のしくみを紹介します。
1. 床の段差・敷居
具体例:
- 和室への敷居(数センチでも危険)
- 浴室・玄関の段差
転倒メカニズム:
- 「段差がある」ことに気づけず、つまずいてしまう
- 足の挙上が不十分でも本人は問題を感じていない
参考文献:
- 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)「高齢者の転倒・転落事故に関する調査」2020
2. 床材の滑りやすさ
具体例:
- 靴下で歩くフローリング
- 濡れた浴室の床
転倒メカニズム:
- 足の裏の感覚が鈍くなり、滑りに気づかない
- 認知症により「危ない場所」と認識できない
参考文献:
- 厚生労働省「高齢者住宅改修に関するガイドライン」2018年版
3. 照明不足や光のムラ
具体例:
- 廊下やトイレが暗い
- 夜間の活動時に足元が見えない
転倒メカニズム:
- 暗い場所が「影」や「穴」に見える
- 光と影の差が強いと、立体であると誤認してしまう
参考文献:
- Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. (1988). Risk factors for falls among elderly persons living in the community. NEJM, 319(26), 1701-1707.
4. 家具・什器の配置と動線の複雑さ
具体例:
- 通路にある車椅子や荷物
- 生活動線上に障害物がある部屋
転倒メカニズム:
- 記憶の障害で「昨日なかった物」にぶつかる
- 回避動作中にバランスを崩しやすい
参考文献:
- Dementia Australia. (2021). Changes in the environment and their effect on people with dementia
環境調整だけでなく「安心して動ける空間づくり」を
環境整備というと「手すり」や「段差の解消」などの“物理的な安全対策”が中心に語られがちです。
しかし、認知症ケアでは「本人の感じ方」に寄り添った工夫こそが、真の予防につながります。
たとえば、次のようなケースを経験したことはないでしょうか?
- 手すりを設置したが、本人が使わずに転倒した
- 黒い玄関マットに怖がって近づけない
- 自室の模様替え後に混乱して歩き回った
こうした場面は『本人の見えている世界』と『私たちの感覚』のズレによって起こります。
✔ その方の“目線の世界”を想像して、寄り添う工夫を
- 白い床に黒いマット:→「穴」に見えて立ち止まる → 明るい色のマットに交換
- 鏡に映る自分の姿:→「知らない人」と感じて不安 → 鏡に布をかけて視界から除く
- 夜の窓の反射:→「外に人がいる」と誤解 → レースカーテンや遮光カーテンで反射を防止
物理的に安全な環境であっても、本人にとって「意味のある・安心できる空間」でなければ、行動は予測困難になります。これが“安心して動ける空間”の鍵です。
家族と介護職、それぞれの視点からの環境整備
家族の視点:
- 「昔から使っていた物」を残したくなる
→ 安心感のある環境として大切ですが、つまずきのタネが隠れていないかの確認も必要です。
介護職の視点:
- 「安全性重視」で家具を動かす
→ ただし、本人が混乱しないよう、変更時は説明や段階的な調整が求められます。
互いの視点を尊重しつつ「今の本人にとって意味があり、安全な空間は何か」を共有していくことが、最も効果的な環境整備につながります。
おわりに
認知症高齢者の転倒を防ぐためには、「環境要因」に目を向けることが非常に重要です。
私自身も、何度も「もっと早く気づいていれば…」と悔やんだ経験があります。
でも、失敗を糧に、次はもっとその方に合った環境をつくろうと工夫を重ねてきました。
環境は“今日から変えられるケア”のひとつ。だからこそ、ケアをする私たちにとっても、とても希望の持てることだと思います。
焦らず、一歩ずつ見直していきましょう。
本人が安心して動ける空間をつくること。そのために、物の配置や照明だけでなく「どう見えているか」「どう感じているか」という“その人の世界”に寄り添うこと。そこにこそ、本当に意味のある環境整備のヒントがあります。
ご本人・ご家族・介護職員がともに視点を合わせ、環境を“安全かつ意味のあるもの”へと変えていく。それが、転倒のない日常と、穏やかな暮らしに繋がるはずです。
小さな工夫の積み重ねが、大きな安心につながります。
今日からできる「ひと工夫」を、ぜひ見直してみてはいかがでしょうか。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
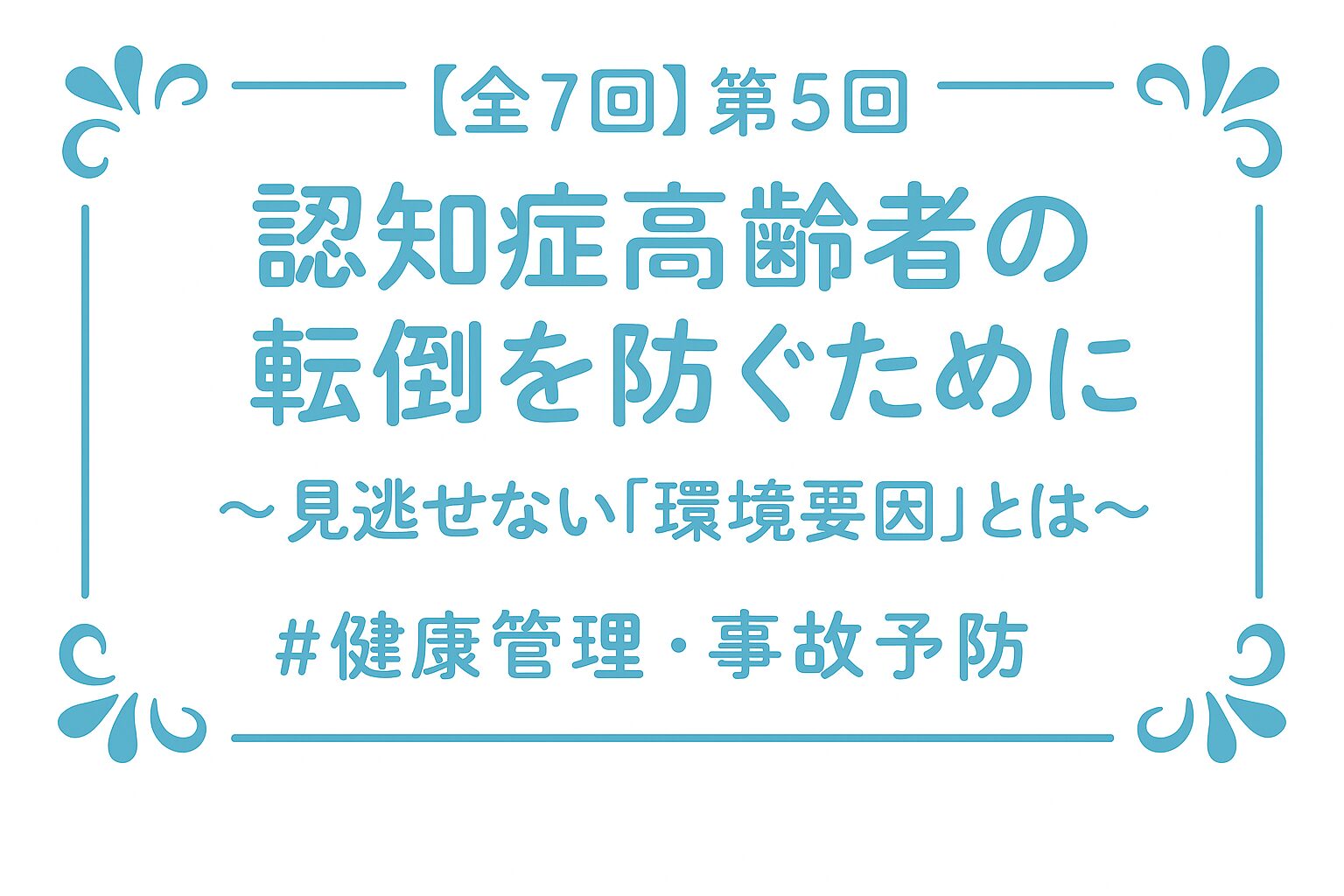


コメント