
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、BPSDが原因で起こる転倒の背景と予防策、BPSDとの向き合い方が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
「夜中にふらふらと動き出して転んでしまった」
「急に怒って立ち上がり、そのまま尻もちをついた」
「“あそこに人がいる”と急に動き出してよろよろと…」
こうした事例は、介護現場やご家族の間でよく見られる場面です。
そしてこれらの行動の背景には、多くの場合「BPSD(行動・心理症状)」があります。
認知症の方が転倒しやすくなる理由は“体の衰え”や“認知機能の低下”だけではありません。
本人の内面にある不安や混乱が、行動として現れ、それが転倒に繋がってしまうケースも少なくありません。
今回は、認知症の「BPSD(行動・心理症状)」が転倒にどう関わるのかを、具体的な例を交えてお伝えしていきます。そして、現場でできる予防策も一緒に考えていきましょう。
BPSDとは何か?
BPSDとは「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」の略で、認知症に伴って現れる行動や心理的な症状を指します。
具体的には、以下のような症状があります。
- 探索的行動(本人なりの理由で歩き回る。※徘徊(無目的に歩き回る)とは別です)
- 焦燥や落ち着きのなさ
- 不安・恐怖・被害妄想
- 幻覚・幻視
- 睡眠障害(昼夜逆転、夜間覚醒など)
- 抵抗・攻撃的な言動
これらの症状は、本人の意思や感情に基づいた行動であると同時に、予期しない動き・危険な行動に繋がりやすく、結果として「転倒」の大きな要因となります。
BPSDによる転倒の具体例とその背景
① 探索的な歩行による転倒
夜間、静かにベッドを抜け出し、廊下を歩き回っている途中で家具にぶつかり、転倒してしまう——。
このような事例は、特別珍しいものではありません。
背景:
探索的な歩行と徘徊とは、本来は区別されるべきものです。
そして、このような探索的な歩行の多くには、本人なりの“目的”が隠れています。
「トイレに行きたい」「家に帰りたい」「何かを探している」など、本人にとっては意味のある行動なのです。
しかし、認知症の影響で時間や場所の認識が曖昧になっているため、現実とのズレが生じます。
また、過去の生活リズムや記憶の残像(たとえば子育てや仕事)に従って動こうとするケースもあります。
このような“探索的な歩行”は、しばしば周囲から見ると「無目的」「落ち着きがない」と捉えられがちですが、本人にとっては「今、やるべきこと」だったりするのです。
問題はその行動そのものではなく、環境やタイミングとの“ズレ”によって転倒などの事故に繋がることです。
対策のヒント:
- 夜間の動線を確保し、足元灯などで安全を見守る環境整備をする
- 定時のトイレ誘導や、帰宅願望が強い時間帯への対応など、ニーズの“先取り”を意識する
- 無理に止めるのではなく、気配を感じ取れる距離での見守りや、“行動の理由”を見つける対話を心がける
探索的な行動は、制限する対象ではなく“気づきのきっかけ”と捉える視点が重要です。
「なぜ動いたのか」を考えることが、転倒予防だけでなく、その人らしさへの理解にも繋がります。
② 幻視・妄想による転倒
「玄関に誰かが来ている」「子どもがあそこにいる」といって急に歩き出し、段差でつまずいて転倒——。
こうした場面も、認知症の方に特有の行動として現れることがあります。
背景:
認知症の中でも、特にレビー小体型やアルツハイマー型の中期以降では、視覚情報の誤認や幻視が見られることがあります。
また、過去の記憶や強い感情に引き寄せられた“意味づけ”が、妄想として現れることも少なくありません。
その際、本人にとっては幻視や妄想は“現実そのもの”であり、驚きや恐怖だけでなく、具体的な行動に結びつくことがあります。
例えば、「知らない人が部屋にいる」「家族が外にいる」といった状況を信じてしまい、急いで移動しようとすることでバランスを崩し、転倒に至るのです。
特に夕方〜夜にかけて不穏・錯乱が強まる“夕暮れ症候群(サンセット症候群)”との関係も指摘されています。
対策のヒント:
- 部屋の照明や窓の映り込み、床や壁の模様など“誤認を招きやすい要素”を最小限に整える
- 幻視を否定せず「そう思われたんですね」と受け止めながら動きを落ち着ける声かけを心がける
- 症状の頻度や内容が生活に影響している場合は、医師と相談し薬物療法や治療方針の見直しも視野に入れる
幻視や妄想は、病的な症状ではありますが、そこに“感情”が伴っている点に注目することが大切です。
「怖かったのかもしれない」「誰かに会いたかったのかも」——そうした解釈が、関わり方と予防策を変えていきます。
③ 抵抗・攻撃的言動による転倒
介助の声かけに対して手を振り払うような仕草を見せ、そのままふらついて転倒してしまう。
あるいは、怒りをあらわにしながら立ち上がり、足元が定まらず尻もちをつく——。
こうした状況も、介護の現場では日常的に見られます。
背景:
認知症のある方が抵抗的・攻撃的になるとき、その多くは“わからない”という不安や混乱が背景にあります。
急な声かけ、体に触れられる驚き、予定外の介助――本人にとっては「自分の身に何が起こるのか分からない」という状況なのです。
また「尊厳を守られたい」という思いや、「自分でできる」と思っている自負がある場合、それが否定されたように感じ、怒りの反応として表れることもあります。
介助者との関係性やタイミング、声のトーン、非言語的な距離感が行動を左右することも少なくありません。
対策のヒント:
- 命令ではなく“提案・選択肢”を含んだ声かけに変える(例:「立ちましょう」→「立ちますか?それとももう少し休まれますか?」)
- 表情・声のトーン・手の出し方など非言語的な配慮を丁寧にする(威圧的にならないよう注意)
- 本人が「自分で決めた」と感じられるような関わりを意識し、安心と信頼を積み重ねていく
抵抗や攻撃的な言動は「性格が変わった」と捉えられがちですが、その多くは環境や関わり方によって緩和される“サイン”でもあります。
不安や混乱に気づき「どうすればこの人は安心できるか?」を問い直すことが、転倒のリスクを下げる第一歩となります。
④ 睡眠障害からくる転倒
夜間に何度も覚醒し、ふらついたまま歩き出して転倒してしまう——。
そんなケースは、認知症の方に限らず高齢者全般に多く見られます。
背景:
昼間の活動不足や体内リズムの乱れにより、夜に眠れず、日中に眠くなる「昼夜逆転」の状態が生じやすくなります。
また、過去に夜勤のある仕事をされていた方や、生活パターンが不規則だった方は、その影響が長く残っていることもあります。
こうした生活リズムの乱れは、自律神経のバランスにも影響します。
本来、日中は交感神経(活動モード)、夜間は副交感神経(休息モード)が優位になることで、自然な眠気が訪れます。
しかし、認知症のある方ではこの切り替えがうまくいかず、夜間にも交感神経が優位なまま覚醒状態が続いてしまうことがあります。
その結果、ふらつきや注意力の低下、転倒といったリスクが高まるってしまいます。
対策のヒント:
- 日中の活動を意識的に確保する(散歩、軽体操、屋外での日光浴など)ことで、夜の自然な眠気を促す
- 午後遅くの長時間の昼寝や、夕方以降のカフェイン摂取を避けるなど、眠気を高める工夫をする
- 夕方以降はテレビや照明の刺激を減らし、リラックスできる音楽やアロマを取り入れるなどして、副交感神経を優位に切り替える環境を整える
このように、「眠れない」から「動く」→「転倒する」という連鎖の根底には、生活リズムと自律神経の乱れがあります。
“眠らせる”ことを目的にするのではなく「眠れる状態を整える」ことが、転倒予防にも繋がるという視点が大切です。
「行動を抑える」のではなく「背景を理解する」
BPSDによる転倒を防ぐために最も大切なのは“行動そのものを問題視する”のではなく“その背景を理解しようとする姿勢”です。
探索的な歩行、幻視、抵抗的な言動——
それぞれに、本人なりの「理由」があります。
- 探索的な動きは、その人の記憶や感覚、目的や習慣が反映されている証かもしれません
- 抵抗は「自分が何をされるのかわからない」という不安のサイン
- 幻視は、記憶の断片が意味づけされ、現実と混ざり合った“理解の形”かもしれません
このように「なぜその行動を取ったのか?」と一歩立ち止まって考えることで、
行動の背後にある思いや不安に気づけるようになります。
決して完璧にわかってあげる必要はありません。
「もしかしたら、こう感じていたのかも」と想像しようとする姿勢だけでも、転倒の予兆に気づく感度が高まり、よりよい関わりに繋がっていくはずです。
環境と関わり方の“二本柱”で支える転倒予防
BPSDがあるからといって「危ないから動かさない」「ベッドに縛る」といった対応に頼るのは避けたいものです。
それは本人の自由や尊厳を奪うだけでなく、筋力や意欲の低下を招き、かえってBPSDの悪化を引き起こすという悪循環につながることもあります。
だからこそ、転倒予防において大切なのは、
- 本人の“動きたい理由”に寄り添うこと
- 安心して動ける“環境と関係性”を整えること
という2つの柱を、バランスよく支える視点です。
転倒を防ぐというと、動きを制限したり、監視を強化したりといった発想になりがちです。
しかし、認知症ケアにおいては「どのように安全に動いてもらうか」「どうすれば安心して動けるか」という考え方が大切になります。
環境の整備や声かけの工夫は、本人の“生きる力”を守ることにもつながります。
私たちに必要なことは、本人の動きを“止める”ことではなく、安心して動けるように“支える”ことなののだと、私は思います。
おわりに:BPSDの奥にある「その人らしさ」を見失わないために
BPSDは、認知症介護の中でも特に対応が難しいと言われます。
たしかに、驚きや戸惑いが多い領域ですし、周囲が疲弊してしまうこともあります。
けれども、それは同時に“その人らしさ”や“人生の記憶”がにじみ出る瞬間でもあります。
- 探しているものは、もしかしたら大切な思い出かもしれません。
- 抵抗の裏には、過去の誇りや自立心が残っているのかもしれません。
- 幻視は、今ここにいない誰かと“再会している時間”なのかもしれません。
私たちができるのは、それらの行動を『困った行動だ』とただ否定するのではなく「その人にとって、どんな意味があるのか」を一緒に想像してみることです。
「転ばせない」ことを目標にするだけでなく、
「この方がどうすれば安心して過ごせるか」を考えること。
その視点こそが、結果として転倒の予防につながっていきます。
行動の裏にある思いに気づき、関わりを丁寧に重ねていくこと。
それが、認知症ケアにおける“本当の転倒予防”なのではないでしょうか。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
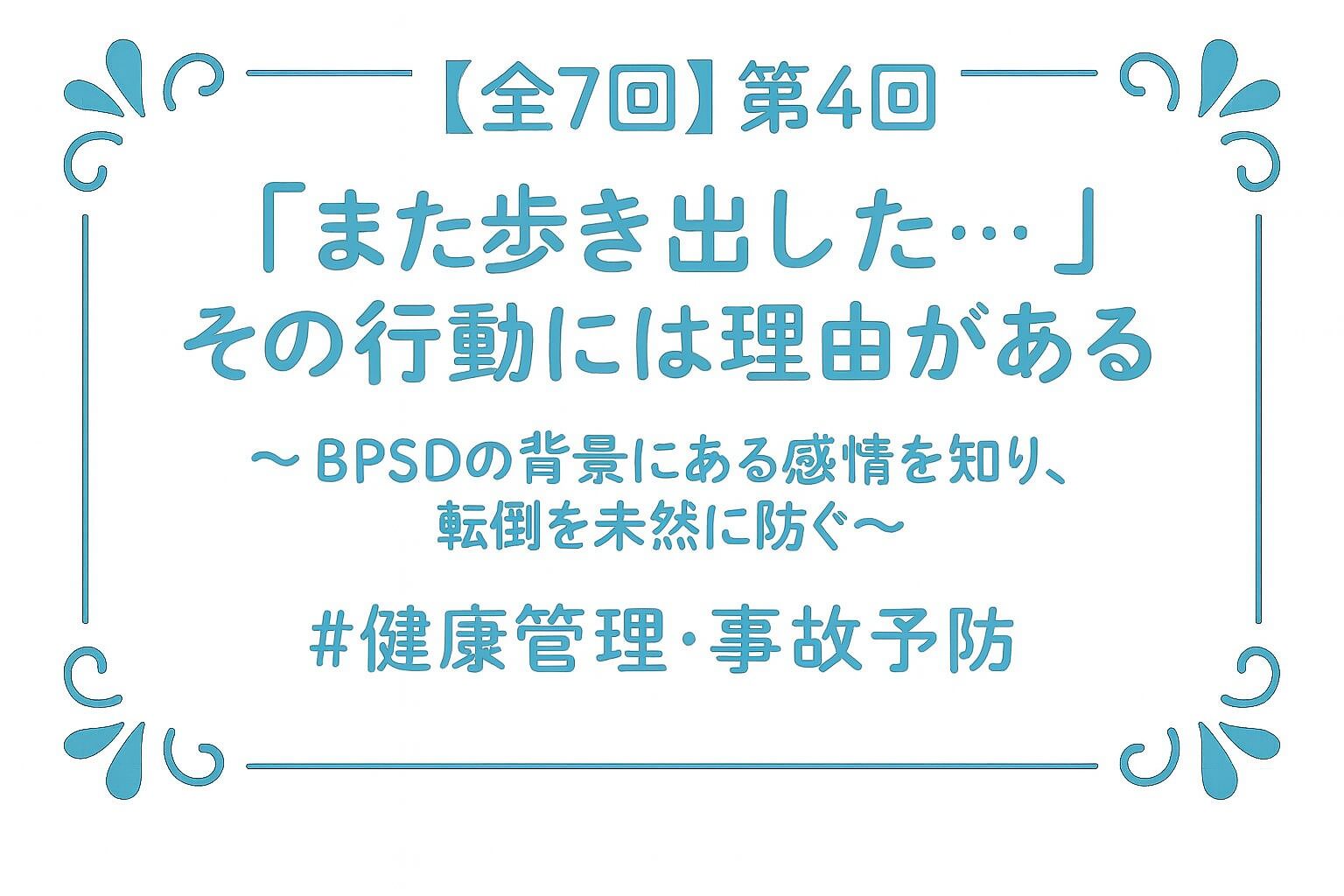


コメント