
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、施設の「普通」と本人の「普通」の違いを理解することで、介護の質と関係性がどう変わっていくのかが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
導入:Aさんのエピソード
これからご紹介する事例は、決して特別なものではありません。
現場では「施設の普通」と「本人の普通」が違うために、誤解や摩擦が生まれることは少なくありません。
このエピソードを通じて、私たちが当たり前に使う『普通』という言葉の危うさと『その人らしさ』を突き詰める素晴らしさを感じていただければと思います。
Aさんは80代の女性。
小さい頃から農家の家に育ち、若い頃からずっと忙しい日々を送ってきました。
お風呂に入るのは、週に一度。
土曜日の夜に、薪で焚いたお湯にゆっくり浸かるのが当たり前でした。それは結婚してからも変わらず、家庭を持ち、子育てを終えたあともずっと続いてきた生活習慣です。
やがて認知症の症状が出始めました。
家族の希望もあり、Aさんは介護施設に入居することになりました。その施設では、衛生面や入居者の快適さを考え、週に2回以上の入浴が“普通”とされていました。
入居して間もない頃、Aさんは職員にこう話しました。
「私、お風呂は週に1回でいいのよ。長年そうしてきたからね。」
1回目の入浴は気持ちよく受けますが、週の2回目になると「今日は結構です」とやんわり断ることがありました。
ところが、このやり取りが次第に職員の中で「入浴拒否」という言葉に置き換わっていきます。
「また断られた」「お風呂に入ってくれない」
そんな声が申し送りで交わされるうちに、Aさんは“介助を断る人”“少し面倒な人”というイメージがついてしまいました。
現場での「ラベリング」が起きる仕組み
介護の現場では、「拒否」という言葉が頻繁に使われます。
入浴拒否、服薬拒否、食事拒否――
確かに介助がうまく進まなかったときの状況を短く表すには便利ですが、この言葉には職員目線の評価が強く含まれています。
「拒否」と言った瞬間、そこには「必要なケアを提供しようとしたのに、本人が受け入れなかった」という構図が生まれます。そして、その背景や理由が置き去りにされがちです。
さらに、こうした評価はチーム内で共有されやすく、次第に固定観念となります。
「Aさんは入浴拒否がある人だから…」
そんな情報が先に頭に浮かぶと、職員は最初から“断られること”を前提に接してしまいがちです。これは結果として、本人との関わりを避けるきっかけにもなります。
こうして「介護が困難な人」「面倒な人」というレッテルが、知らず知らずのうちに現場で作られていくのです。
本当は「困った人」ではなく「困っている人」
Aさんは、本当に介護を拒んでいたのでしょうか?
実際には、長年続けてきた生活リズムや価値観を守っていただけです。週2回の入浴は、Aさんにとっては“多すぎる”ものであり、心地よい暮らし方ではありませんでした。
認知症になっても、これまでの生活習慣や好みは深く身に染みついています。むしろ、認知症によって新しい習慣への適応が難しくなり、長年のやり方を守ろうとする傾向は強くなることもあります。
職員が「当たり前」と思っていることは、必ずしも本人にとっての当たり前ではありません。
違いがあるだけで、それは“拒否”でも“困難”でもなく、単なる意思表示です。
しかし、この意思表示が受け止められず、施設側のルールや習慣に合わせるよう求められると、本人は不安や不満を感じやすくなります。その結果、表情が険しくなったり、声を荒らげたりと、余計に“拒否”と見なされる行動が出ることもあります。
「その人を知る」ために必要な視点
Aさんの事例から見えてくるのは、ケアの質は“その人を知る深さ”に比例するということです。
単に名前や病歴を知っているだけでは、その人の本当の暮らしや価値観は見えてきません。
具体的にどう知るのか?
- 生活歴の聞き取り
- 生まれ育った場所や家庭環境
- 職業や仕事内容
- 趣味や楽しみにしていたこと
- 季節ごとの習慣(盆や正月、農繁期などの行事)
- お風呂・食事・睡眠などの生活リズム
- 清潔に関する考え方(頻度やタイミングのこだわり)
この背景を知っていれば、入浴頻度の理由が理解できます。
- 好き・嫌いの把握
- 好きな食べ物、苦手な食感や匂い
- 好きな音楽や番組
- 居心地のいい場所や時間帯
- 嫌なこと・避けたいこと
- 家族・本人からの情報共有
- 入居時の面談だけで終わらせず、生活の変化に応じて定期的に聞き取りを行う
- 写真やアルバムを見ながら会話すると記憶が引き出されやすい
- 家族が来訪したときに「最近の様子」と「昔の習慣」をセットで確認する
- 日々の観察からの記録
- 表情や声のトーン、行動のきっかけを記録する
- 「入浴時に機嫌がいいのは午前中」など小さな発見を共有
- チームで同じ情報を持つことで対応のばらつきを減らす
それをすることで得られる効果
- 拒否やトラブルの減少
本人の習慣や価値観を尊重することで「なぜそれをしなければいけないのか」という不安や抵抗が減ります。 - 信頼関係の構築
「自分のことを分かってくれている」という安心感が生まれ、介助を受け入れやすくなります。 - ケアの効率化
好きな時間・方法を把握して介助すれば、無理な声かけや説得が減り、職員の負担も軽くなります。 - 本人らしい生活の継続
施設に入っても「自分らしさ」を保てるため、生活の満足度や心の安定につながります。
こうした視点を持つことは、「拒否をなくす」ためだけでなく、本人の人生を尊重しながら、職員も楽に働ける環境を作るための土台になります。
つまり「その人を知る」ことは、本人と職員の双方にとってメリットがあるのです。
一律サービスの弊害
施設では、衛生管理や安全確保、職員のシフト調整のために、ある程度統一されたスケジュールやルールが必要です。
しかし、その“全員一律”のやり方は、本人にとっての心地よさや安心感と衝突することがあるのです。
現場でよくある弊害の例
- 入浴回数や時間の固定
- 全員を週2回、同じ時間帯に入れる
→ 夜型の人は朝の入浴が苦痛
→ 冬場は寒さがつらく、風呂の日が憂うつになる
- 全員を週2回、同じ時間帯に入れる
- 食事時間の一斉提供
- 朝食は7時半、昼食は12時と決まっている
→ 朝はゆっくりしたい人や、昔から遅めの食事の人にとってはストレス
→ 空腹感や食欲に合わず、残食が増える
- 朝食は7時半、昼食は12時と決まっている
- レクリエーションの全員参加
- 毎日午後は体操や工作などを全員で
→ 静かに過ごしたい人、ひとりで読書やテレビを楽しみたい人にとっては疲れる時間になる
- 毎日午後は体操や工作などを全員で
なぜこうなるのか?
- 職員のシフトや作業効率を優先しやすい
- 「皆同じほうが公平」という考えが無意識に働く
- 個別対応に必要な情報や人手が不足している
弊害の結果
- 拒否や不機嫌の増加:「なんでそんなことをしなきゃいけないの」という感情が高まる
- 生活満足度の低下:本人にとって大切な日課や習慣が崩れる
- 職員のストレス増加:拒否対応や説得が増えてしまう
個別ケアのメリット
一律サービスの枠をゆるめ、その人の“普通”に合わせるだけで、現場の雰囲気は大きく変わります。
実際にできる工夫
- 時間帯の柔軟化
- 入浴は午前・午後・夕方の選択肢を用意
- 食事は「先に食べたい人」「少し遅く食べたい人」に対応
- 頻度の調整
- お風呂は週1回でも、清拭や足湯で清潔保持
- レクリエーションは希望者のみで、静かに過ごす選択肢も用意
- やり方の変更
- 洗髪だけ別日にする
- 食事を部屋で食べられるようにする(体調や気分に合わせて)
得られる効果
- 拒否やトラブルの減少:本人に合わせることで、介助がスムーズになる
- 信頼関係の向上:「自分のことを分かってくれている」という安心感が生まれる
- 職員の負担軽減:説得や強引な介助が減り、気持ちにも余裕が生まれる
- 生活の質(QOL)向上:本人が「ここで暮らしてよかった」と感じられる時間が増える
つまり、一律サービスは効率性や公平性の面で必要ですが、それだけに頼ると本人の満足感や信頼を失うリスクがあります。
個別ケアは一見手間に見えますが、長期的には本人も職員も楽になる方向に働きます。
職員自身の振り返り
介護職員は日々忙しく、効率や安全を優先するあまり、本人の背景や思いをゆっくり考える時間が持ちにくい現実があります。それでも、ときどき立ち止まって自分に問いかけてみることが必要です。
- 自分の「当たり前」を、本人に押し付けていないか
- ルールや習慣が、本人の生活の質を下げていないか
- 「拒否」という言葉で、本人の意思や背景を見落としていないか
こうした振り返りをチームで共有し「面倒な人」ではなく「この人にはこういう背景がある」と理解を広げることが大切です。
まとめ
こうした視点を持つことは、大きな改革ではありません。
日々の小さな関わりを意識してちょっと変えてみるだけでも、その人との関係や施設全体の空気を、少しずつ良い方向に変えていくことができます。
「介護が困難な人」「面倒な人」という印象は、必ずしも本人の中に最初からあったものではありません。
それらの印象は、私たち支援者の目の向け方や、施設のルール、職員それぞれの都合や価値観によって、静かに形づくられてしまうことがあります。
Aさんの「入浴拒否」とされた行動も、実は“拒む”ためのものではありませんでした。
それは、長い年月をかけて身についた暮らしのリズムを守ろうとする、ごく自然な自己表現だったのです。
自分の普通を手放さないことは、その人にとっての尊厳を守ることでもあります。
介護の原点は、私たちの基準に合わせてもらうことではなく、その人の歩んできた道にそっと寄り添い、その人らしさを支えることにあります。
だからこそ、私たちがまずすべきことは、本人の歴史や価値観を知ること。そこから見えてくる“その人にとっての普通”を大切にすることです。
そうした日々の積み重ねが、やがて「困った人」というラベルを消し「ここで暮らせてよかった」という安らぎに変わっていくことでしょう。
そのとき初めて、私たちはその方の本当の笑顔に出会えるのかもしれません。
その瞬間、介護する私たちの顔にも、自然と笑顔が浮かんでいることでしょう。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
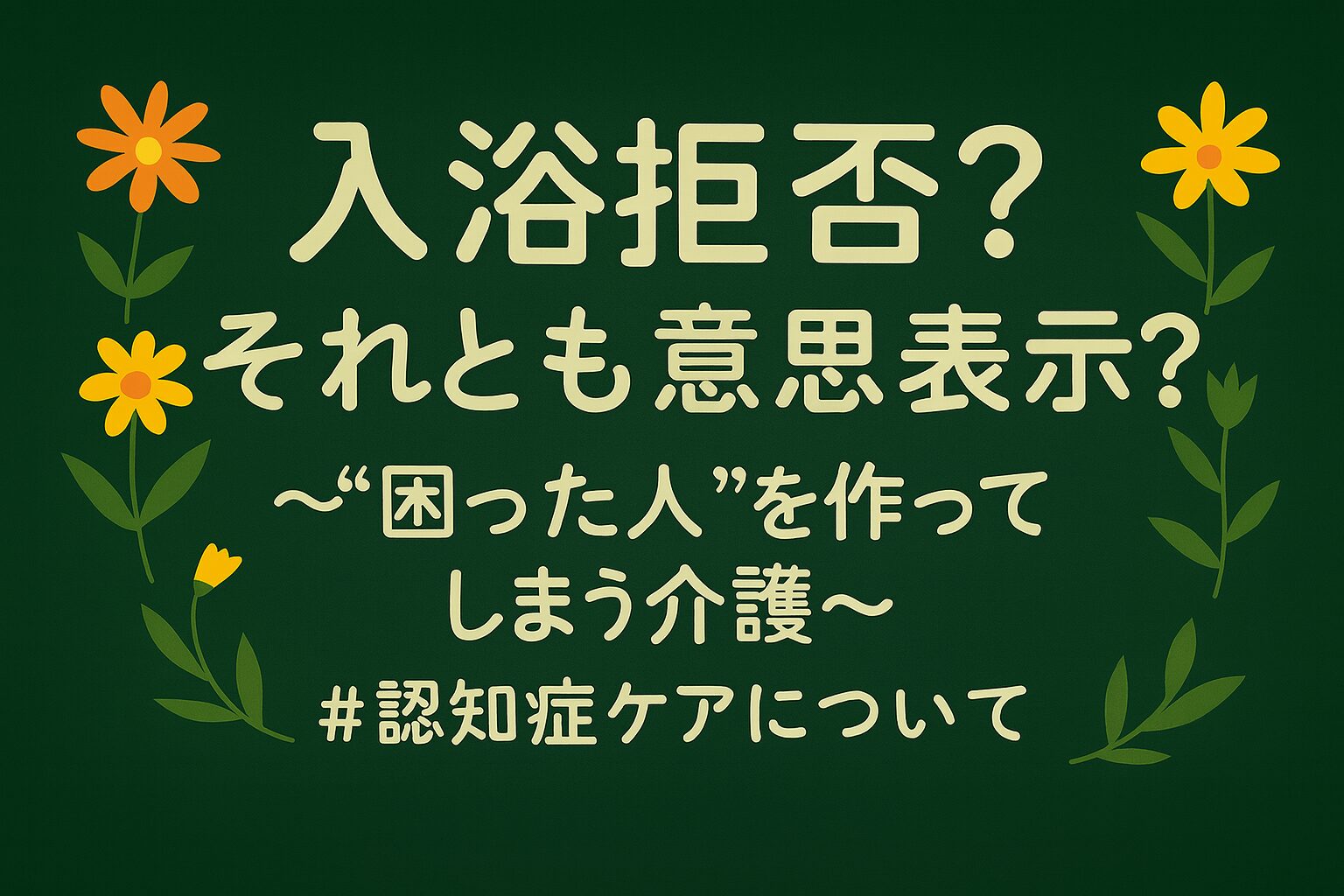
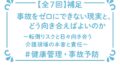
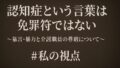
コメント