
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では“常識”や“当たり前”に揺さぶられながらも「その人らしさ」と向き合うケアのあり方が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
「夜はパジャマに着替えるのが普通でしょ?」
「ご飯は決まった時間に食べるのが当たり前」
「テレビは9時で消しましょう」
――介護の現場では、こうした言葉が無意識のうちに飛び交っています。
そのどれもが、一見すると秩序を守るために当然の言葉に思えます。
でも、それは本当に“その人”のためのケアでしょうか?
介護の現場では、職員の「常識」や「当たり前」が、いつの間にか“ケアされる側”の「その人らしさ」を塗り替えてしまうことがあります。
この記事では、私たちが日々当たり前のように使っている“常識”という言葉の背景を見つめ直し
「その人にとっての普通」を大切にするケアとは何かを考えてみたいと思います。
「常識」の正体 ~それは誰のもの?~
人は誰しも、自分が育ってきた環境や文化、経験をもとに「これが普通」「こうするのが当たり前」と感じながら生きています。
しかしその「普通」は、決してすべての人に共通するわけではありません。
たとえば、ある高齢の女性は「夜は普段着のまま布団に入るのが一番」と語っていました。
ところが施設では「夜はパジャマに着替えるのが普通だから」と、職員が毎晩更衣を促すようになり、やがて女性は、次第に不安げな表情を見せるようになりました。
この例のように「本人にとっての普通」が「施設の普通」に押し流されてしまうことは、決して珍しくありません。
“常識”とは、あくまでその人自身の生活の中で育まれてきた価値観であり、それは他人の“常識”とは異なるものです。
それを押しつけてしまうことは「配慮」の名を借りた“侵略”にもなり得るのです。
なぜ「施設の普通」が優先されるのか?
もちろん、施設で生活する以上、全てが自由というわけにはいきません。
複数人が共同生活を送る場では、一定のルールや流れを設けることで安全性や効率性を担保する必要があります。
職員の多くも実際は「良かれと思って」そのルールを守らせようとします。
- 転倒リスクを減らすために夜間の動線を制限
- 食事を一定時間内に済ませることで厨房オペレーションを最適化
- 見守りを効率化するために起床・就寝時間を画一化 など
これらはどれも「施設運営」上、一定の合理性を持っています。
ただし、それが行き過ぎると「人」ではなく「枠」にケアを合わせてしまう事態に陥ります。
「その人にとっての普通」を考えるとは?
では「その人にとっての普通」を尊重するには、何が必要なのでしょうか。
それはまず“その人をよく知ること”から始まります。
- どんな暮らしをしてきたのか
- どんなことに安心を感じるのか
- どんなリズムで生活していたのか
- 何を「嫌だ」「苦手だ」と感じるのか
これらを知ることができれば、たとえば以下のような調整も可能になります。
- 「パジャマではなく普段着で就寝したい」という希望を尊重する
- 「早朝4時に起きるのが習慣だった」という方には無理に二度寝を促さず、早朝対応を工夫する
- 「昼食は遅めが好き」という方には、主食だけ時間差対応をする
とはいえ、すべてを完全に個別対応するのは、やはり現実的ではありません。
でも「この人にとっての“心地よさ”とは何だろう」と考える姿勢が、ケアの質を大きく変えていくのです。
生活歴の「引き継ぎ」が、ケアの質を左右する
では、どうすれば「その人にとっての普通」を実現できるのでしょうか。
その鍵のひとつが「生活歴の引き継ぎ」にあります。
たとえば入居前のアセスメントで
- どんな生活をしてきたのか
- どんな時間帯に活動するのが心地良いのか
- 食事や排泄、入浴のこだわりはあるか
などを聞き取ることは多いでしょう。
しかし、形式的な聞き取りやチェックシートだけでは、その人の“深い当たり前”までは掘り下げきれないことが少なくありません。
“記録”から“共有”へ、引き継ぎの意味を変える
大切なのは「その情報が共有されて、初めて活きる」という意識です。
情報があるだけでは、ケアに大きな影響を与えることはないでしょう。
その人の生活にとって“当たり前だったこと”が、職員の中で「気にかけるべきこと」として共有されなければ、実際のケアの中で活かされることはありません。
たとえば「一日三回のお茶が楽しみだった」という一言が共有されていれば、スタッフの対応や関わり方も変わります。
逆に「昔から一人でお風呂に入るのが落ち着く」と知っていながら、毎回2人対応で介助が入るような場面が続けば、それは“その人らしさ”の剥奪になってしまいます。
私たちの情報共有の質が、そのままケアの質につながる。
「記録するための聞き取り」ではなく「ケアに活かすための理解」を深めていくことが求められます。
現場で生まれるジレンマと向き合う
「その人らしさを大切にしたい。でも、全員に合わせるのは無理」
介護の現場でよく聞く、現実的な悩みです。
実際、ルールを柔軟にすればするほど、他の入居者や職員への負担が増えるケースもあります。
- 一人だけ朝食の時間をズラせば、厨房が二重対応に
- 自由な入浴時間を認めれば、職員の配置が困難に
- 夜間の見守りが難しくなるため、就寝時間の自由度が下がる
こうした問題は、単に「個別ケアが大事」と理想を掲げるだけでは解決しません。
「個人」と「集団」
「自由」と「安全」
このジレンマをどう乗り越えるかが、介護の専門性であり、現場のリーダーの手腕でもあるといえるでしょう。
「正しさ」ではなく「心地よさ」で判断する視点
介護の場面では「こうした方がいい」「この方法が安全」という“正しさ”を基準に、ケアの方向性を話し合い、判断することがあります。
たしかに、集団生活では一定の秩序や効率、安全性の担保が不可欠です。
しかし、こうした“正しさ”がいつの間にか、その人自身の「心地よさ」や「安心」を後回しにしていないか――その視点もまた、不可欠なのです。
“正しいケア”が、心地よさを奪っていないか
たとえば
- 姿勢よく車いすに座る
- 決まった時間にトイレに行く
- 夜は同じ時間に消灯する
どれも「正しい」とされる対応かもしれませんが、本人が「落ち着かない」「眠くない」「無理に起こされるのが苦痛」と感じていたとしたら、それは本当に“ケア”と呼べるのでしょうか。
“正しさ”と“心地よさ”のバランスをどう取るか――
それは個別ケアを実践するうえでの重要な視点です。
介護において必要なのは「マニュアル通りの正解」ではなく、
その人にとっての「ちょうどよい選択肢」を、現場で一緒に探していく姿勢ではないでしょうか。
リーダーや管理職に求められる役割
現場で「その人にとっての普通」を実現していくには、リーダーや管理職の存在が重要です。
単にルールを決めるのではなく「柔軟性の余地」を見出し、職員の声を聴きながら調整していくことが求められます。
リーダーの役割とは
- 職員が「当たり前」だと思っていたケアに、疑問を持てるよう促す
- 「これは誰のためのルールなのか?」を職員と一緒に考える
- 個別対応と集団対応のバランスを、現場の意見をもとに調整する
- 職員が「やってみよう」と思えるような支援的な声かけをする
管理者の役割とは
- 制度やマニュアルの見直しに柔軟性を持たせる
- ケア記録の中で「本人の希望・背景」に関する項目を重視する
- 多少のコストや非効率を「その人らしさのための必要経費」と捉える文化を育てる
こうした取り組みを通じて“施設の常識”が“その人の暮らし”を守るために使われるようになっていきます。
「生活の場」としての視点を忘れない
私たちは時に「施設は“介護の場”である」という意識が強くなり過ぎてしまうことがあります。
でも、本来の施設は“生活の場”であるはずです。
“介護の場”ではなく“暮らしの場”として
自宅での暮らしと同じように「好きな時間に起きる」「ごはんを食べたくないときは食べない」「見たい番組を最後まで観る」――そうした小さな選択の積み重ねが、その人の“日常”であり“尊厳”なのではないでしょうか。
「全員の自由」「全ての希望」を叶えることは難しくても
「その人が“その人らしく”暮らせる余白」は、現場の工夫と対話で作っていくことができます。
私たちが関わっているのは、単なる“入居者”ではなく“人生を歩んできた先輩”です。
その原点に立ち返ることで「施設の当たり前」が変わるきっかけになるかもしれません。
終わりに 〜常識を疑うことから、専門性は始まる〜
「普通はこうする」「当たり前でしょ」
この言葉を使うとき、私たちは無意識に“自分の価値観”を基準にしてしまいがちです。
でも介護は「その人にとっての人生」を支える仕事です。
だからこそ必要なのは「自分の当たり前」を一度脇に置き、
“その人の当たり前”を想像する力
そして
“施設の当たり前”を見直す勇気
です。
すべてを個別にできなくてもいい。
「何が正しいか」も大切だけど「何が心地よいか」を中心に考えることもできる。
そんな現場、そんな、生活の場でありたい。
その一歩は、私たち自身が「常識」を疑うところから始まるのだと思います。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
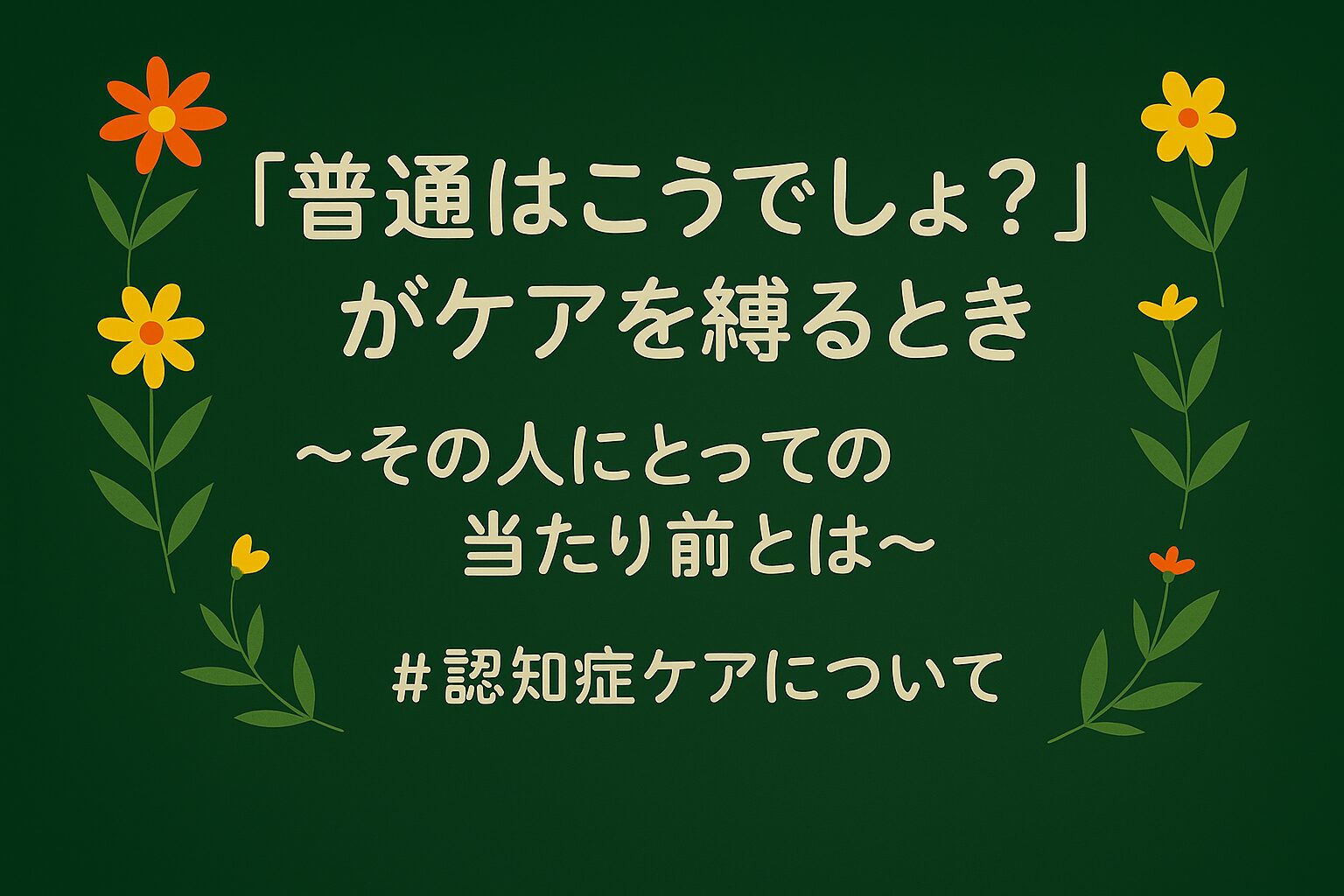


コメント