
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
【この記事で伝えたいこと】
認知症ケアで最も大切なのは、技術よりも「その人を思う気持ちと姿勢」。
ケアは“手段”であり、目的はその人らしく生きられるよう支えることです。
【要点】
- ケアの根本は、その人の尊厳と“らしさ”を守ること
認知症になっても、その人がその人らしく生活できるように支えることがケアの目的だと分かります。 - 技術より先に“思い”が原点となり、ケアの質を決める
どれだけ技術を磨いても、目の前の人を大切にしようとする気持ちがなければ、良いケアにはならないと気づけます。 - ケアは目的ではなく、人生を支えるための手段である
介護技術の提供がゴールではなく、「安心・笑顔・その人らしい日常」を実現するための道具だと理解できます。
【この記事で分かること】
・認知症ケアの本質=「目の前の方への思い」であることが分かる
・技術や専門性は、その人を支援するための道具に過ぎないと理解できる
・家族も地域も、日常の小さな関わりで“ケアの担い手”になれると気づける
家族介護・介護職のどちらでも、安心と安全を守るケア判断がすぐに実践できる内容です。
※詳しい説明・根拠・事例は、このあと本文でやさしく解説します。
認知症ケアとは
厚生労働省は『認知症ケアの理念』として
『認知症のために見失われがちなその人の尊厳、個性、可能性、求めている事(願い、希望)を見出して、本人がその人らしい生(生命、生活、人生)をまっとうできるよう支えていく』
と述べています。
(出典:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」より)。
また『認知症ケア』について少し調べてみると
『認知症の方の尊厳を守りつつ、その人らしい生活を支えること』
とあります。
認知症ケアが大切にしているもの
どうやら『認知症ケア』とは
- 認知症の方の尊厳を見出し守ること
- 認知症となっても、その人らしい生活(生命、人生)を支えること
でということであるようです。
こうした言葉を改めて読み解くと、認知症ケアが目指すものの輪郭がよりはっきりしてきます。
認知症ケアが大切にしている視点
認知症の方は、記憶や判断力の低下により、自分の意思や希望をうまく表現できないことがあります。だからこそ、周囲がその人の内側にある「思い」に気づき、言葉にならない声を拾い上げることが求められます。
認知症ケアとは、その人の背景や価値観、生きてきた歴史を想像しながら、今この瞬間の“らしさ”を支える営みとも言えます。
表面的な行動だけに目を向けるのではなく、なぜそのような言動になるのかを丁寧に読み解こうとする姿勢が、まさに尊厳を支えることに繋がるのです。
認知症ケアを知る目的
実は、認知症ケアの知識や技術だけを習得しても、十分とは言えません。
大切なのは『目の前で困っている人を助けたい』という思いです。
つまり『より良い認知症ケア』だけを学んでも役に立ちません。
認知症ケアを行うためには、大前提として『目の前で困っている人を助けたい』という思いで動き出せる、ということが必要です。
そして『目の前の人が認知症だった時』に役立つ考え方や技術が、認知症ケアなのです。
認知症ケアは特別なスキルではない
認知症ケアは
- 認知症の方の困りごとにはどのような傾向があるか
- その困りごとに対応するには何を知っている必要があるか
- 認知症の方に接する時に気を付けたいこと
などを知ったうえで『目の前の人を支援する』というだけなので、多少の知識は必要かもしれませんが、深い専門性が無くても、相手のことを思いやる気持ちがあれば、認知症ケアは自然と身についていきます。
もちろん、最低限の知識や心構えを学んでおくことは、より良い支援に繋がるでしょう。
●『思い』が認知症ケアを育てていく
そしてこの“思い”による関わりは、支援する私たち自身にも大きな意味をもたらします。
「思い」が原点となるケアは、日々の関わりの中で深まっていくものです。
最初は戸惑いや不安があっても「この人の不安を和らげたい」「少しでも落ち着いて過ごしてほしい」と感じた時、すでにその人はケアの担い手です。
ケアは“お互いに影響し合う”関係性
また“ケアする側”であっても、相手の笑顔や「ありがとう」の言葉で励まされ、癒される場面も多くあります。思いを持って関わることで、支援する私たち自身も報われるという、双方向のやりとりが生まれるのです。
それが、技術だけでは得られない認知症ケアの魅力でもあります。
●ケアの知識は“思い”を行動に変える道具
「困っている人を助けたい」という気持ちは、場所を問わず誰もが持つことのできる力です。
認知症ケアも、その気持ちを具体的な行動に変える手助けをする“道具”のひとつに過ぎません。
たとえば「話しかけ方に迷ったとき」「手を貸すか見守るか判断に悩んだとき」などに、ケアの知識が自然と役立ちます。
認知症ケアはあくまで手段
さらに『認知症ケア』について調べてみると、認知症ケアのポイントとして
- 相手のペースに合わせて見守る
- 相手が理解しやすい言葉で簡潔に話す
- 失敗や間違った言動を責めない
- 孤独にさせない
- プライドを傷つけない
- 目線を合わせて、笑顔、敬語で接し、褒める、謝る態度を見せる
- 相手に興味を向ける
などがといった文言が出てきます。
認知症ケアのポイントとなる視点
これらは、介護施設でケアを提供する際に、間違いなく重要な要素です。
ですがそれと同時に感じるのは
『誰かと関わろうとする時、これらを意識するのは当然ではないか』
『認知症の方と関わるからといって、特別に意識することではない』
という事です。
おわりに ~誰もが担い手になれる“思い”を大切にして~
認知症ケアは“特別な技術”ではなく、思いの延長線上にある
●ケアは“その人を思う気持ち”から始まる
認知症ケアとは『目の前で困っている人が認知症だった場合、その困りごとを解決するための手段の1つ』に過ぎず、認知症ケアを提供すること自体が目的になることはありません。
認知症ケアとは、特別な技術も専門的な知識も必要ではなく、困っている誰かを思いやる気持ちがあれば、自然と備わり養われるものです。
そしてその気持ちに従って行動し、その相手が認知症であった場合に、おのずとその行動が認知症ケアに近づいていく、というだけです。
●支援者自身も報われる、あたたかな関係性
そしてこの“思い”による関わりは、支援する私たち自身にも大きな意味をもたらします。
「思い」が原点となるケアは、日々の関わりの中で深まっていくものです。最初は戸惑いや不安があっても「この人の不安を和らげたい」「少しでも落ち着いて過ごしてほしい」と感じた時、すでにその人はケアの担い手です。
また“ケアする側”であっても、相手の笑顔や「ありがとう」の言葉で励まされ、癒される場面も多くあります。思いを持って関わることで、支援する私たち自身も報われるという、双方向のやりとりが生まれるのです。
家族も地域も、誰もが認知症ケアの担い手になれる
●地域での小さな配慮も立派な認知症ケア
認知症ケアは、介護職員だけでなく、ご家族や地域の方々も担い手の一人です。
家族介護の中で「どう接すればよいかわからない」と迷う時、また地域で困っている高齢者に出会った時にも、この「思い」を出発点に、温かい支援が始まることを願っています。
地域社会の中で、認知症の方が安心して暮らし続けられるためには「介護施設」や「専門職」だけではなく、そこに暮らす一人ひとりのまなざしや関わりが大切です。
近所の人がさりげなく声をかけたり、買い物先で店員さんが気を配ってくれたりすることも、立派なケアのひとつです。
「ひとりで抱え込まなくていい」社会へ
そして何より、家族や周囲の人が「一人で抱え込まなくてもいい」と感じられる社会であることが重要です。
認知症ケアを“特別なこと”ではなく“誰かを思いやることの延長線上”として、もっと自然に語れるような空気を広げていく必要があると、私は思います。
どうか、恐れず、臆せず、困っている方に手を差し伸べてみてください。
あなたが介護のプロでなくても大丈夫です。
家族として、地域の一員として、あるいは施設職員として、それぞれの立場だからこその「小さな一歩」が、認知症の方にとっての安心に繋がります。
その一歩が、きっとあなたにも温かさや喜びを返してくれるはずです。
あなたの思いやりが、きっと誰かを救います。
ここにんでは、そんな「思いを行動に変える」ヒントをお届けしています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
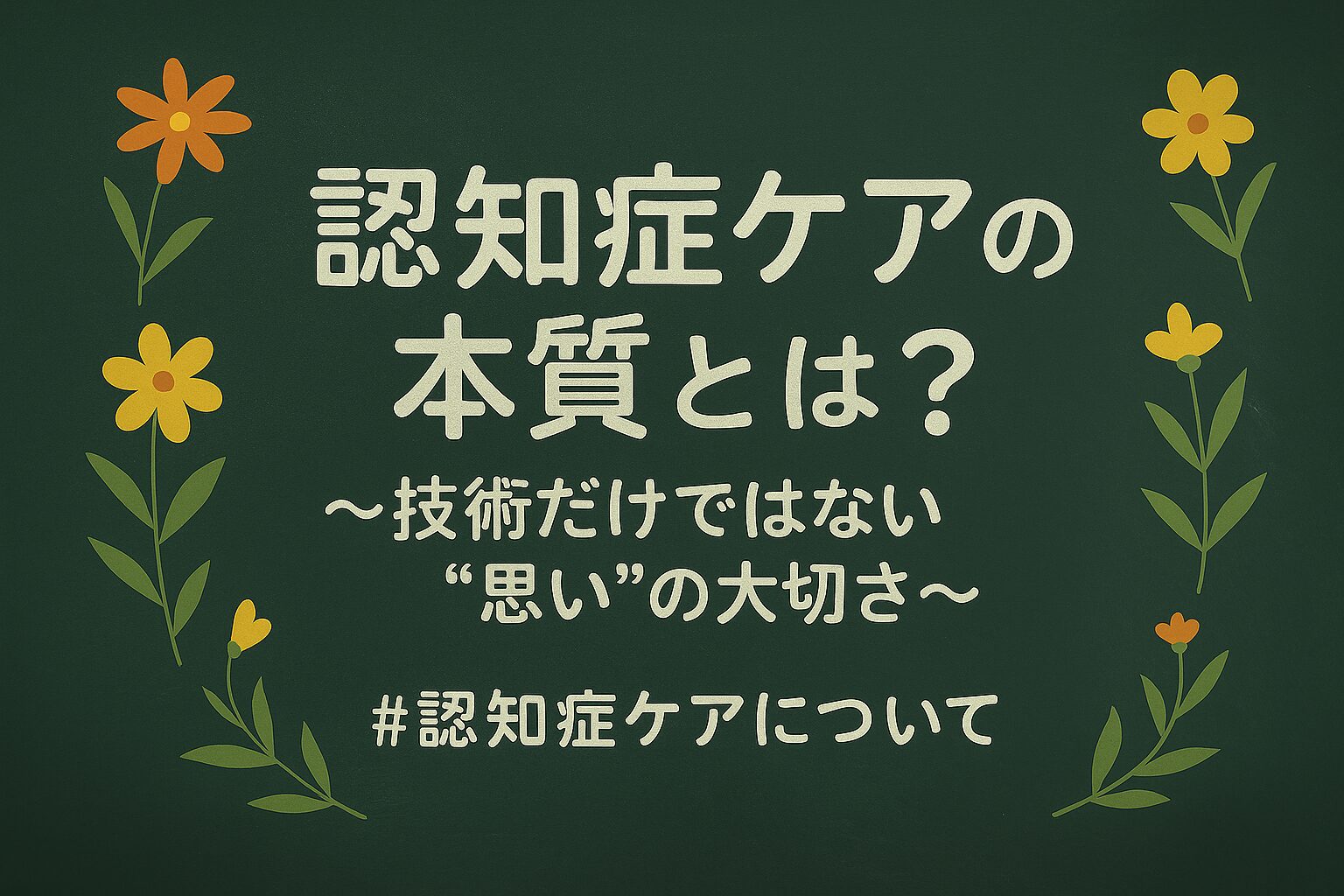
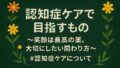
コメント