水分は、体にとって欠かせないもの
私たちの体の半分以上は水分でできています。ところが年齢を重ねると、体内の水分量は少しずつ減り、若い人の60%に対して、高齢者では50%を下回ることもあります。
つまり、ほんの少しの水分不足が、体や心に大きな影響を与えてしまうことがあるのです。
今回は、高齢の方にとっての「水分の大切さ」と「飲み方のコツ」、そして「気をつけたいこと」について、分かりやすくお伝えします。
なぜ水分が必要なの?
少しの不足でも、からだに影響が出る
体の中の水分が1~2%減るだけで、「なんだかぼーっとする」「ふらつく」「口が乾く」「食欲が出ない」などの変化が出ると言われています。3~5%減ると、頭痛や吐き気、倦怠感といった症状が現れます。
そしてそれ以上の水分が体内から失われると、めまいや脱力感、熱中症――更に深刻な状態になると、命に関わることもあります。
特に高齢の方は、「喉が渇いた」と感じにくくなるため、自分では水分不足に気づけないことも少なくありません。
体重50kgの高齢者における水分喪失と体調変化
体重50kgの高齢者は、体内の水分量がおおよそ25,000ml(=25kg)程度とされています。この水分がわずかに失われるだけでも、体調に影響が出やすくなります。以下は、水分喪失量と症状の目安をまとめた表です。
| 水分喪失率 | 喪失量(ml) | 状況の例 | 主な体の変化・症状 |
|---|---|---|---|
| 1〜2% | 250〜500ml |
・コップ1〜2杯の不足 ・軽い飲み忘れ、水分を控えた日 |
・軽度の喉の渇き(感じにくい) ・ぼーっとする、注意力低下 ・口の乾燥、食欲の低下 |
| 3〜5% | 750〜1,250ml |
・1日中しっかり飲めなかった ・軽い発熱、下痢・嘔吐のあと |
・ふらつきや立ちくらみ ・頭痛、軽い吐き気や倦怠感 ・排尿量の減少、脱水症状の進行 |
| 5%以上 | 1,250ml以上 |
・嘔吐・下痢・発汗などが続いた日 ・水分補給がほとんどできなかった |
・脱力感、混乱(せん妄) ・熱中症のリスク上昇 ・尿が出ない、体温調節の異常 ・意識障害、命の危険 |
高齢者は口渇感が鈍く、症状が出るころにはすでに脱水が進んでいることが多いため、喉の渇きを基準にせず、こまめな水分摂取の習慣づけが重要です。
なお、上記の「1〜2%の水分喪失」は500mlペットボトル1本分にすぎませんが、それでも脳の働きや行動量に明確な影響が出るとする研究もあります(Adan, 2012)。
参考文献:Institute of Medicine (2004) Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate;Sawka et al. (2005) “Human water needs”;Adan, A. (2012) “Cognitive performance and dehydration.” Journal of the American College of Nutrition.
水分をとると、こんな良いことが
- 頭がすっきりして、活動量が増える
→ おしゃべりや笑顔が増えたり、立ち上がりやすくなったりすることも。 - 誤嚥のリスクが下がる
→ 覚醒していることで、しっかりとした姿勢で食事ができ、むせにくくなります。 - 便秘の予防に
→ 水分が腸の働きを助け、便を柔らかくします。 - 脳梗塞の予防にもつながる
→ 血液の流れを保ち、ドロドロになるのを防ぎます。
水分をとる時に気をつけたいこと
トイレが増えることでの不安や転倒
「たくさん飲むとトイレが近くなるから……」と、水分を控える方も多いです。でも、それが脱水に繋がってしまうことも少なくありません。
確かに、夜間のトイレが増えると転倒のリスクは高まってしまいます。
特に、慌てて起き上がって、暗い中を移動すると危険です。
対策としては、
- 夕方以降の水分は少なめにする
- 日中にしっかり飲んでおく
- 寝室に近いトイレやポータブルトイレを活用する
- 夜間用のライトや手すりをつける
など“飲まない”のではなく“安心して飲める環境”を整えることが大切です。
頻尿によるストレスや不安
認知症のある方にとって、頻繁にトイレに行きたくなること自体が、不安やストレスの原因になることがあります。
たとえば――
- 「またトイレに行きたくなった…迷惑かけていないかな?」
- 「トイレに行きたいけど、場所が分からない」
- 「さっき行ったばかりなのに、また…」
- 「トイレの場所を聞くのが恥ずかしい、情けない」
こうした戸惑いや不安が、混乱や落ち着きのなさにつながることもあります。とくにBPSD(認知症の行動・心理症状)の一因となることもあるため、注意が必要です。
家族や職員にできる工夫
不安を軽くするために、周囲ができる工夫をご紹介します。
- トイレの場所が一目でわかるようにする
→ 「大きな文字の表示」「ドアにピクトグラム」「床に矢印の目印を貼る」などの視覚的な工夫が効果的です。 - 穏やかに、さりげなく声をかける
→ 「そろそろトイレ行っておこうか?」「いつもの場所にあるからね」など、やさしい声かけが安心につながります。 - トイレの場所を“いつも同じ”にしておく
→ 家具の位置や扉の状態が変わると混乱する方もいます。なるべく環境を固定しましょう。 - 羞恥心への配慮
→ できるだけ自然に付き添う、声をかけるタイミングを工夫するなど、本人の尊厳を守る姿勢が大切です。
一番大切なのは「否定しない」こと
たとえ何度もトイレに行きたがったとしても「また?」「さっき行ったばかりでしょ」と、本人の思いを否定してしまうと、不安が強まり、混乱を招くこともあります。
その背景には「失敗したくない」「迷惑をかけたくない」といった、ご本人なりの一生懸命な思いがあることを、私たちは忘れずにいたいものです。
どんな飲み物がいいの?
◎おすすめの飲み物
- 水・白湯(常温がベスト)
- 麦茶やほうじ茶(カフェインが少なく、胃にやさしい)
- 具だくさんの味噌汁やスープ(食事と一緒に水分がとれる)
- 経口補水液(発熱や下痢など、体調が悪い時に)
△注意が必要な飲み物
- 緑茶・コーヒー・紅茶(カフェインによる利尿作用が強い)
- ジュース(糖分が多く、体重増加と食欲減退の原因になりやすい)
- アルコール(分解のために水分を使ってしまい、逆に脱水を進めてしまいます)
どれくらい、どうやって飲めばいいの?
目安の量
一般的には1日に1200~1500ml(コップ6~8杯)が目安とされています。ただし、心臓や腎臓に持病がある場合は、主治医に相談しましょう。
こまめに、無理なく
一度にたくさん飲むのではなく、
- 起きたとき
- 朝食・昼食・夕食の前後
- おやつのとき
- お風呂の前後
など、生活のリズムの中に組み込むのが、無理なく水分摂取量を増やすコツです。
水分補給を“習慣”にするための工夫
「水分が大事なのはわかっていても、なかなか習慣にならない…」という声もよく聞きます。
高齢の方にとって水分補給を無理なく続けるには、“生活の中に自然に組み込むこと”が大切です。
「時間」を決めて声かけ・準備
例えば「朝のテレビの前に一杯」「おやつのときに一杯」など、決まったタイミングで飲むことで、忘れにくくなります。
施設やご家庭では、職員やご家族が「今、ちょうどいい時間だね」と一緒に飲むのも効果的です。
「見える場所に置く」だけでも変わる
コップや水筒が視界に入ると「そうだ、飲もう」と思い出しやすくなります。
色のついたコップや、持ちやすいマグカップなど、本人が手に取りやすいデザインも大切です。
また、本人が『飲みたい』と思った時にすぐに手に取れるように、常に水分を置いておくことも有効です。ですが『冷めたものをいつまでも置いておく』ということが無いように注意しましょう。
「飲んだ量を見える化」する
チェック表に印をつけるなどして、どれだけ飲めたかを“見える化”することも有効です。
「今日はここまで飲めたね」「あと一杯で目標だね」といったやさしい声かけは、ご本人にとって、小さな達成感に繋がります。
「飲みたくない日」があっても大丈夫
調子が悪い日、気分が乗らない日、トイレが心配な日。
そんなときは、ゼリー飲料や具だくさんスープ、果物など、食べ物からの水分補給も立派な手段です。
「飲ませなきゃ」ではなく、「どうやったら自然にとれるかな?」という視点で考えると、お互いの負担が減ります。
職員・家族が「見守る」ことの大切さ
水分補給は、本人の気づきだけに頼らず、周囲の見守りと工夫で成り立つケアです。
「この人、今日はあまり飲んでいないな」「トイレを気にして我慢しているかも」など、小さな変化に気づけることが、脱水や体調不良の予防につながります。
特に認知症のある方にとっては「飲むこと自体を忘れる」こともあります。
「一緒に飲みませんか」「そろそろ水分をとりませんか?」というやさしい声かけが、ご本人の安心に直結します。
水分補給は“ケア”のひとつです
水分は薬ではありませんが、薬のように効くことがあります。
頭が冴える。食欲が戻る。便秘が楽になる。転ばずに歩ける。
その一つひとつが、ご本人の「できる」を守り、支えることに繋がっていきます。
だからこそ「今日はどれくらい飲めたかな?」「もっと飲める工夫はあるかな?」と、一緒に考え、支える姿勢がとても大切です。
さいごに
高齢の方にとっての水分補給は「のどが渇いたから飲む」ではなく、日々の元気や安全、そして生き生きと過ごすための“習慣”です。
ほんの一口が、その方の「笑顔」や「安心」につながることもあります。
ぜひ、ご家族や職員のみなさんで「水分、ちゃんととれていますか?」と、やさしく声をかけてみてください。
その一言、その気遣い、その優しさが、安心して水分をとれるきっかけになるでしょう。
ここにんでは、こうした日々のケアの中で「ちょっと気になること」や「どうすればいいか迷うこと」について、これからも分かりやすくお伝えしていきます。
この記事が、どなたかの安心につながれば幸いです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
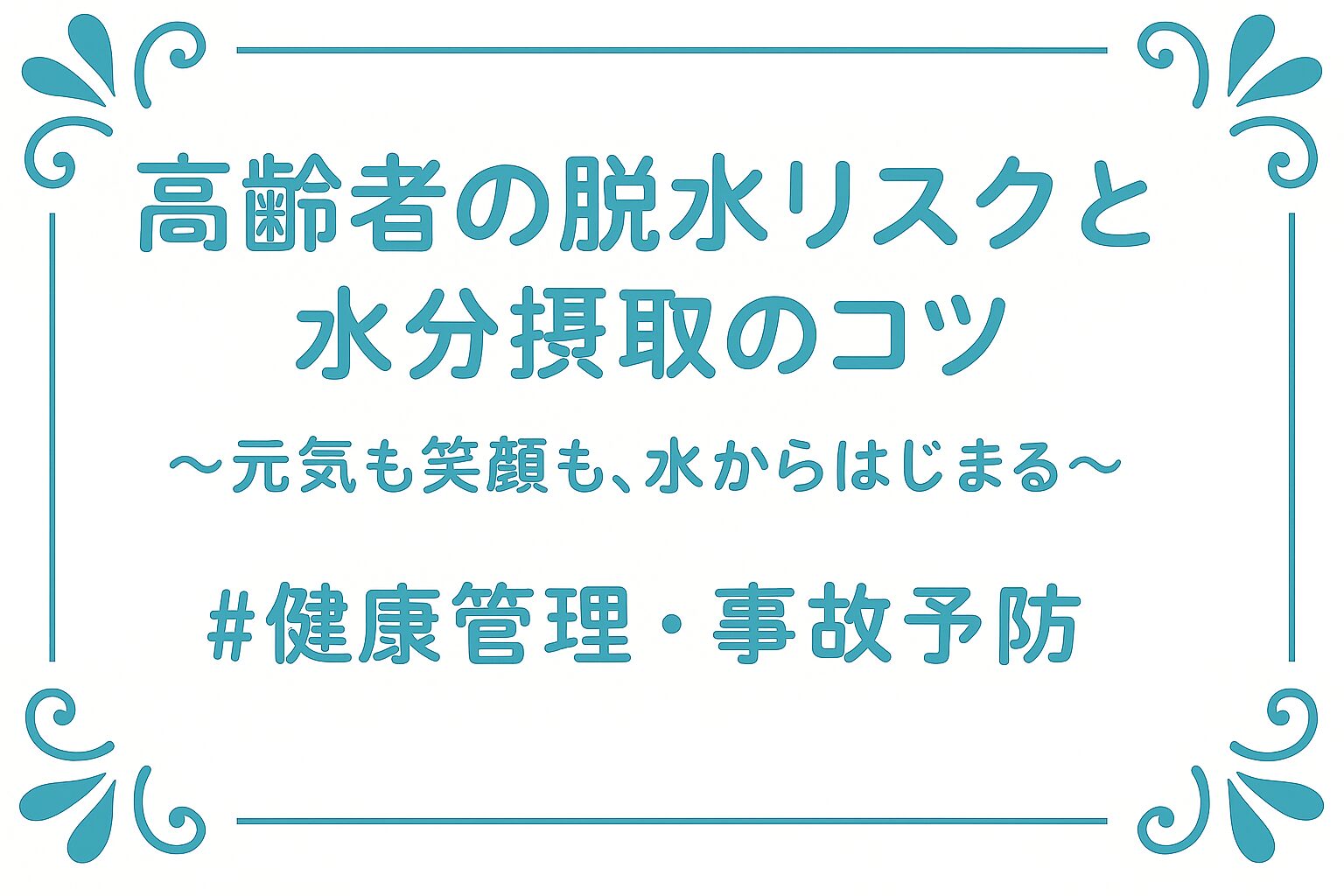
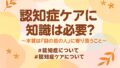

コメント