
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、薬剤(特に多剤併用=ポリファーマシー)が原因で起こる転倒の背景とその予防策について、分かりやすくお伝えします。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
「薬が多すぎると転びやすくなる」――この言葉を聞いて、驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。
高齢になると複数の病気を抱えることが多く、それに伴い、薬の数も増えていきます。さらに、認知症のある方では、不安や不眠、行動症状(BPSD)に対応するための薬も追加されがちです。
しかし、薬の多さそのものが、転倒リスクを高める重大な要因になることが、さまざまな研究で明らかになっています。
この記事では「なぜ薬で転ぶのか?」「どんな薬が危ないのか?」「どう防げばいいのか?」を、ご家族や現場職員の方にもわかりやすく、根拠に基づいてお伝えします。
ポリファーマシーとは? 〜薬が多すぎる状態〜
薬の数が増えるとなぜリスク?
「ポリファーマシー(polypharmacy)」とは、本来は複数の薬を使っている状態を指す医学用語です。ただし現在では、単に薬の数が多いというよりも、
- 本来は不要な薬が含まれている
- 薬同士の相互作用や副作用の管理が不十分
- かえって有害事象を引き起こしている
といった「適正ではない薬の使い方」という意味で用いられることが増えています。
何剤以上で注意が必要?
明確な基準はありませんが、以下のような指標があります。
| 薬の数 | リスクの目安 |
|---|---|
| 1〜4剤 | 比較的安全 |
| 5〜9剤 | 相互作用・副作用に注意 |
| 10剤以上 | 有害事象の発生率が急増 |
- 厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」(2018)では、6剤以上で有害事象のリスクが増加する可能性に言及。
- STOPP/START基準(欧州の高齢者薬物療法基準)でも、5剤以上の併用に対して厳密な再評価が求められている。
特に注意すべき薬の種類とは?
高齢者・認知症患者の転倒リスクと関わりが深い薬は、次の通りです。
1. 睡眠薬(ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系など)
- 代表例:
- ベンゾジアゼピン系:トリアゾラム(ハルシオン)、エスタゾラム(ユーロジン)
- 非ベンゾジアゼピン系:ゾルピデム(マイスリー)、エスゾピクロン(ルネスタ)
- メラトニン受容体作動薬:ラメルテオン(ロゼレム)
- オレキシン受容体拮抗薬:スボレキサント(ベルソムラ)
- 問題点:日中の眠気、ふらつき、記憶力の低下、転倒のリスク増加
- 解説:高齢者では薬の代謝が遅くなるため「寝るために飲んだ薬」の効果が翌朝まで残ってしまい、朝からぼんやりして転倒するケースが多くあります。また、筋肉をゆるめる作用もあるため、バランスを崩しやすくなります。依存や離脱症状にも注意が必要です。
2. 抗不安薬・抗うつ薬
- 代表例:
- 抗不安薬:ジアゼパム(セルシン、ホリゾン)、エチゾラム(デパス)、ロラゼパム(ワイパックス)
- 抗うつ薬:パロキセチン(パキシル)、セルトラリン(ジェイゾロフト)、ミルタザピン(リフレックス)、トラゾドン(デジレル)
- 問題点:立ちくらみ、筋力の低下、集中力の低下、眠気、口渇、便秘など
- 解説:抗不安薬は「緊張をやわらげる」一方で、筋肉もゆるめてしまい、足腰がふらつきやすくなります。抗うつ薬は気持ちの面では効果的でも、副作用として血圧低下や眠気が出やすく、転倒のリスクとなります。特にデパス(エチゾラム)は睡眠薬としても処方されることがあり、重複投与に注意が必要です。
3. 抗精神病薬(認知症の行動・心理症状〈BPSD〉に使われることも)
- 代表例:
- 定型抗精神病薬:ハロペリドール(セレネース)
- 非定型抗精神病薬:リスペリドン(リスパダール)、クエチアピン(セロクエル)、オランザピン(ジプレキサ)、アリピプラゾール(エビリファイ)
- 問題点:過鎮静、パーキンソン様症状(手足のこわばり)、姿勢保持の困難、眠気、ふらつき
- 解説:認知症のBPSD(幻覚、妄想、興奮など)に対応するために使われることがありますが、もともとは統合失調症などの精神疾患のための薬です。高齢者では感受性が強く、副作用が出やすいため注意が必要です。筋肉がこわばったり動きがぎこちなくなったりする副作用(錐体外路症状)が転倒に直結することもあります。
4. 降圧薬(血圧を下げる薬)
- 代表例:アムロジピン(ノルバスク)、バルサルタン(ディオバン)、ニフェジピン(アダラート)、カンデサルタン(ブロプレス)、エナラプリル(レニベース)など
- 問題点:起立性低血圧(急に立ち上がるとフラッとする)
- 解説:高齢者は血圧の調節機能が落ちているため、薬によって血圧が下がりすぎると、急に立ち上がったときにめまいやふらつきが起こりやすくなります。特に、朝起きてすぐやトイレに立ったときにリスクが高くなります。
5. 利尿薬(トイレが近くなる薬)
- 代表例:フロセミド(ラシックス)、ヒドロクロロチアジド(エサックス)、トリクロルメチアジド(フルイトラン)、スピロノラクトン(アルダクトンA)など
- 問題点:夜間の頻尿や脱水による転倒
- 解説:利尿薬はトイレが近くなるため、夜中に何度も起きてトイレに行く→暗がりで転倒、という流れがよく見られます。また、脱水になりやすく、筋力低下や血圧低下を引き起こすこともあります。
※お薬手帳に書かれている薬名と異なることもありますが、上記は主に「一般名(成分名)」と「商品名」を併記しています。ご家族で確認される際の参考にしてください。
薬の副作用が起こりやすくなる背景とは?
「なぜ高齢者や認知症のある方は、副作用が出やすいのか?」
それにはいくつかの理由があります。これを知っておくことで「本人のせいではない」「体質によるものでもある」と、冷静に向き合えるようになります。
高齢者に副作用が出やすい5つの理由
- 加齢による代謝・排泄機能の低下
→ 肝臓や腎臓の働きが弱くなり、薬が体に長く残ることで作用が強く出やすくなります。 - 体重・筋肉量の減少
→ 薬の分布や作用のしかたが変わり、予想以上に効いてしまうことがあります。 - 認知機能低下による自己申告の難しさ
→「ふらついている」「気持ち悪い」と自分から言えないことも多く、周囲が気づきにくくなります。 - 多剤併用による相互作用
→ それぞれの薬の影響が重なって、思わぬ副作用が起きることがあります。 - 「一時的な症状をすぐ薬で抑えたい」という過剰対応
→ 不安や興奮、夜間の徘徊などにすぐ薬を使うと、必要以上に眠気や鎮静が強く出てしまうこともあります。
薬の副作用と転倒のつながり(具体例)
| 症状 | 原因となる薬 | 転倒につながる理由 |
|---|---|---|
| めまい・ふらつき | 降圧薬、抗うつ薬 | バランスを崩しやすくなる |
| 眠気・注意力低下 | 睡眠薬、抗精神病薬 | 周囲への反応が遅れる |
| 筋力低下 | 向精神薬、ステロイド | 支える力が弱くなる |
| トイレに急ぐ | 利尿薬 | 夜間や早朝に起きて転倒 |
夜中にトイレへ行こうとして、寝ぼけたままフラッと立ち上がり、転倒してしまう――そんな場面は、薬の影響によって引き起こされることがあるのです。
「薬名を見たら、まず相談を」 〜家族にできる第一歩〜
睡眠薬、利尿薬、降圧薬、抗精神病薬――これらの名前の一部は、介護現場でもよく見かけます。ご家族が薬袋やお薬手帳を見たとき「あ、この名前、聞いたことがある」と思うことも多いのではないでしょうか。
薬の名前だけで不安になる必要はありませんが
「この薬、うちの親にとっていま必要なのかな?」
「転倒が増えたのは、薬と関係があるかも?」
と気になったときには、医師や薬剤師に遠慮せず相談することが大切です。
薬についての問いかけは、本人の安全を守るための立派なアクションです。ご家族が「薬に関心をもつこと」自体が、転倒予防の第一歩になります。
転倒を防ぐためにできること
1. 「薬の棚卸し」をする
定期的に薬の内容を確認し「いま本当に必要な薬なのか?」を医師と一緒に見直すことが大切です。
- 薬が増えた経緯を振り返る
- 他の病院からもらっている薬を伝える
- サプリや市販薬も含めて見直す
重要なことは『薬が減ると心配』ではなく『薬を整理すると安全になる』という視点を持つことです。
お薬手帳をコピーして、かかりつけ医や薬剤師、または地域包括支援センターに相談してみましょう。「どの薬が今も必要か?」を一緒に整理することが、転倒予防の大きな一歩になります。
2. 転倒の記録と薬の変化をリンクさせる
「薬が変わったタイミングでふらつくようになった」「転倒が増えた」――このような特徴がある場合は、薬の影響が強く出ている可能性があります。自己判断せず、必ず医師や薬剤師に相談してください。
3. 睡眠薬・抗精神病薬は慎重に
これらの薬はBPSDの抑制や夜間せん妄への対応で必要になることもありますが「最終手段」として位置付けられるべきです。
- 非薬物的アプローチ(生活リズム調整、安心できる環境づくり)も積極的に。
- 医師と協議し、最小量での使用や段階的な中止も検討しましょう。
家族・介護職にできること 〜「薬任せ」にしない視点〜
薬は「効く」から「効きすぎる」まで、個人差が大きいのが特徴です。
介護者は次のような視点で、薬と付き合う姿勢を持ちましょう。
- 「症状が出たら薬」ではなく「症状の背景を見る」視点をもつ
- 「この人はこれまでどういう生活をしてきたか?」を医療職と共有する
- 薬が増えた背景に「家族の不安」や「職員の対応困難」がないか見直す
また、転倒やふらつきがあった日は、メモや転倒日誌をつけておくと、医師に相談するときに状況が伝わりやすくなります。「この薬のあとに転んだ」などの情報は、とても重要なヒントになります。
まとめ:薬と安全の“ちょうどよいバランス”を見つけよう
認知症のある高齢者にとって「薬の影響」は転倒という重大事故を引き起こす可能性のある重要なリスクです。
しかし、薬をすべて否定する必要はありません。
大切なのは「その人にとって、本当に必要な薬か?」「今の状態に合っているか?」という視点を持ち、医療・介護・家族が連携して見直していくことです。
あなたの大切な人が、安全に、そしてその人らしく暮らせるように――
“薬との付き合い方”を見直すことから、転倒予防は始まります。
※この記事は、医療・介護におけるガイドラインや学術的文献に基づいて執筆されていますが、個別の医療的判断については、かかりつけ医や薬剤師などの専門家に必ずご相談ください。
【参考文献】
- 厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針(2018年)」
- 日本老年医学会「高齢者の安全な薬物治療ガイドライン2015」
- O’Mahony D, et al. STOPP/START criteria (Version 2). Age Ageing. 2015.
- 日本転倒予防学会 編「高齢者の転倒予防マニュアル」(2020)
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
- 骨折を伴う転倒が深刻な理由とは? ~介護現場における11のリスクと予防のヒント~
- ヒヤリハットは未来を守るセンサー 〜ハインリッヒの法則から考える介護事故予防〜
- 【全7回】第1回:認知症高齢者が転倒しやすい6つの理由 〜原因と予防のために知っておきたいこと〜
- 【全7回】第2回:転倒の身体的要因とは? ~筋力・バランス・疾患との関係~
- 【全7回】第3回:「認知機能の障害」と転倒の関係 ~見えないリスクを理解して予防に繋げる~
- 【全7回】第4回:「また歩き出した…」その行動には理由がある ~BPSDの背景にある感情を知り、転倒を未然に防ぐ~
- 【全7回】第5回:認知症高齢者の転倒を防ぐために ~見逃せない「環境要因」とは~
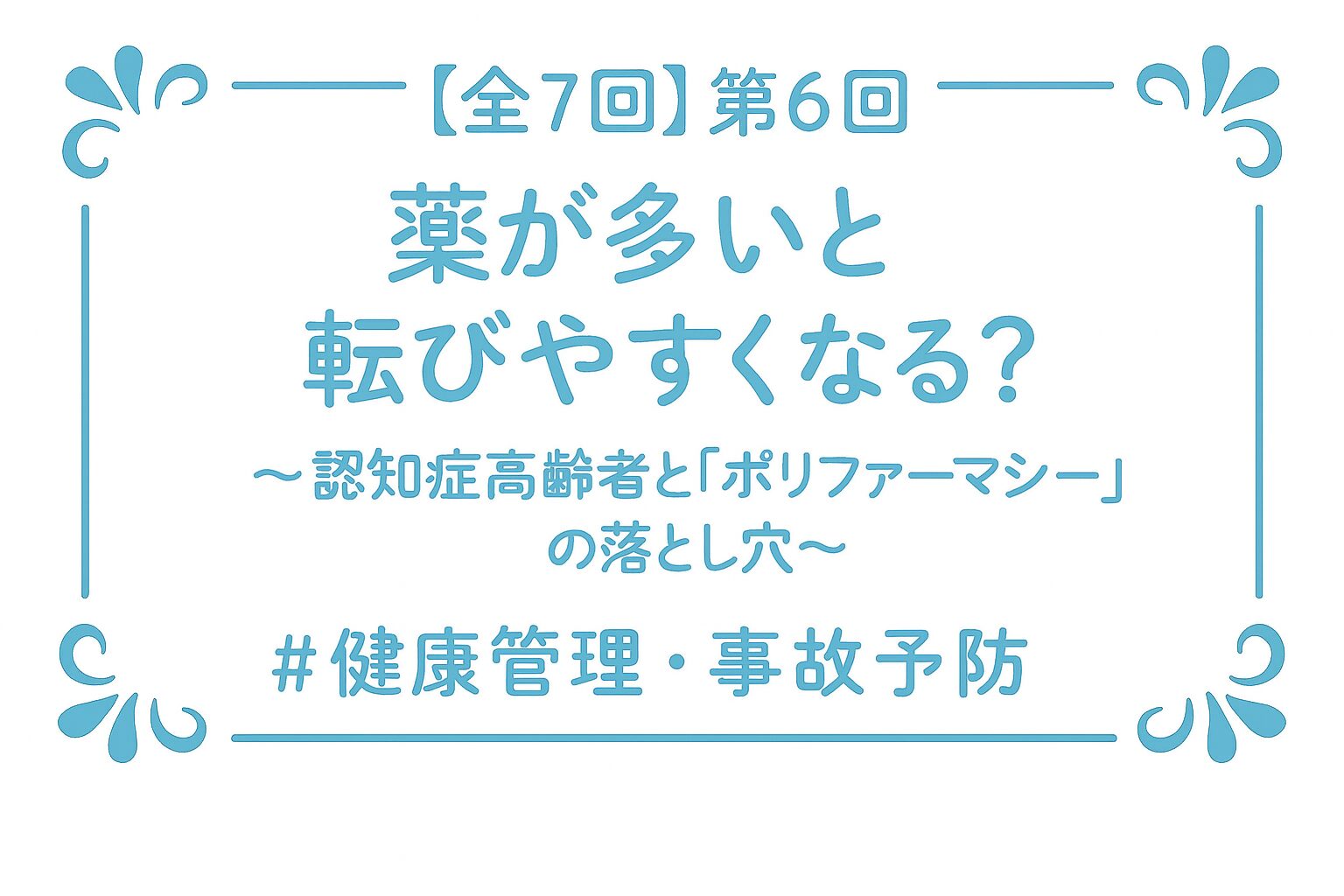


コメント