
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、筋力・バランス・視力・関節・感覚といった身体の変化に注目し、転倒予防のヒントが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
「なぜ、こんなに転びやすくなったの?」
認知症の方を介護する中で、こんなふうに感じたことはありませんか?
「元気に歩いていたのに、最近よくふらつく」
「急に立ち上がって、そのまま倒れそうになる」
「段差があるわけでもないのに転んでしまった」
認知症の方が転倒しやすいのは事実ですが、理由は決して“認知症だから”だけではありません。
その背景には、加齢や病気による身体の変化が深く関わっています。
今回は、転倒の大きな要因となる「身体的な原因」に注目し、その特徴と予防のヒントを分かりやすくお伝えします。
身体的な要因とは?
高齢になると、誰でも体力が落ちてきます。
とくに認知症のある方は、自分の体調の変化に気づきにくかったり、不調をうまく伝えられなかったりするため、周囲が変化を見逃しやすい傾向にあります。
また、認知症によって身体の動かし方がぎこちなくなることもあり「心」と「体」がうまく連携できていない状態になっていることも少なくありません。
ここでは、認知症の方に多く見られる「身体的な転倒リスク要因」を5つに分けてご紹介します。
① 筋力低下(特に下肢の筋肉)
加齢や運動不足により、太ももやふくらはぎの筋肉が弱ってくると、日常動作が不安定になります。特に「立ち上がる」「歩き始める」「方向を変える」などの動作で転倒リスクが高まります。
特に大腿四頭筋(太ももの筋肉)の筋力は、転倒との関連が強く、歩行時の安定性を左右します(日本老年医学会, 2021)。
よくあるサイン:
- 立ち上がりに時間がかかる
- 歩行時に足が上がらず、引きずるように歩く
- ズボンや靴下をはく時に、ふらついたり倒れそうになる
予防のヒント:
- 椅子からの立ち座りを毎日数回行う
- 体操や散歩などを行う
- 長時間ベッドに横にならず、座る・立つ習慣を大切にする
② バランス機能の低下(前庭系・小脳・運動制御系)
バランス感覚は内耳の前庭系、小脳、そして身体の動きを計画・調整する大脳の領域(前頭葉や運動野)など、さまざまな部位が協力して保たれています。
認知症の進行に伴い、歩行とバランスを司る脳の機能連携が崩れることが知られており(Montero-Odasso et al., 2012)、ふらつきや転倒が生じやすくなります。
よくあるサイン:
- 歩いていると左右に揺れる
- 立ったまま脱衣やズボンの着脱をしようとしてよろめく
- 振り向いた瞬間によろける
予防のヒント:
- 廊下やトイレ前に手すりを設置する
- 歩行器・シルバーカーを検討する
- フロアや浴室での滑り止めマットの活用
③ 視力・視野の低下(白内障・緑内障など)
段差や障害物が見えにくくなっているのに、ご本人が「見えづらい」と言わない(または気づいていない)ことがあります。これは特に転倒の隠れたリスクになりやすいです。
高齢者の視力・視野低下は、転倒との関係が多くの研究で示されています(BMJ, 2013)。
よくあるサイン:
- 段差がないところでつまずく
- 影や模様を避けようとしてバランスを崩す
- 明るい部屋から暗い廊下に出て転びそうになる
予防のヒント:
- 明るく均一な照明を心がける
- 床と家具の色にコントラストをつけて見やすくする
- 眼科での定期受診(白内障や緑内障の確認)をすすめる
④ 関節の拘縮・変形・痛み(変形性膝関節症など)
膝や股関節に痛みや変形があると、無意識に体をかばって歩くようになります。その結果、重心のバランスが崩れやすくなり、転倒の危険が高まります(日本整形外科学会, 2020)。
よくあるサイン:
- 片足にばかり重心をかける歩き方
- 足を引きずるような歩行
- 立ち上がり動作時に顔をしかめる
予防のヒント:
- 整形外科で関節の状態を確認してもらう
- 歩行補助具(杖や手すり)の導入
- ベッドや椅子の高さ調整で負担を軽減する
⑤ 感覚障害(足のしびれや麻痺)
脳梗塞や糖尿病などによって、足の裏の感覚が鈍くなると、地面の状態を正確に感じ取れず、つまずいたり、バランスを崩しやすくなります(日本糖尿病学会, 2019)。
見た目にはわかりづらい転倒リスクです。
よくあるサイン:
- 足を床に“ペタン”とつけて歩く
- 靴を履いて左右が逆でも気づかない
- 足の裏を「じんじんする」「何かついてる感じがする」と言う
予防のヒント:
- 医師の診断を受けて、原因に応じた治療を行う
- 足に合った靴や滑りにくいスリッパを選ぶ
- 毎日足を見て、むくみや傷がないか確認する
まとめ|身体に目を向けることで、転倒は防げる
認知症の方が転倒する背景には、こうした身体的な変化が複数重なっていることが少なくありません。
そして多くの場合、それらの変化に「気づくこと」こそが、最も重要な予防策になります。
「年のせいだから仕方ない」と思わず「最近、歩き方が変わったかも?」「座るときに苦しそうだな」といった小さな違和感に注目してみてください。
あなたのその気づきが、ご本人の生活を守る第一歩になるでしょう。
転倒は「本人のせい」だけではありません
介護の現場では、転倒があるとどうしても「注意不足だったのでは」と感じてしまいがちです。
でも、そればかりではありません。転倒の多くは“気づきにくい身体の変化”によるものです。
「あの人は一人で歩けるから大丈夫」ではなく「今の歩き方、安全かな?」と立ち止まってみることが、認知症の方にとって、何よりも安心な支えになります。
転倒は、年齢や認知症だけのせいではありません。
ほんの小さな『あれ?』という違和感に気づけるかどうかが、ご本人のこれからの暮らしを左右するかもしれません。
その“気づき”の力を、ぜひ今日から周囲の目で育んでいきましょう。
【次回予告】
次回は「認知機能の障害編」として
「なぜ認知症の人は“危険に気づかずに転んでしまう”のか?」
を掘り下げていきます。
記憶・判断力・注意力など、認知機能の低下が転倒にどう関係しているのかをやさしく解説し、それを踏まえた具体的な声かけや環境調整のヒントをお伝えします。
参考資料の一覧
- 日本老年医学会『高齢者の転倒予防ガイドライン』(2021年)
- 厚生労働省『健康づくりのための身体活動基準2013』
- 国立長寿医療研究センター『高齢者の視覚障害と転倒』
- 日本整形外科学会『ロコモティブシンドロームと転倒』
- Montero-Odasso et al., Dementia and Gait, 2012
- The BMJ: Visual impairment and risk of falls in older people, 2013
- 日本糖尿病学会『糖尿病性ニューロパチーと転倒』
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
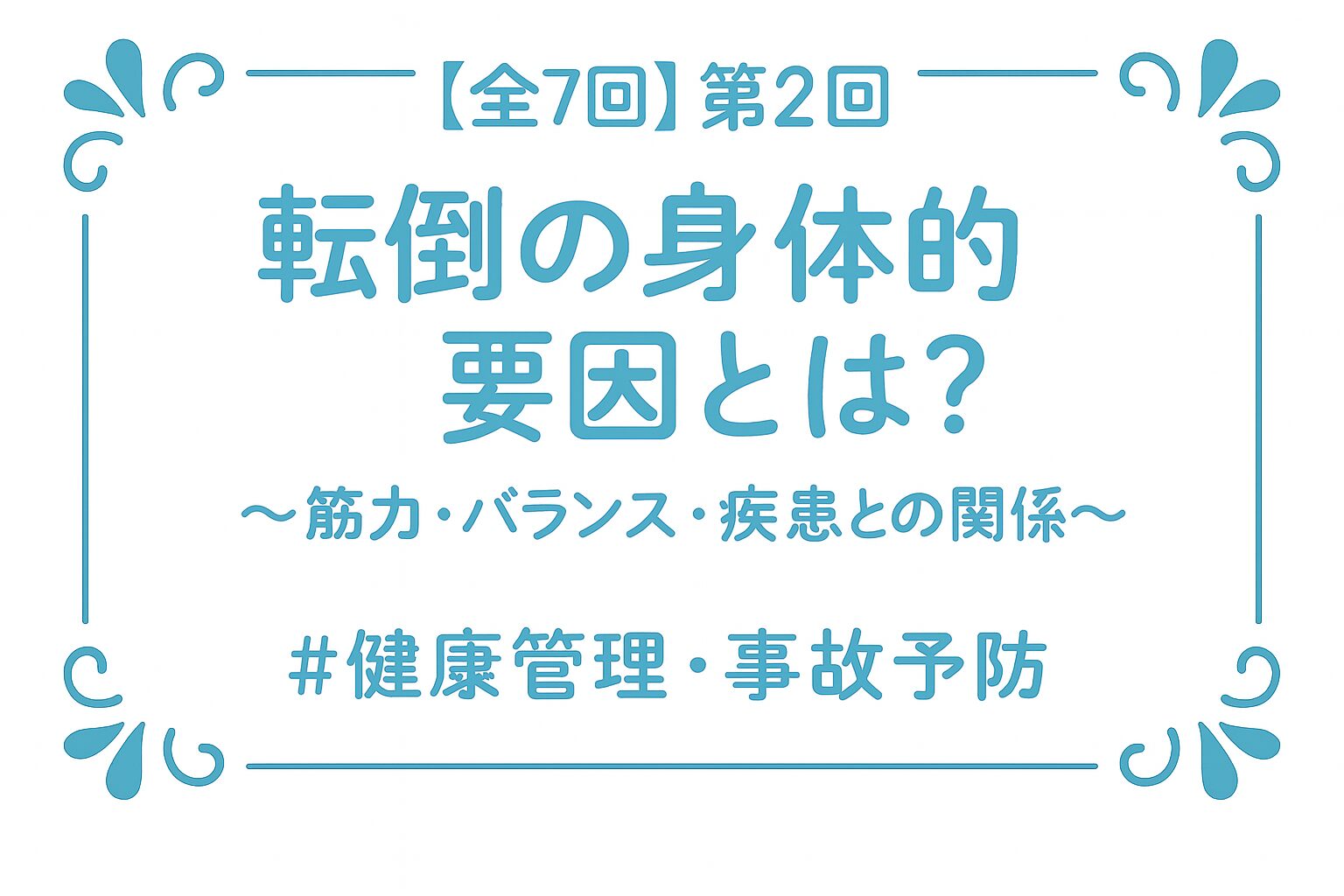


コメント