
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、身体・認知・環境・薬など多面的に転倒リスクを捉えることの大切さが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
なぜ認知症の高齢者は転びやすいのか?
「また転倒してしまった…」「目を離したすきに、ベッド横で転んでいた」
こういった転倒に関する困りごとは、認知症の方を介護するご家族や介護職が直面する、もっとも多い悩みの一つではないでしょうか。
転倒は、単なるケガにとどまらず、骨折や入院、生活の質の低下――そして、認知症の進行にも繋がりかねません。だからこそ「なぜ転倒しやすいのか?」という原因を深く理解することは、予防の第一歩として欠かせません。
この記事では、認知症の高齢者が転倒しやすくなる原因を6つの視点から整理し、それぞれの背景や注意点について、分かりやすくお伝えします。
身体的な衰えによるバランスの低下
- 筋力低下:加齢や活動量の減少により筋力量が低下。特に下肢筋力が低下し歩行が不安定に。特に認知症の方は運動量も少なくなりがち
- バランス能力の低下:姿勢保持や歩行時のバランス調整が困難になる。立ち上がる、方向転換する、狭い場所を歩くといった動作で転倒のリスクが高まる
- 視力・聴力の低下:段差や障害物に気づきにくくなる
- 関節の痛みや可動域の制限:変形性膝関節症、脊椎の変形などにより歩行がぎこちなくなる
このような身体的な問題は、認知症の有無に関係なく起こりますが、認知症の方では自分の状態をうまく伝えられない・痛みに気づかないなどの特徴も重なり、より見えにくいリスクとなります。
加齢や活動量の減少により下肢筋力が低下し、立ち上がりや歩行が不安定になります。姿勢を保つ力も弱まり、視力や聴力の衰え、関節の痛みなども重なることで、より転びやすくなってしまうでしょう。
一見ふつうに歩けているように見えても、実は足元に不安を抱えていることも少なくありません。さりげない声かけや支援者の気づきが、とても大切です。
認知機能の障害がもたらす「判断ミス」
認知症の中核症状には、記憶障害だけでなく、空間認知や判断力の低下も含まれます。
※参考:認知症介護研究・研修東京センター「認知症の理解と関わり」
https://www.dcnet.gr.jp/contents/know/understanding/
- 空間認知障害:段差があることに気づかず踏み外す。また、床のタイル目や模様、黒いマットなどを実際にはない段差や穴と誤認し、歩行がぎこちなくなることも
- 注意力の低下:周囲の障害物に気づけず、避けられない
- 見当識障害:場所や時間の感覚が曖昧になり、夜中に歩き回る
- 判断力の低下:「この椅子は不安定だから使わない方がいい」といった判断ができなくなる
たとえば、ふだん通りの場所でも、「ここに段差がある」という理解がうまくできなければ、今まで平気だった場所でも転倒につながります。
段差があることに気づけない、障害物を避けられない、時間や場所の感覚が曖昧で、思わぬ行動をとってしまう――そんな認知症の中核症状が、転倒の背景にあります。
本人も「なぜ転んだのか」がわからず、戸惑っていることがあります。責めずに、いっしょに安心できる環境を整えていくことで、お互いの信頼感にも繋がっていきます。
行動・心理症状(BPSD)による予期せぬ動き
認知症の方には、以下のような行動や感情の変化がよく見られます。
- 徘徊:目的がなく歩き回ることで、転倒のリスクが上がる
- 焦燥・不安:不安感や落ち着きのなさから急に立ち上がったりする
- 夜間せん妄:暗がりで幻視が見える、混乱することで不自然な動きをする
このような行動は、本人にとって意味があるもの(探し物をしているなど)であることも多く、止めようとするとかえって不穏になるケースもあります。
対応には「環境の工夫」や「安心感の提供」など、専門的な視点が必要です。
※参考:認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000064084.html
認知症の方には、徘徊や焦燥、不安感、夜間の混乱など、心の状態が動きとして現れることがあります。予測がつかない行動が転倒に繋がることも少なくありません。
しかしその行動の裏には「表現できない、伝えたい思い」が必ずあります。安全を守りながら、その人らしさに寄り添うことを大切にしたいですね。
※ちなみに、認知症の方は自分なりの目的があって歩くことがほとんどですので、厳密には『徘徊』という言葉は適切でありません。
今回は、分かりやすくお伝えするためにあえて『徘徊』という表現を使用しております。
環境要因が潜む「つまずきポイント」
本人の状態だけでなく「環境」も転倒に大きく関わっています。
- 段差や絨毯のめくれ:わずかな段差でもつまずきの原因に
- 床の滑りやすさ:フローリングや浴室など
- 照明不足:暗い廊下やトイレが危険な場所に
- トイレまでの距離:遠く・複雑な動線は、夜間の転倒リスクを上げてしまいます
特に夜間のトイレ移動中の転倒は多く「慌てて起きて」「暗がりを通って」「トイレまでに数メートル歩く」という状況が揃うと、事故の危険が一気に高まってしまうでしょう。
わずかな段差や、めくれた絨毯、暗い照明、遠いトイレーー日々の暮らしの中にある小さな「つまずき」が、大きな転倒につながることがあります。
私たちにとっては何気ない場所でも、認知症の方にとっては“迷路”や“障害物”に感じられることも。毎日の動きを見守る中で、そっと整える工夫が安心に繋がっていきます。
薬剤の影響によるふらつき
認知症の方は複数の薬を服用していることが多く、転倒との関係が深いことが分かっています。
※参考:厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」(2018年)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192182.html
以下の薬には特に注意が必要です。
- 睡眠薬・抗不安薬・抗精神病薬:ふらつき、起立性低血圧、判断力の低下
- 降圧薬・利尿薬:トイレの頻度が増え、急いで向かうことで転倒に
- 多剤併用による副作用:薬同士の相互作用で、意識障害や倦怠感が出ることも
支援者の判断で薬を急にやめることはできませんが、定期的な薬剤評価(薬剤師や医師との連携)で見直しをすることが重要です。
複数の薬を飲んでいると、眠気やふらつき、立ちくらみなどが起こりやすくなります。特に夜間やトイレに向かう際には、転倒の原因になることも少なくありません。
「薬をやめさせたい」ではなく「今の状態に合っているか見直したい」と考えることが大切です。その際には、医師や薬剤師に気軽に相談してみましょう。
生活習慣の乱れと栄養状態の低下
転倒のリスクは、日々の生活リズムや栄養状態にも深く関係しています。
- 昼夜逆転:夜間の動きが多くなることで事故のリスクが増える
- 脱水・栄養不足:血圧の低下や立ちくらみによる転倒が起こりやすい
認知症の方は「喉の渇きを感じにくい」「食欲がわかない」といった変化があるため、周囲が水分・栄養の摂取をサポートする必要があります。
昼夜が逆転したり、水分や栄養が不足したりすると、体調が不安定になり、立ちくらみや転倒に繋がることがあります。
でも、本人は気づいていないことも多いのです。こまめに声をかけながら、食事や水分を一緒に楽しむ時間をつくれるように支援していきましょう。
| 原因の視点 | 主な内容 | 注意点・対策例 |
|---|---|---|
| 身体的要因 | 筋力低下、関節痛、バランス機能の低下 | 日常動作の観察、適度な運動やリハビリの支援 |
| 認知機能の障害 | 空間認知障害、判断力・注意力の低下 | 行動パターンを把握し、見守りや声かけを工夫 |
| 行動・心理症状(BPSD) | 徘徊、焦燥、不安、夜間せん妄 | 安心感を与える対応、環境の安定化 |
| 環境要因 | 段差、絨毯、照明不足、トイレの距離 | つまずきポイントの改善、夜間照明の工夫 |
| 薬剤の影響 | 睡眠薬、降圧剤、抗精神病薬、多剤併用 | 医師・薬剤師との連携による見直し |
| 生活習慣・栄養 | 昼夜逆転、脱水、栄養不足 | こまめな水分補給、食事支援、生活リズムの安定 |
まとめ:転倒の背景には「複数の要因」が絡んでいる
認知症高齢者の転倒は「筋力低下」だけ「薬の副作用」だけという単一の原因ではなく、身体・認知・行動・環境・薬・生活習慣といった複数の要素が複雑に絡み合って起こっています。
だからこそ、対策も「運動量、活動量を増やす」「日中に寝ない」「床にマットを敷く」「薬を減らす」といった単発的なものではなく、総合的な視点が求められます。
介護者や職員が「なぜ転倒が起きたのか?」を丁寧に振り返り「どうすれば防げるか?」を一緒に考えていくことが、転倒予防の最も確かな道なのだと思います。
次回は、これらの原因に対してどのような予防策があるのか、具体的にお伝えしていきます。
※この記事は以下の資料を参考にしています
・厚生労働省「高齢者の医薬品適正使用の指針」
・認知症介護研究・研修東京センター「認知症の理解と関わり」
・認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
・公益社団法人 認知症の人と家族の会「転倒と認知症」
※ここに挙げた薬剤の影響やBPSDの傾向は、あくまで一般的な特徴であり、すべての方に当てはまるわけではありません。詳細は医師・専門職にご相談ください。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
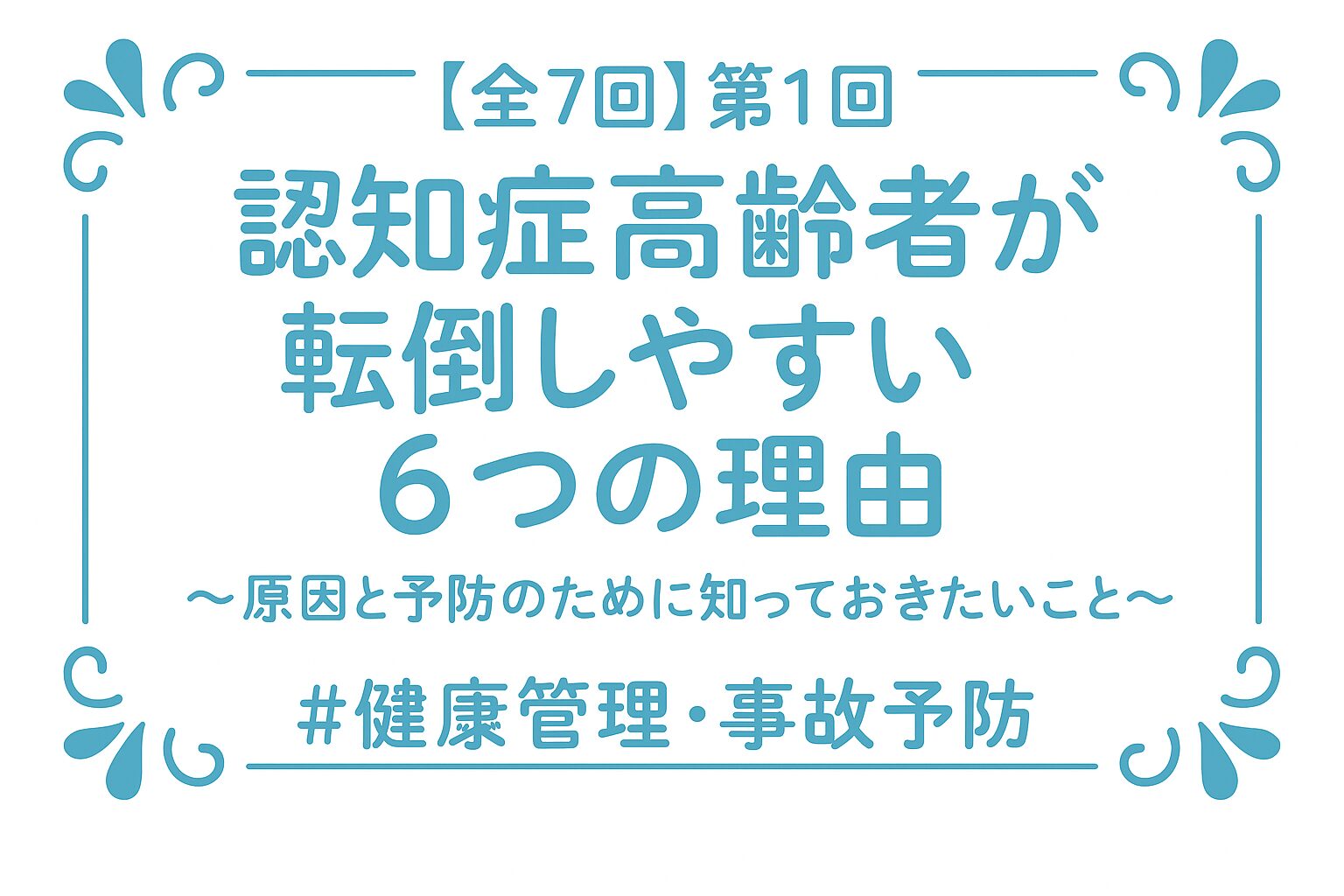
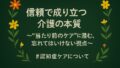

コメント