事故は“起きてから”ではなく“起きる前”にチームで備えるもの
介護の現場で働くなかで、避けて通れない話題のひとつに「転倒事故」があります。
なかでも骨折を伴う転倒は、ご利用者だけではなく、ご家族や職員の思い、施設の雰囲気に至るにまで、深く長い影響を残すことが少なくありません。
もちろん、どれだけ注意しても防げない事故はあります。
すべての転倒や介護事故が職員の責任というわけではありません。ご利用者自身の動き・病状・タイミングなど、複数の要因が重なって事故が起きてしまいます。
それでも「これは防げたかもしれない」と思う事故を、単なる事故として処理しないこと――
そして、事故を“個人のせい”にせず、チームでどう防いでいくかを考えることが、とても大切です。
この記事では、転倒による骨折がなぜ重大なのか、11の理由を通して整理し、最後に事故を防ぐために必要な視点と工夫をお伝えします。
ご利用者の安全を守り、穏やかな生活を続けていくためのヒントにしていただければ幸いです。
本人にとっての影響
① 強い痛みと恐怖の記憶
骨折をすると、激しい痛みを伴います。その痛みの記憶は、たとえ骨折部位が治ったとしても「立ち上がるのが怖い」「歩きたくない」という感情として残ってしまうことがあります。
それは『転倒リスクを減らす』どころか、動くことを避けるようになり、結果的に筋力やバランス機能が低下することに繋がります。
「また転ぶかもしれない」「転んで痛いのは嫌だ」という不安を抱えながら生活することは、本人にとってとても大きなストレスになってしまいますし、ストレスがかかる生活は、間違いなく認知症を進めてしまうでしょう。
② 認知症の進行
入院による環境の変化、慣れない人間関係、そして身体拘束や昼夜逆転…。
認知症のある方にとっては、そうした変化がせん妄や認知機能の急激な低下に繋がることが多々あります。
医療機関が優先するのは、あくまで『入院の原因を治すこと』です。
『今までの生活の継続』や『本人の意思の尊重』『認知症を進行を防ぐ配慮』は、どうしても後回しになってしまう現実があります。
現場ではよく「退院してきたら、まるで別人のようだった」というご家族や職員の声を耳にします。
転倒による痛みや恐怖のストレスに加え、入院生活による認知症の進行――
この二つが重なれば、その方の生活が一変してしまうことも珍しくありません。
これだけでも、骨折を伴う転倒事故は「何としてでも防ぎたい」と思う理由として、十分過ぎるほどではないでしょうか。
③ 生存率の低下
骨折による生存率の低下は、国内外での研究でも示されています。
例えば日本では、高齢者が大腿骨を骨折した場合、5年後の生存率がおよそ50%にまで低下するという研究・報告があります。
同様の傾向は海外での研究でも見られ、入院による筋力低下・肺炎・心不全といった術後の合併症や廃用に加え、生活意欲の喪失も影響していると考えられています。
つまり、転倒による骨折は単なるケガではなく、その人の人生を左右する可能性のある重大な出来事――「命」にも関わる深刻な出来事なのです。
【参考文献】
市村和徳・佐藤直人・安藤幸夫ほか(2009)「高齢者大腿骨近位部骨折患者の生命予後」『臨床整形外科』第44巻第9号, pp.899–902.
Roche JJW, Wenn RT, Sahota O, Moran CG. (2005). Effect of comorbidities and postoperative complications on mortality after hip fracture. BMJ, 331(7529), 1374.
④ 自立の可能性が失われる
転倒のあと、転倒や骨折の再発を危惧するご家族から「もう歩かせないで」「ベッドから降ろさないで」と言われることがあります。
それが本人の安全を守るため、二度と痛くて怖い思いをしないでもらいたい、という思いから出ているとしても、結果として“できる力”を奪ってしまうことになってしまいます。
また過剰な制限は、廃用症候群や拘縮のリスクを高めてしまいます。
廃用症候群や拘縮が進むと、再び立ち上がった時に転倒してしまう可能性は、更に高くなることでしょう。
事故を防ぐ=動かさないではなく、安全に動ける環境を整えることが、本来の「事故予防」なのかもしれません。
ご家族にとっての影響
⑤ 施設への不信感
「見守ってもらえると思っていたのに」「なぜ気づかなかったのか」
転倒事故のあと、ご家族の信頼が揺らぐことがあります。
ご家族が施設を信じてくださっていた分、その気持ちが裏切られたと感じてしまうのも無理はありません。
事故後の対応次第で、関係性が深まることもあれば、離れてしまうこともあります。
⑥ 経済的な負担
入院にかかる費用、交通費、さらにグループホームの場合は入院中も居室費・食費などがかかることが多く、一時的に負担が大きくなってしまうことも少なくありません。
また、退院後に必要になる車椅子やベッド、住宅改修などで、更に出費が続くケースもあります。
職員にとっての影響
⑦ 介護負担の急増
骨折後は、ADL(日常生活動作)が低下し、排泄・移乗・食事・入浴など、すべてのケアの介助量が増えてしまうことがあります。
夜間の見守り回数や体位変換など、追加のサービスや介助が必要となり、スタッフの身体的負担はもちろん、精神的な負担も大きくなります。
⑧ 自信とモチベーションの低下
事故が起きたとき「自分のときに転倒してしまった…」と責任を感じる職員は少なくありません。
家族対応や事故報告、ヒアリングなどが重なればなおさらです。
でも、事故=職員の責任とは限りません。
ルールを逸脱したり、注意義務を怠った場合を除いては、個人を責めるのではなく、チームで振り返ることが大切です。
⑨ 防御的なケアが現場に広がる
「もう転倒させたくない」――その思いから、ベッドから出さない、歩かせない、関わりを最小限にする…。
そんな防御的なケアが現場に広がることがあります。
その気持ちは、もっともです。
『怖かった』『申し訳なかった』『だから次は絶対に起こしたくない』――
しかしその結果として「動かさない」「関わらない」ことが最優先になってしまうと、ご利用者の生活そのものが小さくなってしまいます。
それは「安全」ではなく「生活の縮小」です。
リスクを恐れるあまり“その人らしい暮らし”が奪われていく――そんなジレンマが、現場にはあります。
そして、こうした空気が広がると、職員の声かけや工夫も少なくなり、チームの意欲や活気が目に見えて失われていきます。
「どうすればこの人はまた歩けるか」「転ばずにトイレに行けるか」という前向きな視点が生まれにくくなるのです。
だからこそ事故後には「もう動かさない」ではなく「どうすれば安全に動けるか」をチームで考えることが大切です。
防御的なケアに偏らないよう、リーダーや管理者が声をかけ、動きをつくっていくことが求められます。
施設にとっての影響
⑩ 収入の減少
入院中は医療保険が優先されるため、介護保険の算定ができなくなります。
そのため、一人でも長期入院があると、施設としての収益は大きく減少します。
これは経営上の問題だけでなく、人員配置やケアの質にも影響することになりかねません。
⑪ 信頼と評判の低下
「○○施設で転倒事故があったらしい」
そんな話は、あっという間に地域に広がることがあります。
特にケアマネジャーや地域包括支援センターとの信頼関係が揺らぐと、入居希望者の紹介にも影響します。
信頼を築くのに時間はかかりますが、失うのは一瞬です。
事故を防ぐには「チームの視点」が欠かせない
転倒事故は、ひとりの職員が気をつければ防げる――そんな単純なものではありません。
現場全体で情報を集め、共有し、具体的な動きに落とし込んでいくことが必要なのです。
- 普段からの歩行状況やADLの変化をキャッチする
- 薬の影響(利尿剤・眠剤など)やトイレのパターンを把握する
- 「ふらつき」「滑りそうだった」などの小さなヒヤリハットを見逃さない
- 職員同士で「どうすればこの方の動きを支えられるか」を話し合う
- リーダーや管理者は、職員に具体的なポジショニングや声かけの指示を出す
事故は、チームでしか防げません。
ご家族との関係づくりも「予防」のひとつ
ご家族との信頼関係がどの程度築けているのか――事故が起きたときにこそ、それが明らかになるでしょう。
日ごろからのこまめな報告や、相談しやすい雰囲気づくりが、説明の受け入れやすさを左右します。
こうしたときに役立つのが「アサーション」という考え方です。
アサーションとは、「相手も自分も大切にしながら、正直に伝えるコミュニケーション」のことです。
「責任逃れ」でも「自分を責める」でもなく、「事実と想いをバランスよく伝える」技術です。
事故の説明や普段の会話にこそ、このアサーションの姿勢が活きてきます。
介護現場におけるアサーションの活用については、別の記事で詳しくお伝えいたします。
最後に
転倒事故は、本人の痛みや生活の質を大きく下げるだけでなく、ご家族の信頼、職員のやりがい、そして施設の未来までも左右します。
だからこそ「防げたかもしれない事故」をひとつでも減らすことが、私たちの使命です。
事故を責めるのではなく、そこから学び、活かすことが必要なのです。
転倒を防ぐということは、痛みやリスクを遠ざけるだけではありません。
その人が、その人らしく生きていく時間を守るということ。
それが私たちのケアに託されていることを、どうか忘れずにいたいと思うのです。
小さな声かけ、小さな気づき、小さな工夫。
それらは小さいようでいて、大きな事故や損失を防ぐ力になります。
誰かを責めるのではなく、チームで支え合い、考え合う――
そんな、ご入居者にとってもご家族にとっても、そして職員にとっても頼れるチームであり続けたいと思います。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
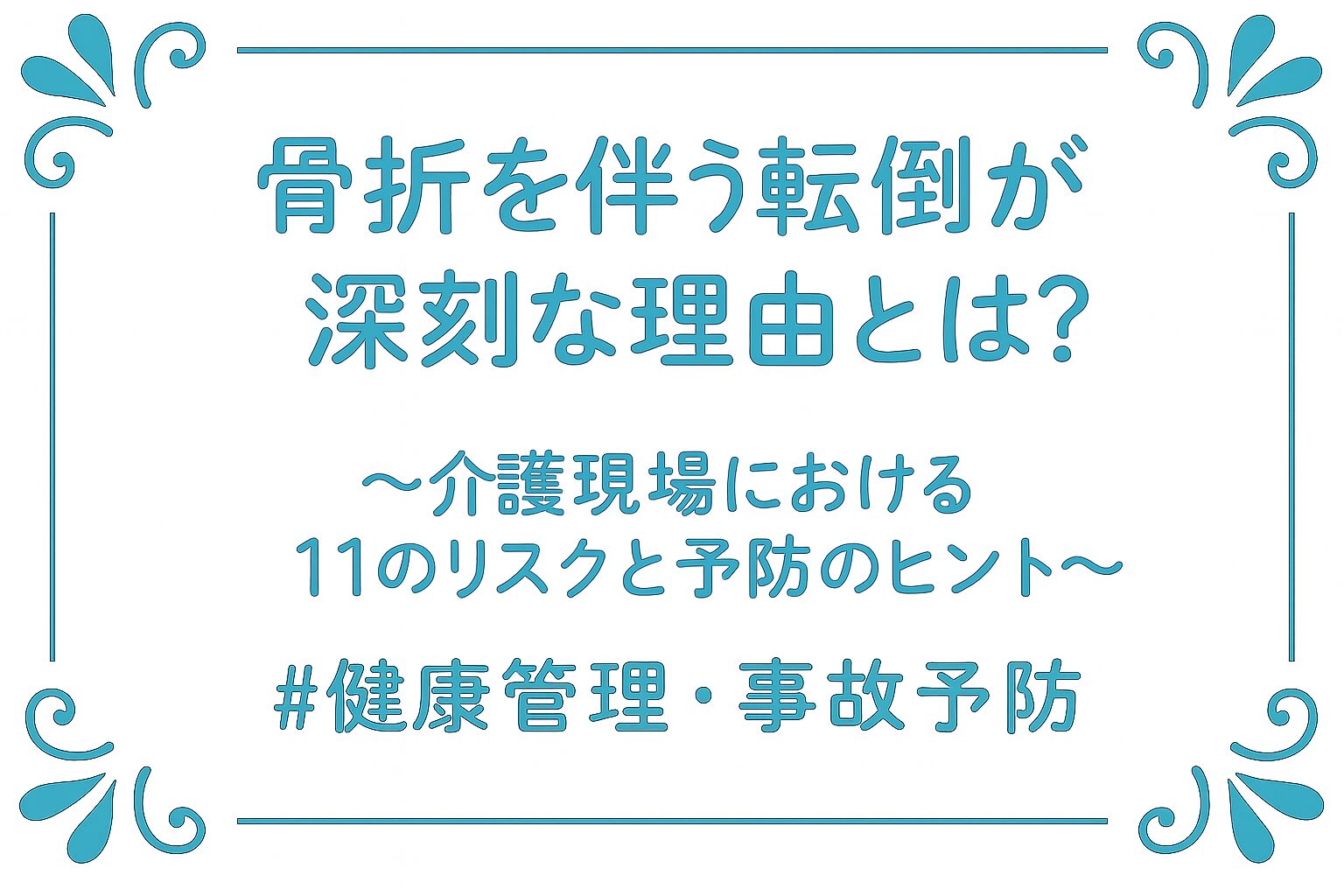


コメント