
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、介護職員の「優しさ」が実は本人の力を奪っているかもしれない――そんな“支援しすぎない支援”の大切さが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに ~「優しさ」は、いつも正しいのか?~
介護の現場でよく見かける光景があります。
食事中に手が止まっている入居者がいれば、職員が口元にスプーンを運ぶ。
靴がうまく履けない様子を見て、職員がサッとしゃがんで履かせてあげる。
トイレまで移動しようとする方がいれば、危ないからと車椅子に乗せて連れて行く。
こうした行動は一見すると、介護職員の「優しさ」や「思いやり」として評価されがちです。
本人が困っているなら、助けたい。
時間がかかるなら、代わりにやってあげたい。
その気持ちは、多くの介護職員が共通して持っているものだと思います。
でも、ふと立ち止まって考えてみてほしいのです。
――その「優しさ」は、本当に本人のためになっているのか?
――それは「できる力」を引き出すケアなのか、それとも「できたはずの力」を奪ってしまう介入ではないのか?
本記事では、現場でよくある“やってあげるケア”が、どのように認知症の方の力や尊厳を奪い、チームケアを乱すのかを考察し、プロフェッショナルとしての介護とは何かをあらためて問い直していきます。
「やってあげる」介護が引き起こす、3つの弊害
① 本人の「できる力」を失わせてしまう
認知症の方でも、環境や声かけの工夫次第で、できることはたくさんあります。
たとえば、
- 自分でスプーンを使って食べられる
- 自分でズボンを履ける
- 自分のタイミングでトイレに行ける
などです。
しかし「時間がかかるから」「かわいそうだから」「大変そうだから」といった理由で、先回りしてやってあげることが続くと、本人はそれを“自分がやるものではなく、やってもらうもの”と認識してしまいます。
こうして「できる」は「やらない」へ。
そして「やらない」は「できなくなる」へと変わっていきます。
介護職の“やさしさ”が、知らず知らずのうちに本人の自立性や尊厳を奪ってしまっているのです。
② ケアを受ける側の“基準”をゆがめてしまう
認知症の方は、職員ごとの対応の違いに敏感です。
- すぐに手伝ってくれる職員 → 優しい人
- まずは見守る職員 → 冷たい人
このような“印象のラベリング”がご利用者様の中で起きてしまうと、支援の質に対する歪んだ理解が生まれてしまいます。
たとえば、本人の力を信じて「もう少し見守ろう」と判断した職員が、本人から「なんでやってくれないの?」と不満を持たれる。
それを見たご家族から「ここの職員さんは冷たい」と言われる。
その結果「本当の意味での支援――自分で出来る力を支援しよう」とする職員が浮いてしまう。
“やってくれる人が基準”になってしまうと、プロとしての正しい支援が否定されるリスクすらあるのです。
③ チームケアの方向性が乱れ、現場がバラバラになる
認知症ケアにおいては、ケアの一貫性がとても重要です。
たとえば、食事の場面で「できるだけ本人に食べてもらう」ことを方針にしているのに、一部の職員が全部食べさせてしまっていると、他の職員の取り組みが意味をなさなくなります。
「〇〇さんはやってくれるのに、あなたはやってくれない」
「どうせあとで誰かがやってくれるし」
そんな風に思われてしまうと、チーム全体のケアが崩れていきます。
職員が「いい人」であろうとすればするほど、チームのケアの軸がぼやけ、その人らしい支援からどんどん遠ざかってしまうのです。
なぜ私たちは「やってあげたくなる」のか?
「やってあげる」ことの先にある“関係性の変化”にも注目を
もうひとつ見落とされがちなポイントがあります。
それは「やってあげる介護」が続くことで、ご本人と職員との関係性のバランスが変わってしまいかねないということです。
支援を受け続けることに慣れると、本人の中で「依存の構造」が出来上がり、自発的な行動が減っていきます。
また、介護職員の側も「自分が支えなければこの人は生活できない」という“支援する側の万能感”に陥ってしまうことがあります。
このような関係性は、互いの“対等な人間関係”という土台を揺るがします。
介護は「してあげる」関係ではなく「ともに暮らしをつくる」関係であるべきです。
そのためには、あえて支援を控え、できるだけ“生活の主導権”を本人に取り戻してもらうことが大切です。
「支えているつもりが、コントロールしていないか」
この問いもまた、介護の本質に迫る視点のひとつです。
優しさの裏にある“心理”を見つめ直す
ここまで読むと「じゃあ私のやっていたことは間違っていたのか?」と戸惑う人もいるかもしれません。
でも、そこには自然で善意に基づいた心理が働いています。
- 困っている姿を見ると胸が痛む
- 時間がかかると業務が詰まってしまう
- 失敗して悲しませたくないという気持ちが働く
- 感謝されることで、承認欲求が満たされる
こうした感情は、決して否定されるべきものではありません。
しかし、プロとしての介護職であるならば、自分の気持ちだけで判断せず「この支援は本人のためになるのか?」という視点を常に持ち続ける必要があります。
優しさとプロ意識がぶつかるとき、私たちは何を選ぶべきか
介護の仕事には、常に“葛藤”がつきまといます。
- 手を差し伸べたい気持ちと、本人の力を信じる視点
- 効率を求める時間管理と、その人のペースに合わせる姿勢
- 目の前の感謝と、長期的な生活の質の向上
このように「優しさ」と「プロ意識」が対立する瞬間が、毎日のように訪れます。
そのとき、どちらを選ぶか。
それこそが、介護職としての本質なのだと思います。
「優しさ」だけなら、誰でも持つことができます。
でも「待つ勇気」「見守る判断」「本人の尊厳を信じる支援」は、訓練と経験を積んだプロにしかできない選択だと、私は思います。
だからこそ、介護は機械にはできない
近年、AIやロボット技術の進化により、介護業界でも自動化や省力化が注目されています。移乗や見守り、排泄支援など、テクノロジーによって補える領域は確実に増えてきました。
しかし、私たちが日々直面するこのような「優しさ」と「専門性」のバランス――「やるべきか、見守るべきか」の判断は、そう簡単にマニュアル化できるものではありません。
目の前のその人が、今どんな気持ちでいるのか。
どこまでなら自分でできるのか。
どのタイミングで声をかけるのがベストか。
それらは、表情、呼吸、微細な動作の変化を感じ取る、人間の“気づく力”にしかできないことです。
だからこそ、介護は機械が大体できる領域では無いのでしょう。
それは、人と人との信頼関係の中で生まれる“生きた支援”だからです。
チーム全体で「やりすぎないケア」の価値を共有しよう
“やらない勇気”を育てるには、教育と仕組みが必要
支援しすぎない介護“やらない勇気”を実践するには、職員一人ひとりの意識改革だけでは限界があります。
なぜなら、時間に追われる業務の中では、効率重視の支援――つまり“やってあげる方が早い”という選択肢の方が、現場では歓迎されがちだからです。
そのためには、新人教育やOJTの段階で「自立支援」や「尊厳保持」の理念をしっかり根付かせることが不可欠です。
また、支援方針に迷ったとき、チームで立ち止まり「この支援は本人の力を活かせているか?」を対話できるような、風通しのよい組織風土も必要でしょう。
リーダーや管理者には、現場のやさしさに寄り添いつつ「やさしさを超えるプロ意識」をチームに伝え続けることが求められます。
“やらない”ことを責めず、むしろ「考えて、選んで、あえて見守る」ことを評価する空気が、現場を根本から変えていくのです。
“見守る勇気”を支える職場づくり
このようなケアを実現するには、チームでの共通認識が不可欠です。
- 「やってあげること」が“優しさの証”ではない
- 「本人を信じて手を出さないこと」が“冷たさ”ではない
- 「できるようになった経験」が“尊厳の回復”につながる
こうした視点を、職員間で共有し、リーダーや管理者が明確にケアの方向性を示すことで、統一された質の高い支援が可能になります。
おわりに ~優しさの奥にある“選択”を、意識しよう~
誰だって、困っている人を見れば手を差し伸べたくなります。それは人として自然な反応であり、介護職として誇るべき感性です。
でも、その「手を差し伸べること」が、本当にその人の未来につながっているかを、私たちは日々問い直さなければなりません。
- 「今は手を出さない方が、その人のためになる」
- 「少し時間をかけてでも、できることを支える」
- 「一緒に悩み、見守るという“安易に支援しない支援”を選ぶ」
そんな選択ができる人こそが、本当の意味で“その人を支える介護職”だと思うのです。
やさしさとプロ意識がぶつかったとき、あなたはどちらを選びますか?
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!

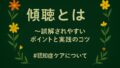

コメント