
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、認知症ケアに欠かせないのは、正しい理解と伝え方の工夫であることが分かります。非言語コミュニケーションから言葉の選び方まで解説します。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
認知症の方との会話ややり取りに、難しさを感じたことはありませんか。
「何度言っても伝わらない」「返事が曖昧」――そして何度も伝えた結果「怒ってしまう」。
そのような場面に直面すると、家族も介護職員も戸惑い、時には無力感すら覚えることがあります。
しかし、これは決して「認知症の方が理解できない人になってしまった」からではありません。多くの場合は 「受け取る力が弱くなっている」 ことに原因があります。
つまり――
- 一度に受け取れる言葉の量が少なくなる
- 受け取った言葉を理解するのに時間がかかる
- 理解しても、行動へ移すことが難しくなる
といった変化があるのです。
大切なのは「受け取れない」のではなく「受け取りにくい」だけだと理解すること。その上で、伝え方の工夫をすれば、驚くほどコミュニケーションが円滑になることがあります。
この記事では、認知症の方と接するうえで役立つ基本的な考え方と実践的な方法を、介護をしているご家族や介護初心者の方向けに、わかりやすく紹介します。
認知症とコミュニケーションの難しさ
認知症になると、記憶や判断力だけでなく「情報を受け取って理解する力」も低下していきます。
これは脳の働きが変化することによる自然な現象であり、本人の努力不足やわがまま、甘えなどではありません。
例えば、私たちでも慣れない外国語を一度に聞かされると、頭が混乱し、理解するのが難しくなりますよね。認知症の方にとっては、母国語である日本語であっても、似たような状態が日常的に起きているのです。
コミュニケーションの基本姿勢
伝え方を工夫する前に、まず 「伝える前の準備」 がとても重要です。
(1) 目線を合わせる
いきなり後ろから声をかけると、誰でも驚きます。認知症の方は特に不安になりやすいため、正面から近づき、目線を合わせることを心がけましょう。
(2) 名前を呼ぶ
「○○さん」と名前を呼ぶことで、相手は「自分に向けられた言葉だ」と認識できます。そこから会話をスタートさせるだけでも、反応が変わります。
(3) 一つずつ、ゆっくりと
行動を促すときは「立って → 歩いて → 椅子に座って」など、動作を小さな単位に分け、短い言葉で伝えることが有効です。
ノンバーバルコミュニケーションの力
人間のコミュニケーションは、言葉だけでなく 非言語(ノンバーバル) が大きな割合を占めています。
表情、声の調子、姿勢、ジェスチャーなど――それらは言葉以上に相手に安心感や信頼を与えます。
よく「目は口ほどに物を言う」と言われますが、これはまさに真理です。笑顔で「一緒に行きましょう」と手を差し伸べると、言葉が届かなくても動作から意図を理解してくださる方は多いものです。
一方で、言葉だけが丁寧でも、表情が険しかったり目が笑っていないだけでも、相手に伝わる感情は全く別のものとなってしまうでしょう。
言葉の工夫 ― 短く、区切って、ポジティブに
(1) 短い文で伝える
「そろそろご飯だから、洗面所で手を洗ってからリビングに来て、そうしたら椅子に座って待っていてくださいね」
――このように一度にたくさんのお願いや声かけをすると、途中で混乱してしまいます。
「ご飯ですよ」→(反応を見てから)「手を洗いましょう」→「椅子に座りましょう」
と、分けて伝えるだけで理解しやすくなります。
(2) 言い換えでポジティブに
私たちも「この料理味が薄いね」と言われるより「これ美味しいね! でももう少し塩を足したらもっと美味しくなるんじゃない?」と言われた方が受け入れやすいと思います。
認知症の方にとっても、その気持ちは同じです。
- 「入れ歯を入れないと食べられませんよ」
→ 「入れ歯を入れた方が美味しく食べられますよ」 - 「動かないと歩けなくなりますよ」
→ 「いつまでも自分の足で歩けた方が楽しいですよ」
否定的な言い方を避け、前向きな表現に変えるだけで、相手の反応は柔らかくなります。
よくある表現とポジティブな言い換え例(10選)
| ❌ よくある表現 | ✅ 言い換え例 | 💡 ポイント・意図 |
|---|---|---|
| 動かないと歩けなくなるよ | 自分の足で歩けた方が楽しいですよ | 怖がらせるのではなく、楽しみを提示 |
| 入れ歯を入れないと食べられませんよ | 入れ歯を入れた方が美味しく食べられますよ | 機能ではなく「味わい」への誘導 |
| 転ばないように歩いてください | 安心して歩けるように、ゆっくりいきましょう | 禁止ではなく、安心感の共有 |
| オムツ替えますよ | 替えてサッパリしましょうか | 行為よりも結果(快適さ)を意識 |
| トイレ行きませんか? | (耳元などで小声で)お手洗い、行っておきましょうか | 言葉の印象と柔らかさと、行動への配慮 |
| ご飯食べないと薬が飲めませんよ | 食べておくと薬もしっかり効きますよ | 条件提示→効果提示へ |
| ちゃんと座ってください | 楽に座れるようにお手伝いしますね | 命令→支援の提案に変更 |
| 起きましょうか(寝ている人に) | そろそろ明るくなってきましたね、今日はいい天気ですよ | 環境との調和を使う表現 |
| 静かにしてください | 他の方が休まれているので、少し声を小さくしてもらえますか | 指摘ではなく、理由+協力依頼 |
| ○○しなきゃダメですよ | ○○すると気持ちがいいですよ/安心ですよ | 否定の義務形→メリット提示へ |
活用のポイント
- 「○○しないと××になる」→「○○すると××できる」に変えると前向きになります。
- 「しなきゃダメ」は、言われた本人を委縮させます。選択肢を持ってもらう言い方が望ましいです。
- 丁寧語でも「命令口調」になっていることに気づく職員は少なく、自分の伝え方は適切かどうかという視点の転換や振り返りも大切です。
「知らない言葉は聞こえない」
『知らない言葉は聞こえない』という言葉を聞いたことがあります。
これは比喩的な表現ですが、実際に認知症の方では語彙や理解力が低下し、耳に入った言葉を意味として処理できないことがあります(厚労省 新オレンジプラン/日本老年精神医学会)。
認知症の方にとっては、かつて覚えていたはずの言葉が出てこなかったり、意味が理解できなくなったりすることがあります。
例えば「トイレに行きましょう」と伝えても通じないとき、別の言葉に置き換えると伝わることがあります。
- トイレ
- お手洗い
- 厠(かわや)
- 雪隠(せっちん)
- 御不浄(ごふじょう)
ただし、昔の言い方は世代・地域・個人の経験で好みが分かれます。 ご家族に“本人にとってなじみがある言葉”が確認できる場合は、ご本人が心地よいと感じる語に限って使いましょう。
家族や職員が「その人の言葉」を知っておくことが、スムーズなコミュニケーションにつながります。
昔の言葉・上品な表現・言い換えの例
- 風呂 → 湯殿、行水
- 食事 → お膳、お食事
- 寝る → おやすみ、ひと休み、横になる
こうした、本人にとって聞き慣れた言葉が出せることで、ご利用者との距離が縮まったり、話が弾むことも少なくありません。
実践のヒント
ここまでのポイントを踏まえて、実際の場面で活かせる工夫をまとめます。
- 相手の目を見て、名前を呼んでから話す
- 動作を小さな単位に分けて伝える
- 一度に一つのことだけを話す
- 否定ではなく肯定的に言い換える
- ジェスチャーや表情を積極的に使う
- 相手が理解できる言葉を探す
これらを意識するだけで「伝わらない」と思っていた方とのやり取りが驚くほど変わることがあります。
言い換えと昔の言葉が有用な理由
1. 現場で即使える実用性
言い換えは、介護現場でのコミュニケーションの質を向上させる武器になります。「言い方一つで応じてもらえる」「拒否が減る」という体験をすることで、職員自身の負担も減り、ケアがスムーズになります。
2. ポジティブな声かけでQOL向上
ご本人の行動や意欲に直結する、言葉選びの重要性を理解してもらえます。
また、本人の尊厳ややる気を引き出すきっかけにもなるので、家族や職員への気づきを促せます。
3. 語彙の少なさ=悪ではないという視点
「知らない=悪」ではありません。
支援者に対して「学ぶきっかけがなかっただけ」というスタンスで伝えることで、相手の防衛反応を減らし「知ることが出来てよかった」と思ってもらえるでしょう。啓発しながら押し付けにならないバランスが大事です。
4. 語彙の豊かさと介護の品位の関係
「ご不浄」「雪隠」「お手洗い」など、かつては当たり前に使われた言葉を知ることで、日本語の奥深さや言葉の文化的背景にも触れられ、教養的な面白さもあります。
5. 言葉の「力」を伝えることができる
同じ内容でも、言い方一つで“命令”にも“寄り添い”にもなってしまう──そういった言葉の影響力を伝えることで、言葉に無自覚だった職員に、新しい視点を届けることができます。
家族や介護者に伝えたいこと
認知症の方との会話が難しくなると、介護者はつい「どうしてわかってくれないの?」と感じがちです。
でも実際には「分からない」のではなく「分かりにくいだけ」なのです。
こちらが工夫をすれば、相手の反応も変わります。
大切なのは「どうしたら伝わるか」と試行錯誤する姿勢であり、それ自体が相手を尊重するケアの形でもあります。
おわりに
認知症の方とのコミュニケーションは、特別な技術ではなく「伝え方の工夫」で改善できることが多くあります。
- 相手に認識してもらってから話す
- 非言語を活用する
- 短く区切って伝える
- ポジティブに言い換える
- その人に合った言葉を選ぶ
こうした小さな工夫の積み重ねが、本人の安心と尊厳を守ることにつながります。
認知症だから「通じない」のではありません。
認知症だからこそ「伝え方が大切」なのです。
日々の関わりの中で、ぜひ今日から試してみてください。
出典・参考文献
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf - 「認知症の人に対する言語聴覚士の関わりについての実態調査」日本言語聴覚士協会
https://files.japanslht.or.jp/notifications/2019/09/20/ninchisyousyouiinkai_chousa.pdf - 「語義失語(意味性認知症を含む)」に関する研究 — 高次脳機能障害学会 等
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hbfr/29/3/29_3_328/_pdf
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
本記事のテーマに関心を持たれた方は、以下の記事もおすすめです。

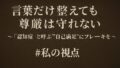

コメント