
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、施設から「今はむずかしい」と言われても、次の一歩を踏み出せるように、家族にできる準備や相談の工夫が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
「施設から断られた」
「ケアマネさんがなかなか見つからない」
そんな状況に直面すると、家族としてはとてもつらいですよね。
「うちの親が悪いのかな」「自分の説明が下手だったのかな」と責めてしまうこともあると思います。
でも、それはあなたやご本人が悪いからではありません。
これは決して特別なことではなく、どなたにでも起こり得ることなのです
だからこそ、いま感じている戸惑いや不安は、あなただけのものではありません。
多くの場合、それは「今の体制では安全にお世話できない」という意味です。
つまり「無理」ではなく“現時点では条件が合わなかった”ということ。
むしろ「断られる経験」を経て条件が明らかになり、その後スムーズな受け入れにつながるケースも少なくありません。
そして、それからの時間は「どうすれば合う場所が見つかるか」を探す時間になります。
今回の記事は、介護の知識が豊富ではなくても前を向くことできるように、そして前に進むことができるように、今日から家族ができる準備と相談のコツをやさしくまとめました。
なぜ「お受けできません」と言われるの?
施設や事業所が「今は難しい」と言う背景には、いくつかの理由があります。
そして実はその多くは、ご本人の安全を守るためなのです。
夜の安全を確保できないとき
夜中に歩き回る、転びやすいなど。
見守りの人が足りないと「事故につながるかもしれない」と判断されます。
医療のお世話が必要なとき
たんの吸引、インスリン注射、点滴など。
その施設に、看護の体制や研修を受けた職員がいなければ、受け入れはできません。
困りごとの“きっかけ”が分からないとき
暴言や手が出るなどの行動があっても、その頻度やタイミングが見えないと、対応の方法が立てづらいのです。
その他によくある理由
夜や医療のこと以外にも「今は難しい」と言われる背景にはこんな事情があります。
1. 職員体制や専門性の不足
- 介護職員の数が国の基準を下回っていると、新たな方を安全に受け入れることができません。
- 特に重度の認知症ケアや医療行為に対応するには、経験や研修を受けた職員が必要で、体制が整っていない場合は「難しい」となることがあります。
2. 建物や設備の制約
- 居室が2階でエレベーターがない、浴室が車いす対応でない、バリアフリー化が不十分など。
- こうしたハード面の事情で、転倒や事故リスクが高いと判断されることがあります。
3. 他の利用者との生活環境の兼ね合い
- グループホームなど少人数制の施設では「今いる利用者さんたちとの相性」も大切です。
- 強い不安や攻撃性のある方を受け入れると、他の利用者さんの生活が大きく乱れてしまう恐れがある場合は断られることがあります。
4. 緊急時の受け入れ条件
- 医師との連携体制が不十分な地域や施設では、夜間・休日にすぐ対応できないこともあります。
- そうなると「万が一の時に安全を守れない」という理由で難しいとされます。
5. 行政・制度上の制約
- 要介護度や認知症の有無など、制度上の対象外になるケース。
- 例えば「グループホームは要介護2以上から」「特定の医療処置は医療保険で」など、法律や制度の線引きに引っかかることがあります。
こうした理由は「あなたのせい」「ご本人が悪い」ということではまったくありません。
むしろ、事故や大きなトラブルを防ぐために必要な判断です。
だから「断られた=拒絶された」ではなく――
「より安全に支えられる場所はきっと別にある」というサインと受け止めてみてください。
今日からできる3つの準備
(1) A4用紙1枚「困ったときの連絡先」
いざというときに迷わず動けるように、A4用紙1枚に連絡先をまとめて、冷蔵庫や電話のそばに貼っておくと良いでしょう。
- 平日昼:担当ケアマネの名前・電話、事業所の番号
- 夜間・休日:地域包括支援センター、自治体の緊急相談ダイヤル
- 医療:主治医、在宅診療、訪問看護
- 救急の流れ:119 → 希望病院名 → 家族の連絡順
→ スマホを探すより早く「まずどこに電話するか」が一目で分かります。
(2) 小さなノート「困りごとメモ」
ケアマネさんとの相談や施設見学の場で「何が困っているのか」を正確に伝えるためのメモです。
- 何が困る?:例)夜に家を出ようとする、週4回
- いつ起きやすい?:例)夕方、入浴後
- 危ない場所:例)台所、玄関の段差
- 病気・薬:既往歴、飲んでいる薬
- 家族の限界:夜の見守りができない など
→ 同じ説明を繰り返さずに済み、職員や医師とも共有しやすくなります。
実際に「困りごとメモ」を用意していたご家族からは「次の相談では話がスムーズに進んだ」「医師やケアマネに安心して任せられた」という声が聞かれます。
また、入所した先の施設の職員にとっても「本人にとって何が辛いのか」「症状が予測できればあらかじめ対策が立てられる」など、単なるメモ以上の価値があります。
ほんの数行のメモでも、現場の職員にとっては大きな助けになるのです。
これも、本人の生活をより良くするための行動であり、間違いなく寄り添いの一歩です。
(3) 相談先を3つ決めておく
- 地域包括支援センター
- 主治医、または病院の相談窓口(地域連携室)
- 近くの居宅介護支援事業所を2~3か所
地図アプリにピンを立てたり、先ほどのA4用紙に電話番号を一緒に書き込んでおくと安心です。
施設に相談する時
断られるのはつらいことです。
でも「聞き方」と「受け止め方」を少し工夫するだけで、次につながるきっかけに変えられます。
最初のお願い(例)
「◯◯市に住む○○(ご本人との関係)です。
夜に家を出ようとすることが週4回あり、家族だけでは見守りが難しい状況です。
もし今はむずかしい場合、何が整えば受けられるのかと、次に相談できる窓口を2~3件教えていただけますか?」
相談して断られたときの返し方(例)
「ありがとうございます。教えていただいた条件と相談先をメモしました。
準備して、またご相談させてください。」
覚えておきたいコツ
- 「なぜ無理ですか?」ではなく「何が整えば可能ですか?」と聞く
- 具体的な窓口名を必ずもらう
- 日付・担当者・要点をメモし、家族で共有する
→ 断られる経験そのものが、次の一歩につながる情報収集になります。
ケアマネさんが見つからないとき
同時に3つの道を進めてみましょう。
- 地域包括に「担当ケアマネがいなくて困っている」と伝える
- 主治医や病院の相談窓口に、紹介をお願いする
- 近くの居宅介護支援事業所に順番に電話をする
→ 断られても「受け入れ条件」を次へ引き継げば、探しやすくなります。
これは「断られ続ける」ことではなく「条件をはっきりさせて合う場所を探す作業」です。
施設見学で聞くと安心な5つの質問
- 夜の体制(見回りの回数、呼び出し対応の目安)
- 困りごとへの対応例(不眠・不安・大声など)
- 医療的な支援(吸引・インスリン・褥瘡ケアが可能かどうか)
- 退去になることがあるケース(理由と防ぐ工夫)
- 入居までに家族が用意するもの(書類、薬、連絡体制)
→ 出てきた条件は「困りごとメモ」に追加しておくと役立ちます。
在宅で「まず48時間」を乗り切る工夫
次の相談につながるまでの「つなぎ時間」をつくるだけで十分です。
- 転倒防止:敷物や段差を片づける/夜は足元灯をつける
- 薬:朝と夕で分ける/飲んだらチェック印をつける
- 見守り:夜だけ家族で交代/短時間の見守りサービスを相談する
- 火や玄関:ガス元栓にカバー/玄関にチェーン/注意メモを貼る
- 緊急時:A4シートに書いた順で電話する
→ 完璧を目指さなくて大丈夫。「次の一歩につなぐ48時間」が大切です。
言葉を少し変えて受け取ると、心が軽くなります
施設や相談先からの言葉は、ときに強く響いてしまいます。
でも、その言葉をそのまま抱え込む必要はありません。
少し言いかえて受け取ることで、気持ちが軽くなり、次の行動につなげやすくなります。
- 「受け入れ不可」→ 「今の体制では安全が守れない」
- 「問題行動」→ 「安全に気をつけたい行動がある」
- 「うちでは無理」→ 「〇〇が整えば可能性が広がる」
言葉を変えるのは現実逃避ではありません。
自分や家族を責めすぎず、前に進むための工夫なのです。
家族会議は15分で十分
大きな話し合いは必要ありません。
やることをひとつだけ決めることがポイントです。
- A4シートの番号・担当者を最新に直す
- 困りごとメモを更新する
- 「誰が・いつ・どこへ電話するか」を1件だけ決める
→ 決めたら解散。小さな一歩を積み重ねることが近道です。
ここまで支えてきたこと自体が、すでに大きな力です。
迷いながらでも一歩ずつ取り組んでいるあなたの姿勢は、間違いなくご本人の安心につながっていることでしょう。
完璧を目指さなくても大丈夫。
小さな工夫と準備こそが、寄り添いの土台になります。
最後に
私たちが目指すのは、「断る/断られる」関係ではありません。
安全に、安心して支えられる場所を一緒に探すことです。
- A4の連絡先
- 困りごとメモ
- 話し方の工夫
- 48時間の乗り切り方
この4つがあれば、もし断られても、次の一手を出すことができます。
今日の小さな準備が、寄り添いを“選ばれた人だけのもの”にしない力になります。
その一歩が、必ず次につながります。
寄り添いとは、ただそばにいることだけを指すのではありません。
条件を探り、次の場所へ橋渡しをしていくこともまた、大切な寄り添いの形です。
あなたの小さな準備と工夫が、その寄り添いをつなぐ力になります。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
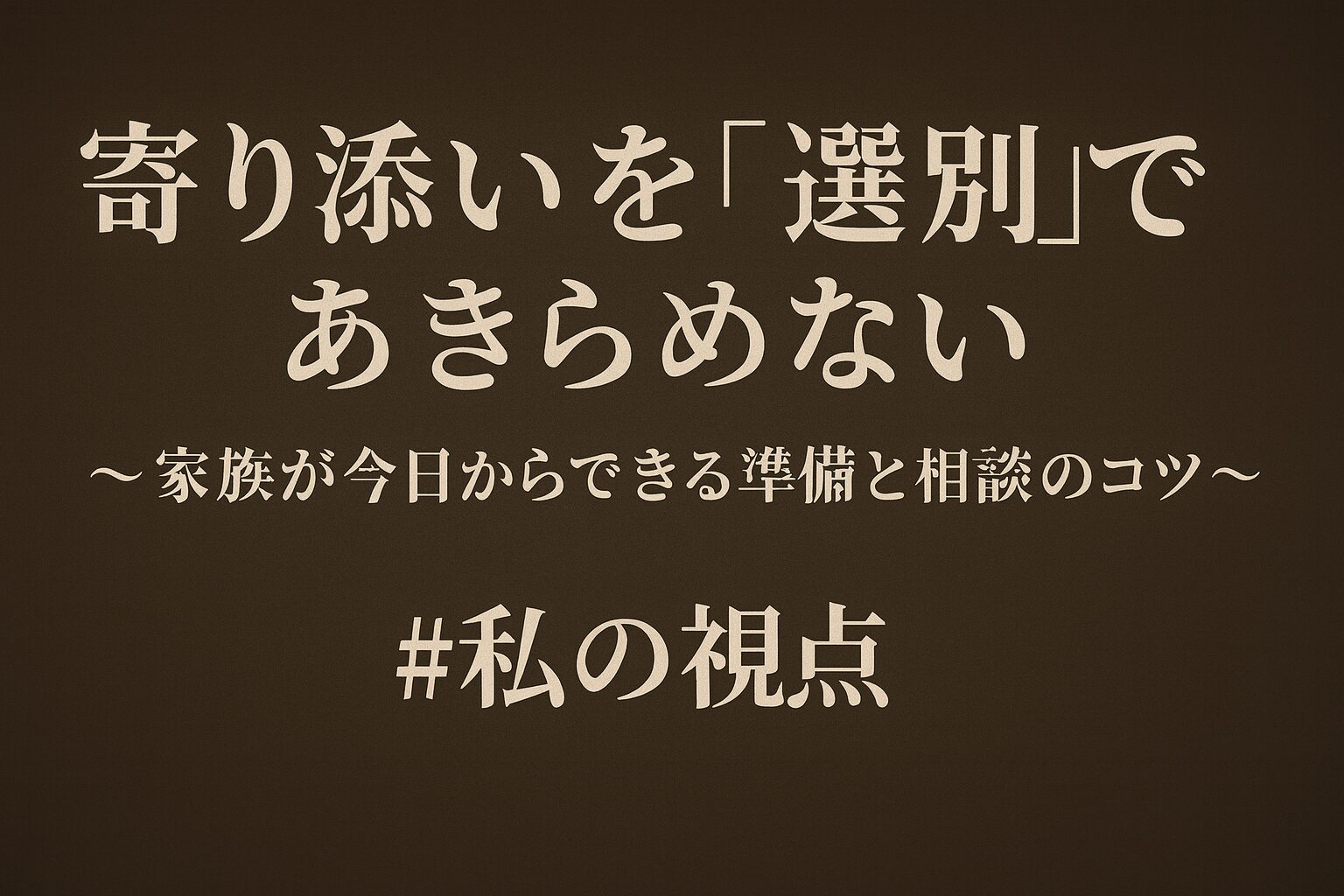
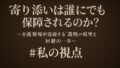
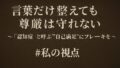
コメント