
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、ケアの本質は誰かの犠牲の上にあるのではなく、互いの尊厳を守り合うところにある、ということが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに
もし、介護職員がご入居者に手を挙げたとしたら、それは即座に「虐待」とされ、SNSや報道で一気に拡散され、世間からの批判にさらされるでしょう。
もちろん、介護に携わる者として、暴力は絶対に許されることではありません。
しかし実際の介護の現場では、ご入居者から介護職員が叩かれたり、暴言を浴びせられたりする場面は少なくありません。
実際に調査では、介護職員の4〜7割が利用者からのハラスメントを経験しており(厚労省)、直近2年以内に被害を受けた職員は26.8%にのぼるとの報告もあります(日本介護クラフトユニオン)。
それでも多くの場合「そういう仕事だから」「相手は認知症だから仕方がない」と、介護職員が感情を飲み込み、我慢することが当たり前とされてしまうのが現実です。
このような不均衡な構図に、私は疑問を感じています。
認知症という言葉が「すべてを正当化する理由」のように扱われる。
そのせいで『本当に守られるべき人は誰なのか』そして『その裏で誰が静かに傷ついているのか』。
これが、全くかみ合っていないと感じるのです。
本記事では、介護現場の現実と、ケアの倫理について考えてみたいと思います。
「相手は認知症だから仕方ない」という言葉の重み
私たち介護職員は、認知症について深く理解し、その症状やご利用者の行動の背景を想像してケアを提供することが求められています。
これは、認知症ケアの基本であり、決して軽視されるべきではありません。
例えば、暴言や暴力的な言動の裏には「不安」や「混乱」、あるいは「恐怖」などの感情が隠れている場合があります。
これらは、ご利用者がはっきりと伝えられない何かしらの“訴え”として表れていると捉え、そこに寄り添う努力をする――それは、認知症ケアのプロフェッショナルとしての重要な姿勢です。
しかし、それが行き過ぎると、いつの間にかこうなってしまいます。
- 「叩かれても仕方がない」
- 「暴言を吐かれても受け入れるのがプロ」
- 「怒鳴られても、私たちが悪いのかもしれない」
こうした考えは、一見「理解が深い」ように見えて、実はまったく逆です。
それは「認知症の方に寄り添っている」のではなく「職員の尊厳を犠牲にして、一見ケアが成り立っているように見える」だけであり、本質的には“諦め”や“放置”に近いものです。
介護職員もまた“守られるべき存在”である
たとえ原因がどこにあろうとも、他人を殴ったり罵倒したりすることは、社会的に見れば「してはならない行為」です。
認知症による影響があったとしても、それが日常的に繰り返されれば、対応する介護職員の心がすり減っていくのは当然のことでしょう。
しかし現実には、職員の側の「しんどさ」や「怒り」「傷つき」が話題になることはほとんどありません。
なぜなら、それを口にすると「感情的すぎる」「向いてないんじゃない?」「その判断が出来ないからここにいるんだよ」と言われる空気があるからです。
- 「人手不足だから仕方ない」
- 「それも含めて仕事でしょ?」
- 「利用者さんは悪気がないんだから」
まるで、介護職員の痛みや葛藤は「感じてはいけないもの」のように扱われています。
けれども、私たち介護職員だって人間です。
叩かれれば痛いし、理不尽な暴言には心が折れます。
何度も怒鳴られれば、明日仕事に行くのが怖くなることだってあります。
それを「相手が認知症だから」という理由だけで我慢し続けなければならないのは、あまりにも過酷ではないでしょうか。
複数の調査が示すように、職員の4〜7割、あるいは9割以上が暴言・暴力を経験しているのです。これは“例外的な出来事”ではなく、構造的な課題だと言えます。
なぜ「免罪符」になってしまうのか
ここには、社会全体の認知症理解と報道のあり方が密接に関係しています。
たしかに近年「認知症の人に優しくしよう」「地域で支えよう」という理解が少しずつ広まりつつあります。
それ自体は、とても喜ばしいことです。
しかし、その裏で――
- 「認知症の人は何をしても仕方ない」
- 「だって、本人には悪気がないから」
- 「叩くのも、叫ぶのも、すべて病気のせい」
という“極端な受け止め方”が浸透し始めていることにも、目を向ける必要があるのではないでしょうか。
実際に、介護職員の9割近くが暴言や暴力の被害を経験しているという調査結果もあります。にもかかわらず『認知症だから仕方ない』と片付けられてしまう――これが“免罪符”の現実です。
特にメディアでは、介護職員の不適切な行為が問題視される一方で、現場で職員が受けている暴力や暴言について報道される機会はほとんどありません。
たとえば、ある施設で職員が入居者様に暴力をふるった――というニュースは大々的に報じられます。
しかしその背景に、日常的に蹴られ、叩かれ、怒鳴られ続けた末に“ケアの破綻”があったとしても、そこには触れられません。
報道の光が当たるのは「分かりやすい加害者」だけ。
その陰で、職員の人間性や苦悩は切り落とされ「介護職 = 加害者」というイメージだけが強調されてしまうのです。
その結果、現場では何が起きていても「職員や環境が悪いのでは?」と疑われる空気が生まれてしまいます。
そして、現場の訴えはかき消され、介護職員の視点は社会に共有されることもなく、まるで『ケアの破綻など最初からなかった』かのように扱われてしまうのです。
認知症への理解が進むことと、暴力や暴言を容認することは、まったくの別問題です。
それを混同したままでは、現場にいる誰もが救われないでしょう。
ケアの本質は、誰か一方の犠牲の上に成り立つものではない
私たちが大切にしている“ケア”という言葉は、本来、誰か一人が我慢して成り立つものではないはずです。
認知症の方の不安や混乱に寄り添い、必要な支援を行うこと。
それと同時に、支援する職員が安心して働ける環境を整えること。
この“両輪”が揃ってこそ、本当の意味での「笑顔を共に生み出す = 認知症ケア」が成立します。
入居者様の尊厳も、介護職員の尊厳も、等しく守られるべきものです。
「ケアは双方向である」
このシンプルな前提が、忘れられていないでしょうか。
管理者としてできること
私は施設の管理者として、現場で頑張ってくれている職員が感情に蓋をしてしまわないよう、日々意識しています。
感情に蓋をしたまま働き続ければ、いずれそれは“折れる”という形で表れます。
だからこそ、まずは感情を否定せずに受け止めることが必要だと考えています。
「そんなこと言っちゃダメでしょ」「何でそんな態度を取ったの?」ではなく、
「怖かったよね」「つらかったね」「よく耐えたね」と声をかけること。
そのひとことで、こわばっていた職員の表情がやわらぐことは、少なくありません。
その上で
- 暴力や暴言が起きた背景を一緒に振り返る
- パターンやタイミングを記録として蓄積する
- 対応をチームで共有し、職員を孤立させない
こうした地道な取り組みが、職員にとっての「心の居場所」になります。
また、ご家族や関係機関に対しても「現場で実際に起きていること」「支援に必要な協力体制」について丁寧に説明し、一緒に“理解の輪”を広げていくことも、私たち管理者の重要な役割だと考えています。
おわりに
認知症の方の言動には、必ず意味や背景があります。
それを頭ごなしに否定せず、丁寧に読み解こうとする姿勢は、介護の専門性そのものです。
しかし同時に、介護職員の「苦しさ」や「痛み」もまた、同じように尊重されなければなりません。
認知症であることが、暴力や暴言を“免責”する理由として扱われてしまう状況では、職員の心は守られません
そして、守られない職員が提供するケアは、必ずどこかで歪みを生むことになります。
「我慢」や「自己犠牲」によってケアが成り立つことがあってはいけません。
相互の尊重と理解、そして支え合いの中にこそ、ケアは成り立つのではないでしょうか。
私たちが介護の現場で向き合っているのは、単なる「業務」ではなく、一人ひとりの人生そのものです。
それは、認知症の方も、介護職員も、どちらも同じです。
だからこそ、どちらか一方だけが黙って傷ついて、何となくケアが回っているように見える構造ではなく、お互いが人として尊重される関係の中でケアが成り立っていく仕組みが必要だと思うのです。
そしてこれは、介護現場だけの問題ではありません。
例えば――
- もし大切な人が介護職として働いていたら、その心や尊厳が守られているかどうか、どう考えますか?
- ニュースで「介護職員の不適切行為」を目にしたとき、その裏にある現場がどのような姿であるか想像できますか?
その視点一つで――現場の苦悩が少しでも理解されることで、介護職員の苦しみもやわらぐかもしれません。
「介護職だから我慢すべき」「認知症の人だから仕方がない」
この両極端な構図をどう乗り越えるか――。
それは、介護職員や管理者だけでなく、社会全体に投げかけられた問いなのだと思います。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなる考え方、技術を発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
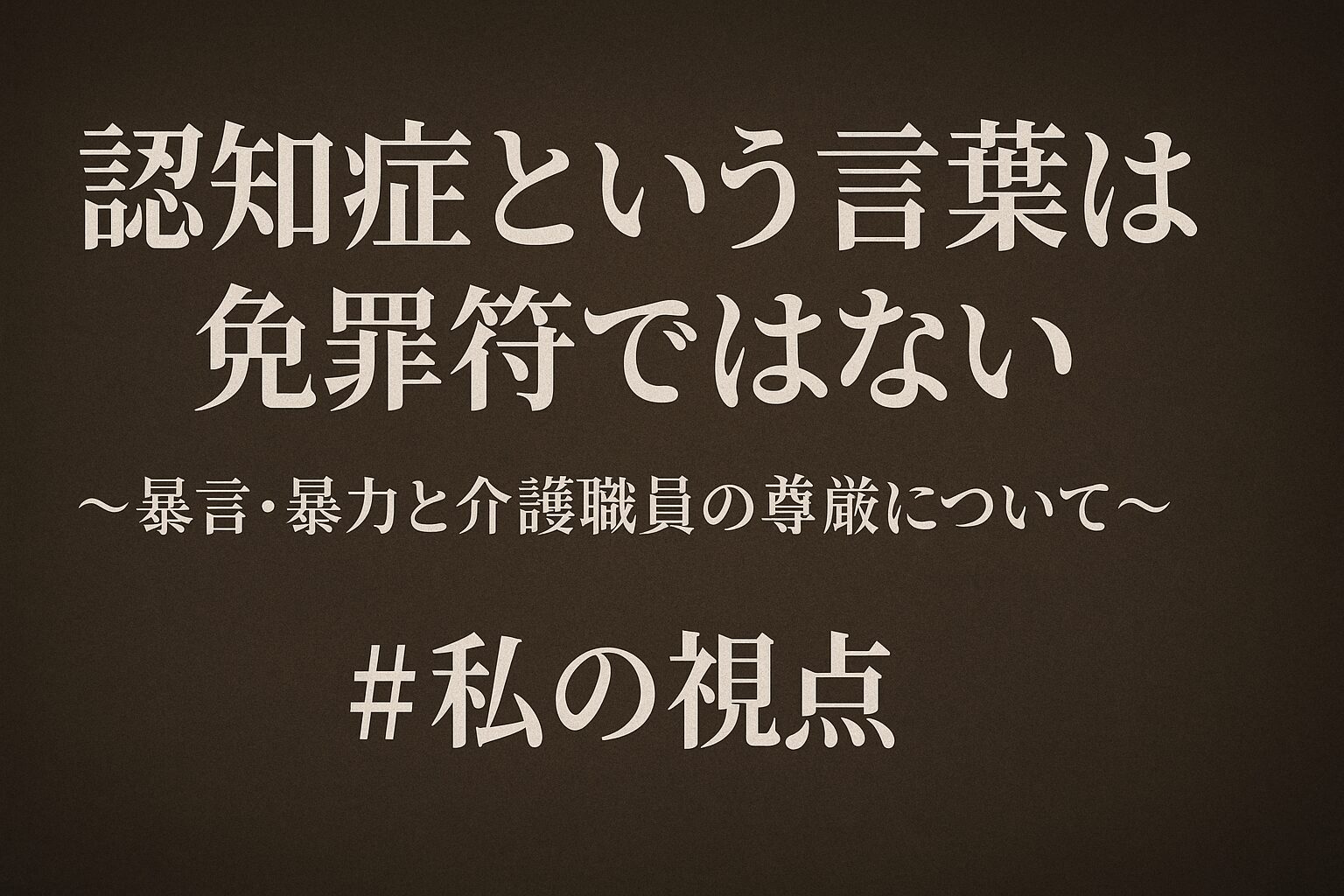
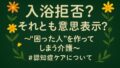
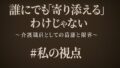
コメント