
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、グループホーム入居の妨げとなる可能性がある、感染症や医療依存度について分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
入居条件:入居に際して障害となる可能性がある条件
「親を施設に入れるなんて…」と悩まれる方も少なくありません。
しかし、グループホームは“家族の介護を放棄する場所”ではなく“本人が安心して暮らすためのもう一つの家”であり“支援者の生活を守るための場所”でもあります。
家族が安心して笑顔で関わり続けるためにも、正しい情報を知って選ぶことが大切です
グループホームの入居条件については
- 絶対に満たしていなければいけない要件
- 必須ではないが、多くの施設で求められている
- 入居に際して障害となる可能性がある条件
- その他、入居を考えた時に確認しておいた方がいい事項
という4つの記事に分けてお伝えをしていきます。
3番目となるこの記事では、グループホームの利用を考えたときにいくつかある条件の中で『もしかしたら入居するにあたっての障害になるかもしれない要件』について説明いたします。
また、その要件を満たしていなかった場合はどうすればいいのか、ということについてもお伝えをしようと思いますので、参考にしていただければ幸いです。
感染症の有無と入居への影響
入居にあたって、診断書の提出を求められるグループホームもあるかと思います。
入居を制限されることのある感染症とは
どのような感染症が該当するかというと『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』の中で定められた感染症の他、B型肝炎や梅毒、疥癬などです。
入居時に感染していた場合は、残念ながら入居を断られるでしょう。
感染症があっても入居できるケース
なお、感染症への対応方針は施設によって異なります。たとえば、B型・C型肝炎などは、適切な感染対策(手袋・ガウン・専用器具など)を取れば受け入れ可能としている施設もあります。
一方で、結核や疥癬など感染経路が明確で施設内での感染拡大の恐れが高いものについては、治療完了後でなければ入居できない場合があります。
「どの感染症まで対応できるか」は、医師の意見書や感染症治癒証明書をもとに、施設と相談して判断されるのが一般的です。
ですが、グループホームへの入居を考える段階ならすでに他のサービス(デイサービスやショートステイ、老健など)を利用していることがほとんどであると思います。他のサービスを利用して問題なく生活が送れているのであれば、このような重篤な感染症にり患していることはほぼないと思います。
施設によっては、それ以外の感染症も『入居をお断りする感染症』に該当しているかもしれませんので、見学時や申し込み時などに確認しておきましょう。
また、過去に感染していて完治した(医者から治ったという診断を貰っている)ものの、治った後も反応が出てしまうことについては特に問題なく入居が進められると思いますが、施設に情報提供だけはしておいてください。
そうすることで、出血時の対応や入浴に関しての配慮などを取ってもらえることが多いと思います。
感染症に関する事前相談について
感染症に関しては、かかりつけ医や地域包括支援センターを通じて相談することもできます。
「どの程度の感染症なら入居可能か」「治療後どのくらいで入居できるか」など、地域の医療・介護連携窓口が情報を持っている場合もあります。
入居を諦める前に、一度相談してみると良いでしょう。
入居に対しての、家族間の意識の統一
家族間で入居に関しての意識の統一が図れているか、ということは、実はかなり重要です。
家族の意見が分かれたまま入居すると起こること
例えば
- 娘は施設入居に反対していたが、息子が強引に話を進めて入居した結果、娘が外出に連れ出してそのまま帰ってこなかった
- 兄が入居を押し進めたら、弟が取り返しに来た
という話を聞いたことがあります。
家族間の意識を統一するためにできること
入居にあたって、家族間での意識の相違がないことが一番望ましいですが、その解消が図れない場合は『家族間で〇〇という状況がある』ということをあらかじめ伝えておきましょう。
また『兄からの電話は取り次がないでほしい』『弟の面会は断ってほしい』『キーパーソンや身元引受人以外からの面会は受けないでほしい』などについても施設は対応してくれると思いますので、取り次がないで欲しい方の名前と電話番号、関係性は最低限伝えてください。
可能であれば『どういった事情で対応しないで貰いたいのか』まで伝えていただけると、施設とより良い関係性が築いていけるかと思います。
ただし基本的には、個人情報保護もあるので、キーパーソンではない方にむやみに『入居しているかの有無』を伝えることはありません。また『本人の妹だけど面会したい』など伝えられても、最初の申し出では『ご家族様を通じてお話をいただきたい』などの対応を取られることが多いかと思います。
契約時に確認しておきたい家族・法的な関係
また施設側としては、契約時に「身元引受人」または「連帯保証人」を明確にしておくことが重要です。
誰が医療同意を行うのか、退去時の費用や遺品整理を誰が担当するのかが明確になっていないと、後々トラブルになるケースもあります。
家族間で意見が一致しない場合は、成年後見制度や任意代理契約の活用を検討するのも一つの方法です。
医療依存度が高い場合の入居制限
ほとんどのグループホームには、医療職が常駐していることはおろか、配置されていることもめったに無いのではないかと思います。
そして介護職は、医行為が行えません。
グループホームでは行えない医療行為
医行為とは『医師の医学的判断と技術がなければ人体に危害を及ぼす、または危害を及ぼすおそれのある行為』のことです。
つまり
- 点滴の流量調整や針の抜き差し
- インシュリン注射(自身で行えるのであれば問題ありません)
- 指先を穿刺しての血糖測定
- 摘便や浣腸(市販のイチジク浣腸は行えます)
- 褥瘡(床ずれ)の処置
- 酸素の流入の調整(外れたカニューレを戻す程度は行えます)
- バルーンカテーテルの管を入れ直す(内容物の破棄は行えます)
などの一切が行えません。
これらの処置が継続的に必要だったり、あるいは認知症が進行したことで自身で行えなくなったといったことがあると『本人が安楽に生活していただける場は施設ではないのではないか』となり、入居を断られたり、退居を進められると思います。
医療依存度が高い方でも入居できるケース
ただし、医療依存度が高い場合でも、訪問診療や訪問看護との連携が取れている施設では、一定の医療的サポートを受けながら生活することが可能です。
たとえば
- 定期的な往診で薬の調整や体調チェックを行う
- 訪問看護が週数回入り、褥瘡処置やバルーン管理を行う
- 夜間は緊急連絡体制を整えている
- 主治医からの『特別指示書』が受けられる
などのケースで、医療体制がある程度は整えられている場合もあります。
施設見学時には「どの医療機関・訪問看護と提携しているか」「急変時の対応体制」も確認しておくと安心です。
看取り対応の有無の確認について
なお、近年は看取りまで対応可能なグループホームも増えています。
医療依存度が上がっても、主治医や訪問看護との連携により「最期まで馴染みの職員に囲まれて過ごせる」環境を整えている施設もあります。
看取り対応の有無や体制も、事前に確認しておくと安心です。
入居をスムーズに進めるための3つの準備ポイント
今回の三つの要件については、入居するにあたっての大きな壁になるものではないかもしれませんが『グループホームに入居して、快適に、安楽な生活を送る』というものを目指した時に障害となってしまうかもしれない内容です。
グループホームは『認知症ケア』に特化している分、実は縛りが多かったりします。
だからこそ、認知症の方とその家族にとって最良の施設であろうとしています。
施設見学時には『感染症の有無や医療依存度について、どの程度までなら対応してくれるのか』『身体的な障害について、どの程度まで受け入れてもらえるのか』といったことについて、事前に相談することをお勧めします。
また、グループホームへの入居をスムーズに進めるために、以下の3点を事前に準備しておくと安心です。
- かかりつけ医に「入居先で必要な医療処置」について意見書をもらっておく
- 家族間で「誰がキーパーソンか」「面会ルール」を話し合っておく
- 施設見学時に「感染症・医療対応・看取り対応」について質問リストを持参する
入居するにあたって条件的には厳しい部分もあるかも知れませんが、是非これらの記事を参考にして、少しでも不安の払しょくや事前に手を打つお手伝いができれば幸いです。
【補足】本記事の参考文献・出典
- 厚生労働省「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
- 厚生労働省「グループホームにおける医療的ケアに関するガイドライン」
- 全国認知症グループホーム協会「感染症対策と入居受け入れ基準」
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
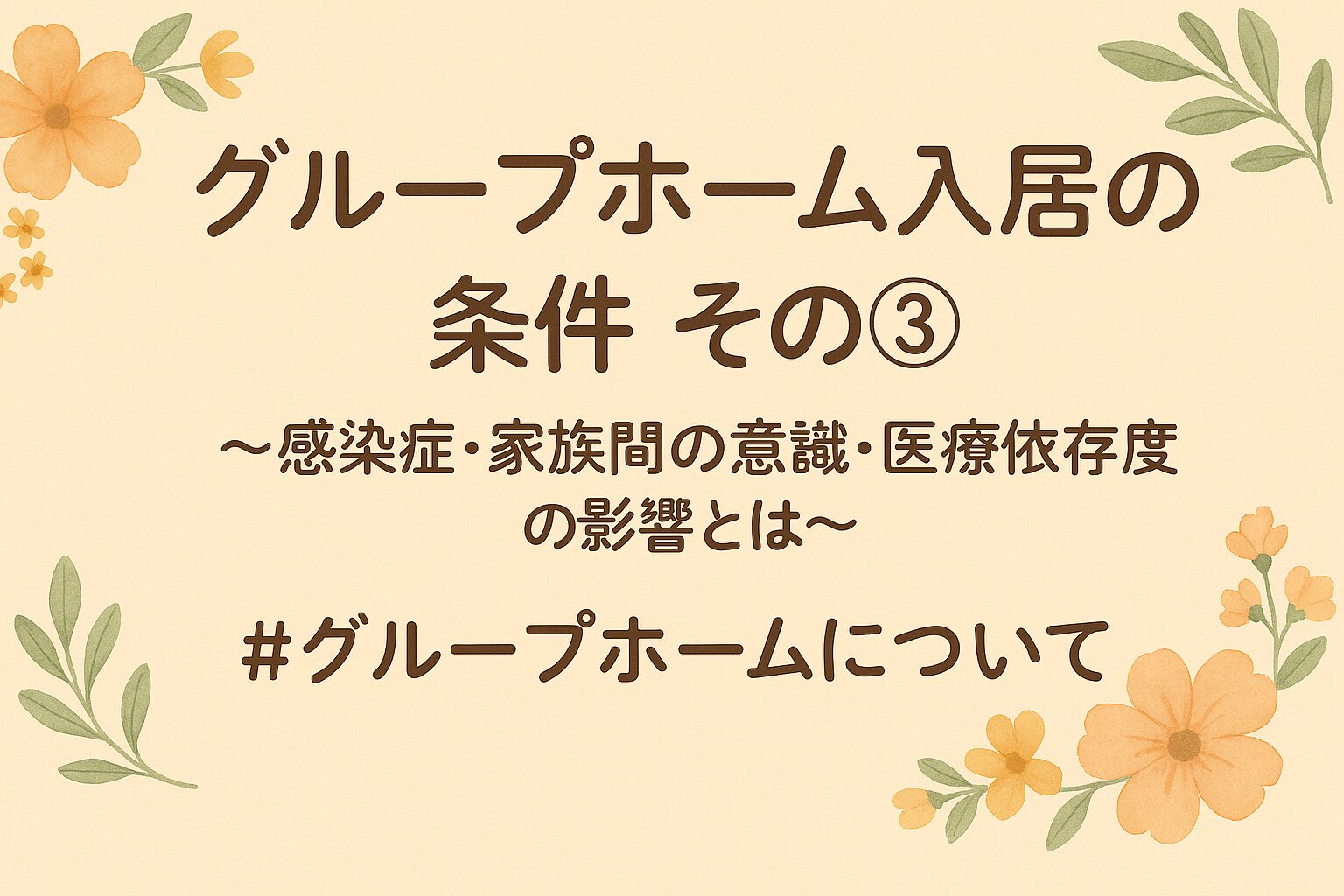
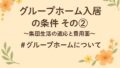
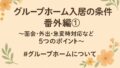
コメント