
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、グループホーム入居のスタートラインが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
入居条件:絶対に満たしていなければいけない要件
「親を施設に入れるなんて…」と悩まれる方も少なくありません。
しかし、グループホームは“家族の介護を放棄する場所”ではなく“本人が安心して暮らすためのもう一つの家”であり“支援者の生活を守るための場所”でもあります。
家族が安心して笑顔で関わり続けるためにも、正しい情報を知って選ぶことが大切です。
グループホームの入居条件については
- 絶対に満たしていなければいけない要件
- 必須ではないが、多くの施設で求められている
- 入居に際して障害となる可能性がある条件
- その他、入居を考えた時に確認しておいた方がいい事項
という4つの記事に分けてお伝えをしていきます。
グループホームは、誰でも利用できるわけではありません。
グループホームの利用にはいくつかの決まりがありますが、最初となるこの記事では「どうしても外せない基本条件3つ」について、わかりやすく解説します。
また、その要件を満たしていなかった場合はどうすればいいのか、ということについてもお伝えをしようと思いますが、今回の『絶対に満たしていなければいけない要件』については、どうにもならない場合も多くありますので、その点はご了承いただきたいと思います。
要介護認定が必要:グループホームの入居資格の基本
グループホームは介護保険を使っての利用となります。ですので、要介護状態にある事が必要となってきます。
要介護度を表す区分は8段階に分かれており、軽い方から
- 自立
- 要支援1~要支援2
- 要介護1~要介護5
となっています。
このうち、グループホームを利用できるのは『要支援2、および、要介護1~要介護5』の方です。
要支援1と自立の方は、利用することができません(申し込みは可能です)。
また入居した後であっても、介護保険の更新の際に要支援1か自立という判定がついてしまうと退去になってしまいますので注意が必要です。
要介護度の認定に不服がある場合の見直し手続き
ですが、介護度の認定に不服がある場合は『審査請求』か『区分変更』という2つの方法でのやり直しが可能です。
ただ、認知症は進行性の病気であり、現時点では治療法はありませんので、入居以降に要支援1以下になるということはまずないと思います。
ですが『要介護5で入居したが、入居して最初の介護度の更新で要介護1になった』という事例は私も何度か経験したことがありますし、非常にまれですが、要支援1で退居になったケースも実際にありますので、油断は禁物かもしれません。
※参照:介護保険法第8条第19項「認知症対応型共同生活介護」では、要支援2または要介護状態にある方が対象とされています【1】。
医師の認知症診断が必要:診断が必要な理由
1つめの、どうにもならない項目です。
まず、認知症の診断が出せるのは医者のみです。
さらに認知症という診断を出すためには『認知症『的』な症状がある』というだけでは無理な場合が多いと思います。
認知症という診断を下すには『脳の器質的な変化がある』ということも必要になってきます。
つまり『脳が委縮している』『脳梗塞などの影響で脳の一部が機能していない』といった『脳の形状に変化があり、それに起因して認知症の症状が出ている』という、誰の目にも明らかな判断材料が必要なのです。
本来であればそれに加えて『脳の器質的な変化に起因して現れた症状により、日常生活を送ることが困難』といった内容も認知症の定義としてありましたが、現在はあまり重要視されていないように思います。
つまり認知症であるということは『家族や周りの人が思うだけではダメ』ということです。
※参照:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」では、医師による適切な診断・早期支援の重要性が明記されています【2】。
住民票の所在地が同一でなければならない理由と例外
2つめの、どうにもならない項目です。
別記事【認知症の方のためのグループホーム ~特徴と利用方法、選び方について~】で、グループホームは地域密着型のサービスである、ということを書きました。
他市区町村の地域密着型サービスは、基本的にはどう頑張っても使えません。これはグループホームだけではなく、地域密着型デイサービスや、地域密着型特養なども同様です。
住民票が同一市区町村にある必要があるのは、グループホームが地域密着型サービスに指定されており”地域の住民のための施設”として設定されているためです。
同一市区町村に住民票がない場合の対応方法
ただし、絶対に利用できないかといわれればそうでもなく
- 住民票の移動(引っ越し)
- 住所地特例(みなし住所)
という2つの方法でかいくぐることもできなくはありません。
ですが、グループホームに住所を移すことは原則不可ですので『入居を希望している施設がある市区町村に親族が住んでいて、その住所に一旦住民票を移す』といったことができなければ、地域密着型施設の利用はほぼ不可能でしょう。
またこのどちらも、基本的には行政は嫌がります。
この項目については、別記事【他市区町村の地域密着型施設を利用するには】でもう少し細かく説明したいと思います。
※参照:介護保険法第8条第19項・第20項において、認知症対応型共同生活介護は「地域密着型サービス」として位置づけられています。
そのため、原則として同一市区町村に住民票がある方が対象です【3】。
条件を満たさなくても、支援を受ける道はあります
グループホームを利用する目的は
・認知症の進行を緩和させ、その人らしい生活を支援する
ことに集約されると思います。
そのために、いくつかの条件が付されています。
グループホームを利用するにあたって、どのような条件があるのか、なぜその条件があるのかといったことを知ってもらい、より有意義にグループホームを役立てていただきたいと思います。
今回ご紹介した3つの条件は、グループホームを利用するうえでの『スタートライン』といえます。
次回は『必須ではないが、多くの施設で求められている』という条件について、詳しくご紹介いたします。
なお一部は繰り返しの表記になりますが、今回ご紹介した3つの条件のうち、いずれかを満たしていない場合でも、すぐに諦める必要はありません。
状況によっては、次のような選択肢を検討できる場合があります。
- 要介護1未満(自立・要支援1)の場合
→ 小規模多機能型居宅介護や通所介護(デイサービス)の利用を検討することで、必要な支援を受けながら在宅生活を継続できます。 - 住民票が他市区町村にある場合
→ 親族が住む市区町村に一時的に住民票を移すことで、グループホームの入居が可能になるケースもあります。
ただし、行政が認めない場合もあるため、事前に必ず自治体の介護保険課へ確認しましょう。 - 認知症の診断がまだ出ていない場合
→ まずは、かかりつけ医や物忘れ外来などで受診し、診断書を取得してから入居相談を進めましょう。
このように、条件を満たさないケースでも、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することで、最適な支援ルートを提案してもらえる場合があります。
まとめ
グループホームの入居条件には、制度的な要件と地域的な制約があり「誰でも入れる施設」ではありません。
しかし、条件を理解したうえで正しい手順を踏めば、希望する施設で安心して暮らす道は開けます。
困ったときは、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、行政と連携しながら最適な支援を探していきましょう。
参考文献・出典
【1】厚生労働省:「介護保険制度の概要」
(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/tetsuzuki/)
【2】厚生労働省:「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000064084.html)
【3】厚生労働省:「地域密着型サービスの概要」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076610.html)
※厚生労働省のサイト構成変更によりリンクが無効になっている場合があります。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
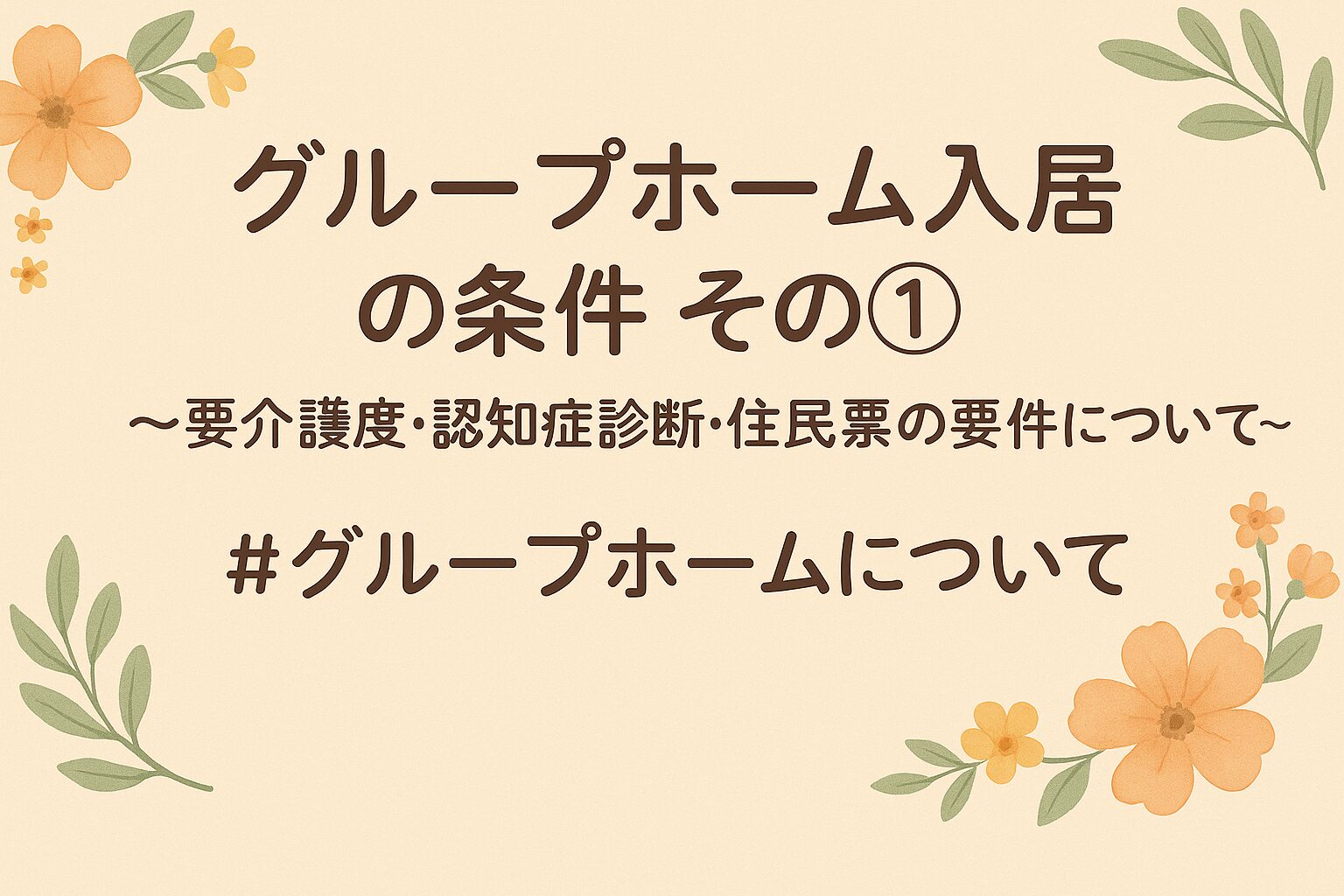
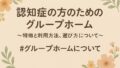
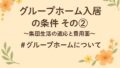
コメント