
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、介護現場で起こる“優しさ”や“寄り添い”のズレ。その背景と、リーダーが軌道修正するための伝え方が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに:ケアの“ずれ”に、悩んでいませんか?
「この職員の対応、ちょっと気になる。でも本人は一生懸命やってるし…」
「“寄り添い”のつもりが、かえって不安を助長してるのでは?」
――そんな葛藤を抱えた経験、ありませんか?
介護現場では、誰もが「入居者様のために」と最善を尽くしています。
それでも“思いの方向”が少し違うだけで、チームケアのバランスが崩れてしまうことがあります。
「その方のために」という思いが強いがゆえに、リーダーや管理者が目指すケアの方向性から逸れたケアが提供されてしまうことがあるのです。
この記事では、
- 職員ごとの“正しさ”や“優しさ”がずれる背景
- そのズレがケアやチームに与える影響
- ズレを軌道修正するための視点の持ち方・伝え方
について、現場目線で考えてみます。
職員ごとの「寄り添い方」「優しさ」がズレる理由
① 経験年数や成功体験の違い
新人職員は「不安や混乱を抑えることが最優先」という、その場の困りごとの解決を優先して考えることが多いように思えます。
ですがベテランになるにつれ「その背景にある感情や記憶に寄り添いたい」「不安を感じる根本とは何だろうか」と考える傾向が強くなっていきます。
どちらも間違いではありませんが、視点の深さや捉える範囲が異なることで、対応に差が生まれます。
② 優しさ=要望を叶えること?
「寄り添う」と聞いて「なるべく要望をすぐに叶えること」と捉える職員もいれば「本当のニーズに応えること」と捉える職員もいます。
たとえば、頻回に「家に帰りたい」と訴える方に対して、
- A職員:「じゃあ一緒に玄関まで行ってみましょう」とすぐに対応
- B職員:「帰りたい理由」を聞き出し、不安の背景にアプローチしようとする
このように「その人のため」の意味するところが職員ごとに違うのです。
③ “自分は良いことをしている”という実感の強さ
職員の中には「自分のケアは優しくて丁寧」「相手に寄り添っている」と自負している方もいます。
だからこそ、リーダーが「そこは少しズレている」と伝えるのが難しくなるのです。
その職員が、人間性を否定されたように感じてしまうリスクがあるからです。
リーダーの苦悩:「ズレている」とは言いにくい
リーダーや管理者としては「チームとしてのケアの方向性」に沿ってケアを統一したい。けれど、職員の思いや意図がある以上、それを否定するような言い方は避けたい。
特に、各々の“優しさ”をベースにしているケアであればあるほど、修正が伝えにくく、受け入れにくいものです。
ズレを正すために必要な「視点のズラし方」
職員のケアを「間違い」「不適切」と断じるのではなく“チームで目指すケアの方向性とのズレ”に焦点を当てることが大切です。以下のような視点を意識してみてください。
「ズレ」は、必ずしも悪いことではない
ここで一度、立ち止まって考えたいのは「ケアのズレ=悪いこと」ではない、という視点です。
むしろ、職員ごとの“ズレ”には、その人の経験・価値観・信念が反映されています。
「何を大切にしたいか」「どんなケアを理想とするか」が違うからこそ、ケアは単なる作業ではなく“人の営み”になります。
たとえば「安全を第一に考える人」と「本人の自由を尊重したい人」では、同じ行動に対する捉え方がまったく異なります。
どちらも「正しい」し、そこには「思い」があります。
だからこそ、リーダーがその“違い”を対立ではなく多様性として受け止め、チームで活かす方向に導けるかが問われます。
ズレを恐れて多様性から目を背けてしまうと、職員は自分の考えを出さなくなり、やがて「言われた通りにやるだけ」の受け身なケアに変わっていきます。
一方で、ズレを“気づきの材料”として扱えば、チーム全体の視点が一段深まり、ケアの質そのものが高まる可能性を秘めているのです。
つまり「ズレをなくす」のではなく「ズレを通して成長するチーム」を目指すことが理想です。
① 「善悪」ではなく「目的とのズレ」に言及する
✕「その対応はよくない」
◯「チームで大事にしている“安心を積み重ねるケア”からすると、ちょっと違う方向かもしれない」
“目的”という共通のゴールをベースにして話せば、指摘は攻撃ではなく提案になります。
② 「個人の考え」より「チームの価値観」に寄せる
ケアやご利用者に対する想いは職員個々であっていいと思います。
でも、ケアの“方向”はチームで揃える必要があります。
そのためには、チームとしての共通言語やケア方針を明文化することが効果的です。
例:
- 「本人の不安を根本から捉える」
- 「困りごとの“背景”に目を向ける」
- 「優しさよりも“安心感の持続”を優先する」
このような『チームの軸』があることで「あなたのやり方は間違ってる」ではなく「チームの軸にもう少し寄せてみよう」という言い方が可能になります。
指摘が前向きに伝わるコミュニケーション術
「ズレ」をチームで言語化する
また、ズレが起きたときに個人単位で終わらせず、チームで共有して言語化する場をつくることも重要です。
「この前の○○さんの対応、どう感じた?」
「本人は安心していたと思う? それとも不安そうだった?」
といった形で、日常の場面をチーム全体で振り返る。
こうした対話を積み重ねることで、
「チームとしての判断軸」が少しずつ形になっていきます。
これは“マニュアル”ではなく、“価値観の共有”です。
たとえば「その人の笑顔をどう捉えるか」もチームによって違います。
笑っている=安心しているとは限らない。
表情の裏に隠れたサインをどう読み取るかは、
チームの感性を磨く時間が必要なのです。
① 質問を使って振り返りを促す
リーダーからの指摘ではなく、本人が気づく形に持っていくと、抵抗感が減ります。
- 「あの対応の後、○○さんの表情はどうだった?」
- 「“また帰りたい”って言われた時、どう感じた?」
- 「今の方法、入居者様にとって“本当に安心できる形”だったかな?」
質問によって、職員が“行動の効果”や“背景への理解”に意識を向けることができます。
② ポジティブフィードバック+提案型の改善
- 「声かけのトーンはとても良かった。だからこそ、もう少しだけ間を取って、不安の理由を待ってみるのはどう?」
- 「丁寧に話を聞いてたね。その姿勢はすごく大事。ただ“帰りたい”が何度も続くってことは、別の訴えが隠れてるかもしれないね」
“できている部分”を認め、そのうえで“さらに良くする”という提案にすることで、職員は「ダメ出しされた」のではなく「レベルアップを求められた」と受け取りやすくなります。
実際の事例から見る「ズレ」とその修正
ケース:不安でフロアを歩き回る方への対応
- A職員:歩き始めるたびに「危ないから座っててください」と制止
- B職員:「どこか行きたい場所がありますか?」と会話しながら歩きに付き添う
- C職員:毎回付き添うことで“満たされた感”を演出し、その後安心して座って過ごせるように誘導
A職員にとっては「転倒リスクを減らす」ための最善。
しかし、本人の心理状態からすれば「制止されることで不安が高まる」可能性もあります。
このような時、リーダーは「どちらが正しいか」ではなく、
「どうすれば本人の不安が減るのか?」というチームの問い直しを共有することが大切です。
チームで話し合うときは「誰が悪いか」ではなく「何を大事にしたいか」から始めると、建設的な対話が生まれやすくなります。
リーダーに求められるのは、「正す」ではなく「気づかせる」
現場をまとめるリーダーや管理者にとって、職員の対応を指摘するのは簡単ではありません。
特に、職員の「優しさ」や「熱意」に基づく行動であれば、なおさらです。
でも、リーダーの役割は、
- 職員の人間性を否定することではなく
- チームケアの軸に“気づき直す”場をつくること
です。
まとめ:バラバラの“優しさ”を、チームの“安心”に変えるために
介護において“寄り添い”や“優しさ”は、とても大切な価値です。
しかし、それが職員ごとにバラバラであれば、入居者様にとっては逆に混乱や不安の原因になりかねません。
大切なのは「優しさを揃えること」ではなく、
「チームとして、どんなケアを目指すか」を揃えることです。
リーダーとしては、個々のケアを否定せず、チームの価値観とすり合わせていく。
その過程で、職員が「なるほど、自分のやり方を見直してみよう」と思えるような“問い”と“視点”を届けていくことが、より良いチームケアへの第一歩になるはずです。
“ズレ”がチームを強くする
大切なのは、ズレを問題視するのではなく「チームで成長するための材料」として扱うこと。
ズレが起こるのは、それだけ一人ひとりが“本気で考えている”証拠でもあります。
リーダーがその熱をくみ取り、方向を合わせていくことで“優しさの多様性”が“チームの厚み”へと変わっていくのです。
迷いながら、試しながら、共に考える時間こそがチームを育てます。
一人の優しさよりも、チーム全体で紡ぐ“安心”が、ご本人に届くケアの形になる――
その積み重ねの先に、入居者様だけでなく、関わる私たち自身の心も穏やかに整っていくのかもしれません。
補足:リーダー向けの実践ヒント(まとめ)
- 「良くなってほしい」気持ちで伝えること
- 質問で気づきを引き出す
- 事実(行動・結果)と感情(本人や入居者の)を分けて整理する
- チームで共有した価値観や方向性に立ち戻る
- 指摘の前に「良かったところ」を必ず伝える
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
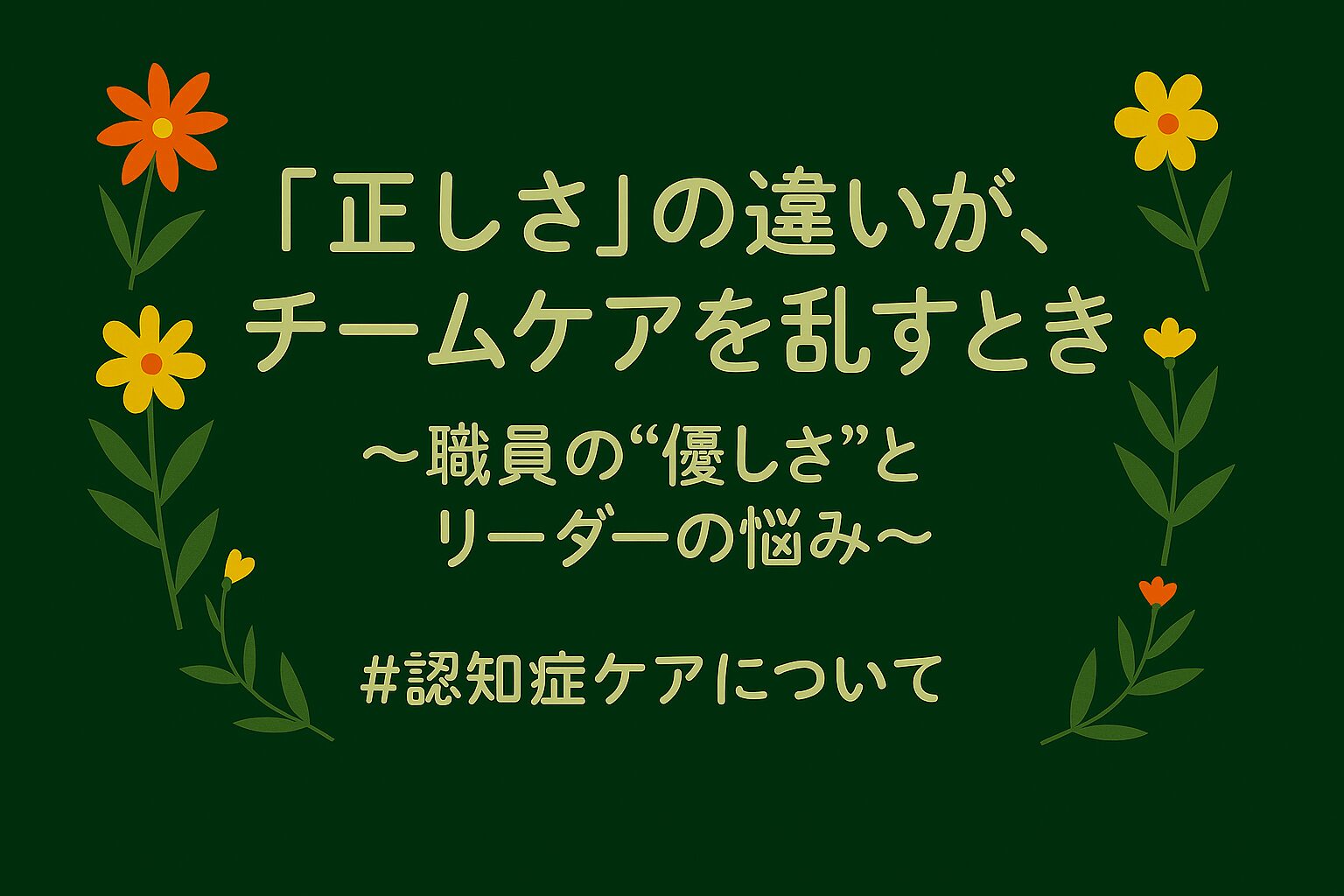

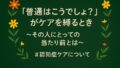
コメント