
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、認知症ケアにおける「寄り添い」の限界と、職員が抱える“寄り添えなさ”というリアルな葛藤が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
介護の現場では「もっと相手に寄り添いましょう」「相手の立場になって考えて」といった言葉が、まるで呪文のように飛び交っています。
もちろん、私たちがケアを提供するうえで“寄り添いの姿勢”はとても大切です。認知症の方の不安や混乱に寄り添い、安心を提供することが、質の高いケアの土台となることは間違いありません。
けれども、現場に立ち続ける中でふと感じることがあります。
- 「誰にでも寄り添えるわけじゃない」
- 「どうしても寄り添いたいと思えない人もいる」
- 「それを口にするのは、間違いなのか?」
今回はそんな、あまり語られることのない“寄り添えなさ”の感情について、正面から書いてみたいと思います。
『寄り添えない自分』を語ることについて
「寄り添いましょう」は正しい。でも万能ではない
「寄り添いましょう」という言葉には、優しさや誠実さ、相手を思いやる姿勢が込められています。まさに、介護の理想像のひとつです。
ですが、それが“常に誰に対しても当然にできるもの”として語られることには、少し違和感を覚えるのです。
現実には、寄り添いたくてもどうしても難しい相手や状況があり、感情の揺れや摩耗は日常茶飯事です。それでも「寄り添うことが善」とされる職場文化の中では、その揺れを口に出すことすら憚られてしまいます。
たとえばーー
- 自分の感情を一方的にぶつけてくる方
- 介護者を見下すような言動が続く方
- 認知症とは関係なく、もともと他者を傷つける態度を取っていた方
——このような相手に対しても「寄り添え」と求められるのは、職員にとって相当なストレスや葛藤を生むものです。
それでもなお「認知症だから仕方ないよね」「職員はプロなんだから我慢して当たり前」という空気感が、現場には漂っているように感じるのです。
「人としての相性」も、無視してはいけない
よく「職員も人間です」と言いますが、これはただのスローガンではありません。
私たちも感情があり、価値観があり、過去の経験があります。そして、それは「誰とでも平等に関われるべき」という、介護職のイメージ、幻想とは、時に相反するものです。
ある人には自然に優しくなれる。
ある人にはなぜかイライラしてしまう。
ある言葉には過剰に反応してしまう。
こうした“感情の揺れ”は、プロであっても避けようがないものだと思います。
そしてそれは、決して恥ずべきことではありません。
むしろ、それを正直に自覚し「無理をして関わろうとすること」よりも、「無理をしない関わり方をチームで模索すること」のほうが、ずっと誠実なのではないかと感じています。
そして、こうした相性の問題は、マニュアルや技術だけではどうにもならない領域でもあります。
どれだけ手順通りの対応をしても、心のどこかで「しんどい」と感じてしまうこと。それが言葉や態度ににじみ出てしまい「不適切な対応」と捉えられてしまうことさえあるのです。
寄り添えない時に、自分を責めないために
「寄り添えない自分」を、許してあげたい
私は、すべての人に深く寄り添えるような完璧な介護職ではありません。
そして、そうでなくてはならないとも思っていません。
むしろ「どうしても心が動かない」「この方とはどう関わっていいかわからない」と感じたとき、その自分の感情に蓋をして“寄り添うふり”をすることの方が、よほど怖いと感じています。
そうした“取り繕いのケア”は、どこかで必ず相手にも伝わります。
介護の仕事は感情労働でもあります。
「自分を偽って笑顔を作ること」はできても、それが続けば心は擦り減っていきます。
だからこそ私は「寄り添えない自分」にもスペースを与えたいと思うのです。
それを恥じるのではなく、むしろ正直に見つめて「じゃあ今の自分にできる関わりは何だろう」と問い直すことが、プロとしての責任ではないかと考えています。
寄り添えないときの自分を受け入れることは、とても勇気が必要です。
「あの人にはできているのに、なぜ私はできないのだろう」「自分は向いていないのではないか」と思ってしまう日もあるでしょう。
ですが、感情は抑えれば抑えるほど内側で膨らみ、やがて自分や相手を傷つける形で表面化してしまいかねません。
だからこそ「寄り添えない自分」も、ケアをより良くするために必要な一部だ、と認めることが、むしろ本当の意味での“寄り添い”に繋がるのではないでしょうか。
「認知症だから寄り添え」ではなく、関係性の再構築を
認知症になることで、思わぬ言動が生まれるのは事実です。前頭側頭型認知症のように、抑制の効かない言動が出る病態もあります。私たちはそこに医学的理解を持ち、環境調整や非言語的な関わりで対応していきます。
でも、その人のもともとの性格や価値観、周囲との関係性の在り方が、認知症の進行後にも色濃く残るケースは多くあります。
- もともと威圧的な父親像が、認知症になっても続く
- 家族をコントロールしようとする性質が、症状によって強調される
そうしたケースで、「認知症だから全部許して」「それでも寄り添って」は、介護者に一方的な負担を強いる構図になってしまいます。
私たちが求められているのは、何があっても無条件に許すことではなく、その人との“再構築された関係性”の中で、可能な限り誠実に関わることなのだと思います。
チームで関わる意味——苦手は「共有すべき弱点」
「自分一人では難しい」と思える相手がいても、それは決して敗北ではありません。
むしろ、一人の限界を自覚し、仲間に委ねられる力は、チームケアにおいて非常に大切な能力です。
誰かが苦手でも、誰かが得意かもしれない。だからこそ現場は「チーム」であるべきなのです。
介護の現場には、価値観の異なる職員がいます。それは、ケアの質を高めるうえで大きな利点です。
ある職員にとっては苦手な方も、別の職員には穏やかに接することができる。
ある職員が受け取れなかった言葉も、別の職員なら意味を汲み取れる。
だからこそ、「自分はこの方との関わりに悩んでいる」と共有することは、弱さの告白ではなく、チームケアの前提であり、資源なのです。
“できないこと”を打ち明け合えるチームは強い。
“無理して関わらなくていい”と思える職場は、職員の心を守る。
寄り添えない瞬間があったとしても、それを共有し、リレーする。
そうした柔らかな連携が、結果的にご利用者にとっての「より良いケア」に繋がっていくのではないでしょうか。
寄り添いの“かたち”は、一つではない
「寄り添う」とは、相手に飛び込むことだけではない
私たちはつい「ちゃんと寄り添うには、もっと感情移入しなければならない」「その人の苦しみに同化するべき」と思い込んでしまいがちです。
けれども本来、寄り添いとは一方的な自己犠牲ではなく、相手の尊厳と自分の尊厳の両方を守る関係性の構築であるはずです。
寄り添いとは、相手の感情のすべてを受け止めることではありません。
無理に心を合わせることでも、相手に完全に同調することでもないと私は思います。
ときには、一歩引いて見守る。
ときには、他の職員に任せる。
ときには、自分自身を守る。
そうした“寄り添いきれない”選択もまた、ケアの一つの在り方です。
そこには、自分の感情を大切にすることで、相手に誠実に向き合おうとする「プロとしての姿勢」**があると、私は信じています。
寄り添いの正しさより、自分の“揺れる気持ち”に誠実でいたい
「この方のそばにいると、どうしても苦しくなる」
「寄り添いたいと思えない。そんな自分が情けない」
そう思ってしまう瞬間は、きっと誰にでもあります。
でも、それはあなたが冷たいからではありません。真剣にケアに向き合っているからこそ、揺れるのです。
寄り添えない日があってもいい。
寄り添いたくないと思うことがあってもいい。
そして、それを職場で話せる関係性があってこそ、ケアは続けられるのだと思います。
“寄り添う自分”だけが正しいのではない。
介護職の本質とは、完璧であることではなく“揺れながらも、誰かに頼りながらでも、関わりを続けようとするその姿”にあるのではないでしょうか。
寄り添うことの難しさも、温かさも。
そのどちらにも揺れながら、私たちは今日も誰かと向き合っています。
そして「寄り添えなさ」を感じた日。
どうか、それを一人で抱え込まないでください。
あなたのその揺れもまた、介護の一部なのですから。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
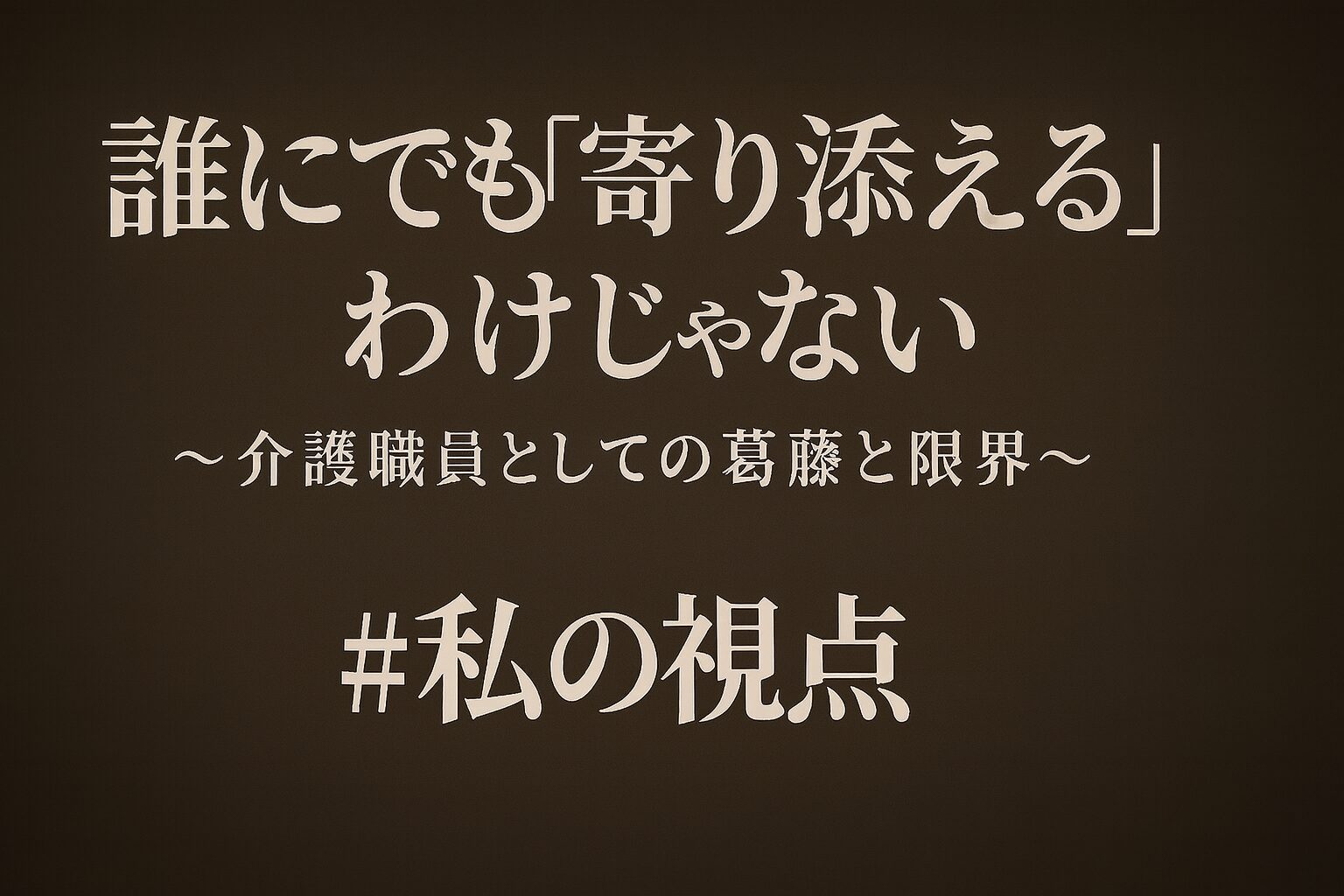
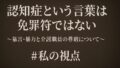
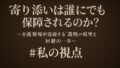
コメント