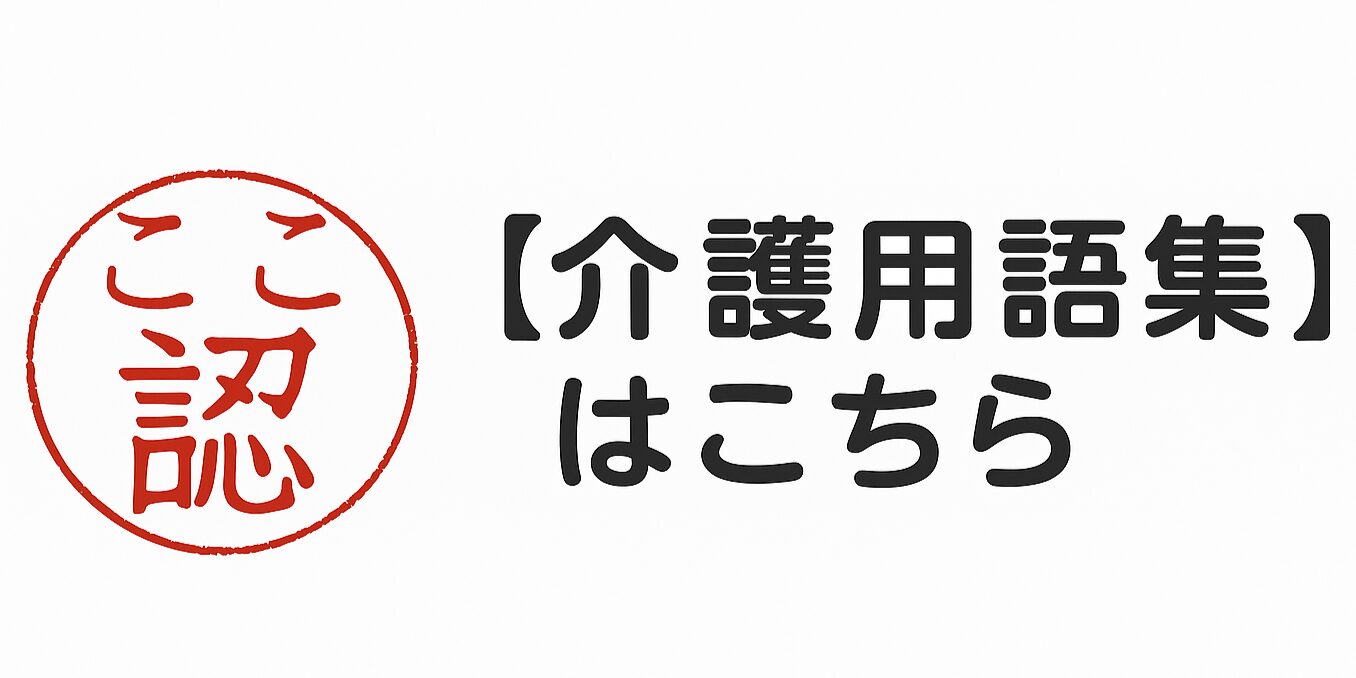ここにん【介護用語集】
2025.06.07
この記事は約8分で読めます。
介護・認知症ケアの専門用語集:やさしい解説
介護の現場や制度では、専門用語がたくさん出てきます。
『聞いたことはあるけど、よく分からない……』
『説明してといわれると難しい……』
そんな方のために、介護や認知症ケアに関する用語をやさしく解説しました。
職員の方も、ご家族も、ぜひご活用ください。
-
利用者の状況を把握して、ケアの方針を立てる前の情報収集。
-
「無気力」「無関心」な状態のこと。喜怒哀楽が非常に乏しく、何事にも反応が薄くなる様子。
-
最も多い認知症のタイプ。記憶障害から始まることが多い。
-
年齢により聞こえが低下する状態。高音から聞きにくくなる。
-
認知症の方が少人数で生活する介護施設。家庭的な環境が特徴。正式名称は『認知症対応型共同生活介護』。
-
介護サービスの内容や目標をまとめた計画書。ケアマネージャーが作成します。
-
介護サービスの調整・手配を行う専門職。正式には『介護支援専門員』。
-
認知症では無いが、物忘れが目立つ状態。早期対応がカギ。MCIともいわれる。
-
関節が固くなり動かしづらくなる状態。
-
認知症の行動・心理症状。中核症状をもとに、環境によって引き起こされる。例:怒り、不安、徘徊など。BPSD、周辺症状ともいわれる。
-
飲み込む力が低下して、食べ物や唾液が肺に入って起こる肺炎。
-
利用者のケアに関わる職種が集まって話し合う場。
-
ケアの計画、職員への指導を行う役割を持つ職員。
-
筋肉量が減る事で、歩行や立ち上がりが困難になる状態。
-
認知症の行動・心理症状。中核症状をもとに、環境によって引き起こされる。例:怒り、不安、徘徊など。BPSD、行動・心理症状ともいわれる。
-
その人が「自分らしく、満足して暮らせているか」を表す言葉心の豊かさや生きがいも重要。QOLともいわれる。
-
感情のコントロールや社会的行動に変化が出やすい。
-
高齢者は喉の渇きを感じにくいため、気付かずに進行しやすい。
-
高齢者や家族のための総合相談窓口。身近な支援拠点。
-
利用者が、住み慣れた地域で支援を受けるための制度。
-
認知症に共通する症状。記憶障害、判断力の低下など。
-
要介護3以上の方が入れる介護施設。費用が比較的安価。
-
記憶・判断・理解・注意など、脳が働く力の総称。加齢や病気で低下することがある。
-
障がいの有無に関わらず、誰もが普通に暮らせる社会を目指す考え方。
-
言葉以外の表情・声・姿勢などによる関わり。認知症ケアではとても重要。
-
「1件の重大事故の背後には、29件の軽微な事故と、300件のヒヤリハットがある」という考え方。
-
相手の立場や人生を尊重する、認知症ケアの基本姿勢。
-
事故にはならなかったが、危険でヒヤッとした出来事。
-
虚弱。健康と要介護の中間。体力・筋力・認知機能が低下。
-
食事・運動・薬の影響で多くの高齢者に見られる。生活の質にも影響する。
-
多くの種類の薬を服用することにより、副作用のリスクが高まること。
-
まっしょうれいかん。体の末端(手足など)が冷たくなる状態。血流の異常や体温低下のサイン。
-
最期のときを、穏やかに迎えられるように支える介護。
-
ケアプランがうまくいっているかを定期的に確認・評価すること。
-
小規模なグループで、一人ひとりに寄り添うケア方式。
-
「見る・話す・触れる・立つ」を大切にする、フランス発祥のケア技法。
-
介護保険サービスを受けるために必要な審査。市区町村が行う。
-
認知症の行動・心理症状。中核症状をもとに、環境によって引き起こされる。例:怒り、不安、徘徊など。周辺症状、行動・心理症状ともいわれる。
-
認知症では無いが、物忘れが目立つ状態。早期対応がカギ。軽度認知障害ともいわれる。
-
その人が「自分らしく、満足して暮らせているか」を表す言葉心の豊かさや生きがいも重要。生活の質ともいわれる。
※この用語集は、医療・介護の専門職向けではなく、一般の方向けにやさしく編集しています。
※より詳細な内容が必要な場合は、公的機関や専門職のアドバイスをご確認ください。