
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、現場での受け入れ判断や運営に悩む管理者・リーダーの方に向け、今後避けられない「寄り添いの選別」リスクと、その回避策のヒントをお届けします。
→ 筆者プロフィールはこちら
はじめに──「寄り添い」は意思だけで守れるのか?
最近、私のもとにも「2つの施設に断られた」というご家族から相談がありました。
理由は「夜間は人手が足りない」「医療依存度が高い」「暴言があるため対応困難」などです。
つまり、ご本人や家族の努力とは関係なく「受け入れられない現実」がすでに静かに広がっています。
これまでの記事では、
- 「認知症という言葉は免罪符ではない」
- 「誰にでも寄り添えるわけじゃない」
という視点から、介護職員の葛藤や限界について綴ってきました。
今回はさらに踏み込みます。
「そもそも、寄り添われる側になれることすら、当たり前ではなくなりつつある」——管理者である私たちは、この現実に正面から向き合う必要があります。
高齢者は増え続けるのに、支える側は減っていく
2040年代の高齢化ピーク
国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本の65歳以上人口は2043年に約3,953万人でピークを迎える見通しです。高齢化率は2040年に35%、2070年には39%近くに達するとされています。
この数字は単なる人口統計にとどまらず、「生活支援を必要とする人が確実に増える」という現実を意味します。とりわけ認知症の有病率は年齢に比例して上がるため、介護現場では「重度認知症かつ医療依存度が高い方」が今以上に増えることが予想されます。これは、現場の管理者にとって受け入れ判断の難しさが増すことを示しています。
さらに、高齢者の増加は地域差も顕著です。都市部では「施設に入りたくても入れない待機」、地方では「担い手がいなくて事業所が閉じる」といった、異なる形の“介護の空白地帯”が広がる可能性があります。2040年代のピークは、全国一律の問題ではなく、地域ごとに深刻な歪みをもたらす時期になるのです。
介護職員は不足する一方
厚生労働省は2040年に約272万人の介護職員が必要と試算しています。しかし、現状は約215万人。あと57万人の確保が必要ですが、若年層の介護職離れや処遇問題が重なり、供給は追いつきません。
介護職員不足の本質は、単なる「数」だけではありません。若手の定着率が低く、経験豊富な中堅が抜け落ちていくことで、チームのスキルバランスが崩れるのが現場の実感です。管理者としては、採用よりもむしろ「辞めさせない仕組み」を考えざるを得ず、負担はさらに増しています。
また、外国人材に頼る流れが進んでいますが、言語や文化の壁を超えて『介護』が提供できるようになるまでには、相当な時間がかかります。今後の人材不足は「誰かが穴埋めしてくれる」状況ではなく、現場ごとに“どう守り抜くか”を考えなければならない段階に入っているのです。
ケアマネジャーの高齢化も深刻
ケアマネの平均年齢は53.6歳。60歳以上が33.5%、40歳未満は7.6%しかいません。実働数も減少傾向にあり、調整役すら確保が難しい時代が迫っています。
ケアマネ不足は単に人数の問題にとどまらず「困難事例を担う人が減る」ことを意味します。特に認知症に伴うBPSDや多重疾患を抱えるケースは、経験豊富なケアマネでなければ支援の糸口を見出すことすら難しいことがあります。ところが、ベテランが退職すると同時にそうのような困難なケースは行き場を失い、管理者が直接調整役を担う場面が増えています。
さらに、ケアマネの配置基準や業務量制限により、担当件数に上限が設けられています。つまり「受け持ちたくても制度的に担当できない」という状況が起きており、制度そのものが“支えの分断”を助長する危険性をはらんでいます。管理者にとっては「ケアマネがつかないまま入居希望が届く」という現実が、今後ますます増えていくでしょう。
現場で静かに始まっている「選別」
管理者として日々直面するのが「受け入れるか、断るか」という判断です。
かつては利用者側が「どの施設がよいか」を選べましたが、今では「人手が足りないから受けられない」「夜間の重度対応は困難」と、施設が利用者を選ぶ場面が、徐々に増えています。
ただしこれは露骨な「拒否」ではありません。
申し込みをしても「空きがない」と言われ続ける、ケアマネが見つからない、調整がつかず在宅介護が崩れる……。
“寄り添われないまま関係が成立しない”という静かな選別が、すでに始まっているのです。
管理者が今すぐ取り組むべき3つのアクション
「選別」と「調整」の違い
現場で避けたいのは「選別」ではなく「調整」です。
- 選別:
「この施設では無理です」とだけ伝え、ご本人と家族を“行き場のない状態”にしてしまうこと。 - 調整:
「この施設では難しいが、包括支援センターや専門ユニットなら対応可能です」と、“次につなげる道筋”を必ず示すこと。
つまり、同じ“受け入れできません”という内容でも、伝え方ひとつで“拒絶”にも“支援”にも変わるのです。
そして“不明瞭な選別”を起こさないために、管理者としてできる一歩は次の通りです。
1. 受け入れ条件の明文化
「対応できる/できない」を曖昧にせず、夜間体制・医療依存度・暴言暴力の頻度などを基準として文書化しましょう。
明文化することで、職員にも家族にも説明しやすくなります。
2. 断るときに代替案を必ず添える
単に「無理です」と言うのではなく「包括支援センターに相談を」「この広域ユニットなら対応可」と、次の行き先を必ず提示します。
これが「選別」ではなく「調整」につなげる鍵です。
3. 困難事例の広域連携を作る
単独の事業所で背負えないケースは、地域の会議体や専門ユニットにつなげる仕組みを整えましょう。
“受けられない=孤立”にならない地域体制をつくることが、管理者の責務になっていくでしょう。
ケアマネ・包括職員と、管理者が協働する視点
- ケアマネ:AIで代替できる業務と、人にしかできない判断を切り分ける。どこがそのラインになるのかを管理者(主任ケアマネ)が整え、施設ごとの特性を勘案しながら依頼することが必要です。
- 包括支援センター:困難事例を一事業所に抱え込ませず、広域で対応できる仕組み作りが必要です。そのためには、地域の施設管理者との連携が重要になります。
家族に伝えておきたい“小さな工夫”
管理者が家族に伝えられる実用的な工夫もあります。
その一つが「困ったときの連絡先をA4一枚にまとめる」こと。
冷蔵庫や電話のそばに貼っておくだけで、家族がいざというとき迷わず動けるような支援です。
「一枚の紙」に書いておくと安心な連絡先の例
とっさの時に慌てず動けるように、以下のような情報をA4一枚にまとめておくと安心です。
- 平日日中の連絡先
担当ケアマネジャーの名前と電話番号、事業所の代表番号 - 夜間・休日の緊急連絡先
地域包括支援センター、自治体の高齢者緊急相談ダイヤル - 医療機関の連絡先
かかりつけ医、在宅診療クリニック、訪問看護ステーション - 救急時の希望フロー
例:119に連絡 → 希望搬送先の病院名 → 家族への連絡順序 - 家族内の連絡体制
兄弟・親族の電話番号、緊急時に連絡する順番
こうして整理しておくと、
- 電話帳やスマホを探す時間が減る
- 「誰に最初に連絡するか」で迷わない
- 家族間で対応の順序を統一できる
といった効果があります。
これらを紙1枚にまとめるだけで、家族にとって“最初の行動の地図”になるのです。
これは選別を回避する大きな仕組みではありませんが、確実に“支えを途切れさせない一歩”です。
終わりに──選別か、調整かは管理者の判断次第
「寄り添い」は美しい言葉ですが、現場では人手不足や制度の限界にさらされ、意思だけでは守れない支援になりつつあります。
だからこそ、私達施設管理者は、
今できる具体策を積み上げることが重要です。
- 受け入れ条件を明文化する
- 断るときは代替案を必ず添える
- 広域連携の仕組みをつくる
この積み重ねが、寄り添いを“選ばれた人のもの”ではなく“みんなのもの”にしていきます。
管理者としての最初の一歩
もちろん、これらは一人の管理者がすべてを完璧に整えるのは難しい取り組みです。ですが、小さな一歩から始めることで、現実的に前へ進めます。
- 受け入れ条件の明文化
→ まずは「過去に受け入れが難しかったケース」を3つ振り返り、共通点をメモしておきましょう。それだけでも「条件のたたき台」になります。 - 断るときの代替案
→ いきなり一覧を用意する必要はありません。地域包括や医療機関との日常的なやり取りの中で「もし自分が断るなら、どこを紹介できるか」を1ケースずつ記録しておきましょう。その積み重ねが代替リストになります。 - 広域連携の仕組み
→ 自分一人で仕組みを立ち上げる必要はありません。まずは月1回の管理者同士の情報交換会や、地域の困難事例に対する検討会などに「困難事例を共有する」議題を入れるだけで、十分な一歩になります。
「寄り添いは、誰のものか?」
その答えを「誰かのものではありません。誰にでもあるものです」と言える社会をつくるのは、管理者である私たちの行動による部分も、大きいのかもしれません。
【参考文献】
- 国立社会保障・人口問題研究所(2023)『日本の将来推計人口(2023年推計)概要版』国立社会保障・人口問題研究所.
- 厚生労働省(2019)『第9期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数』厚生労働省.
- Kaigo Plus(2023)『ケアマネジャーの高齢化と人材不足』Kaigo Plus.
- JobNavi NEXT(2023)『ケアマネジャーの高齢化と人材不足』JobNavi NEXT.
- 株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(2023)『介護人材の需給とサービス提供体制』GemMed.
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2018)『地域包括支援センター業務実態調査』三菱UFJリサーチ&コンサルティング.
- 仙台市健康福祉局(2020)『包括支援センター運営協議会資料:地域包括支援センターの役割と考え方』仙台市.
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
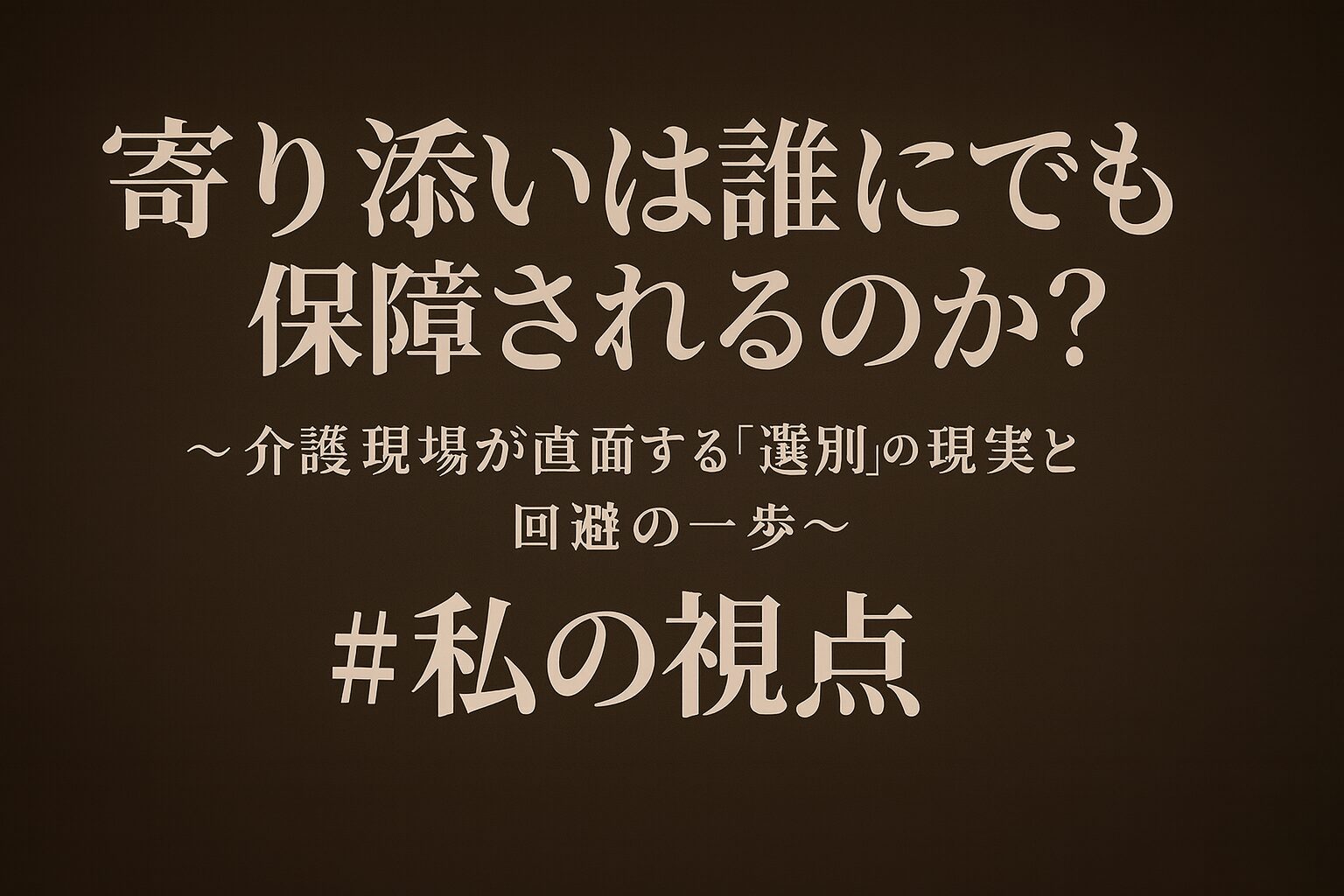
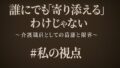
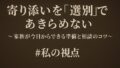
コメント