
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、なぜ認知症と名称が変わったのか、認知症という言葉を使うだけでは尊厳の保持は難しいことと、それはなぜかが分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
※本稿の立場
公的文書・記録・家族説明・対外広報では「認知症」を用いることを前提にしています。
本稿は、現場で本人の尊厳を“実装”するために、言葉の使い方にどこまで自覚的であるべきかを検討するものです。蔑称の容認ではありません。
なぜ「痴呆」から「認知症」になったのか
2004年、厚生労働省に「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」が設置され、6月〜12月にかけて4回の審議が行われました。候補には「認知症」「認知障害」「もの忘れ症」等が挙がり、国民からの意見も踏まえた上で、一般用語・行政用語は『認知症』に改めるという報告書が同年12月24日に取りまとめられ、同日付で各都道府県へ通知されています。背景には、旧称が侮蔑感を与えやすい・状態像を正確に表さない・早期受診の妨げになる、といった課題がありました。その後、行政・報道・教科書等で「認知症」が標準表記となりました。
“正しい言葉”が、現場の思考停止を生むとき
「認知症」という中立語は、世間の偏見や先入観を軽減する最低限の土台です。問題は、土台を“完成形”だと勘違いしてしまうことです。
現場で特に起こりがちなのが
- 言い方は丁寧でも、命令調・急かす・遮るなどの振る舞いで、無自覚に相手の尊厳を損なう。
- 「認知症ですから」とラベルを盾に、その人の個別性や生活史を後回しにする。
- 本人の自己表現(「最近ボケてきて…」など)を即座に矯正し、対話の扉を閉じる。
言葉は容器であって中身ではありません。
容器が正しくても、中身(態度・関係性・環境設計)が粗ければ尊厳は守られません。
「自称」と「他称」を切り分ける ~翻訳という技術~
ご本人が自分を「ぼけ老人」と言うのは、困りごとの自己表現や照れの緩和として機能する場合があります。ここで「その言い方はダメです」と矯正から入ると、羞恥を増幅させ、関係が硬直します。現場の原則はシンプルです。
- 受け止め:「そう感じるとき、しんどいですよね」
- 翻訳(中立語へ):「覚えにくさが増えて困る場面があるのかもしれません」
- 支援に接続:「予定をカレンダーに書いておく、などを試してみませんか」
逆に、職員が第三者に向けて「この方は、ぼけが進んで」と言うのは、力の差からくる“ラベリング”として捉えられる可能性があります。記録・申し送り・家族説明は“機能の具体”で表すのが原則です。
ここでいう 「機能の具体」 とは「ぼけ」「痴呆」といった抽象的な言葉を避けて、実際に観察できる認知機能や行動上の変化を、具体的に記述することを指します。
例で見る「ラベル語」と「機能の具体」の違い
- ラベル的表現
- 「この方は、ぼけが進んでいる」
- 「かなり痴呆がひどい」
→ 主観的で、相手の人となりを“ひとまとめ”にしてしまう表現。
- 機能の具体
- 「新しい出来事を覚えることが難しく、30分前の会話の内容を繰り返し尋ねられる」
- 「食事後に自室への戻り方が分からなくなることが増えている」
- 「複雑な指示を一度に伝えると混乱するため、1ステップずつ伝えると理解しやすい」
→ 観察事実・時間軸・条件を明記しており、ケアや支援につなげやすい。
なぜ「機能の具体」が重要か
- 尊厳を守る
「ぼけ」とまとめずに「記憶保持が難しい」「道順が分かりにくい」と記述することで、本人の人間性や個性を否定せずに済みます。 - チームケアに役立つ
抽象語ではケア方法が共有できませんが、「○○の場面で△△が難しい」と具体的にすれば、支援の工夫が見えてきます。 - 家族への説明が誠実になる
「ぼけています」ではなく「食後に部屋が分からなくなることがあるので、案内を強化しています」と伝えれば、安心と納得につながります。 - 記録のエビデンス性が高まる
客観的事実として残すことで、医師や他職種との連携にも有効です。
現場での実践のポイント
- 5W1Hを意識:「いつ」「どこで」「どんな状況で」「どのような困難が」「どの程度の頻度で」起きたか。
- 支援とのセットで書く:「歩行中に方向が分からなくなる → 職員が同行すると安心して移動できた」。
- 主観的な形容詞を避ける:「ひどい」「かなり」ではなく「週に3回」「5分以上」などの定量表現。
「機能の具体」についてのまとめ
「機能の具体」とは“本人をラベルで括るのではなく、観察可能な事実として表し、ケアにつなげる言葉”です。
たとえば「ぼけが進んでいる」ではなく、
→「新しいことを覚えるのが難しく、名前を繰り返し確認される」
→「複数の指示を同時に理解することが困難」
といった具体的記述こそが、尊厳を守り、支援を導きます。
親密圏と公的圏 ~同じ冗談でも意味は変わる~
一対一の親密圏では、ご本人の自称に軽いユーモアで返すことが自己緩和として機能することがあります。ところが食堂や面会スペースなど公的圏では、同じ冗談が自己卑下の固定化や役割の押し付けに変質しやすいという危険性があります。
職員は笑いの音量を下げる・話題を支援行動へ橋渡しする、といった文脈調整を常に意識すべきです。
「認知症」という言葉を正しく使い“自己満足”を避けるために
〈公式・外向き〉
- すべて「認知症」で統一。
- 表現は機能・行動・必要な支援で具体に。
- 「認知症だから〜できない」と能力の全否定をしない。
〈本人との会話〉
- その人が理解できる語彙を優先。自称の「ぼけ」の引用は一対一でのみ。
- 矯正ではなく翻訳で中立語へ繋ぎ、具体的支援を提示。
- 第三者がいる場では中立語に寄せる(“音量を下げる”)。
〈チーム内〉
- 申し送り・記録は観察+支援(形容詞ではなく事実と対応)。
- 月1回の「語彙棚卸し」と言い換えテンプレの確認と更新。
- 新人教育に“言葉のガイド”を含め、耳トレ(言い換え演習)をルーチン化。
NG/OKのミニガイド(“ラベリング”を避け、機能で語る)
- ×「この方、ぼけが強くて」
→ ○「新しい情報の保持が難しく、初対面の方の顔と名前が結びつきにくいご様子です」 - ×「最近ぼけました?」(第三者の前)
→ ○「最近、物忘れでご不自由な場面が増えていますか?」(一対一で) - 本人:「俺、ボケてもうダメや」
→ 受け止め→翻訳→支援提案(メモの定位置・合言葉など) - ×「徘徊がひどい」
→ ○「目的地への道順が分からず歩かれる。目的探しと案内表示で頻度が減少」
“言葉に守ってもらう”のではなく“言葉で守りにいく”
尊厳は態度×環境×言葉の掛け算です。中でも言葉は、最前線のインターフェース。だからこそ私たちは、言葉の衛生管理を仕組みに落とし込む必要があります。
- 環境設計で言葉を節約:案内表示、定位置のメモ、写真付きスケジュールは、説明の量を減らし、尊厳を守る。
- 呼びかけの一貫性:敬称・名前の先出し・触れる前の声かけは、権力差の軟化に直結。
- 沈黙を待つ:分からない時の沈黙は思考の時間。急かすほど、尊厳は傷つく。
- 選好を守る提案:「A or B?」で詰めず、「Aを先に、Bはあとでも大丈夫」で主導感を残す。
どうすれば“自己陶酔”から抜け出せるか——チェックリスト
今日から、チームで週1のミニふりかえり(10分)を。
- 今週「認知症だから」で話を終わらせた申し送りはなかったか。
- 本人の自称を矯正で潰していなかったか(翻訳→支援に接続できたか)。
- 第三者がいる場で笑いの音量を上げていなかったか。
- 記録は観察+支援で書けているか(形容詞から脱皮できたか)。
- 新人に言葉のガイドを手渡し、耳トレを一度でも実施できたか。
補足:形容詞からの脱皮、とは
具体的に言うと——“ひどい・強い・かなり”といった主観的な形容詞に頼らず、観察可能な事実や頻度、条件で記録する という意味です。
悪い例(形容詞的)
- 「物忘れがひどい」
- 「混乱がかなり強い」
- 「落ち着きがない」
→ どのくらい? どんな場面? 誰が見ても同じ解釈になる? ――が分かりません。
良い例(具体的・事実ベース)
- 「午前中に同じ質問を5回繰り返した」
- 「入浴介助の際に、手順を2回説明しても理解が難しく、職員が動作を見せると理解できた」
- 「食後に自室へ戻ろうとして2度廊下を往復し、職員が声をかけて誘導した」
→ 回数・条件・対応を記録することで、チーム内で共有しやすく、改善策も考えやすい。
なぜ「形容詞から脱皮」が必要か
- ケアの再現性を高める
→ 他の職員が読んでも同じ理解ができる。 - 尊厳を守る
→ 「ひどい」と書かれるより「5回繰り返した」と書かれる方が本人への評価感は弱い。 - 連携に役立つ
→ 医師や他職種に伝えるときに、具体的データは診療や判断に直結する。
記録のちょっとした工夫
- 数値化できるものは数値化(回数・時間・頻度)。
- 条件を添える(「入浴介助のとき」「夜間起床時」)。
- 支援とのセットで書く(「声かけで落ち着き、入浴できた」)。
まとめ:「正しい言葉」は出発点、尊厳は着地点
社会が「認知症」という言葉を整えたのは最低限の前進です。けれど現場がそこで満足した瞬間、尊厳は“置き去り”になります。言葉の本質は“通じること”であり、相手に届き、行動を支え、選好を残すための道具です。
「認知症」という言葉を使い、書くだけで尊厳が守られるわけではありません。
私たちがどんな姿勢で、どんな場面配慮で、どんな“翻訳”を行い、どんな支援に繋げたか——その総体こそが、尊厳の実体です。
「認知症」という言葉に守られているのは、相手ではなく自分の安心ではないか。
そう自問することから、本当に相手を守るケアが始まります。
参考・出典まとめ
- 用語変更の一次資料:厚労省「『痴呆』に替わる用語に関する検討会 報告書」/開催一覧(第1回〜第4回、2004年)
- 自治体の周知例:京都府「『痴呆』に替わる用語(『認知症』)の使用について」
- 実践の基盤:厚労省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」本編および事例集(最新版の周知版を含む)
- PCC(パーソン・センタード・ケア)解説:健康長寿ネット(長寿科学振興財団)
- 研修教材:厚労省「認知症ライフサポート研修テキスト」(コミュニケーション配慮・事例学習)
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
本記事のテーマに関心を持たれた方は、以下の記事もおすすめです。
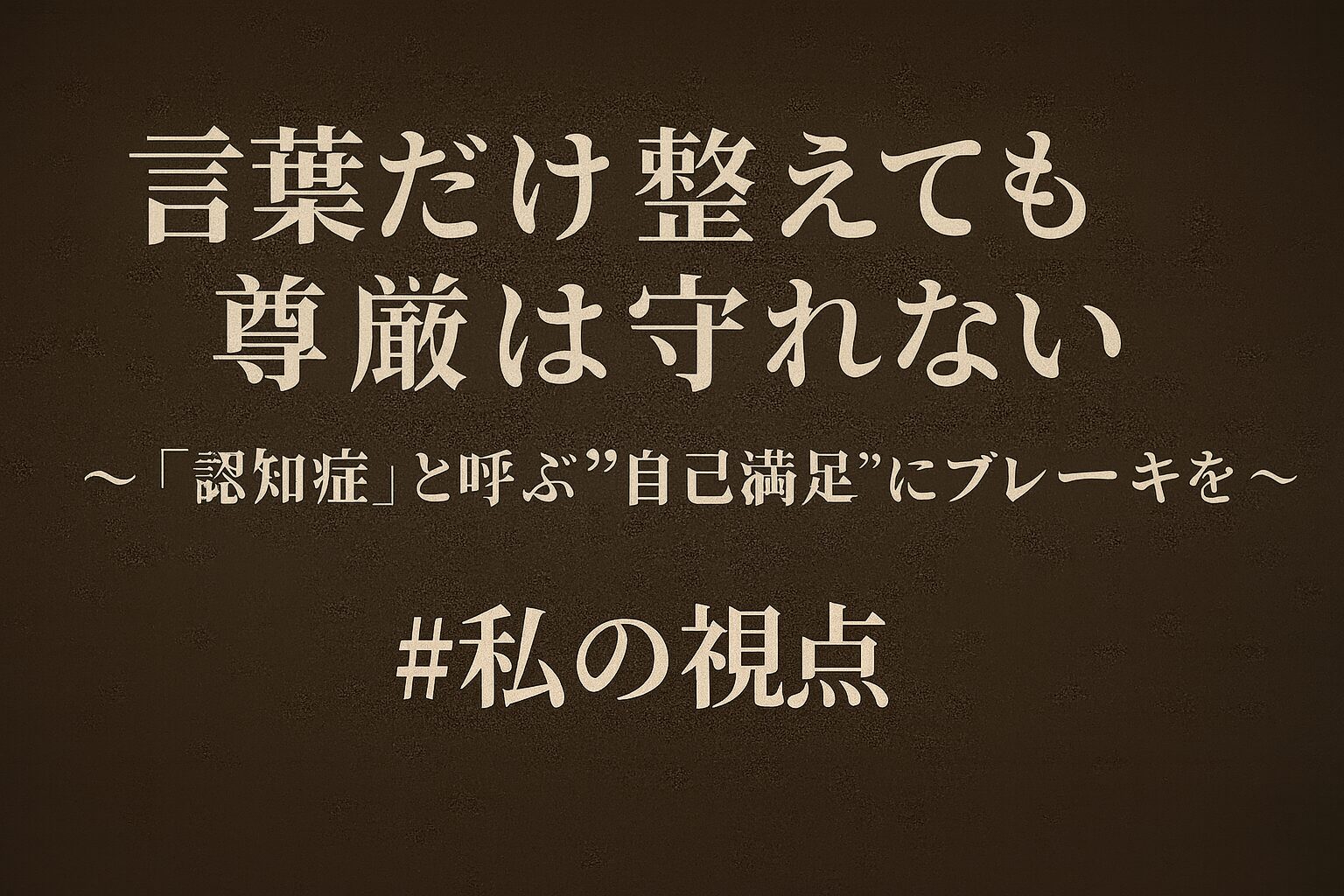
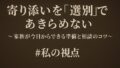

コメント