※この記事は『施設入居を勧める記事』ではありません。
迷っている方が、安心して考えるための材料をまとめた記事です。

※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
【この記事で伝えたいこと】
認知症の方と家族が、お互いに無理をし過ぎず、良い関係を保ちながら生きていくために、施設の利用は「大切な選択肢の一つ」です。
施設は「手放す場所」ではなく、家族の絆を守り、生活を立て直すための『距離』を作る場所ということを、お伝えします。
【要点】
- 家族だからこそ「適度な距離」が必要になることがある
在宅介護は、愛情や責任感が強いほど無理を重ねやすく、関係がすり減ってしまうことがあります。
施設を利用することは、冷たさではなく、関係を守るための選択です。 - 施設にはそれぞれ役割があり、目的によって選ぶ
ショートステイ・特養・グループホームは「一時的な支え」「長期的な生活」「認知症ケアに特化」など、役割がまったく異なります。
状況や困りごとに応じて、合う施設は変わります。 - 正解は一つではなく、相談しながら決めていい
施設入居は急いで決めるものでも、誰かに決められるものでもありません。
地域包括支援センターやケアマネージャーと相談しながら「本人にとってより良い生活」を軸に考えていくことが大切です。
【この記事で分かること】
・認知症の方と家族にとって、施設がどんな意味を持つのか
・ショートステイ・特養・グループホームの違いと役割
・「施設を考え始めるタイミング」の目安
・施設選びに迷ったとき、どこに相談すればいいのか
・施設利用が、家族関係を壊すのではなく守る選択になり得ること
家族・支援者それぞれの立場から「施設を利用する」という判断を、安心して考えられる視点が身につく内容です。
※詳しい説明・根拠・事例は、このあと本文でやさしく解説します。
認知症の方とともに生きるための施設
たとえ認知症を患い、徐々に生活が変わってきたとしても、お互いが大事な家族であることに変わりはありません。
ですが、大切な家族であるからこそ――そして、お互いにとって大切な家族であり続けるため、『適度な距離をおく』ことも、時には必要です。
その距離が、お互いの関係を良い状態で維持する、あるいは改善させるために大いに役立つことを、私は今までの経験や多くのご家族様と関わる中で、実感してきました。
「ちょっと大変かも」と感じたときが、考え始める時期
自宅での認知症の方の介護に困難さを感じてきたり、疲れや不安を感じてきたときは、施設の利用を考え始める時期といえるでしょう。
その際に候補に挙がってくる施設としては
- ショートステイ(短期入所生活介護)
- 特養(介護老人福祉施設)
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
といった施設になってくるかと思います。
それぞれがどういった施設で、どのような時に必要になるのか――本記事では、施設利用という選択肢について、その種類や特徴を分かりやすくお伝えします。
ショートステイとは? 短期間の利用で介護者の負担を軽減
名前の通り、短期間のお泊りが可能な施設です。
先に挙げた三つの中でこのサービスのみ、自宅に戻るために利用するサービスとなります(そうでない目的もありますが、他の二つのサービスは基本的に、入所・入居したら自宅に戻るという事はありません)。
利用の目的としては
- 介護者が休息を必要としたり、体調を崩したとき
- 冠婚葬祭などで介護が行えないとき
- 退院後の一時的な利用
- 入る介護施設が決まらないとき
といったところになります。
つまりどちらかといえば『サービスを受ける本人のため』というよりは『本人の生活を支える家族のため』といった色合いが濃いサービスになります。
また、例えば介護者が体調を崩した際にショートステイを利用することで、一時的に介護の負担を軽減する事ができます。
「一緒にいたいけれど、少し休みたい」と感じたときに
『認知症とはいえ、親と一緒に生活をしたい。でもたまには息抜きをしたい』
『大事な親だけど、四六時中いっしょは……』
『退院したけど自宅での生活が難しい。でも次の場所が決まらない』
といった場合に利用することも、効果的かと思います。
ただし、ショートステイはあくまで一時的な利用が前提です。
そのため「長期的に預けたい」といった希望には対応できません。また、繁忙期や地域によっては予約が埋まっており、希望した時に利用できないこともあります。
特養とは? 終の棲家(すみか)としての役割と特徴
特養は、原則として65歳以上で、要介護3以上の方が利用することができます。
また、よく『終の棲家』とたとえられます。
『介護を必要とする方が、最後まで利用できる場所』としての役割を求めて特養を希望する方が多い、ということが大きいと思います。
また
- 他のサービスに比べて、費用が安価であることが多い
- 施設内の設備が、要介護度が高い方でも対応できるように整っていることが多い
- 現在住んでいる場所に関係なく、別の市区町村の特養でも入所できる(入所を希望する方、入所してもらいたい方を呼ぶことができる)
- 看護師の配置が義務付けられている(常駐ではない)
- 医師の配置が義務付けられている(常駐ではない)
知っておきたい注意点
一方で、特養は「終の棲家」として人気は高いですが、入所までに長期間待たなければならないケースが多いのも現実です。特に都市部では数百人待ちということもあり、「入りたいときにすぐに入れる施設」ではない点には注意が必要です。
特養を視野に入れた時には、早めの動き出しが必要となってくるでしょう。
グループホームとは? 認知症ケアに特化した少人数の施設
グループホームは、認知症ケアに特化した施設です。
利用するためには
- 認知症であること
- 要支援2か、要介護1〜要介護5であること
- 施設がある市区町村に住民票があること
といったことが必須になります。
グループホームならではの強み
グループホームの強みは「少人数での生活」にあります。
1ユニット9名程度で生活を共にするため、職員の目が届きやすく、家庭的な雰囲気の中で安心して過ごせます。地域密着型の施設(市区町民しか利用できない)ということもあり、大規模な施設に比べて入居者同士の関係が近くなり「一緒にご飯をつくる」「掃除を分担する」など、役割を持ちながら、その人のペースに合わせた日常を送れるのも特徴です。
また、そこで働く職員は全員が認知症ケアに特化しているため、行動や心理症状(BPSD)が見られた場合にも、落ち着いて適切な対応ができます。大人数の中で不安を感じやすい方や、家庭的な雰囲気を大切にしたい方にとっては、大きな安心につながります。
利用にあたって知っておきたい注意点
注意点として、グループホームは認知症ケアに特化している魅力がありますが、医療的な処置が必要になった際には対応できないこともあり、医療ニーズが高まったときには別の施設への転居を検討する必要が出てきます。
グループホームについては私の専門でもあるため、別記事【認知症の方のためのグループホーム ~特徴と利用方法、選び方について~】にて細かくお伝えいたします。
ここまで読んで「なんとなく分かったけれど、違いが整理しきれない」と感じた方もいるかもしれません。
「言葉では分かったけど、実際どう違うの?」と感じられる方のために、利用条件や特徴を比較できる表を用意しました。施設選びの参考にしてください。
| 施設名 | 利用条件 | 主な目的 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートステイ (短期入所生活介護) |
要支援・要介護認定を受けている方 | 介護者の休養や体調不良時、冠婚葬祭、退院後の一時利用 | 数日〜数週間の短期間お泊まり | ・介護者の負担を軽減 ・緊急時に利用できる |
・一時的な利用が中心 ・施設に空きがない場合は利用困難 |
| 特養 (介護老人福祉施設) |
原則65歳以上 要介護3以上 |
長期的な入所 「終の棲家」として利用 |
医師・看護師配置義務あり 介護度が高くても生活可能 |
・費用が比較的安価 ・看取りまで対応可能 |
・入所待機が長い場合あり ・居住の自由度は低め |
| グループホーム (認知症対応型共同生活介護) |
認知症と診断されている 要支援2〜要介護5 同じ市区町村に住民票がある |
少人数での共同生活を通じた認知症ケア | 1ユニット9人程度の少人数制 家庭的な雰囲気 |
・認知症ケアに特化 ・地域密着で安心 ・個別性に合わせやすい |
・医療的ケアは限定的 ・入居費用は特養より高め |
その他の選択肢について
本記事ではショートステイ・特養・グループホームを中心に紹介しましたが、実際には他にも認知症の方やご家族が利用する機会の多い施設・サービスがあります。
老健(介護老人保健施設)は、医療ケアやリハビリを受けながら「自宅に戻ること」を目的に、一時的に入所する施設です。退院後のリハビリや、在宅生活へつなげる準備として活用されることが多いです。
小多機(小規模多機能型居宅介護)は「通い」「泊まり」「訪問」を一体的に提供できるサービスです。顔なじみの職員が柔軟に対応してくれるため、自宅での生活を続けたい方や、ご家族の介護負担を軽減したい場合に役立ちます。
また小多機は『地域密着型サービス』であることにも注意が必要です。
選択肢は一つではありません
このように施設やサービスにはさまざまな選択肢があります。大切なのは、ご本人の状態やご家族の希望に合わせて「どのサービスが安心につながるのか」を一緒に検討していくことです。
施設の利用を検討する際は、まずは地域包括支援センターや、担当のケアマネージャーに相談してみましょう。
地域包括支援センターは、地域の高齢者の介護や福祉に関する総合相談窓口です。保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーといった方々が、福祉制度の活用や介護サービスの相談に乗ってくれます。
相談できる専門職の存在
また、担当のケアマネージャーは、どのようなサービスを利用すれば、要介護状態となった方が在宅(自宅)で生活を送ることが出来るかを考えるプロです。
一方で、本人の状態、家族の介護力などを客観的に見極め、施設への橋渡しをしてくれる存在でもあります。
自宅で介護をしたい家族と、ケアマネージャーとの意見が割れることもあるかと思います。
しかしその根底には、どちらにも『要介護状態となって困っている人の生活を、より良くしたい』という思いが流れています。
最後に大切にしたいこと
『本人にとってより良い生活とは何か』を考えた先に『施設入居』という選択肢が浮かんできたときには、先ずは見学をしてみてください。
そして少しでも『そこで笑顔になっている大切な人の姿』が見えたのであれば、少し踏み出してみても良いのではないでしょうか。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさん発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
参考記事
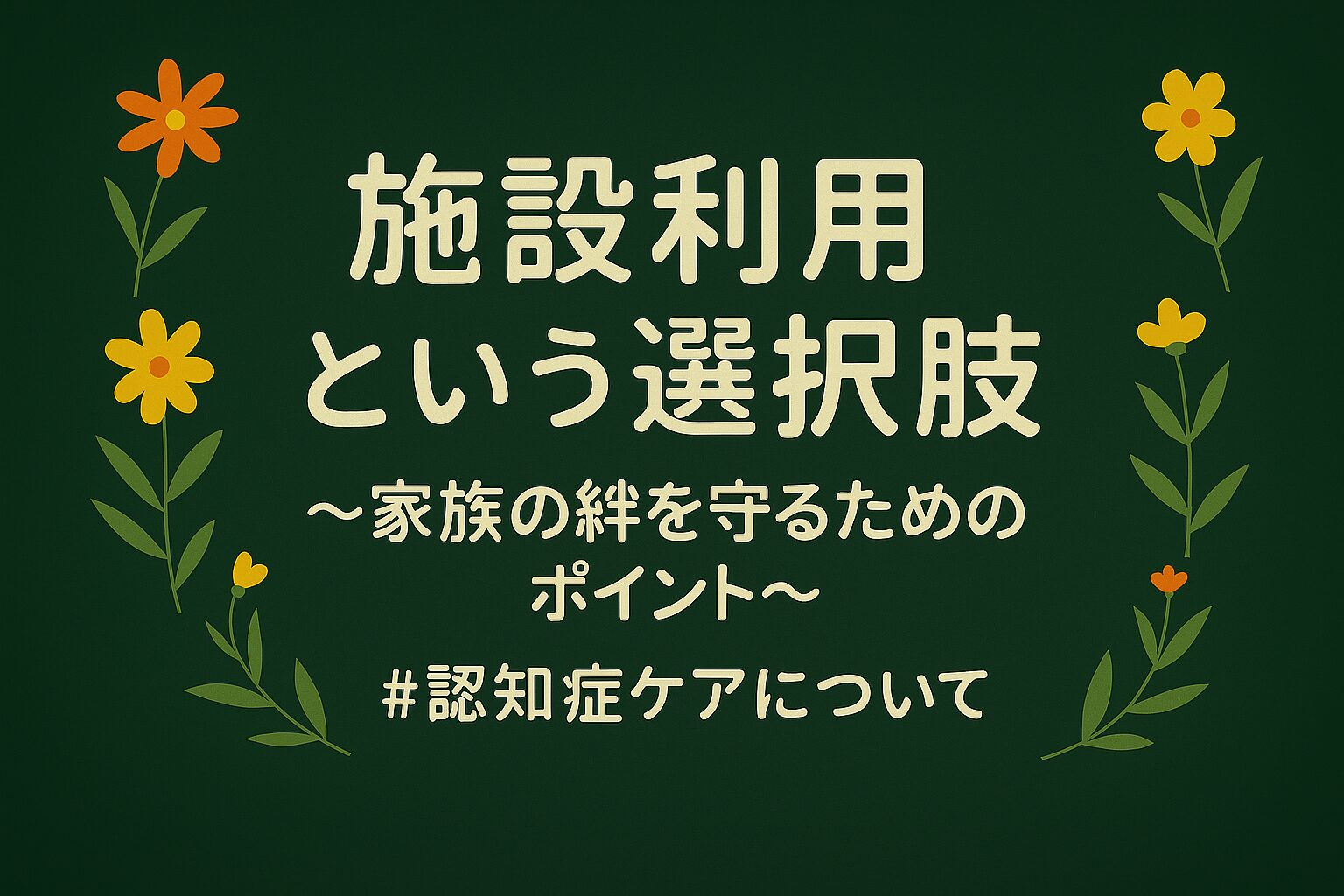
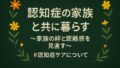
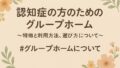
コメント