地域密着型施設の目的
別の記事【グループホーム入居の条件 その① ~要介護度・認知症診断・住民票の要件について~】で『他市区町村の地域密着型施設も利用できなくはない』ということを書きました。
住んでいる市区町村に希望する施設が無い場合、他の地域の施設を利用するには、どうすればいいのでしょうか。
この記事では『どうすれば他市区町村の地域密着型施設を利用できるようになるのか』といったことについてお伝えをしたいと思います。
※基本的に今回の記事の内容については、行政は推奨していないことがほとんどです。
他市区町村の施設を利用するための制度『住所地特例』とは?
一つ目は『住所地特例』を利用する事です。『みなし住所』と呼ばれることもあります。
住所地特例とは『他の市区町村の施設に入っても、元の市区町村が介護保険の負担をする仕組み』のことです。
グループホームで住所地特例を利用する場合
- 住んでいる市区町村のグループホームに空きが無いこと
- 他の市区町村のグループホームを利用しなければならない理由があること
- 利用先の自治体と、本人の住所地の自治体が、ともに住所地特例を認めること
などが必要になってきます。
特に『虐待が疑われるような案件で施設入所を急いでいるが、市区町村内の施設に空きがない』などの場合は、行政からの問い合わせで案件が発生するため、住所地特例が認められての施設入居となる可能性が高いでしょう。
また『市の境に住んでおり、住所がある市内の施設が遠く、隣の市にある施設の方が利便性が高い』なども、利用できる可能性が高くなります。
住所地特例の問題点
多くの場合、行政は『住所地特例』の利用について難色を示します。
その理由はいくつかあります。
A市に住むAさんが、B市のサービスを利用した場合で考えてみます。
①財政負担の不公平感
B市に介護保険料を納めた市民がB市の地域密着型サービスを使う――これが、本来の地域密着型サービスの在り方です。
ですが住所地特例でAさんがB市のサービスを利用する場合、B市は介護サービスを提供するための整備や、そのサービスを管理をする手間が発生するにも関わらず、Aさんの介護保険料はA市が徴収しているため、財源が無いのにサービスの提供や管理を行わなければいけないという事になり、財政的な不公平感が生まれます。
②事務手続きが煩雑
通常の適切な利用方法よりも、介護保険の保険者情報と住所情報の食い違いが発生しやすく、本来行わなくてもよい業務や事務処理の負担が増え、本来気にしなくてもよい些末な部分まで注意を払わなければならず、保険料の徴収や給付に関するミスの原因になりやすいことも挙げられます。
③利用者・家族の混乱
『住民票は今の住所なのに、介護保険の窓口は元の自治体』というねじれが生じているため、申請・相談・手続きが分かりづらく不便に感じ、結果として家族の負担感も大きくなりやすいでしょう。
引っ越して地域密着型施設を使う
もう一つの方法は、単純に『利用したい市区町村に引っ越す』というものです。
ですが、例えば『20年住んでいるが、住所を移していない』場合は、住んでいたとしても地域密着型施設の利用はできません。
理由としては『何年住んでいようが住民ではない』と、市区町村からみなされるからです。
では、市区町村の行政が、何をもって住民とみなしているかというと『住民税を収めているか否か』です。つまり『住所を移していない = 住民税は住所がある市区町村に収められている』ということになります。
では、住所を移せばいいかといえばそう簡単なものではありません。
なぜならば、地域密着型サービスが使いたいがために住民票を移動させることは、基本的には行政が渋る(嫌がる)からです。
『地域密着』の施設を利用するための引っ越しで生じる問題
理由は単純で、受け入れ側の市区町村の介護保険料の負担が増えるからです。
介護サービスを受けたいがために転入する方を際限なく受け入れるということは、介護保険の支出も際限なく増え続けるということになります。
またそもそも地域密着型施設は『住み慣れた地域での生活を継続する』ことが目的ですので、そういった意味でもサービスの利用を目的とした転入は良い顔はされないでしょう。
そういった理由からも、大体の自治体は『地域密着型サービス利用のための転入は受け付けない』か『転入後に地域密着型サービスを利用するためには数ヶ月以上の、住民としての実績が必要』としています。
ただし稀に『転入日から利用可能』『14日以内に手続きを行えば、転入手続き前でも利用可能』という自治体もあります。この辺りは行政によって差が大きな部分ですので、この方法を使う場合は必ず確認しましょう。
ですがおそらく『転入して何日後からグループホームが使えますか?』という質問を行政の窓口でしてしまうと不審に思われますので、利用したい地域密着型サービスの管理者に確認した方が良いかと思います。
大抵の管理者はそのあたりは押さえていると思いますし、仮にその時点で知らなくとも、行政に確認をしてくれるはずです。施設の管理者がこの確認をすること自体は比較的普通ですし、管理者にとっては今後の運営のためにも必要な知識であることは間違いありませんので、転入希望の方が確認するよりは怪しまれないでしょう。
今回は、自分が住んでいる自治体ではないところにある地域密着型施設を利用するには、ということについてお伝えいたしました。
前述したとおり、地域密着型施設とはそもそも『住み慣れた地域で生活するために利用する』ということが大前提です。ですので『住み慣れていない地域で生活をする』ことは、地域密着型施設を利用する目的から大きく外れていると言わざるを得ないでしょう。
しかしそれでもなお、他市区町村の地域密着型施設の利用を考えなければならない場面があるかも知れません。
そういった時は、どうすればいいか自分一人で悩まず、先ずは地域包括支援センターや、市区町村の介護保険担当に相談してみる事が良いでしょう。
それでもどうにもならなかった時に、この記事の内容が、問題解決の一助になれば幸いです。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
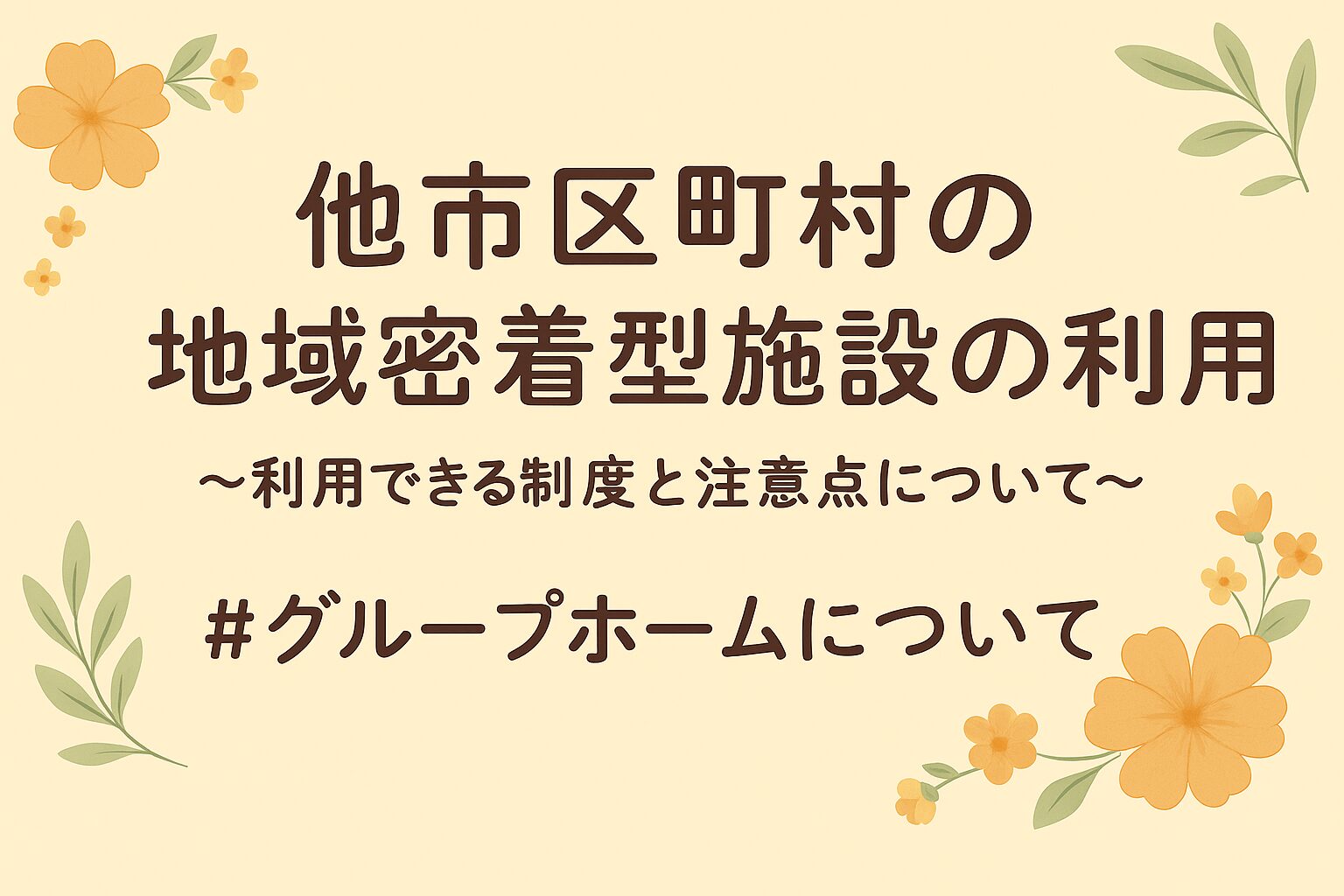

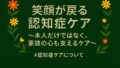
コメント