
※この記事は、認知症グループホームで10年以上勤務し、現在は管理者として働く筆者が執筆しています。
ご本人・ご家族・介護職員、それぞれの立場をふまえたケアの視点をお届けします。
本記事では、空間認知・注意力・判断力などの低下が引き起こす転倒リスクと、その予防策が分かります。
→ 筆者プロフィールはこちら
「なんで今、そこで転ぶの?」
認知症の方の介護をしていると、思わぬところで転倒してしまうことが少なくありません。
たとえば、こんな場面を見たことはありませんか?
- トイレに行こうとして、椅子から立ち上がった直後に転倒
- ベッドから降りようとして座ったら、ずり落ちてしまった
- 廊下で職員を呼びながら、ふらついて壁にぶつかった
実はこれらの転倒や転落は、段差があったわけでも、足腰が弱っていたわけでもないことが多いのです。
では、なぜ転倒が起きてしまったのでしょうか?
その背景には「認知機能の障害」が関わっています。
認知機能の障害とは?
「認知機能」とは、周囲の状況を理解し、適切に判断し、自分の体を動かすために必要な脳の働きのことです。
認知症になると、こうした認知機能が少しずつ低下していきます。
転倒に関わる代表的な認知機能の障害は、以下のようなものです。
1. 空間認知障害
→ 自分と物との距離感や、床の高さ・奥行きの認識がうまくできない
→ 「段差がないと思った場所に段差がある」「ベッドの端を踏み外す」といった事故に直結します
たとえば、頭頂葉の右側(特に上頭頂小葉)が空間の認知に関与し、アルツハイマー型認知症ではこの領域が萎縮することが、画像研究でも確認されており、距離感の認識が不正確になることがわかっています(Yamamoto et al., 2011)。
具体例:
- ベッドの高さを見誤り、降りようとして転落
- 段差に気づいていても「これくらいの高さ」と思って踏み出し、バランスを崩す
- 壁や手すりとの距離感がわからず、手すりに手を伸ばしたものの空振りして転倒
2. 注意力の低下
→ 周囲の危険に気づく力が低下し「見る」「気づく」「避ける」といった反応が遅れがちになります。また、歩行中に注意がそれると、障害物や段差を認識できずに転倒につながります。
認知症では、前頭前野の機能低下により“選択的注意(たくさんある情報の中から、自分にとって重要なものだけを選んで注意を向ける脳の働き)”が困難になり、歩行時に注意を二重課題(会話や環境音)へ向けるとバランス制御が著しく悪化するという研究もあります(Montero-Odasso et al., 2012)。
具体例:
- 廊下を歩いている途中、他のものに気を取られて足元のマットにつまずく
- 歩いている時に誰かに話しかけられて注意がそがれ、いすの足に引っかかって転倒
- 呼び止められて振り返った拍子にバランスを崩し、後ろ向きに転倒
3. 見当識障害(時間・場所・人がわからなくなる)
→ 今が何時か、どこにいるか、誰がいるかなどの見当識が混乱すると、不適切な時間帯や状況で行動し、環境とのズレが原因で転倒することがあります。
具体例:
- 深夜に「朝だ」と勘違いしてベッドを離れ、薄暗い室内で家具にぶつかって転倒
- トイレの場所がわからなくなり、廊下をうろうろしてふらつく
- 来客と思い込んだ職員に会おうと急に立ち上がり、バランスを崩して転倒
4. 判断力の低下
→ 状況に応じて「危ないかもしれない」と判断する力が弱くなります。安全確認や慎重な行動ができず、危険を過小評価して無理な行動に出てしまいます。
具体例:
- 濡れた床を見ても「平気だろう」と思い込み、足を滑らせて転倒
- 「椅子に届く」と思って手を伸ばすが実際は遠く、支えを失って転倒
- 屋外の段差を「これくらいなら」と思って無理に上がろうとして足を引っかける
5. 実行機能障害(段取りを組み立てて行動する力の低下)
→ 行動の順序を組み立てたり、目的に合わせた行動を選ぶことが難しくなります。そのため、必要な準備や安全確認を飛ばして動いてしまい、結果として転倒につながることがあります。
段取りや順序立ては“実行機能”と呼ばれ、前頭前野の働きに大きく依存しています。
実行機能は日常生活の安全行動と深く関連しており、認知症の初期段階からこの機能が低下することで転倒リスクが高まることが明らかになっています(Royall et al., 2004)。
具体例:
- 杖を使うべきなのに、先に歩き出してしまいふらついて転倒
- 立ち上がる前に車いすのフットレストを上げ忘れて、足が引っかかる
- トイレに行こうとしてズボンを脱ごうとしながら移動し、足元が乱れて転倒
認知機能の障害からくる転倒を防ぐには?
①「今、何をしようとしているか」に寄り添う声かけ
行動の意図を読み取り、一歩先を見越したサポートをすることが大切です。
特に認知症の人に対しては、支援者が行動の目的を理解し、段階的に支援するアプローチ(スキャフォールディング)が、転倒や混乱を減らすという研究があります(Kitwood, 1997)。
声かけ例:
- 「トイレですか? 一緒に行きましょうか」
- 「足元に段差があります。ゆっくりで大丈夫ですよ」
② 空間認知障害への工夫:「見え方の誤解」を補う環境づくり
空間認知のズレによって転倒が起きやすくなるため、視覚的にわかりやすい環境が重要です。
具体策:
- 床と段差の色をしっかり分ける(濃淡の違いをはっきりさせる)
- トイレ・ベッドの位置に照明を設け、影ができにくいようにする
- 錯視を起こしやすい模様の床材は避ける
- 壁や家具に「立体感」を持たせる配色(白一色よりも縁取りなどが有効)
③ 注意を分散させない環境をつくる
テレビの音や人の声が多いと、注意がそれて危険に気づきにくくなります。
歩行時には静かな環境で、声かけは短く、わかりやすくが基本です。
実際に、歩行時の二重課題(Dual-task:歩行+会話など)を与えた高齢者では、転倒率が約2倍に上昇するという研究があります(Shumway-Cook et al., 1997)。
④ 「見える化」して判断力を補う
- 段差の手前に黄色や赤の滑り止めテープを貼ることで、視認性が上がり「段差がある」と脳に伝わりやすくなります
- 床の素材で濡れていることが分かりにくい場合は、立て看板や色の変化で示す
- 進行方向にわかりやすい矢印や案内表示をつける
⑤ 行動の「順番」を支援する
実行機能障害がある方には、行動の段取りをサポートすることが有効です。
具体例:
- 起立時に「杖を取ってから立ちましょう」とステップを分けて声かけ
- 椅子の横に杖をセットしておくなど、行動を促す配置を工夫する
まとめ
認知症による転倒は「見えない障害」が原因になっていることが多くあります。
転倒の要因として、身体的な衰えよりも認知機能の低下がより大きな影響を持つとする研究もあり(Yamada et al., 2012)、なかでも「注意」「判断」「空間認知」などの機能が特に関連性が高いとされています。
空間の感覚や距離感、注意や判断、行動の順序といった脳の機能が低下することで、日常動作が思わぬ事故につながってしまうのです。
「気をつけて」と声をかけるだけでは防げない転倒を、環境整備と適切なサポートで未然に防ぐことができます。
本人の尊厳を守りながら、安全な暮らしを支えていくために、認知機能の変化を理解し、それに応じた対応を心がけましょう。
その“見えないリスク”に気づけるかどうかが、大切な人を、転倒から守る第一歩なのです。
参考文献・引用元
- Yamamoto, K. et al., (2011). Right parietal dysfunction and spatial disorientation in Alzheimer’s disease. NeuroImage, 54(2), 892–899.
- Montero-Odasso, M. et al., (2012). Gait and cognition: A complementary approach to understanding brain function and the risk of falling. Journal of the American Geriatrics Society, 60(11), 2127–2136.
- Royall, D. R. et al., (2004). Executive control function: A review of its promise and challenges for clinical research. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 59A(3), 255–260.
- Yamada, M. et al., (2012). Cognitive decline as a risk factor for falls in older adults: A population-based longitudinal study. Journal of the American Geriatrics Society, 60(6), 1076–1083.
- Shumway-Cook, A. et al., (1997). Attentional demands and postural control: The effect of sensory context. Physical Therapy, 77(4), 438–449.
- Kitwood, T, (1997). Dementia Reconsidered: The Person Comes First. Open University Press.
【次回予告】
転倒の背景には「不安でうろうろする」「怒って立ち上がる」「職員を誰かと勘違いして慌てる」など“心の動き”が原因になっていることもあります。
次回は「徘徊」「怒り」「誤認」など、行動・心理症状(BPSD)が引き起こす転倒リスクに焦点を当て、心の動きと転倒の意外なつながりについてお伝えいたします。
ここにんでは、認知症介護を”楽にする”ためのヒントとなるような考え方、技術をたくさんを発信しています。
詳しくは ➡【はじめての方へ ここにんってどんなブログ?】をご覧ください!
関連記事
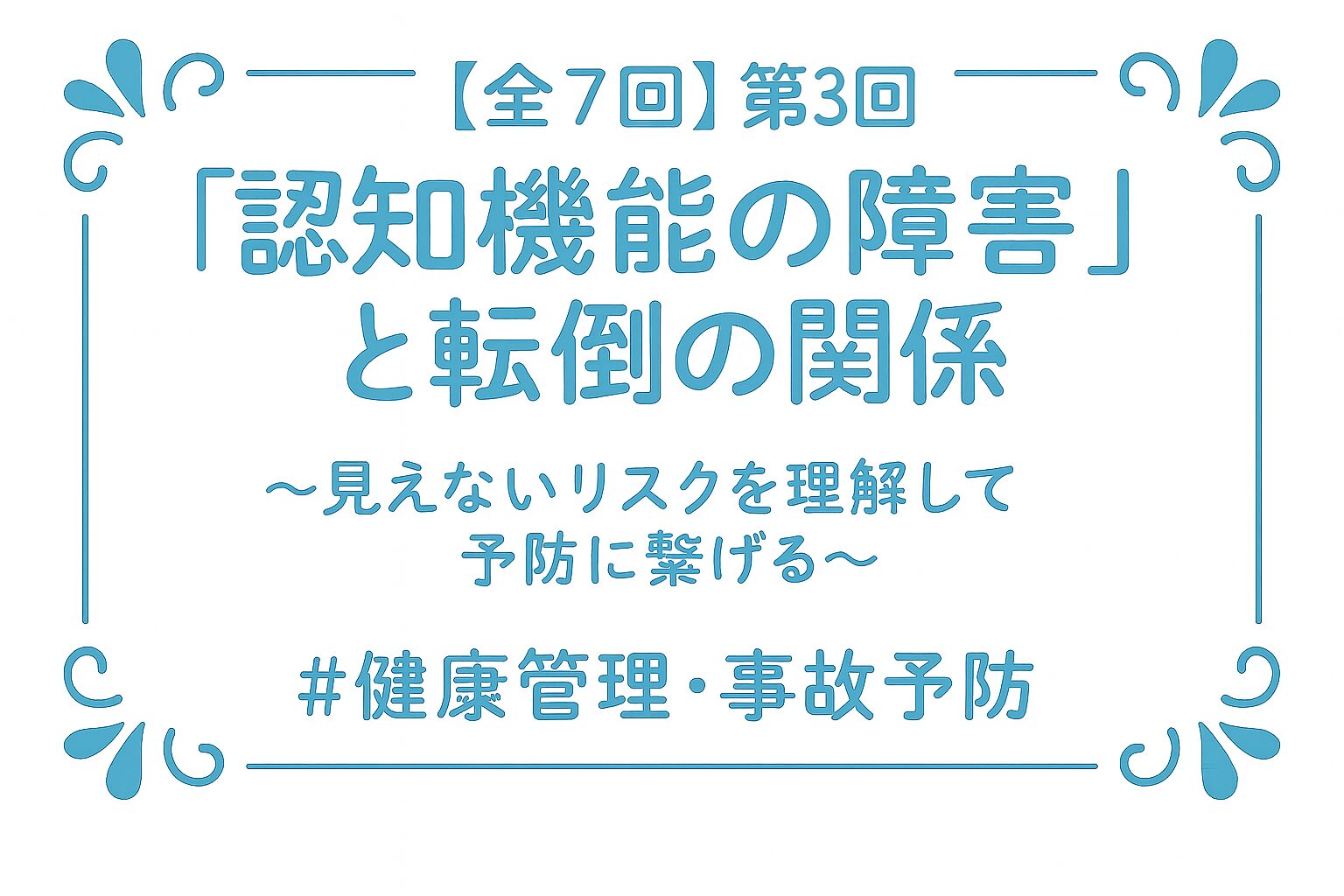


コメント